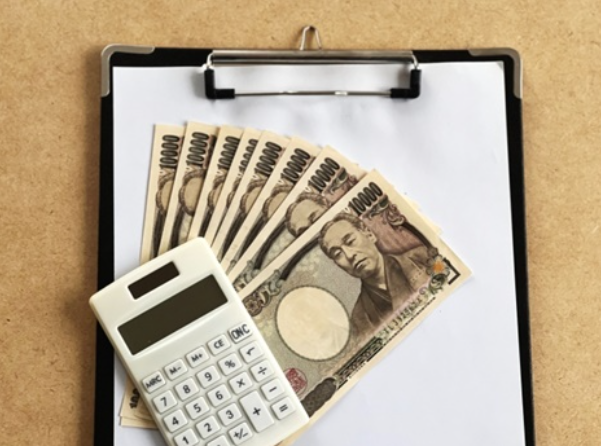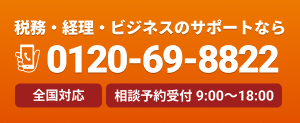メニュー
- 融資
事業計画書の作成方法とは?作成する際のポイントやメリットについて解説

事業計画書とは、企業のビジョンや経営方針、収益見込みなどを整理し、一つの文書にまとめたものです。
決まった形式は存在していないので、既存のテンプレートなどを活用しつつ、目的や事業内容に最適な形で作成することが重要になります。
本記事では、事業計画書の作成方法について紹介します。
他にも「事業計画書を作成する際のポイント」や「事業計画書を作成するメリット」についても解説していきます。
ぜひこの記事を参考にして、事業計画書の作成方法について理解を深めてみてください。
目次
事業計画書とは?
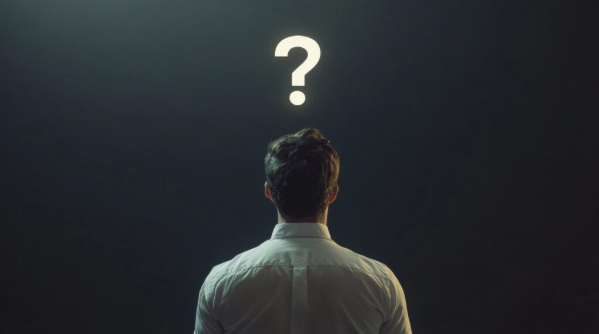
事業計画書とは、企業が目指す目標や事業の方向性、具体的な行動指針、収益の見通しなどを明確にし、社内外で共有するための文書です。
事業の全体像を整理し、目標達成のための詳細な計画が記載されています。
主に資金調達や許認可申請を行う際に求められることが多いですが、法律上の作成義務や決まったフォーマットはありません。
このように、事業計画書は誰が読んでも分かりやすい形でまとめた資料のことです。
目的
事業計画書の目的は、自社のビジネス全体の方向性を明確にし、その実現に向けた具体的な戦略を示すことにあります。
また、資金調達や支援を得るために、投資家や金融機関などに提出を求められる場合もあります。
しかし、計画書を作成すること自体が目的化し、肝心の事業の実現性や妥当性がなくならないように注意が必要です。
事業の強みや独自性を十分に検討し、それを論理的かつ具体的に書類へ落とし込むプロセスを重視することが重要です。
必要性
事業計画書の作成は、法律で義務付けられているものではありませんが、資金調達や許認可の取得、補助金の申請などを進める際には、事業計画書の提出が求められる場合が多くあります。
また、事業の方向性や目標を文書として整理することで、創業者自身が事業のビジョンを明確にしやすくなるという利点もあります。
事業計画書の作成方法

事業計画書の作成方法については、以下の8つが挙げられます。
- 創業メンバーの情報
- 創業動機や目的
- 事業実績
- 商品やサービス
- 取引関係
- 借入状況
- 必要資金と調達方法
- 事業の見通し
それぞれの作成方法について解説していきます。
創業メンバーの情報
事業計画書を作成する際には、創業者や創業メンバーの経歴や資格を詳しく記載しましょう。
特に、これまでの職務経験や取得資格が事業と関連している場合は、当時の具体的な業務内容を含めることで、融資担当者に良い印象を与えやすくなります。
重要なのは、「この人物がなぜこの事業を成功させられるのか」を明確に伝えることです。
しかし、事業と関係のない情報を盛り込むと、かえって評価を下げる可能性があるため注意が必要です。
創業動機や目的
事業を立ち上げる理由や背景については、単なる思いつきではなく、しっかりとした計画や情熱があることを伝えることが重要です。
そのため、創業を決意した経緯や、その過程で培った経験を具体的に記載しましょう。
特に、これまでの経験と事業内容の関連性を明確にすることで、第三者に対して説得力のある説明ができます。
また、事業を始める上での決め手となった出来事や環境の変化なども補足すると、よりリアルなストーリーとして伝わります。
事業実績
事業に関する経歴を重点的に記載し、限られたスペースを有効に活用しましょう。
例えば、会社勤務時にチームリーダーとしての経験がある場合は、具体的な役職や成果、身につけたスキルを詳しく述べることで、経営者としての適性をアピールできます。
また、最近の収入状況は自己資金との関係を示す重要な要素となるため、記載するようにしましょう。
学歴についても、特に事業に関連する分野を学んだ学校や留学経験があれば強調すると、信頼性が増します。
参考:「MBA留学とは?費用や準備期間、平均年齢などまとめて解説|スクールウィズ」
このように、融資担当者が専門知識を持っていないことを考慮し、どのような実務経験があり、どのスキルを習得したのかを具体的に説明することが大切です。
商品やサービス
ビジネスの核となる「取扱商品・サービス」の項目ですが、記入スペースは限られているので、簡潔かつ分かりやすく、商品の魅力を伝えることが重要です。
抽象的なキャッチコピーではなく、具体的な情報を盛り込むことで、商品やサービスの特長が際立ちます。
具体的に記入する際は、次のポイントを意識するようにしましょう。
- 「誰に・何を・どのように提供するのか」を明確にする
- 料金や単価を記載し、ビジネスモデルを示す
- 商品の特長や強みを簡潔に表現する
- 専門用語を避け、誰でも理解できる言葉を使う
- 経営者の経歴や実績と関連付けて説得力を持たせる
また、市場に多くの見込み顧客がいたり、過去の営業経験で高い実績を上げたなどの要素を盛り込むと、より魅力的なアピールになります。
取引関係
販売先がすでに決まっている場合は、主な取引先や関係する企業の名称、シェアなどの情報を具体的に記入します。
万が一、販売先が未確定でも、取引の可能性がある企業があれば、その情報を記載しておくようにしましょう。
また、、商品を安定的に供給できることを示すために、仕入先や外注先についても詳しく記述することが重要です。
借入状況
事業主の個人的な借入状況を記載する際は、返済明細書を参考にしながら、借入先や資金の用途、残高、および年間の返済額を正確に記入しましょう。
創業時に融資を申請する場合、審査では事業主本人の借入状況も確認されます。
しかし、個人としての借入があるからといって、必ずしも不利になるわけではありません。
例えば、住宅ローンを組んでいる場合、それは金融機関の審査を通過した実績があることを示し、社会的信用の証として評価される可能性もあります。
必要資金と調達方法
必要な資金・調達方法は、なぜ特定の金融機関からこの金額の融資を受ける必要があるのかを明確に説明する項目です。
これは審査において特に重視されるため、十分な根拠を示すことが求められます。
設備資金は、事業を開始・運営する上で欠かせない投資であり、その必要性を証明する資料が求められます。
例えば、店舗の改装費用なら業者の見積書、賃貸物件なら賃貸契約に関する書類が必要となります。
審査担当者は、投資額が適正かどうかを慎重に判断するため、設備投資の内容が適切であるか十分に検討するようにしましょう。
運転資金については、売上原価や経費との整合性が求められます。
運転資金の適正な金額は、一般的に3~4か月分の原価や経費を基準とするのが目安です。
そのうえで、自己資金も加味した計画を立てる必要があります。無理のないバランスとしては、自己資金と融資を半々程度に設定するのが理想的です。
このように、必要な資金計画を明確にし、適正な調達計画を示すことが、スムーズな融資審査につながります。
事業の見通し
新しく事業を立ち上げた直後に黒字化するのは、現実的には難しいのが一般的です。
しかし、融資を受けるためには、起業後半年から1年以内には事業が軌道に乗り、黒字化する計画を立てるのが望ましいです。
そのためには、早期の黒字化が見込めるビジネスプランを策定することが重要です。
もちろん、その計画が実現可能であることを裏付ける根拠も示す必要があります。
創業前の段階では売上高を正確に算出するのは難しいですが、「客単価 × 想定客数」でシンプルに見積もる方法が有効です。
また、経費については予想よりも多めに見積もっておくことで、リスクを考慮した現実的な計画を立てることができます。
事業計画書を作成する際のポイント

事業計画書を作成する際のポイントについては、以下の5つが挙げられます。
- 具体的に記載する
- わかりやすく書く
- 競合を調査する
- 一貫性を持つ
- データに基づいた根拠を提示する
それぞれのポイントについて解説していきます。
具体的に記載する
企業の概要を明確に伝えるためには、会社の歴史、従業員数、ビジネスモデルなどの基本情報に加え、代表者の経歴や実績を盛り込むことが効果的です。
これにより、資金提供者が企業や事業の方向性を具体的にイメージしやすくなります。
また、売上の増加について触れる際には、単に数値を示すだけでなく、「どのような要因で成長したのか」を詳しく説明することが重要です。
具体的な理由を明記することで、今後の利益拡大の可能性について説得力を持たせることができます。
さらに、企業の強みだけでなく、現在直面している課題やそれに対する対応策についても記載すると、事業の透明性が高まり、投資家や関係者の信頼を得やすくなります。
わかりやすく書く
情報を伝える際には、長い文章だけでは要点がぼやけてしまい、読者にとって理解しにくい場合があります。
特に、事業内容を知らない人にも伝わるように、簡潔な表現を心がけるようにしましょう。
また、文章だけでなく、シンプルなグラフや図を活用すると、視覚的に理解しやすくなります。
さらに、フォントの種類や文字のサイズ、レイアウトにも配慮すると、より読みやすい資料になります。
フォントは基本的に統一し、強調したい部分には太字や文字サイズの変更を適度に活用すると効果的です。
しかし、強調を多用しすぎると、かえって重要なポイントが埋もれてしまうため、バランスを考えて使用することをおすすめします。
競合を調査する
市場全体や競合の分析結果を反映させることで、自社ならではの戦略や収益目標をより具体的に示すことが可能になります。
競合が提供する商品やサービスのターゲット層を理解することで、自社の事業計画において差別化を図り、異なる市場を狙ったり、より広範な顧客層を取り込む戦略を立てたりすることができます。
こうした明確な差別化を打ち出すことで、事業計画の説得力を高めることにつながります。
一貫性を持つ
計画書は複数の項目で構成されていますが、それぞれの内容に一貫性を持たせることが重要です。
例えば、現状分析で高齢化の進行をビジネスチャンスと捉えているにもかかわらず、実際に提供する商品やサービスのターゲットが若年層である場合、計画全体に矛盾が生じてしまいます。
また、文章で説明している内容と、数値で示されたデータに食い違いがないよう注意しましょう。
どれだけ優れたアイデアであっても、計画書の細かい部分で矛盾や違和感があると、読み手の納得を得ることが難しくなるのも事実です。
このように、事業計画書で一貫性を持たせるために、内容全体の整合性をしっかりと確認することが大切です。
データに基づいた根拠を提示する
事業計画書を作成する際には、データに裏付けられた根拠を示すことが重要です。
たとえば、政府機関が公表している統計情報や、業界の専門家による研究結果を活用することで、主張の信頼性が高まります。
また、収集した情報が二次情報である場合は、その出典をたどり、一次情報を確認することが求められます。
こうしたプロセスを経ることで、事業計画書の信頼性が向上し、計画の実現可能性をより強くアピールできることにつながります。
事業計画書を作成するメリット

事業計画書を作成するメリットについては、以下の3つが挙げられます。
- 事業をスムーズに進めることができる
- 融資の判断材料になる
- 事業内容を可視化できる
それぞれのメリットについて解説していきます。
事業をスムーズに進めることができる
新しい会社や事業を立ち上げる際には、経営の方針や経営陣の目標を従業員がしっかりと理解することが重要です。
これにより、業務が円滑に進み、組織全体の方向性が統一されます。
また、業界の動向や競合他社の状況、自社がターゲットとする顧客層、事業の目的や目標を明確にすることで、社員の意欲向上や業務の効率化にもつながります。
さらに、事業計画書を取引先などの関係者と共有することで、事業の根拠やビジョンを明確に示せるため、信頼関係の構築にも役立ちます。
このように、経営者が定めた方針を分かりやすく伝えることで、組織内外の理解を深め、円滑な事業運営につなげることができます。
融資の判断材料になる
事業計画書は、金融機関や投資家が融資の可否を判断するための重要な資料となります。
利益の予測や事業の安定性が明確に示されていることで、その事業の将来性やリスクを見極める手助けとなります。
また、融資の審査に必要な情報を網羅した事業計画書を作成すれば、審査期間の短縮につながるだけでなく、融資が承認される可能性も高まります。
事業計画書には、事業の概要だけでなく、売上予測や将来的な成長見込み、必要なコストなどを具体的な数値で記載しましょう。
さらに、数値を示す際には、その根拠となるデータを併せて提示することが重要です。
事業内容を可視化できる
事業計画書を作成することで、事業の方向性や現在直面している課題を明確にし、客観的に検討しやすくなります。
また、事業を立ち上げた背景や込めた思いを文章に落とし込むことで、事業の独自性や競争優位性が浮き彫りになり、他社との差別化ポイントや課題が明確になります。
事業の構想を言語化することにより、具体的な実施プロセスや必要なステップが整理され、事業を円滑に進めるための指針が得られます。
さらに、事業計画を作成する過程では、必要な資金の試算だけでなく、利益を生み出すためのマーケティング戦略や人材確保、ターゲットとなる顧客層へのアプローチ方法など、事業の成功に欠かせない要素を検討することが求められます。
事業の詳細を具体的に整理することで、実行すべき課題が明確になり、不要なコストや労力を削減できるというメリットもあります。
事業計画書を作成する際には事業内容を整理しよう!

今回は、事業計画書の作成方法について紹介しました。
事業計画書は、ビジネスの内容や戦略、将来的な収益の見通しなどを整理し、説明するための文書です。
特に、新たに事業を立ち上げる際や、既存の事業を拡大する際に資金調達を目的として活用されます。
また、事業計画書を作成する際は、まずビジネスの基本的な方向性を明確にすることが重要で、「誰に、何を、どのように提供するのか」という視点を意識しながら構想をまとめることで、目指すべき事業の姿がより具体的になります。
今回の記事を参考にして、事業計画書を作成してみてください。
‐免責事項‐
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は 国税OB・元税務署長 が所属し、 確定申告・相続・会社設立・融資サポート・労務手続きなど 幅広いサービスを提供する税理士法人です。
全国からの 税務・労務相談実績 年間1,000件以上
税理士法人松本の強み
- 税務署目線、税理士目線、お客様目線の三方良しの考え方でアドバイス
- 過去の無申告分から税務調査、相続、会社設立まで幅広く対応可能
- 融資や助成金、補助金の申請など資金調達サポートにも豊富な実績
- 顧問税理士が対応に困った案件も途中からサポートできます
30秒で完了かんたん融資診断