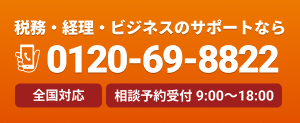メニュー
- 融資
運転資金はどこから借入する?金額の目安や資金調達方法、融資の際の注意点を詳しく解説

運転資金が不足しそうになったときに考えるのが融資などの資金調達ですが、運転資金をどこで借りることができるのか、いくら借りるのが良いのか、心配になる方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、運転資金の調達方法や借入額の目安、融資の申し込みをする際の注意点などを解説します。
事業を継続していくためにも運転資金はなくてはならない存在ですので、ぜひ最後までご覧いただき、自社にとってベストな借入先を検討してみてください。
目次
運転資金とは

そもそも運転資金とは、企業が日々事業活動を営むために必要な資金のことを指します。
運転資金が不足すれば、商品の仕入れができなかったり、事務所の賃料や光熱費、従業員への給料を支払えなくなったりして、事業を続けるのが困難になります。
開業するにあたって、創業時にどれくらいの資金が必要なのか、という点に関心が向きがちですが、事業を続けていくためには運転資金の確保が必要となるのです。
設備資金との違い
運転資金と混同されやすいものとして「設備資金」があります。
運転資金が事業運営を続けていく中でかかる費用をまかなうための経常的にかかる資金であるのに対し、設備資金は事業に必要な資産を購入するための資金です。
具体的には製造設備や機械、OA機器、システム関連費、Webサイト構築費用など、基本的に貸借対照表の「固定資産」の欄に計上されるもので、事業の将来のために使う資金であり、運転資金と区別されます。
運転資金の内訳
運転資金は、大きく以下の2つで構成されています。
- 固定費
- 変動費
固定費は、家賃や人件費など、売上高の増減に関係なく一定額が発生する費用を指し、開業時などは固定費を抑えた方が良いと言われています。
変動費は、仕入費や荷造運賃など、売上高や生産量と連動して変わる費用で、売上や生産量が大きくなれば増加するものです。
運転資金の項目
運転資金は具体的に、以下のような日々事業を続けていくための資金です。
- 仕入れ
- 家賃・テナント料、リース料
- 水道光熱費
- 通信費
- 人件費、福利厚生費
- 広告宣伝費
- 外注費
- 租税公課
- 金融機関への返済
- 保険料 など
開業時に運転資金について考える際は、事業内容と照らし合わせながら、資金が発生するか確認しておきましょう。
必要な運転資金の目安
どれくらいの運転資金が必要になるかは業種や事業規模、資金使途によっても異なります。
一般的には、3~6か月分の運転資金を調達額の目安にすると良いでしょう。
たとえば、飲食店など資金の回収期間が短い場合は手元にあるお金が少なくても問題ないでしょうが、入金までの期間を長く要する場合には不足分を補うために資金調達が必要になります。
必要な運転資金の金額が判断しにくい場合は、以下の計算式のいずれかを参考にしてください。
- おおよその運転資金=売掛債権+棚卸資産-買入債務
- 正確な運転資金=平均月商×(売上債権回転期間+棚卸資産回転期間-買入債務回転期間)
運転資金の種類

運転資金は、資金が増減するかどうかで固定費と変動費で分類できるとお伝えしましたが、使用目的によって以下のような種類にも分類できます。
- 経常運転資金
- 増加運転資金
- 減少運転資金
- 季節運転資金
- 設備未払金決済運転資金
資金調達する際には、借入理由を説明するためにも、これらを把握しておくことが重要です。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
経常運転資金
経常運転資金は、企業が現在と同じように事業をそのままの状態で維持、運営しつづけるための運転資金を指します。
常に発生する仕入れの費用や人件費、光熱費、家賃などが経常運転資金です。
日本企業においては主に掛取引を採用しており、支払いと入金でタイムラグが発生するため、この不足分の資金を補うために必要となります。
運転資金は多くの場合、この経常運転資金のことをいいます。
増加運転資金
増加運転資金は、事業が順調に成長し、売上が増加しているときに必要になる運転資金です。
売上が伸びると支出も増え、通常の運転資金以上の資金が必要になるので、経営の成長を支えるために増加運転資金が必要になります。
飲食店の場合、店が繁盛して食材の仕入れを増やすときなど、従来よりも多くかかる仕入れ資金がこれにあたります。
減少運転資金
減少運転資金は増加運転資金とは反対に、事業不振により売上が減少しているときに必要になる運転資金を指します。
売上が減ると仕入れなどの資金は減るものの、従業員の給料や事務所の賃料、水道光熱費などの固定費は変わらず支払い続けます。
そこで、これらの不足分を補うための「つなぎ資金」として減少運転資金が必要になるのです。
企業は減少運転資金をつなぎとしてキャッシュフローを回しながら、経営を建て直していかなければなりません。
季節運転資金
季節や特定の時期ごとに必要になる運転資金を季節運転資金といいます。
たとえば以下のようなケースが挙げられます。
- 夏・冬のボーナス月は従業員へのボーナス支給のために通常よりも人件費が増える
- クリスマスやバレンタインなどのイベントで仕入れが増える
- 夏は繁忙期だが冬は閑散期のため売上が下がる
このように、季節や時期によって余分に資金が必要になるという場合に、不足分を補うために必要な運転資金です。
設備未払金決済運転資金
事業を行うにあたって、必要な設備や機器を購入したりリースしたりする費用は、通常は設備資金に分類されます。
しかし、設備資金として購入した費用の一部が半年以上支払えなかった場合、その未払い分に充てる資金は設備未払金決済運転資金として、運転資金に分類されることになっているのです。
たとえば、工場で使用する機械を分割で購入して導入し、その後業績悪化により支払いが滞ってしまった場合、この状態が半年以上続けば設備未払金決済運転資金となります。
運転資金の効果的な調達方法7つ

運転資金が不足すると、最悪の場合倒産してしまう恐れがあるため、運転資金をしっかり確保しておくことが重要です。
ここでは、運転資金を確保するための資金調達方法と、その特徴についてご紹介します。
民間の金融機関の融資
都市銀行・地方銀行・信金・信組など民間の金融機関の融資が運転資金の調達方法として最も一般的です。
銀行融資には銀行の判断で行うプロパー融資や、中小企業を中心とした信用金庫による融資、銀行が融資するために企業の返済を信用保証協会が保証する信用保証協会の保証付融資などがあります。
民間の金融機関の融資は比較的金利が低く、審査に通れば継続的な取引が可能となりますが、その分審査が厳しく、審査期間も長くなる傾向にあります。
日本政策金融公庫の融資
日本政策金融公庫は、政府が100%出資する金融機関で、中小企業・小規模事業者・個人事業主の経営や資金調達をサポートしています。
日本政策金融公庫が提供する融資は条件を満たせば無担保、無保証人での融資を受けられるほか、金利も比較的低金利で、一定期間返済を据え置く制度もあるのが特徴です。
融資の審査は比較的長く、相談から融資実行まで2カ月程度かかるため、急ぎで運転資金が必要な場合には他の資金調達方法を検討した方が良いでしょう。
自治体の制度融資
運転資金の融資として、自治体の制度融資を利用する方法もあります。
制度融資は、金融機関・自治体・信用保証協会の3つの機関が連携して行うもので、小企業や個人事業主が対象の融資です。
制度融資は低金利で長期間借りられる点や元本を返済しない据置制度がある点がメリットとなりますが、自治体によって融資の対象者や利用条件に違いがあるほか、制度融資を行なっていない自治体もあるため、運転資金の調達先として制度融資を検討している方はあらかじめ確認しておきましょう。
ビジネスローンの活用
ビジネスローンは、ノンバンクが提供している事業制ローンを指します。
金融機関や公的機関からの融資と比較しても審査が優しく、申し込みから融資実行までの期間も短いため、銀行のプロパー融資の審査に落ちてしまったり、急に資金が必要になったりした場合の資金調達方法として適しています。
ただし、ビジネスローンは比較的金利が高く設定されており、大きな金額には対応していないケースが多い点に注意が必要です。
国や自治体による補助金・助成金の活用

国や地方自治体が運転資金として活用できる補助金・助成金を用意しているケースがあり、融資と違い、基本的に返済する必要がない点が大きなメリットとなるため、積極的に活用したい資金調達方法です。
中小企業が利用できる補助金や助成金として、以下のものがあります。
- ものづくり補助金
- 持続化補助金
- IT導入補助金
- 事業承継・引継ぎ補助金
補助金や助成金は、所定の手続きで申請を行い、審査を通過すれば受け取れます。
ただし、申請の手続きに手間がかかり、申請してから入金までの期間も長くなるため、急な資金調達には向いていません。
ファクタリング
運転資金の確保としてファクタリングという方法もあります。
ファクタリングとは、企業(債権者)が保有している売掛金(売掛債権)をファクタリング会社へ売却することで、早期資金化を実現できるサービスです。
会社間取引では、商品を売上げてから資金化されるまでに、時間がかかりますが、ファクタリングを利用すればすばやく現金を得られます。
また、借入ではないため、信用情報に影響が出ないというメリットがありますが、手数料が高いケースもあるので注意が必要です。
クラウドファンディング
近年、起業時によく利用される資金調達方法としてクラウドファンディングがあります。
クラウドファンディングとは、インターネットを通じて不特定多数の支援者から資金を集める方法で、現在ではクラウドファンディング専門のプラットフォームが多数あり、それらに登録して広く資金を募ることが可能です。
また、資金を集められるだけでなく、消費者の反応を確認できる、ファンを増やせるなどのメリットもあります。
また、クラウドファンディングはお金を集める人(事業者)と出資者の関係により、以下の3つのタイプに分かれます。
- 購入タイプ(出資する代わりにリターンとして商品やサービス、オリジナルのグッズなどを得られる)
- 融資タイプ(出資することで利息を得られる)
- 寄付タイプ(出資者が出資をしても見返りがない)
運転資金を借入する際の注意点

運転資金の借入は、事業を続けていくための大切な資金調達手段であり、運転資金が不足している企業にとっては必要不可欠なものです。
しかし、些細なことで重大なトラブルが生じる場合もあるので慎重に行わなければなりません。
ここでは、運転資金を借入する際に注意するべきポイントをご紹介します。
借入の理由を明確にする
金融機関の融資審査では、「どのような目的でいくら使うのか」という点が重視されます。
使途が分からなければ、運転資金としてではなく、別の目的で使われるのではないかと疑われてしまいます。
そうすると返済が滞る恐れがあるため、審査が厳しくなるのです。
そのため、なぜ融資が必要なのか、その理由を明確に説明できるようにしましょう。
借入額や返済期間をよく見極める
融資前に実現性の高い返済計画を練ることも重要です。
あくまで運転資金として必要十分な借入額を設定し、資金繰り表を作って順調に返済できることを融資先に主張する必要があります。
返済期間については、つい最長期間で設定してしまう企業も多いですが、金利がかさむほか、完済前に追加で融資を受ける必要が生じると審査が厳しくなる恐れがあるため、実際に返済できる範囲で長すぎない期間に設定するのが望ましいです。
借入理由以外の目的では使用しない
運転資金として借り入れた資金を、運転資金とは異なる目的で使うことはできません。
たとえば、借入金を事務所の賃料に充てると伝えていたにも関わらず設備投資に使っていれば、目的外使用とみなされます。
もし、金融機関に目的外使用の事実が発覚した場合、重大な約束違反となり、資金の一括返済を求められたり、今後の融資を断られたりと、厳しく罰せられ、信用を大きく失墜させることになってしまうので、注意が必要です。
融資先を慎重に選ぶ
運転資金を借入する際は、融資先の金利や手数料、審査基準などを比較し、慎重に選ぶことが重要です。
運転資金を借入する方法は多岐にわたり、それぞれ特徴や利点が異なります。
まずは自社の経営状況や資金繰りを正確に把握し、申し込み前に調査を行ったり相談したりして自社に合った融資先を見つけましょう。
そして、融資先との信頼関係を築くために、適切な情報開示や説明、コミュニケーションなどが求められます。
運転資金の借入を成功させよう

ご紹介した通り、融資以外にも運転資金を調達するための方法はありますので、それぞれの特徴やメリット・デメリットを比較しながら、自社に最も適した資金調達方法を見つけてみてください。
また、資金調達がうまくいかなければ資金繰りが悪化し、倒産してしまう恐れもあるため、必要に応じて税理士などの専門家に相談するなどして対策をとりましょう。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は 国税OB・元税務署長 が所属し、 確定申告・相続・会社設立・融資サポート・労務手続きなど 幅広いサービスを提供する税理士法人です。
全国からの 税務・労務相談実績 年間1,000件以上
税理士法人松本の強み
- 税務署目線、税理士目線、お客様目線の三方良しの考え方でアドバイス
- 過去の無申告分から税務調査、相続、会社設立まで幅広く対応可能
- 融資や助成金、補助金の申請など資金調達サポートにも豊富な実績
- 顧問税理士が対応に困った案件も途中からサポートできます
30秒で完了かんたん融資診断