メニュー
起業・開業
歯医者開業の方法とは?開業にかかる費用や流れについても徹底解説

読了目安時間:約 7分
歯医者の開業には、多くの手続きや多額の資金が求められるため、必要な費用や開業までの流れなどを事前に把握しておくことが重要です。
本記事では、歯医者開業の方法について紹介します。
他にも「歯医者開業にかかる費用」や「歯医者開業までの流れ」についても解説します。
ぜひこの記事を参考にして、歯医者開業の方法について理解を深めてください。
目次
歯医者の開業パターン

歯医者の開業パターンについては、以下の2つが挙げられます。
- 保険診療メイン
- 自由診療メイン
それぞれのパターンについて解説します。
保険診療メイン
多くの歯医者では、保険診療を主体とした診療スタイルを採用しています。
保険診療では、患者さんの自己負担率は医療費全体の1割から3割程度とされているため、幅広い層に利用されています。
また、歯や口腔内の健康を総合的に守る役割を担い、社会貢献性の高い医療行為とも言えます。
しかし、診療報酬は国によって低く設定されており、収益性には大きな制約が伴います。
多くの歯科医院では保険診療を基盤としつつ、一部で自由診療を導入し、材料や治療内容を拡充する形が一般的です。
自由診療メイン
自由診療では、保険適用外の高品質な素材を使用したり、先端的な医療機器を取り入れた治療を提供することが可能です。
治療費に関しては歯科医院自身が自由に設定できるため、利益率を高めつつ、より高度な医療サービスを実現できます。
しかし、治療費が高額になるため、患者層が限られ、集患には工夫が求められるというデメリットも挙げられます。
ただし、一般的には基本的な治療は保険診療で行われ、自由診療のみを扱う歯科医院はごく少数です。
歯医者の開業科目

歯医者の開業科目については、以下の5つが挙げられます。
- 科目①:歯科
- 科目②:小児歯科
- 科目③:矯正歯科
- 科目④:歯科口腔外科
- 科目⑤:審美歯科
それぞれの開業科目について解説していきます。
科目①:歯科
診療科目の歯科は、一般的な歯科治療全般が含まれています。
ほとんどの歯医者が「歯科」として開業しており、必要に応じて他の診療科目も併記されるケースが見られます。
診療科目ごとに求められる専門知識や技術が異なるため、1人の歯科医師が複数の科目を担当するのは難しいのも事実です。
そのため、複数の診療科目を掲げる歯科医院では、通常、複数人の歯科医師が在籍してチームで診療を行っています。
科目②:小児歯科
小児歯科は、成長期の子どもたちを対象に、歯の健康を守るための専門診療を行う分野です。
乳歯から永久歯へと移行する時期には、大人とは異なる注意深い対応や、成長に合わせた専門的な配慮が求められます。
また、子どもたちが不安を感じにくいように、診察室のデザインや医院全体の雰囲気づくりにも工夫があると集患にもつながる可能性があります。
科目③:矯正歯科
矯正歯科は、主に歯並びを整えるための専門的な治療を行う開業科目です。
一般的に矯正治療は保険適用外の自由診療となり、機能面の改善だけでなく、審美性にも配慮した施術が行われます。
治療には数年単位の長い期間がかかることも多く、患者さんとの信頼関係を深めながら進めていくことが特徴です。
矯正治療だけを専門に扱うクリニックも存在しますが、通常の歯科診療とあわせて矯正治療を提供している歯科医院も少なくありません。
科目④:歯科口腔外科
歯科口腔外科では、口の中やその周辺に生じる病気やけがに対して専門的な治療を行っています。
特に親知らずの抜歯が多く見られるほか、顎の関節に関わる不調の顎関節症、口内炎、舌や粘膜に現れる異常といった、通常の歯科診療では対応が難しい症状にも対処しています。
また、口腔がんに対する治療や大規模な手術については、主に病院に併設された歯科口腔外科部門で実施されるのが一般的です。
科目⑤:審美歯科
審美歯科は、歯の白さを高めたり、歯並びを美しく整えたりと、見た目の美しさを追求する治療を中心としています。
審美を重視する治療は、公的医療保険の対象外となるため、基本的にすべて自費診療になります。
また、通常の保険診療では金属の被せ物が使用される部位に対して、自然な歯に近い色合いの被せ物にする施術も審美歯科に含まれます。
審美歯科は保険医療制度上、正式な診療科目としては扱われていませんが、多くの歯科で自由診療の一環として提供されています。そのため、歯医者のホームページや広告を通じて診療内容に誤解が無いようわかりやすく伝える工夫が求められます。
歯医者開業にかかる費用

開業にかかる費用としては、大きく初期費用と運転資金(開業後、経営が安定するまでにかかる費用)の2つを想定しておく必要があります。
歯医者開業にかかる費用については、以下の2つが挙げられます。
- 初期費用
- 運転資金
それぞれの費用について解説していきます。
初期費用
歯医者の新規開業に必要な資金は、一般的に5,000万円以上とされています。
初期費用には、主に次のような項目が含まれます。
- テナントの賃貸料や物件購入費
- クリニック内装工事にかかる施工費
- 営業許可や各種免許申請など、法的手続きに必要な諸費用(保険加入に関わる費用など)
- 開業時の広告・宣伝活動に必要な経費
- 医療機器や診療器具などの導入コスト
設備については新品を購入する代わりに中古品やリースを選ぶことで、初期投資額を抑える工夫も可能です。
ただし、初期費用は開業する地域や場所、ゼロからの新規開業か、既存の医院を引き継ぐ形かなどによっても、必要な費用は大きく変動します。
運転資金
開業後に事業が安定するまでに必要となる運転資金は、事前にしっかりと見積もっておくことが重要です。
具体的に運転資金で考慮すべき費用には、以下が挙げられます。
- スタッフへの給与
- 施設の賃料
- 電気・水道などの光熱費
- 集客のための広告・宣伝費
- 設備や器具のメンテナンス費用
- その他(歯科用資材、事務用品、消耗品の補充費用など)
開業に際して必要となる初期投資や運転資金は一部を自己資金でカバーし、不足分については銀行融資などを活用するケースも多いです。場合によっては自治体などの補助金制度の対象となることもありますが、申請要件や審査基準が厳しく、必ずしも利用できるわけではないため注意が必要です。
歯医者開業までの流れ
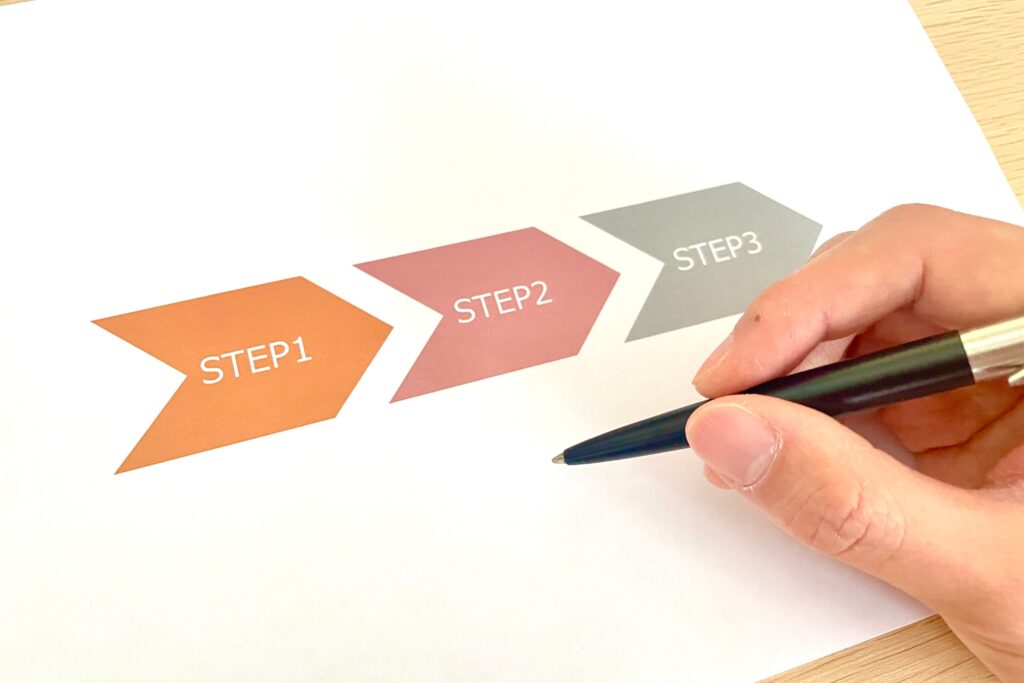
歯医者開業までの流れを把握しておくことで、スムーズに開業することにもつながります。
具体的に、歯医者開業までの流れについては、以下の通りです。
- コンセプトの検討
- 開業エリアを選ぶ
- 事業計画書の作成
- テナントの選定
- スタッフの採用
- 保健所に開設届を提出
- 広告や宣伝を行う
それぞれの項目について解説していきます。
コンセプトの検討
歯医者を開業する際には、まず最初に「どのような医院にしたいか」という事業コンセプトを慎重に練り上げることが重要です。
自身が得意とする診療分野や達成したい売上目標、自らの将来的な目標年収やキャリア設計などさまざまな要素を総合的に踏まえて方向性を固めるようにしましょう。
開業エリアを選ぶ
歯医者のコンセプトにふさわしい開業エリアの選定からスタートするようにしましょう。
ターゲットとする患者層が多く、将来的にも人口増加や通勤・通学者の増加が期待できる地域を選ぶことも戦略のひとつです。
その際、近隣の歯科医院の数や診療内容など、競合状況についても事前に詳しくリサーチしておくと安心です。
開業候補地がある程度絞り込めたら、次は具体的な物件探しに進みます。
事業計画に合わせた予算内で、コンセプトにマッチした物件を選定するようにしましょう。
事業計画書の作成
事業戦略や開業予定の地域・物件がある程度固まった段階で、事業計画書の作成に取りかかるようにしましょう。
事業計画書では、1日の想定来院数や月間売上の目標を設定し、それに伴う必要経費や借入額を見積もります。
また、毎月支払う家賃やスタッフの人件費、水道光熱費などの固定費を算出し、さらに開業時にかかる初期費用も詳細に整理を行います。
実現可能な売上目標を設定し、借入に必要な金額や毎月の返済額も具体的に計画に組み込むようにしましょう。
テナントの選定
テナントの選定をする際には、将来的な運営も見据え、必要な椅子の数や設備を無理なく設置できる広さがあるかをしっかり確認するようにしましょう。
また、駅や中心街からのアクセスの良さ、患者さんが気軽に訪れやすい立地かどうかも重要なポイントです。
さらに、看板が目立つ位置に設置できるか、建物の清潔感や日常の管理状態がどうかといった点も総合的に評価し、慎重に検討したうえで契約手続きを進めることが大切です。
スタッフの採用
物件が決定した段階から、スタッフの採用活動を本格的に進める必要があります。
実際に、スタッフの採用は、資金調達や医療機器の導入準備と同じくらい、重要なプロセスになります。
歯医者では、歯科衛生士や歯科助手、歯科技工士といった専門職の人材が欠かせません。
そのため、どの程度人件費に予算を充てるかを事前に明確にしておくことが重要です。
人件費率も含めた詳細な資金計画については、税理士に依頼して試算してもらうと安心と言えます。
また、開院後に人手不足に陥らないよう、早い段階から採用活動を計画的に進め、面接にも十分な時間を確保しておくことも重要です。
保健所に開設届を提出
歯医者を開業する際には、必ず保健所への開設届の提出が求められます。
開設届は、診療業務を開始できる状態になった段階で行い、所在地を管轄する保健所に、開設後10日以内に届ける必要があります。
開設日とは、診療開始日とは異なり、内装工事等が完了し、診療所の設備・環境が保健所の基準を満たし、診療可能な状態となった日を指します。
提出する書類には、診療時間や診療曜日など、運営に関する具体的な情報を記載します。
保健所の審査をクリアした後は、次に地方厚生局に対して保険医療機関の指定申請を行います。
この申請が受理され、医療機関コードが付与されることで、保険診療を行う資格が得られます。
通常、申請から医療機関コード発行までにおよそ1カ月、保健所への開設届の手続きから承認までは2カ月前後かかるのが一般的です。
このため、スムーズに開業したい場合は、少なくとも開業希望日の約3カ月前には開設届を提出しておくのが理想です。ただし、開設届の提出時期や必要書類は、自治体や保健所によって異なる場合があります。詳細は必ず管轄の保健所に確認しましょう。
広告や宣伝を行う
歯科医院を安定して運営していくためには、医療広告ガイドラインを遵守しつつ、適正な情報発信を通じて地域住民に医院の存在を知ってもらうことが重要です。特に、ホームページの活用や認知度向上に向けた取り組みが効果的です。
特に、インターネット検索を利用する人が増えている現在では、医院専用のホームページを用意することが効果的です。
実際に、院内の設備や雰囲気を実際に見てもらうことで、初めての方でも安心して足を運びやすくなります。このような取り組みは、自然な口コミの広がりにもつながる可能性が高まります。
医療広告ガイドラインでは、誇大表現の禁止、治療効果の過剰な強調、料金透明性の確保などが義務付けられているため、これらを遵守し、地域住民に正確かつ適切な情報提供を行いましょう。
参考:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)|厚生労働省
歯医者を開業するメリット

歯医者を開業するメリットについては、以下の2つが挙げられます。
- 収益を伸ばせられる
- 治療の自由度が高い
それぞれのメリットについて解説していきます。
収益を伸ばせられる
歯医者を開業するメリットとして、適切な経営により収益を伸ばしやすい点が挙げられます。
特に歯科医は、虫歯治療だけでなく、定期的な検診やメンテナンスを目的に訪れる患者も多く、一度来院した患者が長期的に通い続けるケースも多いため、収益性を高めやすい職種と言えます。
そのため、適切な経営戦略やマーケティング施策を講じることで、中長期的に収益性を高め、事業規模を拡大することが目指せます。ただし、地域特性や経営努力によって結果は異なる点に留意が必要です。
治療の自由度が高い
歯医者を開業すれば、診療の方向性はすべて自分自身で決定することができるので、治療の自由度が高いというメリットがあります。
どのような医療方針を打ち出すか、ターゲットとする患者層をどう設定するかも、自分自身の裁量次第です。
例えば、できるだけ歯を抜かない治療に重きを置いたり、定期検診やメンテナンスを通じて予防医療に力を入れるといった選択も可能です。
歯医者を開業するデメリット
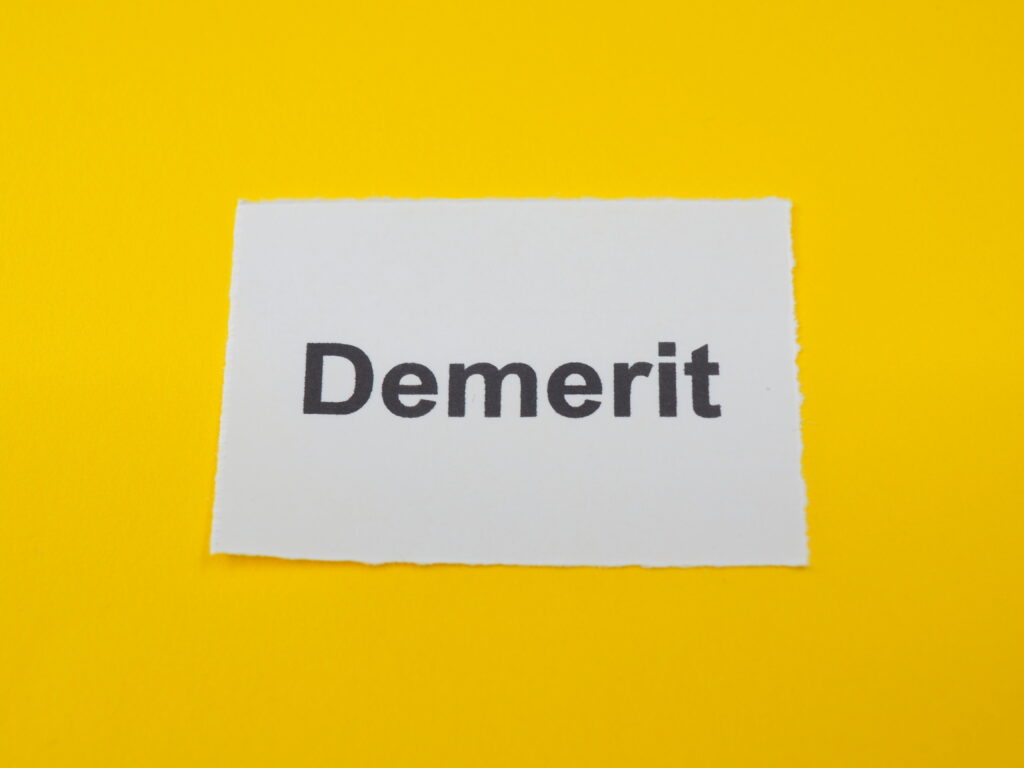
歯医者を開業するデメリットについては、以下の2つが挙げられます。
- 開業資金が必要
- 経営責任が伴う
それぞれのデメリットについて解説していきます。
開業資金が必要
歯医者を開業する際、大きなハードルとなりやすいのが資金調達の問題です。
開業には、医院の内装・外装工事費、物件の賃料が必要となり、加えて治療に必要な各種医療機器を揃える費用も無視できません。
また、開業後すぐに収益が安定するとは限らないので、運営資金も確保しておく必要があります。
経営責任が伴う
歯医者を開業するということは、自分自身がその施設の最高責任者になるので、経営責任が伴うデメリットが挙げられます。
医療現場でのトラブル対応や経営リスクなども含め、開業医はすべての責任を背負う立場となります。
経営責任やストレスに対する自身の適性を事前に考慮し、必要に応じて専門家のサポートを受けることも検討しましょう。
歯医者の開業をスムーズに進めよう!

今回は、歯医者開業の方法を紹介しました。
スムーズな開業後の運営を実現するためには、事前に十分な余裕を持って計画を進めることが大切です。
また、開業後も経営の早期安定化を目指す必要があります。
今回の記事を参考にして、歯医者の開業をスムーズに進めていただければ幸いです。
‐免責事項‐
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。





