メニュー
創業融資
新宿区で受けられる創業融資とは?流れや審査に通るためのポイントについても解説

読了目安時間:約 7分
開業や起業に伴う負担をできるだけ軽減するためには、創業融資を適切に利用することが大切です。
創業融資は、地域ごとに設けられている自治体限定の制度も数多く存在するので、これから創業融資を検討している方は、内容を事前に把握しておくと良いでしょう。
本記事では、新宿区で受けられる創業融資について紹介します。
他にも「新宿区で創業融資を受ける際の流れ」や「新宿区で創業融資の審査に通るためのポイント」についても解説します。
目次
新宿区で受けられる創業融資

新宿区で受けられる創業融資については、以下の3つが挙げられます。
- 創業等支援融資制度
- 中小企業向け制度融資
- 新規開業・スタートアップ支援資金
それぞれの創業融資について解説します。
創業等支援融資制度
創業等支援融資制度では、融資限度額は最大2,000万円で、実質負担金利は年率0.2%以下(令和7年1月時点)となっています。
対象者については、以下のいずれかに該当する方です。
- 法人または個人でこれから創業を計画している方
- 既存の事業から分社化を予定している方
- 法人または個人で創業後5年以内の方
- 分社化によって創業し、5年以内の方
本来の利率は年1.8%以下とされていますが、新宿区の利子補給により、借入時の実質金利は年0.2%(最大で1.6%を補助)程度となります。
さらに、信用保証料についても最大26万円を上限として補助を受けることができます。
融資を受けるための条件として、法人の場合は、 事業拠点と法人登記上の本店が新宿区内の同一住所である必要があります。
また、個人事業主の場合は、 事業所が新宿区内にあることが求められます。
ただし、新宿区に1年以上居住している方については、都内の他地域で創業する場合も対象となる場合があります。詳細は区の担当窓口に確認してください。
中小企業向け制度融資
新宿区の中小企業向け制度融資には、代表的に以下の4種類があります。
- 一般融資
- 創業等融資
- 政策融資
- 商店街融資
この制度は、新宿区が地域内の中小企業の支援を目的に、金融機関と連携して融資を仲介する仕組みです。
融資限度額が2,000万円で、金利が年1.8%で融資を受けることができます。(令和7年1月時点)
また、融資が実行されると、区が利息や信用保証料の一部を補助してくれるのが特徴です。
対象者として、法人の場合は、新宿区内に本店を置き、同一の事業を1年以上継続して運営しており、かつ本店登記も1年以上区内で継続している企業が対象です。
個人事業主の場合は、事業の拠点が新宿区内にあり、1年以上にわたって同じ業種で営業していることが必要です。
新規開業・スタートアップ支援資金
新規開業・スタートアップ支援資金は、最大融資額が7,200万円で、金利が年2.60%〜3.70%(令和7年1月時点)で融資を受けることができます。
新たに起業を計画している方、または開業後おおよそ7年以内の方が対象となります。
税務申告が2回未満の方には、特例措置が設けられています。
- 原則として、担保や保証人は不要
- 金利が一律で0.65%低く設定される
ただし、日本政策金融公庫・新宿支店は、都内の複数の自治体を管轄しているため、時期によっては電話がつながりにくいこともあります。スムーズに手続きを進めるため、必要に応じて税理士などの専門家のサポートを活用することも検討ましょう。
参考:日本政策金融公庫
新宿区で創業融資を受ける際の流れ
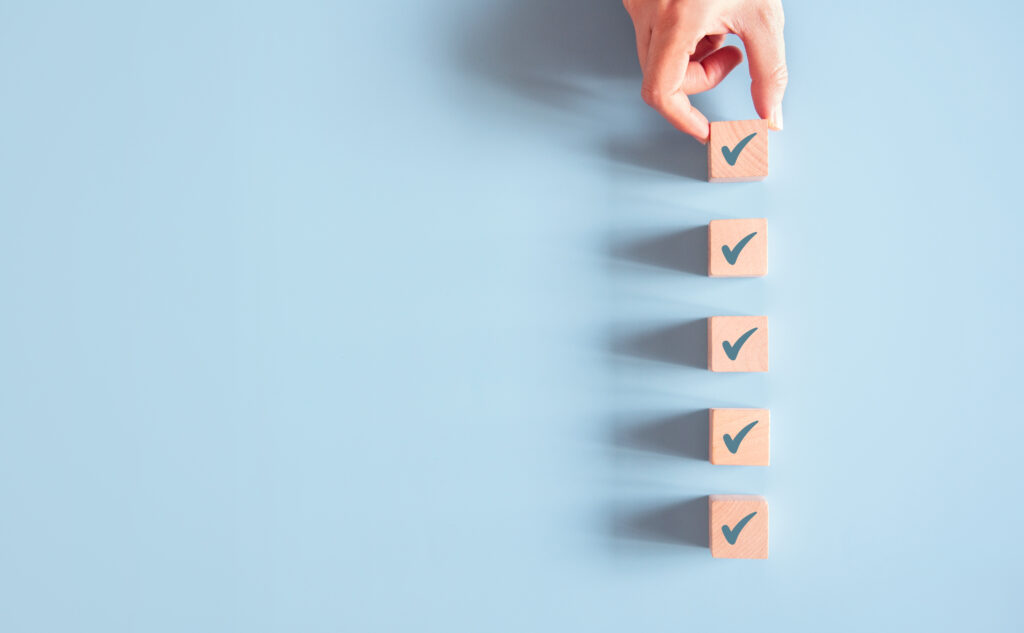
新宿区で創業融資を受ける際の流れについては、以下の通りです。
- 融資あっせん書の取得
- 融資申し込み
- 審査
- 保証協会で審査
- 融資実行
それぞれの項目について解説していきます。
融資あっせん書の取得
新宿区の創業融資を希望する場合、まず最初に必要なのが融資あっせん書の取得です。
そのためには、区の担当相談員との面談を事前に申し込む必要があります。
面談を受ける際には、法人または個人事業主で必要となる書類が異なります。
具体的に、必要な書類については、以下の通りです。
| 法人 | 個人事業主 | |
| 必要書類 | ・制度融資紹介申込書 ・法人事業税に関する納税証明書 ・代表者個人の住民税納税証明書 ・登記簿謄本 ・法人税の確定申告書 ・決算書 ・勘定科目内訳書 ・試算表 ・見積書(設備資金が対象の場合) ・法人実印 | ・制度融資紹介申込書 ・個人事業税の納税証明書 ・代表者本人の住民税納税証明書 ・住民票 ・所得税の確定申告書 ・設備資金に関する見積書 ・実印 |
書類が揃ったら、新宿区文化観光産業部産業振興課に連絡して面談予約を行います。
予約は電話で受け付けており、当日の予約は不可になっているので、事前に余裕を持って連絡するようにしましょう。
融資申し込み
新宿区から融資あっせん書を入手した後は、区と提携している創業支援に対応可能な金融機関に対して、融資の申請手続きを行います。
あっせん書には使用できる期限が設けられており、発行日から約1か月以内に申し込みを完了する必要があるため、期限をしっかり確認しておくことが重要です。
審査
融資の申し込みを行った金融機関においては、申請内容をもとに融資が可能かどうかの審査が実施されます。
この審査では、提出された事業計画や資金繰りの見通し、財務内容などが銀行の担当者によって詳細に確認されます。
また、審査にあたっては個別に必要となる書類が指定される場合もあるため、事前に金融機関の担当者へ確認しておくことが大切です。
審査に通過した場合には、金融機関が東京信用保証協会に対して保証申請の手続きを進める流れとなります。
金融機関での審査を終えた段階では、まだ正式に融資が決定されたわけではないので注意が必要です。
保証協会で審査
金融機関が東京信用保証協会へ保証の申し込みを行うと、東京信用保証協会で内容の審査が実施されます。
審査では、以下のような観点から申込者の状況が確認されます。
- 企業の財務内容
- 今後の業績予測や事業運営の計画
- 経営者の個人信用に関する情報
- オフィスや事業所の現地確認
また、審査の過程で、必要に応じて追加の書類提出を求められることがあるので、あらかじめ保証協会の担当者に確認しておくと安心です。
融資実行
融資申込後、取扱金融機関および東京信用保証協会による審査が完了すると、申込者は金融機関と金銭消費貸借契約を締結し、その後、融資金が指定口座に振り込まれます。
資金が入金された後は、あらかじめ決められた返済計画に基づいて、元本と利息の返済を進めていくことになります。
事業の休止・廃止や本店所在地の区外移転などがあった場合には、利子補給が打ち切られる可能性があり、結果として金利負担が増えるケースもありますので、事前にご確認ください。
新宿区の補助金

新宿区の補助金については、以下の3つが挙げられます。
- 特定創業支援等事業
- 新製品・新サービス開発支援補助金
- 産業雇用安定助成金
それぞれの補助金について解説していきます。
特定創業支援等事業
特定創業支援等事業は、補助金や助成金そのものではありませんが、区が指定するセミナーや講座、個別相談などのプログラムを修了することによって、いくつかの優遇措置を受けられる制度です。
例えば、指定された融資制度の利率優遇や一部の補助金・助成金の申請資格を得られるなどといった支援が用意されています。
対象となるのは、以下のいずれかに該当する方です。
- 今後6ヶ月以内に区内での創業を予定し、具体的な事業計画を持っている個人
- 区内で創業してから5年未満の個人事業主
- 区内に設立して5年未満の法人
- 個人事業から法人成りし、区内に会社を設立後5年未満の方
このプログラムを通じて、創業に必要な経営スキルや資金計画、人材育成、販路開拓などの知識を体系的に学ぶことができます。
こうした知識を身につけながら、さらに各種の優遇制度も活用できるので、効率的な支援策と言えます。
新製品・新サービス開発支援補助金
新製品・新サービス開発支援補助金は、地域内や同業種内で「革新的」と認められる取り組みに対して、審査の結果により最大100万円の補助金が交付されます。
評価は客観的な観点から行われ、独自性や新規性がポイントとなります。
補助金の対象となるプロジェクトの例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 新製品開発に向けた試作品の作成
- アプリケーションやシステムなど、革新的なソフトウェアの開発
- 新サービス展開のために必要な最新技術機器の導入
- 新製品に関する特許出願や取得
法人・個人を問わず申請可能で、必要書類を提出し、所定の審査を通過した事業者に補助が決定されます。
申請の受付期間はおおよそ1か月で、採択されるのは7件前後と、応募数に対して限られた枠となっています。
産業雇用安定助成金
産業雇用安定助成金は、業界や経済変動に対応するため、一時的事業縮小時に生産性向上策として人材受け入れを支援する国の助成制度です。
この制度では、受け入れた人材1人につき支給される金額が以下の通り定められています。(令和7年4月時点)
- 中小企業の場合:最大250万円
- 中小企業以外の企業:最大180万円
このように、人材不足や事業運営の困難を少しでも和らげるため、本助成制度は、企業の支えとなる重要な施策と言えます。
新宿区で創業融資の審査に通るためのポイント

新宿区で創業融資の審査に通るためのポイントについては、以下の5つが挙げられます。
- 融資希望額に応じた自己資金を準備する
- 説得力のある資金計画を立てる
- 現実的な内容を事業計画書に記載する
- 滞納や支払延滞をしない
- 事業経験をアピールする
それぞれのポイントについて解説していきます。
融資希望額に応じた自己資金を準備する
日本政策金融公庫から融資を受けるためには、希望する融資額に見合う自己資金を準備することが重要な要素となります。
一般的に、自己資金の3〜4倍程度まで融資されることが多いですが、これは目安であり金融機関によって異なります。
万が一、手元資金が不足している場合は、生活費を見直す、収入を増やすなど、自己資金を増やす方法を検討することも大切です。
説得力のある資金計画を立てる
新宿区で創業融資の審査に通るためのポイントとして、資金の使い道を具体的に示し、説得力のある資金計画を策定することが重要です。
資金用途が曖昧なままだと、融資の必要性が十分に伝わらず、審査に落ちる可能性や、希望額より少ない金額しか借りられないリスクがあります。
そのため、融資を受ける理由や使途を明確に記載し、見積書や資金繰り表といった資料を用いて具体的な裏付けを行うことが求められます。
さらに、起業・開業後の売上見込みや仕入れ、必要経費など資金の流れを可視化しておくことも大切です。
このように、審査担当者に対して「返済できる見込みが十分にある」と感じてもらえるよう、実現可能性の高い資金計画を立案するようにしましょう。
現実的な内容を事業計画書に記載する
新宿区で創業融資の審査に通るためのポイントとして、現実味のある事業計画書を作成することが重要です。
実行可能性の低い計画では、金融機関からの信頼を得ることは難しいので、どのような事業を展開するのかを明確かつ具体的に示すことが必須です。
例えば、事業の詳細な内容や既に取引が見込まれる企業リストを添付するなどして、計画の現実性を裏付ける材料をできるだけ多く盛り込むように心がけるようにしましょう。
滞納や支払延滞をしない
新宿区で創業融資の審査に通るためには、日常的な支払いの管理が重要です。
特に、税金や公共料金、各種ローンやクレジットカードなどの支払いで遅延や未納がないことは、審査においてプラス材料となる場合があります。
融資の申込みに際しては、申請者本人の信用情報も調査対象となるため、信用履歴にマイナス要素があると、融資の承認が難しくなることがあります。
そのため、これまでに支払いの遅れや滞納を経験した覚えがある方は、自分自身の信用情報を確認してみることをおすすめします。
事業経験をアピールする
審査を通過するためには、これから始める事業に関する知識や実務経験を示すことが有利に働きます。
例えば、以前に同じ業界で勤務していた経験がある場合や、事業に関連する職種に従事していた場合には、その実績が計画の信頼性を高める材料となります。
まったく新しい分野に挑戦するよりも、融資の審査を通過しやすくなる傾向があります。
また、経営経験がなくても、業界関連の職歴や専門資格の保有は、事業遂行の準備が整っていることを示す要素として評価される可能性があります。
新宿区の創業融資を上手く活用しよう!

今回は、新宿区で受けられる創業融資について紹介しました。
新宿区の創業融資を活用することで、一定の条件を満たせば、利子補給や補助制度により初期コストの一部を軽減できる可能性があります。
しかし、各融資には明確な対象要件が定められており、利用するには多くの書類提出や手続きが必要になります。
そのため、自分自身の状況に合った制度を選び、必要な手続きを漏れなく行うことが重要です。
本記事を参考に、ご自身の状況に合った創業融資を検討・活用してください。
‐免責事項‐
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。





