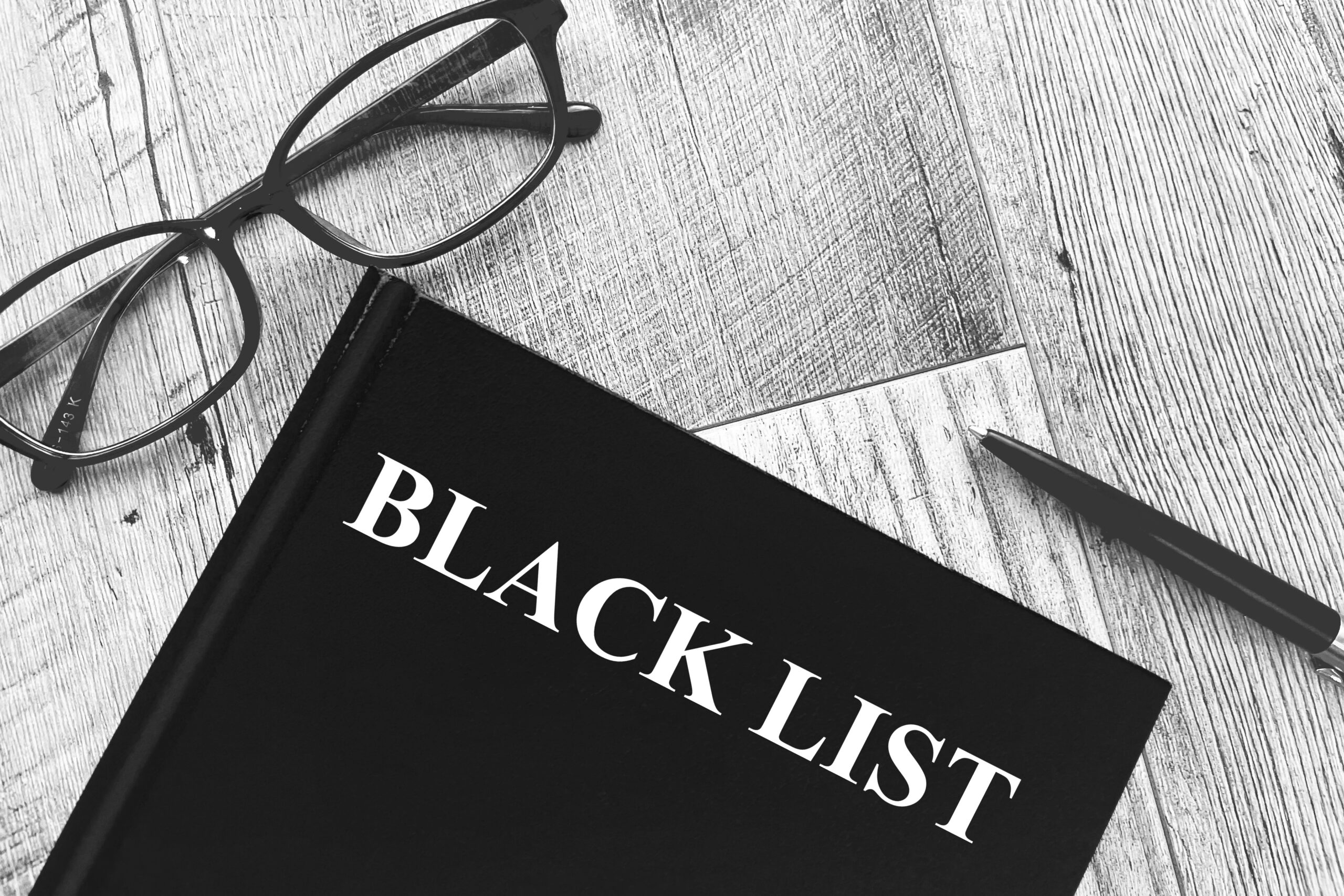メニュー
創業融資
協調融資とは何なのか?メリット・デメリットや成功させるコツについても徹底解説

読了目安時間:約 6分
協調融資とは、複数の金融機関が連携して、一つの企業や団体に対して融資を行うことを指します。
1社だけで融資が難しい場合でも、複数の金融機関が資金を分担して提供するので、より多額の融資を受けられる可能性が高まります。
本記事では、協調融資とは何なのかを紹介します。
他にも「協調融資を利用することのメリット・デメリット」や「協調融資を成功させるコツ」についても解説していきます。
ぜひ本記事を参考にして、協調融資への理解を深めてください。
目次
協調融資とは何なのか?

協調融資とは、複数の金融機関が連携して、1つの企業に対して資金を貸し出す方法です。
1つの金融機関だけで融資を行うのではなく、複数の機関が共同で取り組むことで、企業の資金ニーズに対応する仕組みです。
一般的には、大企業や中堅企業など比較的大規模な資金調達を目的としたケースが中心でしたが、近年では中小企業に対しても、このような形態での融資が広がりを見せています。
特に、日本政策金融公庫などの公的機関が民間の金融機関と連携して中小事業者を支援する事例が増えています。
協調融資には、主に以下の3つの形態があります。
- 日本政策金融公庫と民間金融機関による連携
- 商工組合中央金庫と民間金融機関の協力
- 複数の民間金融機関同士の連携
上記のうち、中小事業者にとって比較的利用しやすいのは、日本政策金融公庫と民間金融機関が連携するケースです。
参考:民間金融機関との連携の取り組みについて|日本政策金融公庫
協調融資を利用するメリット
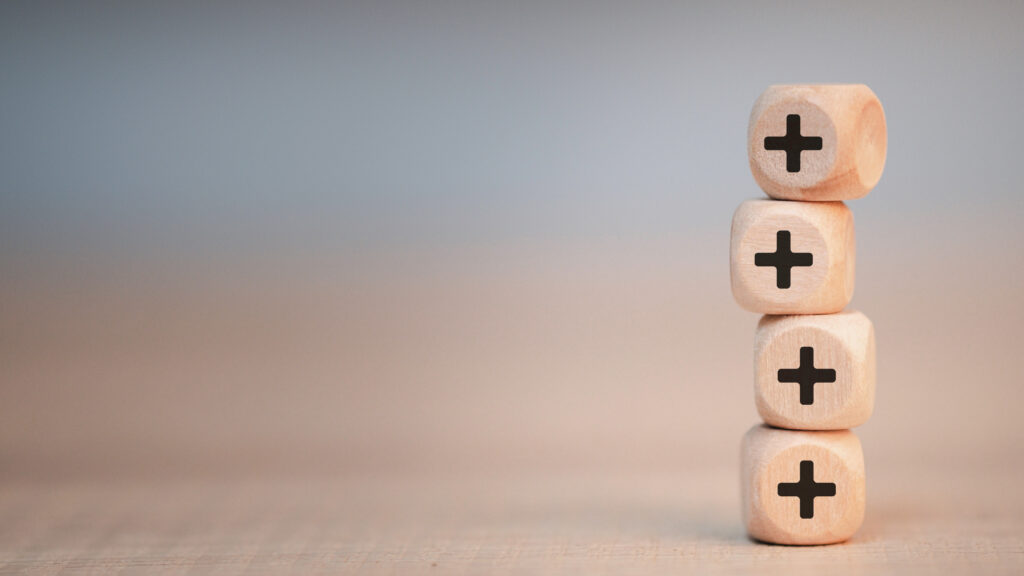
メリットについては、以下の4つが挙げられます。
- 創業時でも融資を受けやすくなる
- 多額の資金を調達しやすい
- 手続きの手間を減らせる
- 資金調達先の幅が広がる
それぞれのメリットについて解説します。
創業時でも融資を受けやすくなる
協調融資の活用によって、創業期であっても一定の要件を満たせば融資の実行につながる可能性があります。
民間の金融機関は新規開業や経営再建中の企業に対しては融資に慎重な姿勢を見せることが多く、融資審査が通りづらいのも事実です。
日本政策金融公庫は預金業務を行わず、政府系の金融機関として起業初期や再建途上の中小企業に対して積極的に融資を行っています。
そのため、日本政策金融公庫との協調融資や信用保証協会による保証付きの融資を組み合わせることで、民間銀行側も貸し倒れのリスクを軽減でき、融資の実行に踏み切りやすくなります。
このように、協調融資を利用することで、新たにビジネスを始めるスタートアップ企業でも、資金面での安心感を持ちながらスムーズに融資を受けられます。
ただし、創業者に対する融資は依然として慎重な審査が求められるため、実現性の高い事業計画や自己資金の有無などが大きな判断材料となります。
多額の資金を調達しやすい
協調融資を活用すると、多額の資金を比較的調達しやすいというメリットが挙げられます。
一般的に、必要な金額が多くなると、一つの金融機関だけで全額を借り入れるのは困難になることがあります。
しかし、複数の金融機関が協力して融資を行う「協調融資」ならば、それぞれの金融機関が一部ずつを分担するため、希望額に応じた借入がしやすくなります。
また、金融機関側にとっても、貸付リスクが分散されることで、慎重な審査を経たうえでも前向きな融資判断がされやすくなります。
その結果、単独の金融機関での申し込みでは通らなかった融資も、協調融資を通じて実現するケースも多くあります。
手続きの手間を減らせる
協調融資では、代表行(アレンジャー)を通じて手続きを進めるため、ある程度の書類の共通化や調整が可能です。(金融機関ごとに個別対応が求められる場合もあります。)
例えば、複数の銀行から個別に資金を調達しようとする場合、それぞれの金融機関に対して個別に連絡を取り、書類の準備や提出を行う必要があります。
一方で、協調融資を活用すれば、通常は代表となる銀行とのやり取りだけで済みます。
提出書類も多くの場合、形式が統一されているため、煩雑な準備を避け、スムーズに融資手続きを進めることが可能です。
ただし、複数の金融機関が関与するため、ケースによっては調整や確認作業が増える場合もあり、事前準備が重要です。
資金調達先の幅が広がる
協調融資を利用することで、資金調達先の幅が広がるメリットも挙げられます。
具体的には、複数の金融機関に対して融資の申し込みを行い、借入の実績を積み重ねることで、将来的な資金調達の手段を広げられます。
実際に、事業を進展させる中で、成長戦略の一環として設備導入や規模拡大に多額の資金が求められる場面も出てきます。
こうしたとき、複数の金融機関と継続的な関係を築いておけば、資金調達の選択肢が増え、結果的に融資を受けやすくなる可能性が高くなります。
協調融資を利用するデメリット

デメリットについては、以下の2つが挙げられます。
- 融資審査に時間がかかる
- 融資が利用できない場合もある
それぞれのデメリットについて解説していきます。
融資審査に時間がかかる
協調融資のデメリットとして、手続きに要する時間が比較的長くなることが挙げられます。
単独での融資であれば、一つの金融機関とのやり取りで済むためスムーズに進めることができますが、協調融資の場合は複数の金融機関が関与するため、調整や審査に時間がかかってしまう傾向があります。
例えば、日本政策金融公庫から単独で融資を受ける場合、利用する制度にもよりますが、通常は融資が実行されるまでに約1か月とされています。
一方、協調融資では複数の機関との連携が必要となるため、資金が手元に届くまでに2~3か月ほどかかるケースも珍しくありません。
そのため、協調融資を利用して資金を調達したい場合は、必要な時期に遅れないよう、十分な時間的余裕をもって準備・申請を行うことが重要です。
融資が利用できない場合もある
他の融資でも同じことが言えますが、必ずしも資金調達が成功するとは限らないデメリットが挙げられます。
実際に、協調融資で借入を希望しても、金融機関との合意に至らなければ資金は得られません。
複数の金融機関が連携して融資を行う仕組みであるため、その中のどの金融機関からも承認が得られなければ、全体としての融資成立が難しくなる場合があります。
場合によっては、融資そのものが断られてしまったり、希望金額よりも少ない額でしか承認されないといったケースもあります。
協調融資を成功させるコツ

協調融資を成功させるコツについては、以下の5つが挙げられます。
- 実現可能な事業計画書を作成する
- 金融機関と信頼関係を築く
- 支払いの遅延や滞納をしない
- 自己資金を準備する
- 資金の使い道を明確にする
それぞれのポイントについて解説していきます。
実現可能な事業計画書を作成する
協調融資を成功させるコツとして、具体性と実現性を備えた実現可能な事業計画書の作成が挙げられます。
事業計画書は、今後の展望を明確に示し、金融機関に対して将来の成長性を伝える重要な資料です。
成長戦略に必要な設備投資や資金活用の内容はもちろん、市場動向や競合状況、顧客ターゲットの分析結果などを基に、収支予測を立てることが求められます。
また、信頼性を高めるには、収支に関する数値の裏付け資料を併せて提出するのが効果的です。
金融機関と信頼関係を築く
協調融資を成功させるコツとして、金融機関と信頼を築くことが挙げられます。
実際に、複数の金融機関が関与する場合でも、中心的な役割を果たす主要取引銀行との連携が取れていなければ、融資の実現は難しくなります。
そのため、融資が必要なときだけに接触するのではなく、日頃から銀行担当者と継続的に情報交換を行い、良好な関係性を築いておく姿勢が求められます。
また、経営環境や事業方針に変化が生じた際には、その都度迅速に報告し、必要な書類や資料の提出を丁寧に行うことが、信頼感を高めることにつながります。
支払いの遅延や滞納をしない
協調融資を受ける際には、自身の信用を損なわないように支払いの遅延や滞納をしないように心がけることが重要です。
特に、ローンの返済遅延や税金・公共料金の未払いは、信用情報に悪影響を及ぼしてしまうので注意が必要です。
支払いや返済を期限内に確実に行っていれば、信用上の評価が下がることはありません。万が一返済が滞ると、その記録は個人信用情報機関に「事故情報」として登録され、将来的な融資に不利となります。
税金や光熱費などの公共料金の支払いも、基本的な経済的責任とみなされており、これを怠ると返済能力に疑問を持たれる要因となります。
そのため、常日頃から返済や支払いの管理を徹底し、信用に傷をつけないよう努めることが、協調融資を成功させるポイントとなります。
参考:初めての融資と信用保証
自己資金を準備する
事業を始めるにあたって、自己資金の有無は、その人がどれほど真剣に取り組んでいるかを示す大切な指標となるので、自己資金を準備しておきましょう。
金融機関は、起業者が自身の資金を投入しているかどうかをチェックし、事業への本気度を見極めます。
しかし、家族や友人からの借入金は、自己資金として認められない場合が多いため、あらかじめ注意が必要です。
このように、できる限り自身の資金を用意しておくことで、融資の審査に通るための大きな後押しとなります。
資金の使い道を明確にする
協調融資を成功させるコツとして、資金の使い道を明確にすることが挙げられます。
実際に、融資を申し込む際には、その金額に妥当性があるかどうかが重要な判断材料となります。
貸し手の立場からすれば、「どのような目的で、どの程度の資金を必要としているのか」がはっきりしていなければ、安心して融資することはできないのも事実です。
そのため、資金使途と申込額との間に整合性が見られない場合、融資審査を通過するのは難しくなる可能性があります。
協調融資を利用する際の注意点

協調融資を利用する際の注意点については、以下の2つが挙げられます。
- 再挑戦には時間と改善が求められる
- スケジュールが煩雑になりやすい
それぞれの注意点について解説していきます。
再挑戦には時間と改善が求められる
協調融資の審査に落ちてしまうと、再挑戦には時間と改善が求められる点に注意が必要です。
保証協会付きの融資が却下されると、他の金融機関で申請しても同様の結果になる可能性が高くなることが考えられます。
これは、保証協会の審査情報が他の銀行とも連携されているので、再申請しても審査の土台が変わらないからと言えます。
再び融資に挑戦するには、不承認となった理由をしっかりと分析し、それに対する改善策を講じた上で、おおよそ半年程度の期間を空けてから、再度申請することをおすすめします。
スケジュールが煩雑になりやすい
協調融資を利用する際には、複数の金融機関と同時に調整を図る必要があるため、スケジュールが煩雑になりやすいので注意が必要です。
それぞれの金融機関が求める書類の種類や内容が異なり、手続きの進行速度にもばらつきが生じがちなのも事実です。
例えば、設備の手配や人材の採用といった事業計画の進行に対して、融資のタイミングが合わず、開業や事業の立ち上げに遅れが出るケースも見受けられます。
このように、協調融資を利用する際には、スケジュールが煩雑になりやすいので、しっかりとスケジュールを管理することが重要と言えます。
協調融資で資金調達を成功させよう!

今回は、協調融資とは何なのかについて紹介しました。
協調融資は、複数の金融機関が共同で資金を貸し付ける仕組みです。
日本政策金融公庫では、多様な民間金融機関と連携し、この協調融資の導入を積極的に進めています。
この制度を利用することで、一つの金融機関からの融資では難しい大口資金の調達が可能となり、手続きの一部も簡略化されるというメリットがあります。
一方で、資金実行までにはある程度の期間を要し、審査が通らない可能性もあるので、協調融資を検討する際には、メリットだけでなくデメリットや注意点についても事前に理解しておくことが大切です。
本記事を参考に、協調融資の成功に向けて着実に準備を進めましょう。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。