メニュー
起業・開業
出資と融資の違いとは何か?出資の受け方や融資の種類についても徹底解説
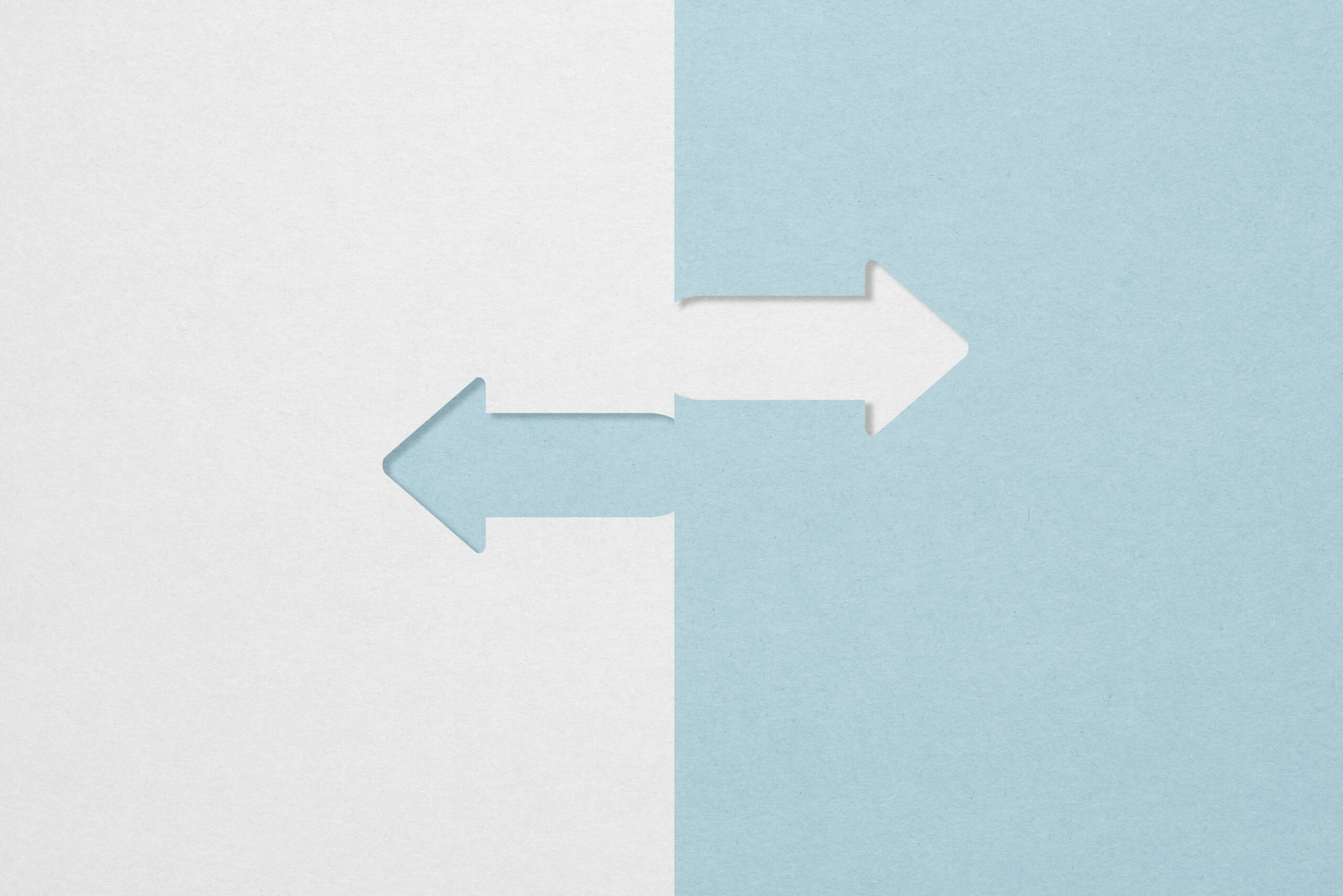
読了目安時間:約 7分
事業資金を調達する方法にはさまざまな手段がありますが、その中でも代表的なのが「出資」と「融資」です。どちらも資金を提供してもらう点では共通していますが、資金提供者との契約上の関係性や、返済義務の有無など重要な違いがあります。
簡単に言えば、融資には返済義務があり、出資には返済義務がないという点が最大の違いです。また、資金提供者への対応や関係構築の方法も大きく異なります。
出資と融資の違いを正しく理解し、事業の状況や目的に応じて最適な資金調達方法を選ぶことが、資金活用の成否を分ける鍵となります。
本記事では、出資と融資の違いをわかりやすく解説するとともに、出資を受ける際のポイントや、融資の主な種類についても紹介いたします。
ぜひ、資金調達の選択にお役立てください。
目次
出資と融資の違いとは何か?

出資とは、企業や事業活動に対して、金銭や不動産などの資産を提供する行為を指します。法的には、金銭の出資のほか、不動産や設備などの現物出資も認められますが、労務や信用といった無形の提供は、出資とはみなされない点に注意が必要です。
出資する側は、将来的なリターンを期待して、金銭や財産を企業へ投じており、出資額の大小にかかわらず、利益を見込んで資本を提供する行為全般が「出資」と呼ばれています。
一方、融資とは、資金を貸し出すことであり、貸した側は返済を前提としています。
融資は企業に「借入金」として負債計上されますが、出資は「資本金」として企業の自己資本を形成します。
そのため、出資と融資は似ているようで本質が異なるので、それぞれの性質を理解し、適切な選択を行うことが事業運営の成功につながります。
具体的に、出資と融資の違いについては、以下の9つが挙げられます。
- 資金提供者
- 資金提供の目的
- 重要視している点
- 返済義務の有無
- 保証人や担保の有無
- 対象となる企業
- 経営の自由度
- 難易度
- 金額
それぞれの項目について解説していきます。
資金提供者
出資の資金提供者は、主にエンジェル投資家やベンチャーキャピタルといった投資家層です。
エンジェル投資家は、主に起業初期の企業や起業家を、個人の資金で支援する投資家です。
一方、ベンチャーキャピタルは、将来的な成長が見込まれる企業に特化して資金を提供する法人組織であり、スタートアップ企業などに対して専門的に出資を行います。
融資における資金提供者としては、主に銀行や信用金庫、日本政策金融公庫などの公的な金融機関が挙げられます。
これらの機関は、返済を前提として企業や個人に資金を貸し付ける役割を担っています。
資金提供の目的
出資における資金提供者の目的は、その企業が成長していく中で得られる利益が挙げられます。
具体的には、提供した資金の対価として企業の株式を取得し、その株式に対する配当を通じて収益を得る可能性があります。
また、企業価値が上がれば保有する株を売却してキャピタルゲイン(差益)を得ることも視野に入れています。
エンジェル投資家やベンチャーキャピタルのように、高いリスクを引き受けつつも、大きな成果を目指す投資形態です。
一方、融資の資金提供の目的は、貸した資金に対する利息収入を見込んでいます。
主に銀行や金融機関が担い、返済の確実性が何より重視されます。
そのため、融資先は安定した経営基盤があり、返済能力に信頼のおける企業に限定されやすく、収益よりも、安全性や安定したリターンを重視する傾向があります。
重要視している点
出資を行う際、投資家は企業の将来性や成長ポテンシャルを重視しています。
特に、新しいアイデアや革新的な技術を持ち、高い成長が見込める事業に対しては、大きな収益を得られる可能性があると見て出資をしているケースも多いです。
一方で、融資に関しては返済能力の確かさが重要視されます。
貸し倒れのリスクを避けるため、安定した売上や利益を出している企業、あるいは明確なビジネスモデルと収益計画を持つ企業が、金融機関から評価されやすいです。
返済義務の有無
出資は、一般的に返済義務がない資金調達手段とされています。
そのため、融資と異なり返済資金の確保を必要としない点が特徴です。ただし、出資契約によっては将来的な買い取りや利益分配の取り決めがある場合もあるため、契約内容の確認は重要です。
一方で、融資を受けた場合には原則として返済の責任が生じます。
したがって、事業の運営においては、まず借入金の返済に充てるための資金を確保し、一定の安定収入を維持する体制づくりが求められます。
保証人や担保の有無
出資を受ける場合、原則として担保や保証人の提供は不要です。
出資者は、将来的なリターンを見込んで資金を提供するため、返済義務のない資金調達手段として位置づけられます。一方で、出資者側にとっては、成果が得られないリスクも伴います。
一方、融資を受ける際には、一般的に担保や保証人が求められることが多いです。
これは、返済が困難になった場合の損失を回避するための安全策として機能します。ただし、すべての融資において担保や保証人が必要というわけではありません。
例えば、日本政策金融公庫が実施する創業融資などでは、一定の条件を満たせば担保や保証人を不要とする制度も設けられています。こうした制度を活用することで、創業期の事業者でも比較的利用しやすい資金調達が可能となります。
参考:挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)|日本政策金融公庫
対象となる企業
出資の対象となる企業は、多くの場合、革新的なサービスや技術を持ち、将来的に大きな市場拡大が見込まれるスタートアップや新興企業が挙げられます。
実際に、エンジェル投資家やベンチャーキャピタルといった出資者が、高い利益を見返りとして期待していることが理由になります。
特に、未開拓な市場や最先端技術に関わる企業は急速な成長を遂げやすく、出資が成功すれば、初期投資額に対して非常に大きな利益を生む可能性があります。
一方、融資を受ける対象の企業は、すでに一定の業績を上げており、安定した収益構造を持っていることが重要視される傾向があります。
銀行や信用金庫などの金融機関は、貸し出した資金が確実に返済されることを前提に融資判断をおこなうため、堅実で継続性のあるビジネスを展開している企業が主な対象となります。
参考:
・日本エンジェル投資家協会
・一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会
経営の自由度
資金を提供してくれる出資者は、その対価として株式を受け取ることができるので、会社の経営に一定の発言力を持つことになります。
エンジェル投資家のような出資者は、多くの企業支援の実績を持っており、経営面で貴重な助言を得られる可能性があります。
しかし、そうした出資を受け入れることで、自社の意思決定の自由が一部制限されるリスクがあるのも事実です。
融資による経営への影響については、会社の経営方針や意思決定に口出しされることは基本的にありません。
そのため、経営の自主性は守られますが、借入金は返済義務を伴い、財務的なプレッシャーが重たくなってしまうので注意が必要です。
難易度
出資を受けるには相応の難しさが伴います。
理由としては、投資家が企業の将来的な成長性や独自性のあるビジネス戦略に強く注目する傾向があるからです。
革新性の高いサービスや技術を備えていれば注目を集めやすいものの、優れた競合も多いので、資金提供を得るには明確な差別化と魅力的なアピールが求められます。
一方で、融資も簡単に得られるものではありませんが、企業の信用力や収益の安定性がしっかりしていれば、有力な資金調達手段となります。
ただし、創業初期や事業実績が乏しい場合は、審査が厳しくなることもあるため、状況に応じた資金調達方法の検討が必要です。
金額
出資金額は、投資家がその企業にどれだけの成長性を見込むかによって大きく左右されます。
スタートアップなどでは、数百万円から数千万円程度が一般的な目安とされています。
一方で、将来的に大きな拡大が期待されるビジネスには、数億円に達するような多額の出資がおこなわれるケースもあります。
事業の将来性が高く評価されるほど、大きな資金を引き出す可能性も高まります。
融資額については、提出された事業計画や業績の見通し、信用状況などをもとに決定されます。
多くの中小企業では、融資金額は数百万円から数千万円程度に収まるのが一般的です。
ごく一部ではありますが、信用度が高い企業であれば、銀行などの金融機関から数億円規模の融資を受けるケースもあります。
出資の受け方とは

出資者や出資の受け方にはさまざまな形態が存在するため、それぞれの特徴をしっかりと理解し、比較することが重要です。
具体的な出資の受け方については、以下の3つが挙げられます。
- 受け方①:エンジェル投資家(個人投資家)
- 受け方②:ベンチャーキャピタル
- 受け方③:クラウドファンディング
それぞれの受け方について解説していきます。
受け方①:エンジェル投資家(個人投資家)
個人投資家は、個人の判断で支援を行う投資家のことを指します。
特に創業間もないスタートアップやベンチャー企業を支援する投資家は「エンジェル投資家」と呼ばれています。
エンジェル投資家の中には、経済的リターンだけでなく、起業家のビジョンや社会的意義に共感して出資する方も見受けられます。ただし、出資者としては何らかの成果を求めるのが一般的です。
このような支援は、資金の返還や株式の買い戻しを強く求められることが少ないため、起業家側にとってはリスクが比較的少ない資金調達手段と言えます。
受け方②:ベンチャーキャピタル
ベンチャーキャピタルとは、設立間もない企業や革新的なスタートアップに重点的に資金を提供する投資会社のことを指します。
こうした企業は独立して運営されることもありますが、銀行や証券会社のグループ企業として活動しているケースも少なくありません。
将来的な成長が期待できる企業に対し、大きなリスクを取りながら資金提供を実施し、上場や企業買収によって投資益を得ることを目指しています。
資金を受ける側にとっては、借入とは異なり返済義務がないことや通常の銀行融資よりも多くの資金を得やすいというメリットがあります。
しかし、出資契約の条件が厳しかったり、出資に見合う成果が求められたりするケースがあるので注意が必要です。
受け方③:クラウドファンディング
クラウドファンディングとは、ネットを通じて多くの人々から少しずつ資金を集める資金調達の仕組みです。
具体的にクラウドファンディングには、以下のように4つのタイプがあります。
| クラウドファンディングのタイプ | 特徴 |
| 購入型 | 支援者に対して、代わりに商品やサービスを提供する形式 |
| 寄付型 | 金銭的な見返りを求めずに、純粋に支援を募る方法 |
| 株式投資型 | スタートアップなどが未上場株式を投資対象とし、資金提供を受ける方式 |
| ファンド投資型 | 特定のプロジェクトに対する投資で、売上などの成果に応じた利益の分配を行うスタイル |
しかし、資金が集まらないリスクもあるので、事前にどれほどの支援が期待できるのかを見極めたり、目標未達時の対応策を考えておくといった準備が重要です。
融資の種類とは

融資の種類については、以下の3つが挙げられます。
- 種類①:日本政策金融公庫の融資
- 種類②:制度融資
- 種類③:ビジネスローン
それぞれの種類について解説していきます。
種類①:日本政策金融公庫の融資
日本政策金融公庫は、企業活動を後押しすることを目的とした政府系の金融機関であり、民間の銀行や信用金庫などが提供するサービスを補完する役割を担っています。
一般に、民間の金融機関よりも比較的低い金利で融資が受けられるので、資金調達時の利息負担を軽減しやすいのがメリットです。
一定の条件のもとで担保や保証人なしで融資が可能で、資金を得やすい制度として注目されています。
しかし、利用条件や審査基準は厳格であり、申し込みの内容や条件によっては、審査に時間がかかることもあります。資金が必要なタイミングに間に合わないケースもあるため、急ぎの場合は他の手段も考慮しましょう。
参考:日本政策金融公庫
種類②:制度融資
制度融資とは、地域の中小企業が円滑に資金調達をおこなえるよう、自治体・金融機関・信用保証協会の三者が協力して提供する支援制度です。
信用保証協会は、公的な機関であり、中小規模の事業者が銀行などから資金を借りやすくするために「保証人」の役割を果たします。
この制度を活用する場合、利用者は保証協会へ保証料を支払う必要がありますが、自治体によってはその費用の一部を助成する仕組みも用意されています。
基本的に、その地域で事業を行っている中小企業が対象となります。
また、日本政策金融公庫の融資制度と同様に、比較的金利が低く、創業直後の企業にも利用しやすいのが特徴です。
しかし、複数の機関が関与するため、手続きにはある程度の時間がかかってしまうデメリットがあります。
参考:東京都中小企業制度融資
種類③:ビジネスローン
ビジネスローンとは、企業活動に必要な資金を確保するための融資制度です。
住宅や車両の購入に用いられるローンとは異なり、ビジネスローンは開業資金や運転資金など多様な企業経営資金ニーズに迅速に対応可能な融資手段です。
特長として、申請のハードルが比較的低い点にあります。
銀行融資と比べて審査の基準が緩やかで、通常は担保や保証人が求められず、審査結果も迅速に出されるケースが多いです。
一方で、適用される金利がやや高く、融資可能な金額に上限があるというデメリットもあります。
他の融資制度と比較して、慎重に検討することが重要です。
資金調達の目的に応じて適切な方法を選びましょう

今回は、出資と融資の違いについて紹介しました。
出資と融資は、全く異なる資金調達の方法です。
それぞれにメリットとデメリットがあり、どちらが優れているかというよりも、用途や企業の状況に応じて最適な選択をすることが求められます。
資金調達を検討する際には、それぞれの特徴を理解し、ビジネスを展開する際の判断材料にすることをおすすめします。
今回の記事を参考にして、資金調達の目的に応じて出資か融資を選ぶようにしましょう。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。





