メニュー
起業・開業
社長は社会保険に入れないのか?必要な手続き・書類や入らなかった場合のペナルティも紹介

読了目安時間:約 6分
法人を設立すると、原則として健康保険・厚生年金の適用事業所となり、加入義務が発生します。ただし、役員報酬が発生していない場合など、実態により被保険者資格が認められないケースもあります。
本記事では、社長は社会保険に入れないのかについて紹介します。
他にも「社長が社会保険加入時に必要な手続き・書類」や「社長が社会保険に入らなかった場合のペナルティ」についても解説していきます。
ぜひこの記事を参考にして、社会保険について理解を深めてみてください。
目次
社長は社会保険に入れないのか?

社長であっても、社会保険への加入が求められます。
社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険など複数の公的保険制度を総合的に指します。
一般的に、社会保険というと、健康保険と厚生年金保険の2つを指して使われることが多く、これらは法律によって事業所単位での加入が義務づけられています。
健康保険における被保険者の定義は「適用事業所に使用される者」であり、従業員だけでなく会社の代表者である社長もその対象に含まれます。
たとえ社長一人で運営している法人であっても、社会保険への加入が求められるのです。
しかし、社長で社会保険への加入が不要なケースもあります。
具体的に、社長が社会保険への加入が不要なケースについては、以下にて解説していきます。
参考:健康保険法 | e-Gov 法令検索、厚生年金保険法 | e-Gov 法令検索
労災保険が不要なケース
労災保険は、原則として労働者を雇用している事業主に加入義務がある制度です。
そのため、労働者を一切雇用していない場合や、法人代表者(社長)のみで事業を行っている場合には、労災保険の加入義務はありません。
具体的には、以下のようなケースでは労災保険は不要です。
- 従業員を雇っていない個人事業主
- 社長1人で経営している法人(役員のみの会社)
- 家族だけで運営しており、労働者を雇用していない場合
なお、これらのケースでは労災保険の強制加入は不要ですが、現場作業や危険を伴う業務に従事する場合は「特別加入制度」を利用して任意で加入することが可能です。
加入の要否や必要性は、事業の内容や働き方によって異なるため、具体的な状況に応じて労働基準監督署などに相談すると安心です。
参考:労災補償 |厚生労働省、雇用保険法|厚生労働省、労災保険への特別加入 |厚生労働省
雇用保険が不要なケース
雇用保険は、労働者を雇用している事業に加入義務が生じる制度です。
したがって、労災保険と同様に、労働者を一切雇用していない場合や、法人の代表者(社長)や役員のみで運営している場合には、雇用保険への加入義務はありません。
これらのケースでは雇用保険の強制加入は不要ですが、事業拡大に伴い従業員を雇用した時点で加入義務が発生します。そのため、将来的に雇用を予定している場合は、制度の内容を事前に理解しておくことが大切です。
社長が健康保険・厚生年金加入時に必要な手続き・書類

会社設立後には、社会保険への加入が必要になり、期限が定められています。
特に、健康保険と厚生年金保険については、設立後5日以内に手続きを済ませなければならないので、早めの対応が求められます。
具体的に、社長が健康保険・厚生年金加入時に必要な手続き・書類については、以下の3つが挙げられます。
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届
それぞれの項目について解説していきます。
健康保険・厚生年金保険新規適用届
健康保険・厚生年金保険 新規適用届とは、企業が初めて健康保険および厚生年金保険に加入する際に提出が求められる手続き書類です。
申請をおこなう際には、適用届のほかに、発行日が提出日から90日以内である「会社の登記簿謄本(原本)」の添付が必要です。
また、登記上の本店所在地と実際の事業所の所在地が異なる場合には、実際の所在地を確認できる書類も添付資料として必要になります。
申請書の記載方法や提出書類の詳細は、日本年金機構の公式サイトに記載されているので、事前に確認しておきましょう。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届は、新たに従業員を雇い入れた際に、その人が健康保険および厚生年金の被保険者となるために必要な手続き書類です。
この届出は、会社に所属するすべての対象者について提出する必要があります。
提出に必要な申請書は、日本年金機構の公式サイト内にある該当ページからダウンロード可能です。
健康保険被扶養者(異動)届
社長に配偶者・子ども・親などの扶養親族がいる場合、「健康保険被扶養者(異動)届」の提出が必要です。
この申請用紙は、日本年金機構の公式サイト内「被扶養者(異動)届」ページよりダウンロード可能です。
扶養親族との関係性を確認するために、提出日から起算して90日以内に発行された戸籍謄本または住民票の添付が求められます。
また、所得税法上の扶養に該当しない親族を健康保険上の扶養とする場合や、被扶養者の個別事情に応じて、追加の書類提出が必要となることがあります。
社長が雇用保険加入時に必要な手続き・書類

雇用保険制度は、働く人々の生活の安定や、再就職をスムーズに進めるために、失業時に給付金を支給する仕組みです。
企業がこの制度に関する手続きをおこなう際は、事業所の所在地を所管するハローワークに届け出をおこなう必要があります。
雇用保険の対象となるのは、週の決まった勤務時間が20時間以上であることと、雇用期間が31日以上見込まれている条件を満たしている従業員です。
この条件を満たす場合は、たとえパートタイマーやアルバイトであっても、雇用保険の加入対象となります。
具体的に、社長が雇用保険加入時に必要な手続き・書類については、以下の2つが挙げられます。
- 雇用保険適用事務所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
それぞれの項目について解説していきます。
雇用保険適用事務所設置届
会社設立後、雇用保険の対象となる従業員を採用した場合には、その時点で「雇用保険適用事業所」としての手続きが求められ、従業員を雇用保険に加入させる義務が発生します。
手続きの際には、労働基準監督署で受理された「労働保険関係成立届」の事業所控えに加え、実際の雇用状況や賃金支払いの事実を示す書類の提出が必要です。
具体的には、労働者名簿、雇用契約開始から現在までの賃金台帳、出勤記録など雇用の実態を裏付ける資料が求められるので、事前に揃えておくようにしましょう。
雇用保険被保険者資格取得届
従業員の中に雇用保険への加入が必要な方がいる場合は、「雇用保険適用事業所設置届」を所定の期日までに提出する必要があります。
この届出は、該当従業員の資格取得日が属する月の翌月10日までに、管轄のハローワークに届け出が必要になります。
また、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することで、「雇用保険資格取得等確認通知書」が発行されます。
社長が労災保険加入時に必要な手続き・書類

労災保険とは、従業員が仕事中や通勤途中に負傷したり、病気や死亡した場合に、必要な補償を行う制度です。
正式には「労働者災害補償保険」と呼ばれており、働く人々とその家族の生活を守るために設けられています。
また、一人で事業を行っている社長自身は、原則として労災保険の対象外です。
しかし、従業員を雇うことになった場合には、その時点で加入手続きが必要になります。
また、建設業の一人親方など、業務中にケガをする可能性が高い職種の方は、「特別加入制度」を利用して労災保険に加入することが可能です。
具体的に、社長が労災保険加入時に必要な手続き・書類については、以下の2つが挙げられます。
- 保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
それぞれの項目について解説していきます。
保険関係成立届
労働保険の対象となる事業所として認定された場合には、「保険関係成立届」の提出が義務付けられます。
保険関係成立届は、労働基準監督署またはハローワークのいずれかにおこなう必要があります。
また、届出の期限は、保険関係の成立日から数えて10日以内です。
提出にあたっては、法人の登記事項証明書(原本)を添付する必要がありますので、事前に準備しておくことをおすすめします。
労働保険概算保険料申告書
労働保険の保険関係が新たに成立した場合には、その年度にかかる労働保険料を「概算保険料」として納める必要があり、その際に使用される書類が「労働保険概算保険料申告書」です。
労働保険概算保険料申告書とは、保険関係の開始日から数えて翌日より50日以内に提出しなければならず、その際に概算保険料も一緒に納付します。
労災保険料は、支払う賃金総額に対して、所定の労災保険料率を掛けて算出されます。
しかし、保険料率は事業の種類ごとに異なっているので、厚生労働省が公開している「労災保険料率表」を参考にすることをおすすめします。
社長が社会保険に入らなかった場合のペナルティ

社長が社会保険に入らなかった場合のペナルティについては、以下の4つが挙げられます。
- 過去2年間の保険料を徴収される
- 罰金が課される
- ハローワークに求人を出すことができない
- 補助金・助成金が受けられなくなる
それぞれのペナルティについて解説していきます。
過去2年間の保険料を徴収される
社長が社会保険に入らなかった場合のペナルティとして、過去2年分までさかのぼって保険料を徴収されることがあります。
さらに、社会保険での警告を受け取った後も加入手続きを取らずにいると、最終的には年金事務所の職員が事業所へ直接訪問し、調査をおこなうことになります。
この調査は法律に基づいておこなわれるので、事業主はこれを拒否することはできません。
また、指定された納付期限までに支払いが完了しないと督促状が発行され、期日を過ぎても未納が続く場合には延滞金が発生する点にも注意が必要です。
罰金が課される
社長が社会保険に未加入のまま事業をおこなっている場合、罰金が課されてしまうリスクがあります。
具体的には、健康保険法第208条により、最悪の場合、50万円以下の罰金や最長6カ月の懲役が科される可能性もあり得ます。
これらの罰則はすぐに適用されるわけではなく、特に悪質と判断されるケース、例えば虚偽の報告をしたり、行政からの複数回の加入勧告を無視し続けた場合には、法的措置が取られる可能性が高くなります。
また、取引先や顧客の信頼を失い、事業継続が困難になるリスクもあるため、社会保険への適正な加入は経営上の重要なポイントといえます。
ハローワークに求人を出すことができない
社会保険に未加入の企業は、原則としてハローワークでの求人掲載に制限を受ける場合があります。
ハローワークは、費用をかけずに利用できる公的な就職支援機関であり、その利用を通じて各種の助成金や補助金を申請することも可能です。
企業が成長を続けていくためには、必要に応じて人材の確保が求められます。
そのため、社会保険未加入の状態が理由で、有望な人材の採用機会を逃すことがないよう注意が必要です。(詳細は最寄りの管轄ハローワークに確認を推奨します。)
補助金・助成金が受けられなくなる
社会保険に未加入のままだと、資金調達面で不利になる可能性があります。
実際に、多くの補助金や助成金の制度では「社会保険および雇用保険の適用事業所であること」が支給要件として設定されているので、保険未加入の状態では申請自体ができないことがあります。
このように、開業時には準備費や仕入れ資金など出費がかさむので、補助金や助成金が受けられるようにしっかりと社会保険に加入するようにしましょう。
忘れずに社会保険の手続きをしよう!
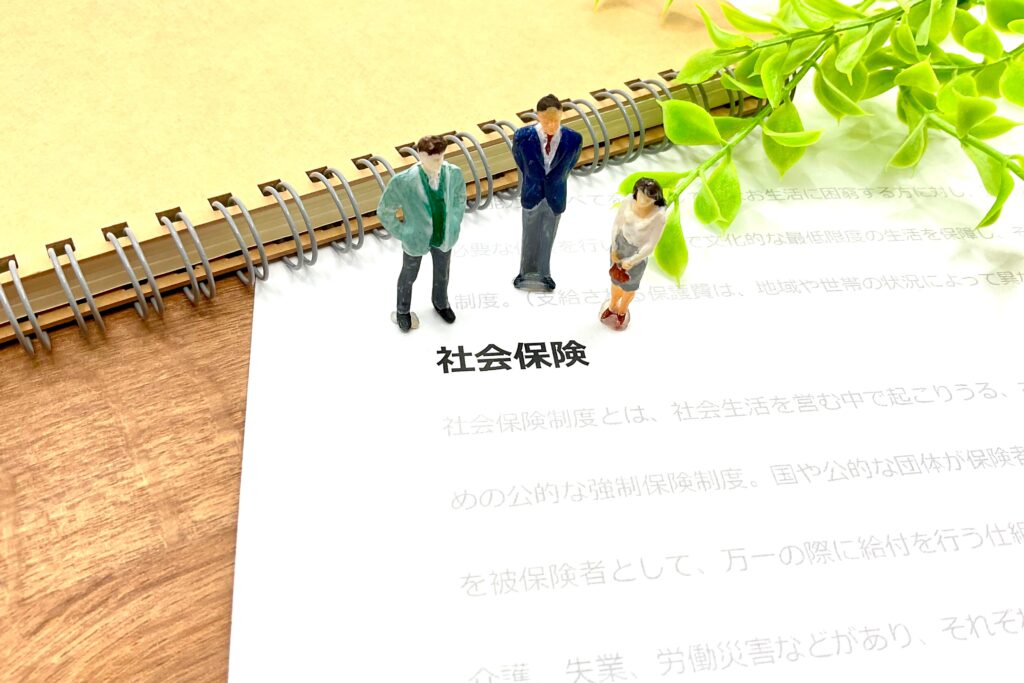
今回は、社長は社会保険に入れないのかについて紹介しました。
社長の場合でも、原則として社会保険への加入が求められます。
加入に際しては、定められた期間内に必要書類を提出する必要があるため、スケジュールを確認して早めに対応することが重要です。
万が一、社会保険未加入のままにしておくと、法的な罰則を受ける可能性があるので、あらかじめ注意が必要です。
今回の記事を参考にして、社会保険関連の手続きの流れを確認しておき、忘れずに社会保険の手続きをするようにしましょう。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。





