メニュー
法人化
法人成りすると税務調査の対象になりやすい?対象になりやすい法人の特徴も紹介

読了目安時間:約 6分
個人事業主から法人化(法人成り)を行った場合、税務署が全体の状況を把握する過程で税務調査が行われるケースもあると考えられます。
特に、法人化の前後で取引の引き継ぎや経費処理の方法が変わることから、適切に処理できているかどうかを確認されることがあります。そのため、過去の個人事業分を含めて帳簿や申告内容を整理しておくことが重要です。
本記事では、法人成りした場合に税務調査が行われやすい理由や対象になりやすい法人の特徴、リスクを減らすための準備や注意点について解説します。
正しい知識を持ち、あらかじめ適切な対策をとることで、安心して事業運営を進められるでしょう。
目次
法人成りすると税務調査の対象になりやすい?
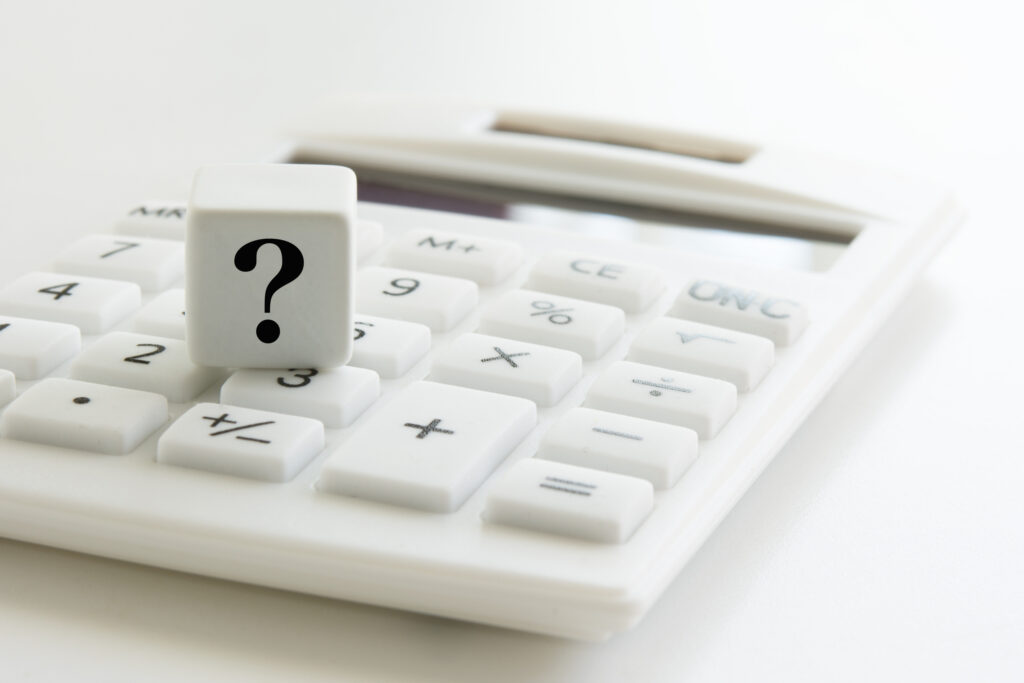
個人事業主に対する税務調査の実施率は全体のおよそ1%程度と、比較的低い水準にとどまっている一方で、法人についてはおよそ1%程度と、国税庁が公表する統計上、個人よりも調査件数が多い傾向にあります。
これは、法人の方が取引規模や経費計上の範囲が広がるため、税務署が重点的に確認を行う対象となりやすいことが背景にあります。ただし、調査の有無は売上規模や業種、申告内容など多様な要因によって左右されるため、「法人化すると必ず調査リスクが高まる」というわけではありません。
いずれにしても、法人化を検討・実行する際には、日頃から正確な記帳と適切な申告を心がけることが重要です。
参考:国税庁|令和6年度 査察の概要
法人成りした後に税務調査の対象になりやすい理由

個人事業主から法人成りした後は、税務署から注目されやすいケースがあるといわれています。必ず調査が入るわけではありませんが、法人化のタイミングは税務上の確認を受けやすいと考えておくと安心です。
法人成りした後に調査対象になりやすい主な理由として、以下の3つが挙げられます。
- 個人事業廃業から期間が経つと調査できなくなるため
- 法人成りの手続きで税務処理のミスが生じやすいため
- 税負担軽減の意図的な操作がないか確認するため
個人事業廃業から期間が経つと調査できなくなるため
税務には「更正の期間制限(いわゆる時効)」があり、個人事業を廃業してから一定の期間が経過すると、税務調査の対象から外れることがあります。税金の時効は原則として5年間(悪質な場合は7年間)となっており、時効に達する前は過去の申告について調査が行われる可能性があります。
そのため、個人事業から法人へ移行した際には、廃業前の個人事業時代の申告内容についても税務署が確認を行うことがあります。特に法人化直後の数年間は、過去の申告も含めて調査の対象となるケースがあるため、注意が必要です。
このように、法人成り後しばらくは過去の申告状況に関心が向けられる可能性があることを理解し、帳簿や資料を適切に整えておくことが望ましいでしょう。
参考:国税庁|税務手続について
法人成りの手続きで税務処理のミスが生じやすいため
法人成りを行った直後の数年間は、税務署から過去の個人事業の申告内容や法人設立後の処理について注目されることがあります。特に法人化の手続きでは、会計・税務上の取り扱いに注意すべき点が多いため、申告内容に誤りがないか確認されやすい傾向にあります。
実際の税務調査では、次のような点が確認されるケースが多く見られます。
- 資産や負債の法人への移行が適切に行われているか
- 役員報酬が適正に設定されているか
- 法人と個人の資金が明確に区分されているか
- 売上や経費の計上時期、契約関係の引き継ぎが適切か
法人成りの過程には多くの会計・税務上の留意点が存在するため、専門家に相談しながら正確に手続きを進めることが望ましいでしょう。
税負担軽減の意図的な操作がないか確認するため
法人成りを行う際には、個人事業で発生した売上や経費の法人への移行処理を適正に行うことが重要です。
法人成りのタイミングを利用して、売上や費用の計上時期を調整し、個人事業の課税額を意図的に抑えようとするケースも少なからずあります。例えば、個人事業で発生したはずの売上を法人の計上に変更したり、法人に本来属する経費を個人側で処理したりと、形式的な帳簿操作がおこなわれることがあります。そのため、税務署は法人化に伴う申告内容について正確な申告が行われているかを注意深く確認する傾向があるのです。
法人化のタイミングでは、売上や費用の計上期間や移行処理を正確に整理し、帳簿や申告書を適正に作成することが大切です。必要に応じて、税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。
参考:財務省|加算税制度の概要①(基本情報)
税務調査の対象になりやすい法人の特徴

調査対象になりやすい法人の特徴については、以下の6つが挙げられます。
- 売上が急に伸びている
- 事業規模が大きい
- 申告漏れを過去に指摘されている
- 申告内容に不審点が多くある
- 税務調査の対象になりやすい業種である
- 業績が良いのに赤字決算を計上している
それぞれの特徴について解説していきます。
売上が急に伸びている
売上が不安定に推移していた企業が、ある時期を境に急激に業績を伸ばした場合、税務署が関心を持つことがあります。
税務署は、申告内容に過不足や誤りがないかを確認するため、業績の変化を含めさまざまな情報を参考に調査対象を選定します。例えば、急激な売上増加や利益増加があった場合、過去の申告との整合性や会計処理の適切性などが注目されることがあります。
特に、黒字で利益を上げている企業は、万が一申告に誤りがあった場合に追徴税額が大きくなるため、調査の対象に含まれやすい傾向があります。一方で、赤字企業であっても、調査の必要性がないわけではなく、税務署は企業規模や過去の申告状況などを総合的に判断して調査対象を決定します。
このように、急激な成長や好業績を上げている企業では、税務署からの視点を意識した適切な帳簿管理や申告対応が重要です。
事業規模が大きい
大規模な事業を展開する企業では、日常的に多数の取引を扱うため、経理業務が複雑になりやすい傾向があります。そのため、帳簿の記載ミスや税務処理の不備が生じやすくなる可能性があります。
税務署はこうしたリスクを踏まえ、申告内容や取引状況を確認することがあります。また、申告内容に誤りがある場合は、納税額に影響が出ることがあります。例えば、売上の計上や経費処理に不備があると、追加で納税が必要になる場合があります。
このようなリスクを回避するためには、日常的に帳簿を正確に整備し、適切な税務処理を行うことが重要です。税理士によるチェックやアドバイスを活用することで、正確な申告と安心の経営につなげることができます。
申告漏れを過去に指摘されている
過去に申告漏れを指摘されたことがある法人は、税務署からの関心が高まる場合があります。
実務上、税務署では過去に指摘を受けた企業について、帳簿や取引内容の適正を確認することがあります。
特に、以前の指摘事項が適切に改善されていない場合には、追加で確認や指導が入る可能性があるため、継続的に税務上の整備を行うことが重要です。
申告内容に不審点が多くある
経費の内容に一般的な範囲から外れるような点がある場合など、申告内容に不自然な部分があれば、税務署は申告内容の妥当性を確認することがあります。
例えば、通常はあまり交際費を要しない業種であるにも関わらず、比較的高額な交際費が計上されている場合には、税務署から詳細な確認を受けることがあります。交際費については、税務上認められる範囲が定められているため、計上の際には注意が必要です。
また、全体の経費割合が一般的な水準を大きく上回る場合や、特定の経費が他に比べて著しく多い場合も、申告内容の確認対象となることがあります。
このような場合、経費が実際の事業に関連しているか、適切に計上されているかを確認するため、領収書や契約書、業務関連性を示す資料などの提出を求められることがあります。
税務調査の対象になりやすい業種である
税務署の調査では、現金取引が多い業種や、収益構造が複雑な事業や、帳簿管理が難しい業種において注意が払われる傾向があります。
具体的に、以下のような業種は、調査対象になりやすいと言えます。
- 飲食業
- インターネット関連のサービス業
- 風俗営業を含む接客業
- 医療関係
- 不動産の売買や賃貸を扱う事業
- 建築や土木工事を手がける企業
- 娯楽サービス業
- 宗教活動を行う法人
- 弁護士法人や法律事務所
そのため、帳簿類や取引の記録を日頃から正確に整理・保管し、調査に迅速かつ適切に対応できる体制を整えておくことが重要です。
参考:国税庁|令和5事務年度 法人税等の調査事績の概要
業績が良いのに赤字決算を計上している
継続的に赤字決算を申告している企業や、売上が伸びているにもかかわらず赤字を計上している法人は、税務署による確認の対象になりやすい傾向があります。
ただし、赤字はあくまで会計上の数値であり、必ずしも実際の経営状況を正確に反映しているとは限りません。
税務署は、帳簿や決算内容の整合性を確認することがあります。そのため、毎年赤字申告を続ける場合でも、帳簿の正確性や決算の透明性を保つことが重要です。
企業は、適切な会計処理と記録の整備を行い、必要に応じて税理士に相談することで、安心して経営に取り組むことができるでしょう。
法人成り後に税務調査のリスクを減らすポイント

法人成り後に税務調査のリスクを減らすポイントについては、以下の4つが挙げられます。
- 個人事業時代の帳簿書類などは保管しておく
- 個人事業主と法人の申告内容には一貫性を持つ
- 帳簿内容の引き継ぎをしっかりとおこなう
- 税理士に相談する
それぞれのポイントについて解説していきます。
個人事業時代の帳簿書類などは保管しておく
法人成り後も、個人事業時代の帳簿や書類は適切に保管しておくことが大切です。
法人化したからといって過去の書類を廃棄すると、税務上の保存義務に抵触する可能性があります。
具体的には、帳簿や請求書、領収書などの書類は、少なくとも7年間は保管しておくことが税法上推奨されています。
適切な期間、書類を整理・保管することで、万一の税務調査にもスムーズに対応できるようになるでしょう。
参考:国税庁|記帳や帳簿等保存・青色申告
個人事業主と法人の申告内容には一貫性を持つ
個人事業から法人へ移行した際には、申告内容に変化が生じることがあります。その変化について、税務署から説明を求められることもあるため、事前に理由を整理しておくと安心です。
例えば、個人事業時代には経費として計上されていなかった項目を、法人化後に経費として計上する場合には、取引の内容や目的を明確にしておくことが重要です。
また、経費の正当性を証明するための領収書や契約書などの証憑書類を整理・保管し、必要に応じて説明できる体制を整えておくことが望まれます。
帳簿内容の引き継ぎをしっかりとおこなう
法人成り後に税務調査のリスクを抑えるためには、個人事業時代の帳簿内容を整理し、法人に適切に引き継ぐことが重要です。
個人が保有していた資産は、原則として法人へ売却する形で移行されます。固定資産の評価については、帳簿価額や市場価額を考慮して設定する必要があります。
棚卸資産については、税務上の一般的な目安として販売価格の一定割合以上で法人に売却するケースが多く、詳細は個別の状況に応じて判断されます。
また、課税事業者の場合、こうした資産の売却は消費税の課税対象となるため、適切な処理が求められます。借入金やその他の負債を法人に引き継ぐ場合も、金融機関の承諾や再審査が必要となる場合があります。
法人成りにあたっては、個人事業時代の各勘定科目を正確かつ税務上適切に処理し、帳簿を整理することが不可欠です。必要に応じて、税理士に相談しながら進めることをおすすめします。
税理士に相談する
法人成り後の税務調査に備えるためには、早めに税理士に相談しておくことが有効です。
税理士に相談することで、申告内容の確認や帳簿・資料の整理、調査時の立ち会いなど、調査に向けた準備や対応を適切にサポートしてもらえます。
税理士が関与していることで、調査への対応がよりスムーズになりやすく、不安を軽減する助けになることもあるでしょう。
税務調査を安心して乗り切るためにも、法人成りのタイミングで税理士に相談することをおすすめします。
税務調査の対象にならないように帳簿管理を徹底しよう!

今回は、法人成り後の税務調査についてご紹介しました。
法人成りによって必ず調査対象になるわけではありませんが、売上や利益に大きな増減があった場合や、過去に申告に関して指摘を受けた経緯がある場合には、税務署の関心が向きやすいことがあります。
そのため、日常的な帳簿の記録を正確に行い、経費や収入の管理を適切に実施することが重要です。
本記事を参考に、法人成り後も適切な帳簿管理を心がけ、税務リスクの軽減につなげましょう。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。





