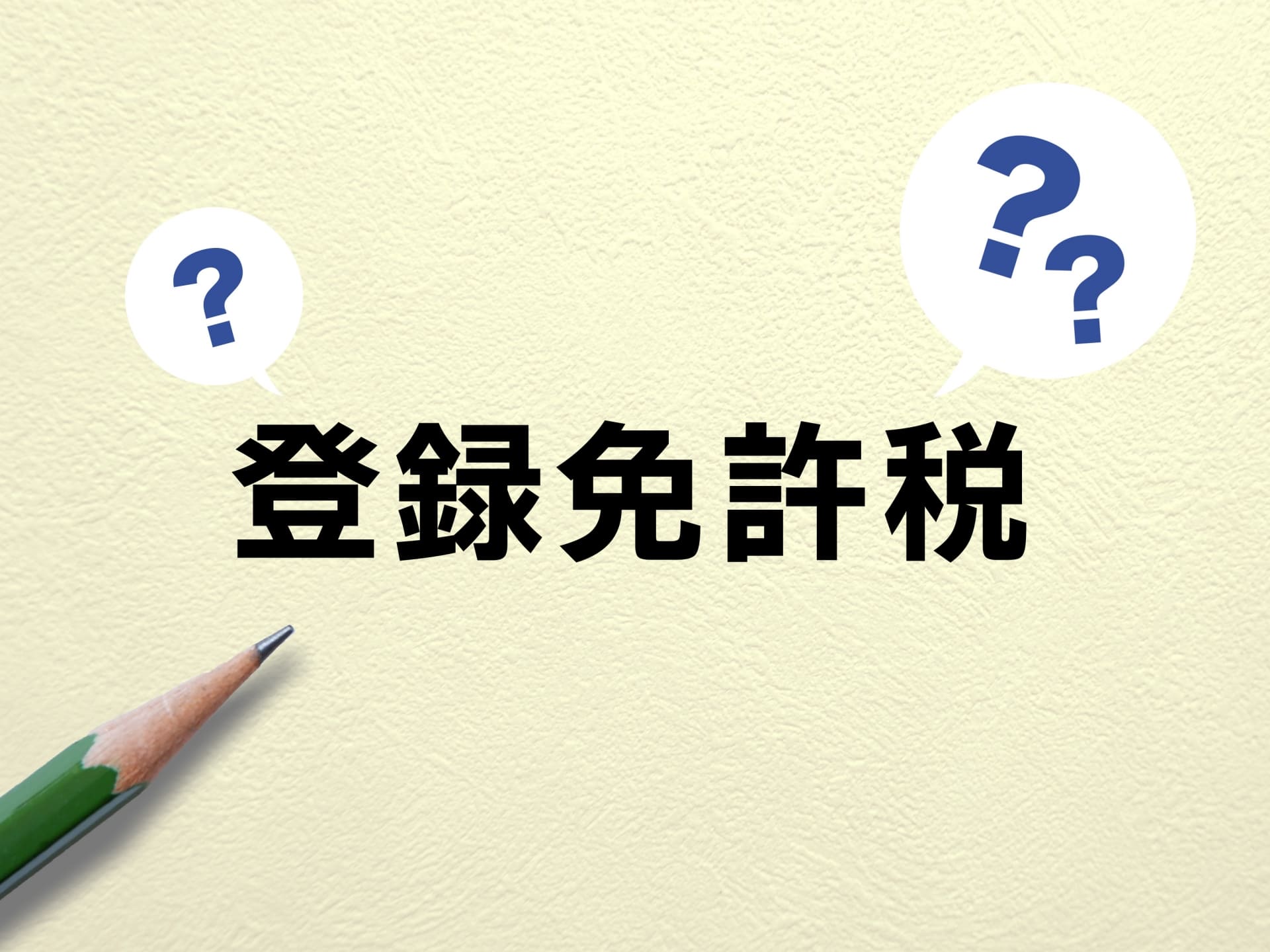メニュー
会社設立
自己資金とは?認められる資金から貯めるコツについて徹底解説

読了目安時間:約 7分
自己資金とは、外部からの借入ではなく、個人が保有する資金を指します。
金融機関の融資審査では、自己資金の額は返済能力や事業への本気度を示す重要な判断材料とされています。ただし、融資の可否は自己資金額だけで決まるものではなく、事業計画の実現性・担保・経営者の経験などを総合的に判断されます。
本記事では、自己資金の基本的な考え方に加え、「自己資金として認められる資金・認められない資金」や「自己資金を効率的に準備する方法」についても解説します。
事業計画や融資準備の参考として、自己資金の理解を深める一助としてご活用ください。
目次
自己資金とは?

自己資金とは、個人や法人が自ら保有している資金のことを指します。
個人の場合、独立開業に向けて積み立てた貯金や銀行口座の残高などが該当します。
自己資金の大きな特徴は、自身の判断で使途を決定できる点です。外部からの融資や出資に比べて利用用途の制約が比較的少なく、事業の初期費用、運転資金、設備投資、商品開発や技術研究など、さまざまな事業活動に活用しやすいです。
ただし、会社設立時に個人資金を出資として利用する場合は、会計処理や税務上の扱いに注意が必要です。自己資金の管理・活用方法を誤ると、後の税務申告や融資審査に影響する可能性もあるため、適切な管理が重要です。
自己資金の必要性
自己資金は、事業に関する融資を受ける際の審査で、重要な参考要素の一つとされています。
多くの金融機関では、申込者がどの程度の自己資金を保有しているかを確認し、返済計画や資金繰りの信頼性を判断する材料とします。
たとえば、一定の自己資金を用意している場合、予期せぬ支出や売上変動があった際にも、資金を柔軟に活用できる可能性があると評価されることがあります。反対に、元手がほとんどない状態で融資を申し込むと、返済が滞るリスクが高いと判断されてしまう傾向があります。
ただし、自己資金が少ない場合でも、事業計画の具体性や担保・保証の有無など、他の審査要素と合わせて総合的に判断されます。
そのため、金融機関から資金調達を行う際には、自己資金を適切に準備するとともに、計画的な資金運用の内容を示すことが望ましいとされています。
資本金との違い
自己資金と混同されやすいものに資本金があります。資本金とは、法人を設立する際に出資者が会社に提供する資金で、会社の登記にも記載されるものです。株式会社の場合は株主からの出資、合同会社の場合は出資社員からの出資が該当します。
資本金は貸借対照表(バランスシート)にも記載され、会社の資金基盤や事業規模を示すひとつの指標となります。また、事業開始後に利益が安定するまでの運転資金として活用され、製品開発や設備投資、マーケティング、人材採用などさまざまな用途に使うことが可能です。
一般的に、十分な資本金を確保しておくことで、金融機関や取引先からの信用力が高まり、事業運営の安定性の一助となります。ただし、資本金の額だけで会社の安定性が決まるわけではなく、事業計画や資金繰りの管理も重要です。
参考:国税庁|貸借対照表作成の手引き
自己資金と認められる資金

自己資金と認められる資金として、以下の6つが挙げられます。
- 自分名義の預貯金通帳に貯めている資金
- 配偶者・子名義の預貯金通帳に貯めている資金
- 返済義務のない贈与された資金
- 自分自身の退職金
- 自己資産を売却した資金
- 第三者割当増資で得た資金
それぞれの資金について解説していきます。
自分名義の預貯金通帳に貯めている資金
自分名義で長期的に積み立ててきた預金は、自己資金として認められることが一般的です。
このような積立型の自己資金は、資金の出所が明確である点や、計画的に資金管理が行われていることから、金融機関からの評価が得やすいとされています。そのため、創業時の自己資金として用意する一つの方法として、多くの方に利用されています。
創業時に融資を申し込む場合、金融機関から預金通帳のコピーの提出を求められることが一般的です。その際、申請日から過去6か月分の取引履歴が確認できるよう、通帳の記録を整理しておくと安心です。
また、自己資金として使用する予定の金額についても、通帳や資金計画書などで確認できる形で管理しておくことが望ましいです。
金融機関は、自己資金の額や全体に占める割合をもとに、創業者の事業に対する姿勢や資金計画の妥当性を判断します。
配偶者・子名義の預貯金通帳に貯めている資金
配偶者や子名義の預金口座にある資金を融資審査で「自己資金」として扱える場合があります。ただし、これは金融機関の判断や融資制度によって異なり、必ず認められるわけではありません。
このような資金を活用する場合は、資金提供者である配偶者や子からの承諾を証明する書類(同意書や委任状など)の提出が求められることがあります。また、金融機関によっては、資金提供者の収入や支出の状況についても確認が必要になるケースがあります。
そのため、事前に家族の資金状況を整理し、必要な書類を準備しておくことが重要です。融資審査において安心して手続きを進めるためには、専門家に相談することをおすすめします。
返済義務のない贈与された資金
返済の必要がない形で受け取った金銭的援助も、場合によっては創業時の自己資金として認められることがあります。
たとえば、親族や知人から創業支援を目的として贈与された資金が該当します。ただし、この場合は、贈与であることを証明する書類(贈与契約書や贈与税の申告書・納税証明書など)が必要となる場合があります。
また、金融機関からは、資金提供者との関係性や贈与の目的について説明を求められることもあるため、贈与の経緯や目的を整理しておくことが重要です。
加えて、贈与を受けた資金は本人名義の預貯金口座に入金されている状態が望ましく、通帳への記録が資金の流れを示す証拠として役立ちます。
参考:国税庁|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
自分自身の退職金
退職金は、融資や事業資金として自己資金に含められる場合があります。
退職金とは、勤務年数や役職に応じて企業から支給されるもので、退職後の生活資金や事業資金として活用されるケースがあります。ただし、自己資金として認められるかどうかは、金融機関や融資制度の判断によります。
退職金を自己資金として利用する場合は、支給額や時期を確認できる書類(退職証明書や退職金支給明細など)の提出が求められることがあります。また、退職金には所得税・住民税の課税対象となる部分があるため、控除の適用状況や納税手続きを事前に確認しておくことが重要です。
必要に応じて、税理士に相談することで、税務上の扱いや手続きを正確に把握したうえで活用できます。
参考:国税庁|退職金と税
自己資産を売却した資金
所有している資産を売却して得た資金は、条件によっては自己資金として活用できる場合があります。
たとえば、自宅や土地、株式などの保有資産を売却し、現金化することで創業や事業運営の資金に充てることが可能です。
ただし、金融機関によっては、資金の出所や使用目的の確認、売却に関する書類の提出を求められることがあります。
また、不動産や株式の売却によって利益が生じた場合は、譲渡所得として課税される可能性がありますので、申告や納税に注意が必要です。
第三者割当増資で得た資金
第三者割当増資とは、特定の個人や法人に対して新たに株式を発行し、出資を受けることで資金を調達する方法です。
増資によって得た資金を自己資金として利用する場合には、株式の譲渡契約書や出資証明書、株主名簿など、出資に関する証拠書類の提出が求められることがあります。また、金融機関や審査機関によっては、出資者の資金の出所や出資の目的の確認が行われる場合もあります。
さらに、株式の発行により既存株主の持ち株比率が変動する「株式の希薄化」の影響にも注意が必要です。増資を検討する際には、経営への影響や資本政策を踏まえた慎重な判断が重要です。
参考:日本証券業協会|第三者割当増資の取扱いに関する指針
自己資金と認められない資金

自己資金として認められにくい資金については、以下の3つが挙げられます。
- 預貯金通帳に入っていない資金
- 返済義務のある借りた資金
- 見せ金と判断される資金
それぞれの資金について解説していきます。
預貯金通帳に入っていない資金
自宅で現金を保管している、いわゆる「タンス預金」は、金融機関では自己資金として認められないのが原則です。これは、資金の出所が明確でない場合、金融機関が融資審査で重視する預貯金通帳の記録などによる確認が困難になるためです。
もしタンス預金を事業資金として活用する場合は、事前に銀行口座に入金しておくことが望ましいでしょう。ただし、融資申請の直前に一括で入金すると、短期間の資金移動として判断され、自己資金として十分に評価されない場合があります。
そのため、計画的に銀行口座へ入金し、資金の流れを明確にしておくことが重要です。
返済義務のある借りた資金
他人から借りたお金には返済義務があるため、一般的には自己資金としては認められません。借入金は一時的に手元にある資金であっても、自分自身の所有財産とは見なされないためです。
たとえば、親族や友人などから借りたお金も、返済義務がある場合は自己資金には含まれません。
ただし、返済義務のない「贈与」として受け取った場合は自己資金として扱われることがあります。この場合は、贈与契約書を作成し、贈与の事実や目的を明確にしておくことが望ましいです。
また、贈与税の課税対象となる場合があるため、税務上の取り扱いについては事前に確認しておくことをおすすめします。
見せ金と判断される資金
短期間で高額な資金が口座に入金された場合、金融機関の審査において自己資金として認められにくいケースがあります。特に、融資申請の直前に多額の資金が一括で振り込まれた場合は、資金の出所が明確でないと判断される可能性があり、「見せ金」と見なされるリスクがあります。
そのため、このような資金を自己資金として活用する場合は、入金の経緯や正当性を示す書類を事前に準備しておくことが重要です。例えば、預金の振込明細や贈与契約書、売却契約書などが該当します。
参考記事:自己資金が少ない!会社設立時の資本金に見せ金を利用したらどうなる?
自己資金であることを証明するポイント

自己資金であることを示す際には、銀行通帳の記録や支出に関する領収書などを提示することが一般的です。
通帳のコピーだけでは内容の確認が難しい場合もあるため、必要に応じて原本の提示を求められることがあります。
また、資金をいつからどのように積み立ててきたかという経緯も、通帳などの記録を通じて確認されることがあります。こうした情報から、継続的な貯蓄の習慣や資金管理能力が評価される場合があります。
自己資金を貯めるコツ

自己資金を貯めるコツについては、以下の3つが挙げられます。
- 短期間で貯めないようにする
- 自己資金と認められない資金を把握しておく
- 専門家に相談する
それぞれのコツについて解説していきます。
短期間で貯めないようにする
自己資金を準備する際は、短期間で大きな金額を無理に貯めるのではなく、計画的に少しずつ積み立てる方法も検討すると安心です。
一度に多額を貯めようとすると、生活費とのバランスが難しくなる場合や、貯蓄計画が続きにくくなる場合があります。
そのため、時間をかけて計画的に積み立てることは、無理のない自己資金の準備方法の一つとして有効です。
自己資金と認められない資金を理解しておく
自己資金であることを証明する際には、資金の出所や正当性を明確に示すことが重要です。
一般的に、自己資金として認められるためには、銀行口座や預金通帳など、記録が残る形で管理されていることが必要です。
例えば、自宅で保管している現金、いわゆる「タンス預金」は、金融機関が出所を確認しにくいため、原則として自己資金として扱われにくい傾向があります。ただし、出所が証明できる書類を用意できる場合は、認められるケースもあります。
また、親族や知人から一時的に借りた資金は返済義務があるため、基本的には自己資金には含まれません。一方で、返済の必要がない贈与であれば、適切な証明書類をそろえることで自己資金として扱える場合があります。
このように、資金の透明性や正当性を示すことは、金融機関からの信頼につながります。起業や事業計画にあたっては、計画的な積み立てと記録の管理を意識して自己資金を準備することが大切です。
専門家に相談する
自己資金を準備する際は、専門家に相談することも有効です。
例えば、ライフプランや資金計画など幅広いお金の相談には、ファイナンシャルプランナー(FP)が適しています。一方、税務や会計に関する相談は、税理士に相談するのが適切です。
税理士は、確定申告や節税のアドバイスはもちろん、法人の会計業務や税務調査への対応、相続手続きや相続税対策に関しても専門的な助言を提供できます。
また、無料相談を行っている専門家も一部存在しますが、内容や条件は事前に確認することをおすすめします。
税理士法人松本|会社設立専門の税理士・社労士・行政書士がフルサポート
計画的に自己資金を貯めよう!

今回は、自己資金について解説しました。
自己資金とは、預金や退職金、所有している資産の売却益、返済義務のない贈与金など、原則として本人が管理できる資金を指します。ただし、退職金や贈与金を利用する際は、税務上の制限や手続きがある場合がありますので、事前の確認が重要です。
自己資金は、会社設立時の初期費用や事業運営資金、設備投資などに活用されることが多く、金融機関による融資審査の際には、資金の積み立て状況や管理状況が参考情報の一つとして評価されます。ただし、融資の可否や金額は自己資金だけでなく、事業計画や信用情報など複数の要素により判断されます。
事業を始める際は、税務面や法的手続きを踏まえた上で計画的に資金を準備することが大切です。必要に応じて、税理士やファイナンシャルプランナーに相談するとより安心です。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。