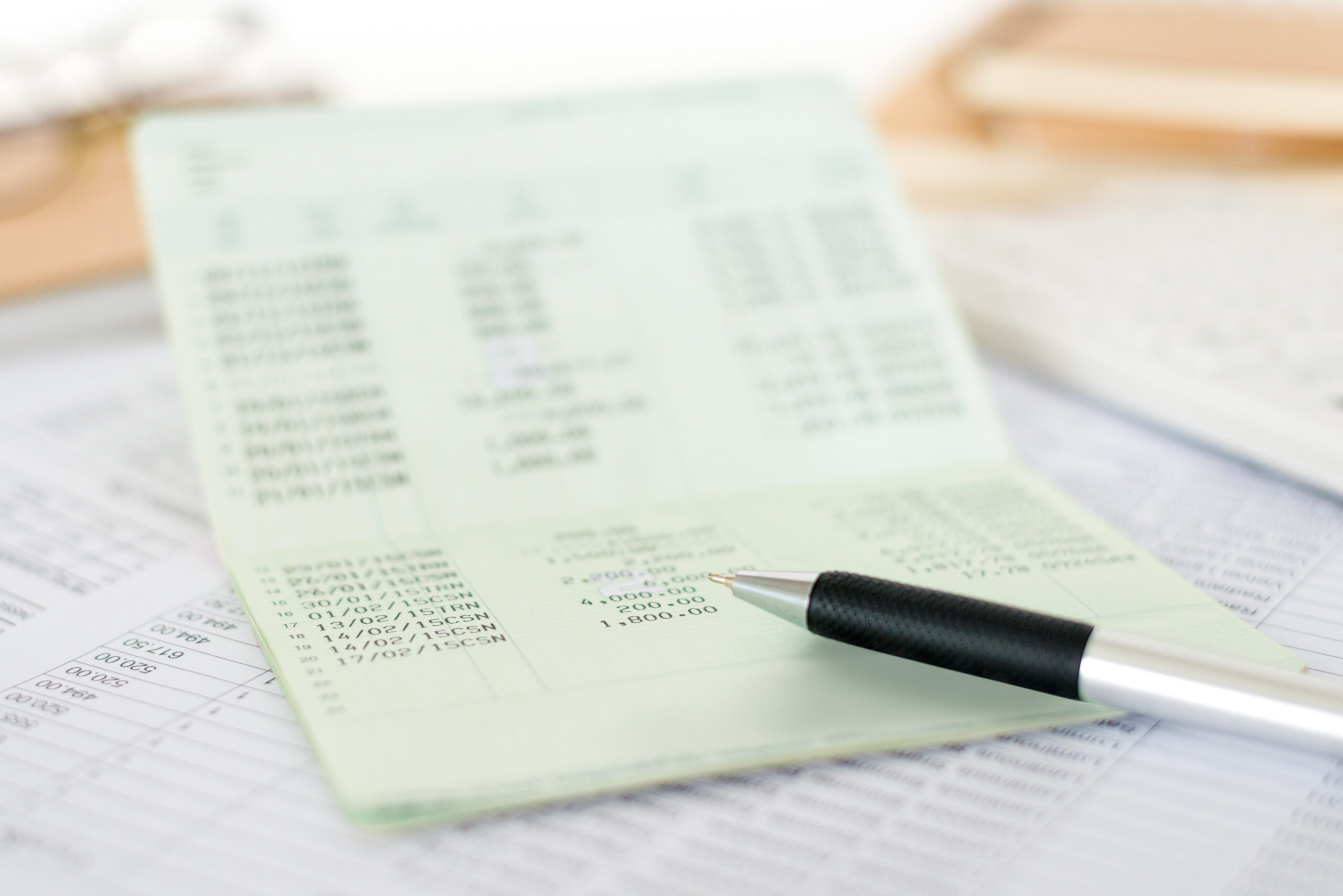メニュー
会社設立
マイクロ法人の作り方とは?メリット・デメリットや注意点についても紹介

読了目安時間:約 8分
マイクロ法人を設立する際には、手続きの流れやメリット・デメリットを正しく理解しておくことが大切です。
必要な書類や手順を把握していないと、設立に時間がかかったり、専門家への依頼費用など想定外のコストが発生する可能性があります。
また、設立時の判断内容によっては、税金や社会保険料の負担が想定よりも大きくなるケースもあるため、事前に十分な検討が必要です。
本記事では、マイクロ法人の基本的な作り方や、設立のメリット・デメリット、注意すべきポイントについて分かりやすく解説します。
実際に設立を検討する際は、事業内容や収益状況に応じて、税理士などの専門家へご相談ください。
目次
マイクロ法人の作り方とは?

「マイクロ法人」というのは法律上の正式な用語ではありませんが、少人数で運営する小規模な法人を指す言葉として一般的に使われています。
ここでは、一般的な株式会社を設立する際の基本的な流れを紹介します。
- 定款作成
- 定款認証
- 法人印鑑の作成
- 出資金の払い込み
- 各種手続きの実施
参考:法務省|株式会社の設立手続(発起設立)について
①定款作成
マイクロ法人を設立する際には、定款の準備が欠かせません。
定款には、会社法で定められた必須事項を正しく記載する必要があり、主な記載項目は次のとおりです。
- 法人が行う事業の内容
- 会社の名称(商号)
- 主たる事務所の所在地
- 設立時に出資される資産の金額またはその最低額
- 発起人の氏名または名称と住所
- 発行可能な株式の総数
これらの内容を事前に整理しておくことで、定款作成時のミスや手続きの遅れを防ぐことができます。
もし記載漏れや誤りがある場合、定款の効力に影響するおそれがあり、再作成が必要となるケースもあります。
定款は、紙で作成する方法と電子定款で作成する方法の2種類があります。
紙の定款を作成する場合は通常3部製本し、1部を公証役場用、1部を会社保管用、もう1部を登記申請用として使用します。一方、電子定款の場合はPDFデータとして作成・提出でき、印紙代4万円を節約できる点がメリットです。
紙の定款では、製本後に各ページを見開き状態にして発起人の実印で割り印を行い、最終ページの署名欄にも実印を押します。電子定款の場合は、発起人の電子証明書を利用して電子署名を付与するため、押印は不要です。
参考:法務省|定款作成支援ツールの使用方法
②定款認証
株式会社を設立する際には、作成した定款を公証役場に提出し、公証人による認証を受ける必要があります。
一方で、合同会社・合資会社・合名会社については、定款の作成は必要ですが、公証役場での認証手続きまでは求められていません。
認証の申請は原則として事前予約制となっており、会社の本店所在地を管轄する公証役場に連絡して、公証人との面談日時を予約します。
また、現在では電子署名を用いた「電子定款」による認証も可能で、印紙税が不要となるなど手続きの効率化が進んでいます。
公証役場によっては、事前に定款案をメール等で送付し、内容の確認を依頼できる場合もあります。訪問前に必要書類や提出方法を確認しておくことで、当日の手続きをスムーズに進められます。
参考:法務省|一人会社の設立登記申請は完全オンライン申請がおすすめです!
③法人印鑑の作成
法人設立後に登記を紙で申請する場合は、申請書類に会社の実印を押印する必要があります。
そのため、会社名(商号)が決まった段階で、早めに実印を作成しておくとスムーズです。
一方、登記手続きをオンラインで行う場合は、印鑑の提出は原則不要です。
ただし、銀行融資の申し込みや不動産契約などでは、実印の提出を求められるケースも一般的なため、今後の取引を見据えて準備しておくことをおすすめします。
また、実務では、銀行口座の開設に使用する「銀行印」や、請求書・領収書などに押す「角印」も使用頻度が高いため、法人設立と同時に用意しておくと安心です。
④出資金の払い込み
会社設立にあたっては、出資金の払い込み手続きを行う必要があります。
設立時点では法人名義の銀行口座を開設できないため、出資金は発起人個人の口座や現金で受け取るのが一般的です。出資金の払い込みが完了したら、その事実を証明できる書類を用意しておきましょう。
具体的には以下の資料が参考になります。
- 通帳の表紙・裏表紙(支店名、口座番号、口座名義が確認できるページ)
- 出資金が入金された取引明細のページ(入金日・金額が確認できるもの)
通帳を使用できない場合やインターネットバンキングを利用している場合は、金融機関名・口座名義・入金日・入金額が明記された取引明細画面を印刷したもので代用できます。また、現金払いの場合は領収書を保管してください。
これらの資料は、法人設立時の登記申請で「払込みが行われたことを証明する書類」として添付する必要があります。大切に保管しておきましょう。
⑤各種手続きの実施
会社設立後は、行政機関への各種届出も忘れずにおこなうことが重要です。
法務局での登記が完了した後は、税務署や関係機関への書類提出が必要になる場合があります。税務署へ提出する代表的な書類としては、以下のようなものがあります。
- 法人設立届出書
- 青色申告承認申請書(希望する場合)
- 給与支払事務所等開設届出書(従業員がいる場合)
- 源泉所得税の納期の特例に関する申請書(該当する場合)
- 棚卸資産の評価方法に関する届出書(棚卸資産を扱う場合)
- 減価償却資産の償却方法に関する届出書(固定資産がある場合)
また、従業員を雇用する場合には、社会保険や労働保険に関する手続きも必要です。
手続き窓口は以下の通りです。
- 健康保険・厚生年金:年金事務所
- 労災保険:労働基準監督署
- 雇用保険:ハローワーク
これらの手続きを適切に行うことで、法令を遵守した会社運営をスタートすることができるでしょう。必要に応じて、税理士や社会保険労務士への相談を検討するのがおすすめです。
参考:国税庁|A1-8 所得税の青色申告承認申請手続
マイクロ法人を作るメリット

マイクロ法人を設立することによる代表的なメリットとして、以下の5点が挙げられます。
- 経費計上の幅が広がる
- 取引上の信用力が得られる可能性
- 社会保険料を抑えられる場合がある
- 税負担の最適化が期待できる
- 消費税の免税事業者となる可能性がある
それぞれのメリットについて解説していきます。
経費計上の幅が広がる
マイクロ法人のメリットの一つに、経費として計上できる範囲がある程度広がる点が挙げられます。
個人事業主の場合、経費として認められる支出には一定の制限がありますが、法人化すると、事業関連の支出を条件に応じて経費として処理できるケースがあります。
例えば、法人の代表者が受け取る役員報酬は、税法上の要件(定期同額給与など)を満たす場合に法人の経費として計上できます。これにより、法人税の課税所得を適切に圧縮することが可能です。
また、法人化により、退職金の積立や、事業に関連する生命保険料や出張時の日当なども、条件次第で経費に計上できる場合があります。
これらの制度を適切に活用することで、法人としての税負担の軽減につなげられる可能性があります。
参考記事:法人だったらなんでも経費で落とすことができるは嘘!注意点を解説
取引上の信用力が得られる可能性
マイクロ法人を設立すると、法人格を持つことにより一定の信用の目安として取引先に認識されやすくなる場合があります。
法務局で法人登記を行うことで、会社名(商号)や所在地、資本金、事業目的などの情報が公的に記録され、取引の際の安心感につながることがあるのです。
また、法人として登記されることで、金融機関からの融資や、法人を対象とした補助金・助成金の制度に申し込むことが可能になる場合もあります。ただし、融資の可否や制度の利用は審査や条件によって異なります。
参考:法務局|商業・法人登記申請手続
社会保険料を抑えられる場合がある
マイクロ法人を設立することで、社会保険料の計算方法が個人事業主とは異なる点があります。
個人事業主は原則として国民健康保険と国民年金に加入し、所得に応じて保険料が決まるため、収入が増えると負担も増加します。一方、法人の役員として加入する健康保険・厚生年金では、保険料は原則として「役員報酬の額」に応じて算定されるのです。
そのため、役員報酬の設定によっては、個人事業主として支払う場合よりも社会保険料の負担を抑えられる可能性があります。
ただし、報酬の設定には税務上・労務上のルールがあるため、極端に低く設定すると問題となる場合があります。法人化による社会保険料の影響は、事前に試算しながら検討することが重要です。
参考:国税庁|No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
税負担の最適化が期待できる
マイクロ法人を設立することで、所得の受け取り方を「事業所得」から「給与所得」に変えることが可能です。
法人の役員報酬として所得を受け取る場合、給与所得控除が適用されるため、所得税や住民税の計算上、有利になる可能性があります(給与所得控除は2025年以降、最低65万円が控除されます)。
ただし、法人設立には設立費用や社会保険料の負担が発生するため、必ずしも税負担が軽減されるとは限りません。収入状況や経営計画に応じて、法人化のメリット・デメリットを慎重に判断することが重要です。
消費税の免税事業者となる可能性がある
個人事業主の場合、原則として前年または前々年の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となり、消費税の申告・納付が必要になります。
一方、新たにマイクロ法人を設立し、事業の一部を法人で行う場合、設立初年度などの条件により消費税の免税事業者として扱われる可能性があります。
免税事業者となると、取引先から受け取った消費税を納税する義務はなくなるため、手元資金を残しやすくなるメリットがあります。また、消費税の申告・納付の手間が省ける点も利点です。
ただし、2023年10月から導入されたインボイス制度により、免税事業者との取引条件が不利になる可能性もあります。
そのため、免税事業者として運営するか、あえて課税事業者として適格請求書発行事業者に登録するかは、事業規模や取引先との関係を踏まえて慎重に判断することが重要です。
参考:国税庁|インボイス制度について
マイクロ法人を作るデメリット

マイクロ法人を設立する際の主なデメリットとして、以下の3点が挙げられます。
- 設立・維持に費用がかかる
- 事務手続きの手間がかかる
- 赤字でも法人住民税が発生する
それぞれのデメリットについて解説していきます。
設立・維持に費用がかかる
マイクロ法人を設立する際には、設立や維持にかかる費用を事前に把握しておくことが重要です。
例えば、株式会社を設立する場合はおおよそ20万〜30万円前後、合同会社であっても10万円程度の費用が必要になります。
また、法人を運営していくうえでは、毎年の法人住民税(均等割)や会計・税務申告の費用など、固定的な支出が発生します。
決算や税務申告を税理士に依頼する場合の報酬は、業務の内容や規模に応じて異なりますが、目安として10万円〜20万円前後となるケースが多く見られます。
参考:株式会社と合同会社のどちらがよいか | 起業マニュアル – J-Net21
事務手続きの手間がかかる
マイクロ法人を設立する場合、個人事業主として活動していたときと比べて、経理や事務処理の方法が変わることがあります。
個人事業主であれば、基本的に年に一度の確定申告で手続きが完了しますが、法人の場合は「法人決算」と「法人税の確定申告」を毎期ごとに行う必要があります。
特に、マイクロ法人を株式会社として設立した場合には、以下の書類の作成・提出が必要です。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 勘定科目内訳明細書
- 法人事業概況説明書
これらの書類は正確な会計処理と税務知識を必要とするため、経理経験が少ない方にとっては自力での作成が難しい場合があります。
その場合は、税理士など専門家に依頼することが一般的です。税理士に依頼することで、書類作成の正確性や税務リスクの軽減が期待でき、安心して事業運営に集中できます。費用は発生しますが、法人運営の効率化やトラブル防止への「投資」として考えることができます。
参考:国税庁|C1-1 法人税及び地方法人税の申告(法人税申告書別表等)
赤字でも法人住民税が発生する
マイクロ法人を設立した場合、事業が赤字であっても「法人住民税の均等割」を納める必要があります。均等割の税額は会社の資本金や従業員数、所在地の自治体によって異なりますが、最も小規模な法人でも年間数万円程度の負担が発生することがあります。
そのため、事業が赤字続きの状態でマイクロ法人を設立すると、個人事業主のままの場合よりも住民税の負担が大きくなってしまう場合があるので注意が必要です。
ただし、個人事業主の場合と比べた負担の大小は、事業内容や所得状況、所在地によって異なります。法人化のメリット・デメリットを総合的に検討した上で判断することをおすすめします。
参考:総務省|地方税制度|法人住民税
マイクロ法人を作る際の注意点

マイクロ法人を作る際の注意点として、以下の2つが挙げられます。
- 脱税行為を疑われないようにする
- 節約効果が限定的となることがある
それぞれの注意点について解説していきます。
脱税行為を疑われないようにする
マイクロ法人を設立する際には、税務署から「脱税目的ではないか」と誤解されないよう、税務上の手続きや事業運営の方法に注意することが大切です。
特に、個人事業を継続しながらマイクロ法人を運営する場合は、両者の事業内容や収入の区分を明確にしておくことが重要です。
個人事業と法人の活動内容が重複している場合、税務署から事業区分や収入配分について確認される可能性があります。こうした状況を避けるためには、帳簿や契約書などの書類を整理し、事業の性質や収入源を明確にしておくことが望ましいでしょう。
節約効果が限定的となることがある
会社員が自身でマイクロ法人を設立する場合、社会保険料の取り扱いには注意が必要です。
基本的に、会社員として勤務している企業と、設立した法人の両方で社会保険料の負担が発生する可能性があります。
そのため、法人側での社会保険加入が免除されるわけではなく、場合によっては節約効果が限定的となることがあります。
また、複数の勤務先や法人から報酬を受け取る場合、報酬の合計額をもとに社会保険料が計算されます。算出された保険料は、各報酬の額に応じて按分され、それぞれの給与や報酬から納付される仕組みです。
具体的な節約効果や手続きについては、加入する社会保険の種類や役員報酬の設定によって異なるため、税理士や社会保険労務士に相談することをおすすめします。
制度の仕組みを理解してマイクロ法人設立を検討しよう

今回は、マイクロ法人の作り方について概略をご紹介しました。
個人事業主とマイクロ法人では、課税の仕組みや設立手続き、報酬の扱いなどに主な違いがあります。
そのため、マイクロ法人を設立することで得られるメリットや生じる可能性のあるデメリットについて、税金・保険・運営コストなどの観点から慎重に検討することが大切です。
設立を検討している場合や判断が難しい場合は、税務の専門知識を持つ税理士に相談し、個別の状況に応じた客観的なアドバイスを受けることをおすすめします。
この記事を参考に、ご自身にとって最適な選択を検討してみてください。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。