メニュー
会社設立
定期同額給与とは何か?損金算入が認められる条件から注意点についても徹底解説

読了目安時間:約 6分
定期同額給与とは、役員に対して毎月一定の時期に同じ金額を支給する形式の役員報酬を指します。
この支給形態を法人の損金(経費)として計上するためには、法人税法で定められた要件を満たす必要があります。そのため、事前に正しいルールを理解しておくことが重要です。
本記事では、定期同額給与の基本的な仕組みをはじめ、損金算入が認められる具体的な条件や実務上の注意点についても解説します。
定期同額給与の考え方をしっかり押さえて、適切な役員報酬の設定に役立ててください。
目次
定期同額給与とは何か?

定期同額給与とは、1か月以内の一定期間ごとに、法人が役員へあらかじめ定めた同じ金額を支給する報酬の形態を指します。
支払いサイクルや金額の固定性という点では、一般社員の月給制に近い形式ですが、役員報酬の場合は株主総会や取締役会などで、あらかじめ支給額を正式に決定しておく必要があります。
税法上の3つの要件(支給時期・金額・決定時期)をすべて満たす場合に限り、定期同額給与は損金算入が認められます。
ただし、支給金額の変更は自由に行えるわけではなく、原則として会計期間の開始日から3か月以内に限り改定が認められています。継続して損金算入を受けるためには、適切な時期と手続きを踏むことが重要です。
参考:国税庁|No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
役員報酬の決定方法
役員報酬の設定には以下のような特徴があります。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 株主総会の決議が必須 | 報酬の金額は、会社の定款に明記されているか、あるいは株主総会の承認によって確定。 |
| 原則として年度単位で見直し | 報酬額の変更は、基本的に事業年度ごとに行われ、大幅な変更をする際には一定の税務要件を満たす必要がある。 |
| 給与とは異なる税制が適用される | 一般社員の給与とは異なり、役員報酬には特有の税務上の取り扱いや社会保険の扱いがある。 |
役員報酬の設定は、税務・資金繰りに影響を与える重要な経営判断です。法令を遵守しつつ、会社の経営状況に見合った設計が求められます。
定期同額給与の損金算入が認められる条件

定期同額給与を法人の損金(経費)として認めてもらうためには、税法上、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 支給額が毎月同額であること
- 事業年度の開始から3か月以内に支給額を決定していること
- 臨時改定事由や業績悪化改定事由に該当しないこと
これらの条件を満たしていない場合、支給額の一部または全部が損金として認められないことがあります。
以下で、それぞれの要件について詳しく解説します。
支給額が毎月同額であること
定期同額給与とは、毎月同一金額を一定の時期に継続して支給する報酬形態を指します。
この条件を満たしている場合に限り、役員報酬を法人の損金として計上することが認められます。
一方で、以下のようなケースでは原則として損金算入が認められないため注意が必要です。
- 年度途中で報酬額を変更した場合
- 月によって支給額に増減があった場合
- 一時的な追加報酬を支給した場合
特に、会社の業績に合わせて途中で報酬を増減させると、税務上の損金算入要件を満たさなくなる場合があります。
適切な報酬設計を行うためには、制度の仕組みを正しく理解し、必要に応じて税理士などの専門家に相談することが大切です。
事業年度の開始から3か月以内に支給額を決定していること
役員報酬は、原則として事業年度の開始日から3ヶ月以内に金額を確定し、その後は基本的に変更せずに支給する必要があります。
この期限を過ぎて報酬額を変更した場合、変更後の支給分については税務上の扱いが限定される可能性があり、法人税の計算上に影響が出る場合があるので注意が必要です。
参考:国税庁|No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
臨時改定事由や業績悪化改定事由に該当しないこと
原則として、役員報酬の途中変更は認められていません。ただし、税務上は「臨時改定」や「業績悪化改定」と認められる場合に限り、変更が損金算入の対象となることがあります。
「業績悪化改定」とは、会社の財務状況が著しく悪化し、やむを得ず役員報酬の引き下げが必要と判断される場合の改定を指します。たとえば、資金繰りが深刻な状況や事業環境の大幅な悪化などが考えられます。
ただし、日常的な資金繰りの変動や目標未達など、軽微な理由のみでは認められないケースが多いため、改定を検討する際には税務上の判断基準や証拠書類を十分に確認することが重要です。
参考:国税庁|役員給与に関するQ&A
定期同額給与の損金算入が認められないケース

定期同額給与は、一定の条件を満たす場合に限り、法人の損金として計上できます。条件を満たさなくなると、その支給分は損金算入が認められないことがあります。
特に、以下のようなケースでは注意が必要です。
- 事業年度途中から定期同額給与を支給した場合
- 事業年度開始から3ヶ月後に金額を増減した場合
- 特定の月だけ金額が増加した場合
これらの条件を正しく理解することで、法人税上のリスクを回避できます。それぞれ詳しく説明します。
事業年度途中から定期同額給与を支給した場合
事業年度の途中から役員への定期同額給与を支給した場合、原則としてその報酬は損金として算入できません。
創業直後など、事業開始直後に十分な収益が見込めず、報酬を後から支給する場合も同様です。
ただし、税務上の取り扱いや例外規定(臨時改定や業績悪化改定など)により、一定の条件を満たせば損金算入が認められるケースもあります。
報酬支給のタイミングや事業年度の設定については、事前に税理士と相談し、適切な手続きを行うことが重要です。
参考:国税庁|No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
事業年度開始から3ヶ月後に金額を増減した場合
事業年度開始から3ヶ月を過ぎて役員報酬を変更した場合、原則としてその変更分は法人税の損金として認められない可能性があります。
一方、事業年度開始から3ヶ月以内に行う報酬改定は「通常改定」として扱われ、一定の要件を満たせば損金算入が可能です。
このように、役員報酬の改定はタイミングや理由によって税務上の扱いが変わるため、事前に計画的な判断を行うことが重要です。
特定の月だけ金額が増加した場合
役員報酬は、原則として「定期同額給与」として事前に定められた金額を継続的に支給する必要があります。事前の届け出を行わず、特定の月だけ報酬を増額した場合、その増額分は定期同額給与として扱われない可能性があり、損金算入が認められない場合があります。
例えば、ある月だけ通常の支給額に加えて追加報酬を支払うと、月ごとの支給額に差が生じ、定期同額給与の条件を満たさなくなるおそれがあります。
そのため、基本報酬額を超える部分については、税務上の損金算入が認められない可能性があることに注意が必要です。
定期同額給与を改定できるタイミング

定期同額給与が税務上損金として認められるタイミングは、原則として以下のように整理できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業年度開始から3ヶ月以内に決定する場合 | 役員報酬は、原則として事業年度の開始日から3ヶ月以内に確定する必要がある。この期間を過ぎて変更した場合、税務上の損金算入が認められない可能性がある。 |
| 職務変更などのやむを得ない事情がある場合(臨時改定事由) | 例えば、社長の退任や役員の昇格など、役職変更に伴う報酬の改定は、職務内容に応じた適正な範囲で行われる場合に限り、損金算入が考慮されることがある。ただし、増額・減額の可否や算入範囲は、個別の事情や税務判断によって異なる。 |
| 法人の経営状態が著しく悪化した場合(業績悪化改定) | 経営が著しく悪化し、報酬の減額がやむを得ない場合には、損金算入の対象となることがある。増額については原則として認められない。なお、「業績悪化」の具体的な判断は、営業損失の発生など客観的な資料で示される必要がある。 |
いずれの場合も、臨時改定や業績悪化による改定は例外的な措置です。改定内容の正当性を示す資料や記録を残しておくことが、税務上の安全性を確保する上で重要です。
参考:国税庁|役員給与に関するQ&A
定期同額給与の注意点
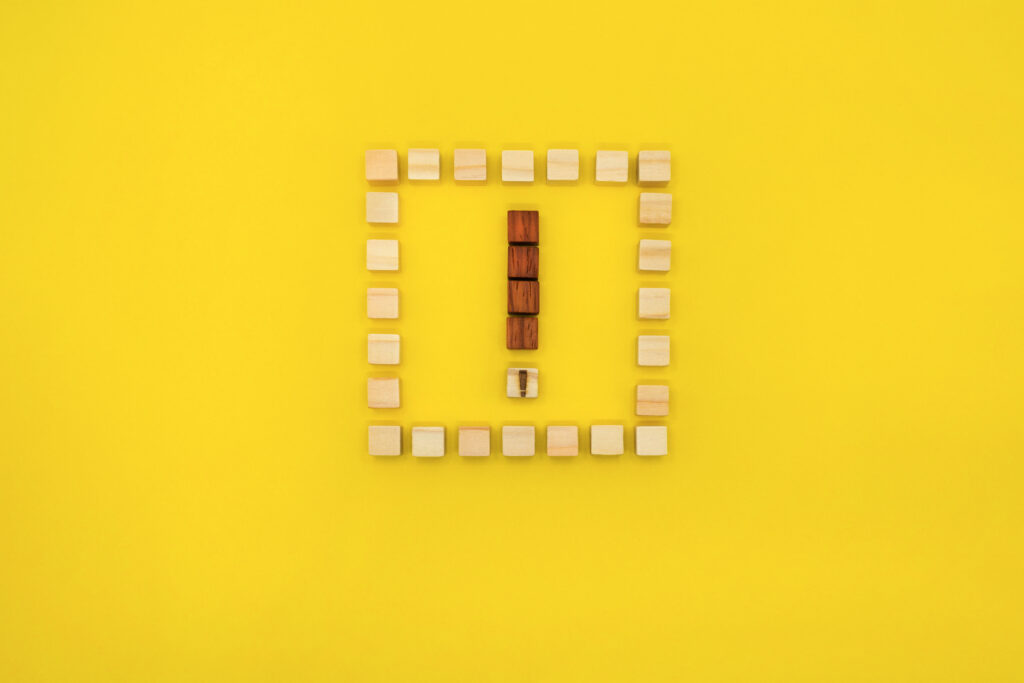
定期同額給与を設定する際には、以下のポイントに注意が必要です。
- 損金不算入部分は法人税も所得税も負担する
- 金額改定は事業年度開始日から3ヶ月以内であること
- 設立初年度でも改定は事業年度開始から3ヶ月以内であること
- 経済的利益も定期同額給与として認められる
- 同業他社の相場も参考にする
それぞれの注意点について解説していきます。
損金不算入部分は法人税も所得税も負担する
定期同額給与として認められず、税務上「損金不算入」と判断された場合、その該当金額は法人の経費(損金)として扱われません。その結果、法人の課税所得が増加し、法人税の負担が増えることがあります。
一方で、支給された役員報酬は個人の所得として課税対象となります。したがって、法人側では損金算入できず、役員個人では所得税が課されるという点に留意する必要があります。
参考:国税庁|定期給与の額を改定した場合の損金不算入額(定期同額給与)
金額改定は事業年度開始日から3ヶ月以内であること
役員報酬は、原則として事業年度開始後3か月以内に金額を確定する必要があります。この期間内に株主総会で報酬の上限額を決定し、議事録を作成して正式に承認を受けることが、税務上の損金算入要件を満たすために重要です。
また、株主総会の開催前に報酬の支給を開始する場合は、承認を前提として行う必要があり、臨時株主総会などで対応することが求められます。
なお、3か月目の報酬が実際に翌月に支払われる場合でも、税務上は支払日ではなく報酬が発生した月を基準として取り扱われるため、3か月目までの報酬は改定前の金額で処理されるのが一般的です。
設立初年度でも改定は事業年度開始から3ヶ月以内であること
設立初年度においては、役員報酬の定期同額給与の設定が重要なポイントとなります。
事業開始直後は収益が安定しないことが多く、報酬の金額設定に悩む場面も少なくありません。しかし、税務上、定期同額給与として認められるためには、原則として事業年度開始から3か月以内に報酬額を確定しておく必要があります。
この期限を過ぎて設定や改定を行った場合、原則として損金算入が認められず、法人税の負担が増える可能性があります。ただし、業績悪化や臨時の事情による改定については、例外的に認められる場合もあります。
そのため、初年度であっても、定期同額給与の取り扱いには注意が必要です。設定のタイミングや金額に迷う場合は、早めに税理士に相談し、適切な対応策を検討することが望ましいでしょう。
経済的利益も定期同額給与として認められる
税法上、現物や経済的利益も役員報酬として扱われる場合があります。
つまり、会社から現金で直接支払われていなくても、役員が実質的に利益を受けている場合には、報酬とみなされることがあります。
例えば、役員の私的な支出を会社が負担している場合や、会社名義の社宅に役員が入居して賃料を支払っていない場合などがこれに該当することがあります。
このような経済的利益も、毎月の金額が一定であれば、条件次第で定期同額給与として損金算入が認められる場合があります。
一方で、金額にばらつきがある場合や、そもそも給与として想定していなかった経済的利益が後から報酬と判断される場合には、損金算入が認められず、役員に所得税が課されることもあり得ます。適切な処理のためには、事前に税務上の取り扱いを確認することが重要です。
参考:国税庁|No.5202 役員に対する経済的利益
同業他社の相場も参考にする
役員報酬の金額を決定する際には、まず自社の利益状況や財務体質を踏まえることが基本となりますが、同業他社の報酬水準を参考にすることも有効です。
ただし、これはあくまで目安であり、税務上の妥当性は会社の実態や定期同額給与の要件に基づき判断されます。
役員報酬を定期的かつ一定額で支給する「定期同額給与」として設計することは、損金算入の要件を満たすために重要です。
このため、業務内容や会社規模に照らして著しく高額または低額な設定にならないよう配慮し、安定的かつ根拠のある報酬体系を構築することが望ましいといえます。
適正な役員報酬の設定は、税務リスクを回避しつつ、企業経営の健全性を維持するうえでも役立ちます。
役員報酬を適切に設定するなら専門家に相談しよう!

今回は、定期同額給与について解説しました。
定期同額給与とは、役員に対して毎月一定額を支給する仕組みで、支給額があらかじめ決められている点が特徴です。
役員報酬は法人税上の損金として計上できる一方で、税法上は適正な運用が求められます。
報酬額の設定は、法人の税負担や役員個人の納税額に影響を与える場合があるため、慎重な判断が重要です。
不安がある場合は、税務の専門家である税理士に相談することで、制度に沿った報酬設計を検討することが可能です。
役員報酬の適切な設定を検討する際には、今回の記事を参考にしつつ、専門家の意見も活用してみてください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。





