メニュー
法人化
サラリーマンはマイクロ法人を設立できる?タイミングやメリット・デメリットについても紹介

読了目安時間:約 7分
会社員として勤務していても、マイクロ法人を設立することは可能です。
ただし、サラリーマンがマイクロ法人を設立した場合、状況によっては税負担の軽減につながるケースもあれば、想定していたほどの効果が得られないケースもあります。そのため、事前に十分な検討が必要です。
本記事では、サラリーマンがマイクロ法人を設立できるのかという基本的な点を整理し、あわせて「設立を検討するタイミング」や「メリット・デメリット」についてもご紹介します。
ぜひこの記事を参考に、サラリーマンのマイクロ法人について理解を深めてみてください。
目次
マイクロ法人とは?
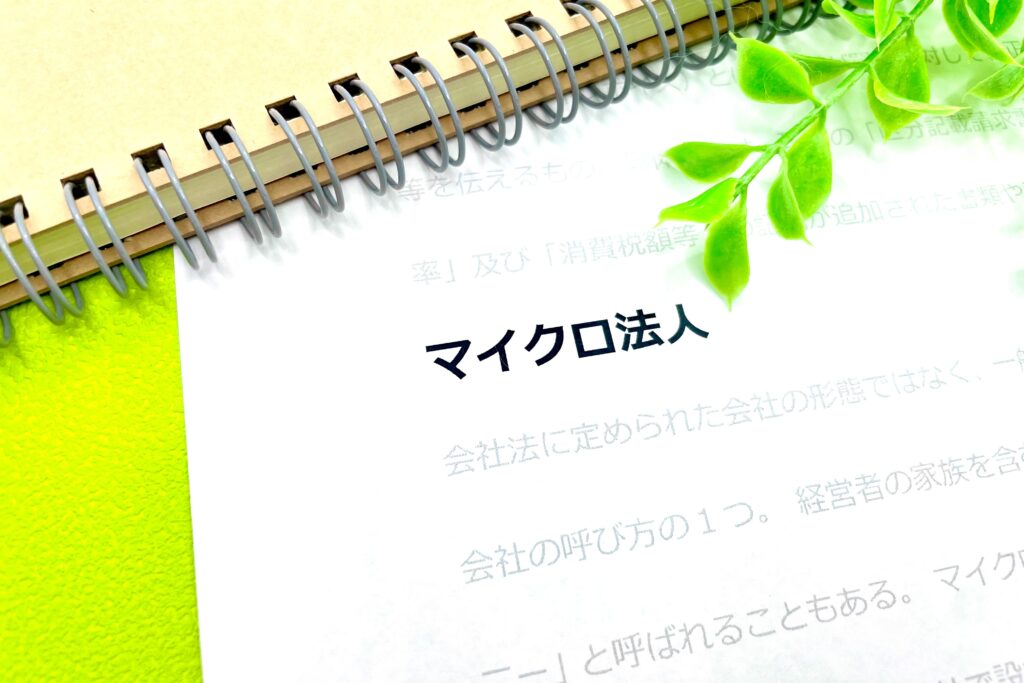
マイクロ法人とは、基本的に代表者本人が中心となり、少人数で運営される小規模な法人形態を指します。
株主や役員の人数も最小限で構成されるケースが多く、個人事業を法人化した形態の一つとしても利用されているのがマイクロ法人です。活用の背景には、事業の信用力向上や、税金・社会保険料の負担を考慮した事業運営の工夫といった目的があります。
近年では、フリーランスや一人で事業を営む方の間でも、マイクロ法人の設立が選択肢のひとつとして注目されています。
サラリーマンはマイクロ法人を設立できる?

サラリーマンであっても、いわゆる「マイクロ法人」を設立することは可能です。
会社法等の法律では、会社員が法人を設立することを直接的に禁止する規定は存在しません。そのため、実際に会社員として勤務を続けながら法人を立ち上げるケースも見られます。
ただし、勤務先の就業規則や雇用契約において、副業・兼業が制限されている場合があります。この場合、法人設立そのものが規則違反とみなされ、注意・指導や懲戒などの対象となる可能性も否定できません。そのため、勤務先の就業規則や雇用契約をあらかじめ確認しておくことが必要です。
サラリーマンがマイクロ法人を設立すべきタイミング

サラリーマンが副業をしている場合、法人を設立したほうが有利になるケースがあります。特に以下のような状況では、法人化を検討するきっかけとなることがあります。
- 副業所得が一定の金額に達したとき
- 消費税の課税事業者になる見込みがあるとき
- 取引や資金調達などで社会的信用が求められるとき
それぞれのタイミングについて見ていきましょう。
副業所得が一定の金額に達したとき
副業所得が一定の金額に達した場合、給与所得と合算した場合に高い税率が適用されやすくなるため、法人設立を検討するケースが出てきます。
日本の所得税は累進課税制度を採用しており、所得が増えるほど税率が上昇します。
例えば、課税所得695万円超〜900万円以下の場合の所得税率は23%、900万円超〜1,800万円以下では33%と段階的に高くなっていきます。そのため、副業所得が一定の金額に達した場合、給与所得と合算することで税率が上がる可能性があります。
この段階でマイクロ法人を作り、副業の売上を法人で受けるようにすれば、累進課税の所得税ではなく、法人税を適用できます。
また、法人化することで、役員報酬として所得を受け取るほか、家族を従業員として雇用し、実際に業務を依頼して給与を支払うことで、家計全体の所得分散を図り、税負担を軽減できる可能性もあります。
その際は、税務上の問題とならないよう、業務実態や職務内容に見合った報酬であることが大前提となります。不当に高額な給与や、実態のない業務に対する支払いは、税務調査で否認されるリスクがあるため注意が必要です。
参考:国税庁|所得税の税率
消費税の課税事業者になる見込みがあるとき
消費税の課税対象になる見込みがあるときもマイクロ法人の設立を検討するタイミングです。
具体的には、基準期間(原則2年前)の課税売上高が1,000万円を超えると、翌々年度から消費税を納める義務が生じます。
例えば、副業などで売上が年間800〜900万円台に達している場合、今後1,000万円を超える見込みがあると想定されます。その際、新たに法人を設立することで、一定の条件のもとで設立後しばらくは消費税の免税事業者として扱われる可能性があります。
この免税期間を利用すれば、顧客から消費税を受け取っても納付義務がないので、その分資金繰りを改善できる可能性があるのです。
ただし、免税事業者であることが必ずしも顧客などの取引先にとって有利に働くわけではなく、特にインボイス制度開始後は適格請求書発行事業者の登録が求められ、免税事業者としての扱いが不利になる場合もあります。
参考:国税庁|消費税の仕組み
取引や資金調達などで社会的信用が求められるとき
社会的信用が求められるときも、サラリーマンがマイクロ法人を設立するタイミングの一つです。
例えば、事業の規模を広げたかったり、資金を集めたいなどの場合はマイクロ法人の設立は有効な選択肢となります。
実際に、個人事業や副業で順調に成果を上げていても、法人格を持たないことが足かせとなり、以下のような制限を受けることがあります。
- 金融機関から事業資金を借りにくい
- 法人カードやクレジットカードの審査が通りづらい
- BtoB取引など一部の企業と契約が結べない
- 求人媒体や業界イベントの参加条件を満たせない
しかし、法人化により登記情報や代表者肩書きが明確になるため、個人事業よりも取引や金融機関の対応で有利になる場合があるのです。
また、補助金や助成金、各種融資制度の中には「法人であること」が利用条件となっているケースも少なくないため、今後の事業戦略や資金調達の幅を広げる上でも、法人化は有力な手段となります。
サラリーマンがマイクロ法人を設立するメリット
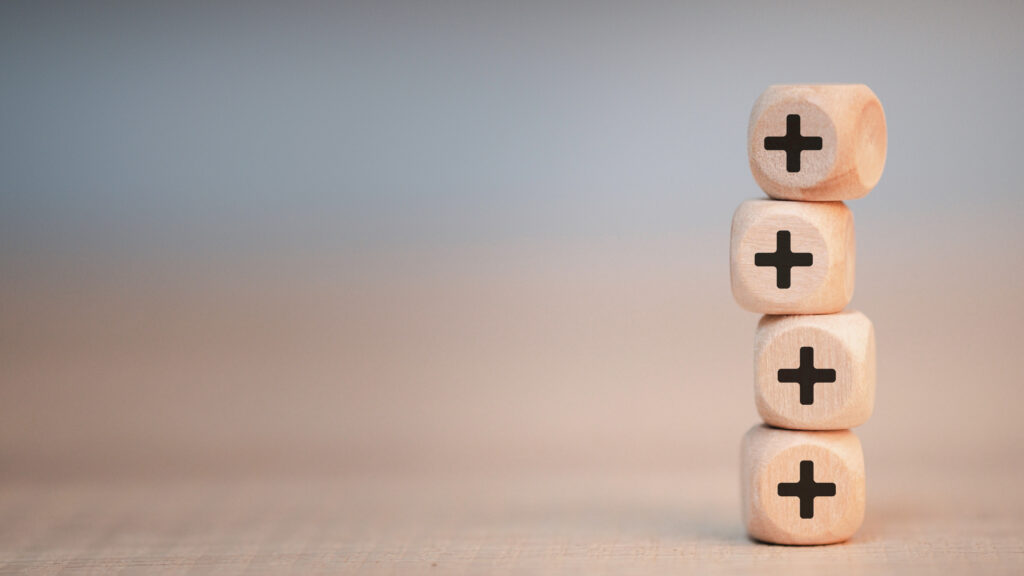
サラリーマンがマイクロ法人を設立するメリットとして、以下の3つが挙げられます。
- 節税効果が期待できる
- 社会的信用度が高まる
- 経費計上できる範囲が広がる
節税効果が期待できる
マイクロ法人を設立することのメリットの一つとして、まず節税効果が期待できる点が挙げられます。
個人が支払う所得税は「累進課税方式」が採用されており、収入が増えるにつれて税率も上昇し、最高税率は45%で、さらに住民税を加えると合計で最大55%まで負担が増えます。
一方、法人が納める法人税は、所得額や法人形態によって税率が変動しますが、基本税率は23.2%です。
これに地方法人税などを含めても、実効税率はおおよそ34.5%にとどまり、個人に比べて最高税率は低くなります。
そのため、一定以上の高所得者の場合、事業を法人化することで税負担を抑えられる可能性があります。ただし、個別事情により異なるため、具体的な試算は税理士にご相談ください。
参考:国税庁|所得税の税率
社会的信用度が高まる
個人事業主と法人を比較すると、法人は登記簿や資本金といった要素があるため、対外的に信頼性を示しやすいメリットがあります。
法人を設立するには、法務局での登記が不可欠で、登記が完了することで、国が正式にその存在を認めたこととなり、登記簿謄本には設立日などの情報が明記されます。
さらに、法人は資本金1円から設立可能ですが、社会的信用を高めるために一定以上の資本金を用意する場合があり、その点も信頼性向上の一因と言えます。実際に、資本金があるという事実は、企業としての財務的な基盤を示しています。
一方で、個人事業主の場合は「事業を始めよう」と思った時点で開業することもでき、税務署へ開業届を提出する必要はありますが、法人登記のような公的な登記制度はありません。
こうした要素から、法人は取引先や金融機関から高く評価されやすく、結果として融資の承認が得やすかったり、仕事の受注につながりやすかったりする傾向にあるのです。ただし、必ずしも法人だから信用されるとは限らず、事業内容や実績、財務状況も大きな判断材料となります。
経費計上できる範囲が広がる
マイクロ法人を設立することで、個人事業主と比べると、経費として認められる範囲は広くなる点もメリットです。
個人事業主の場合は、生活費などの私的な支出と、事業に関連する支出が日常的に混ざって発生することが多く、その中から事業に関係する部分だけを選び出して経費計上する必要があるのです。
一方、法人の場合、役員報酬や福利厚生費など、個人事業主では計上しにくい費用を経費として扱えるケースがあります。
ただし、法人であっても事業に関連しない支出は経費になりません。名目は会社の支出であっても、実際には経営者や従業員が私的に使用している場合などは経費として認められないので注意が必要です。
参考:国税庁|必要経費の知識
サラリーマンがマイクロ法人を設立するデメリット

サラリーマンがマイクロ法人を設立することのデメリットとして、以下の4つが挙げられます。
- 設立費用がかかる
- 事務手続きが煩雑になる
- 赤字でも税金の支払いが必要になる
- 維持費が発生する
設立費用がかかる
マイクロ法人を作る際には、初期費用が必要になる点がデメリットとなります。
例えば、株式会社を新たに立ち上げる場合はおおよそ20〜25万円、合同会社であれば約10万円ほどの費用が一般的です。
さらに、バーチャルオフィスや電話代行サービスを導入する場合、これらは設立時の費用とは別に毎月の利用料が発生し、年間を通して一定額の維持コストも必要になります。
そのため、税負担や社会保険料の軽減を目的にマイクロ法人を設立する場合には、その節約効果が設立および運営にかかる費用を上回るかどうかを事前に試算しておくのがおすすめです。
事務手続きが煩雑になる
マイクロ法人を設立する場合、個人事業主と比べて事務作業の負担が増える可能性がある点もデメリットとなります。
個人事業主の場合は、年に一度の確定申告だけで手続きが完了しますが、マイクロ法人の場合はそれに加えて法人の決算申告も必要であり、具体的には、以下のような資料の提出を求められます。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 勘定科目内訳明細書
- 法人事業概況説明書
上記の書類を自力で作成するのは難しく、多くの場合は税理士などの専門家へ依頼することになり、その分の費用負担が発生してしまいます。
赤字でも税金の支払いが必要になる
マイクロ法人を設立することのデメリットとして、赤字でも税金の支払いが必要になる点も挙げられます。
個人事業主であれば、事業が赤字の年度には所得税や住民税は発生しません。一方で、法人は赤字の場合でも、法人住民税の均等割が発生します。
均等割とは、前年の所得額に関係なく、対象となる全ての法人や個人に一律で課される税金です。
法人住民税の均等割は自治体によって異なりますが、多くの自治体で約7~8万円が標準的な金額です。
そのため、利益が出ていない年でも一定額の税負担が発生する点は、マイクロ法人設立を検討する際のデメリットの一つと言えます。ただし、個人事業主の場合でも、住民税の均等割が発生するケースはあるため、法人だけの特殊な負担とは限りません。
参考:総務省|法人住民税
維持費が発生する
マイクロ法人の設立においては、初期費用のほかに維持費が発生する点もデメリットです。
マイクロ法人を立ち上げる際には、一定の初期費用が必要となり、株式会社であればおおよそ24万円、合同会社の場合は約10万円が目安です。
また、開業時だけでなく、運営するにあたっては、バーチャルオフィス利用料やサービス利用料、専門家への報酬といった、一定の維持コストが必要です。これらのサービス費用は月単位で発生するので、年間ベースで見るとかなりの金額になってしまうケースもあります。
これらの費用は事業規模や利用するサービス内容によって変動するため、設立による節税効果とのバランスを事前に試算しておくことが重要です。
サラリーマンがマイクロ法人を設立する際の注意点

サラリーマンがマイクロ法人を設立する際の注意点として、以下の2つが挙げられます。
- 社会保険料の節約はできない
- 脱税行為だと判断されないように注意する
社会保険料の節約はできない
会社員がマイクロ法人を設立しても、社会保険料を大きく削減できるケースは多くありません。
勤務先ですでに社会保険に加入している場合でも、法人側での役員報酬の設定によっては、追加で社会保険加入義務が生じることがあります。
勤務先の社会保険に加入中のサラリーマンの場合、法人で役員報酬をもらうと新たな社会保険加入義務が生じるため、社会保険料が増加する可能性が高く、節約できるケースは稀です。
複数の会社から報酬を得ている場合には、報酬を合算した金額を基準に保険料が決定され、その金額を各会社に按分して納付する仕組みです。算出された総額は、各会社からの報酬比率に応じて分割され、それぞれの給与から天引きされる形で納付されます。
ですから、「節税できる」と思い込んで安易に法人化すると逆効果になる場合があるので注意が必要です。
参考:日本年金機構|複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き
脱税行為だと判断されないように注意する
サラリーマンがマイクロ法人を設立する際には、脱税行為だと判断されないように注意が必要です。
マイクロ法人を設立すること自体は、個人事業主や会社員であっても法律違反にはあたりませんが、税務署から脱税の疑いを持たれる可能性があります。
特に、個人事業と法人を並行して運営する場合、事業内容や収益区分を明確に区別しておかないと、税務署から「所得を分散させているのではないか」と疑義を持たれる可能性があります。
不要な税務調査リスクを避けるためにも、適切な区分経理や契約関係の整理を行うことが重要です。
マイクロ法人を設立するかどうかは慎重に判断しよう!

今回は、サラリーマンはマイクロ法人を設立できるかどうか紹介しました。
サラリーマンであってもマイクロ法人を設立することは可能ですが、その目的や事業内容によってメリット・デメリットは大きく異なります。
たとえば、副業で一定の収益が見込める場合には、法人化することで社会保険や税務上の取り扱いが変わる可能性があります。ただし「登記費用」「複雑な申告手続き」「赤字でも法人住民税が発生する」といった負担もあり、必ずしも節税につながるとは限りません。
また、売上規模や経費の状況によっては、個人事業主として活動したほうが結果的に税負担を抑えられるケースもあります。
そのため、法人化するかどうかは将来の事業計画や収益の見込みなどを総合的に判断することが重要です。
実際に法人設立を検討される場合は、専門家である税理士にご相談いただくことで、最適な選択が可能になります。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。





