メニュー
会社設立
株式会社の設立人数は何人から?1人で設立するメリット・デメリットも解説

読了目安時間:約 7分
株式会社は発起人が1人でも設立可能ですが、取締役会を設置する場合や、許認可が必要な特定事業では、法律により役員や従業員の人数要件が定められていることがあります。
また、1人で事業運営を行う場合、意思決定や業務負担が集中し、経営に支障をきたすリスクもあるため注意が必要です。
株式会社を設立する際は、自社にとって無理のない適切な人数を検討し、人数によるメリット・デメリットを十分に把握しておきましょう。
本記事では、「株式会社の設立に必要な人数」や「株式会社を1人で設立することのメリット・デメリット」、「株式会社を設立する際の手続きの流れ」についても解説していきます。
ぜひこの記事を参考にして、スムーズな株式会社の設立に役立ててください。
目次
株式会社の設立人数は何人から?
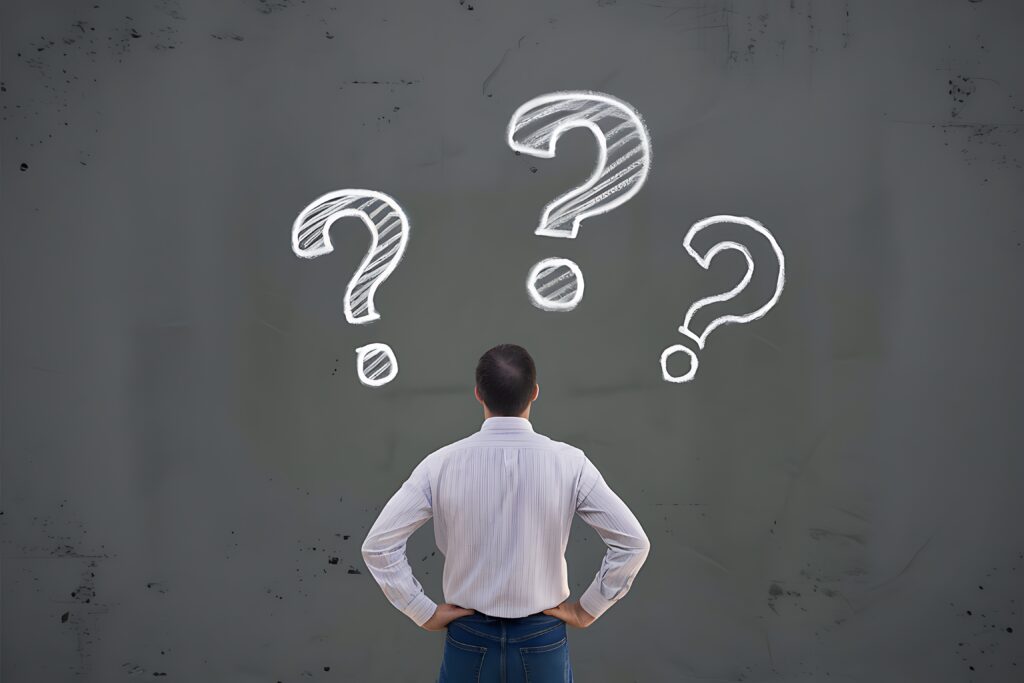
株式会社を設立する際に必要な人数は、会社法の改正により大きく見直され、最低1名で設立可能です。その1人が取締役と株主の役割を兼ねることもできます。
この改正は、平成18年に施行された新しい会社法によるもので、以前は取締役会の設置が義務だったため、最低3人の取締役を用意しなければならない決まりがありました。
しかし、現在では取締役会の設置が任意となり、個人でも株式会社を設立・運営できるようになりました。
この制度変更によって、特にスタートアップや個人事業主が法人を設立しやすくなり、ビジネス展開の自由度が高まりました。ただし、税制面でのメリット・デメリットについては、個々の状況に応じた慎重な検討が必要です。
株式会社を1人で設立することのメリット

株式会社を1人で設立することのメリットについては、以下の4つが挙げられます。
- 柔軟な経営判断ができる
- 採用コストを抑えられる
- 必要資金を抑えられる
- 株式会社設立の手続きの負担が少ない
それぞれのメリットについて解説していきます。
柔軟な経営判断ができる
会社を設立する際に1人で立ち上げる場合は、事業の方針や重要な決定を自分ひとりで行えるため、判断が迅速になり、ビジネスの展開にも柔軟に対応しやすくなります。
これに対して、複数人で設立した場合は、経営方針や重要な事項を共同で協議・決定する必要があり、意見調整に時間がかかることから、機動的な対応が難しくなるケースもあります。
もちろん、複数の役員とともに起業すれば、様々な視点から意見を出し合いながら会社運営ができるというメリットもあります。
採用コストを抑えられる
1人で株式会社を設立することで、従業員の維持費や採用コストを抑えることができます。
一般的に、会社設立直後や創業間もない段階では、従業員の採用に多くの困難が伴います。
企業としての信用力がまだ十分に確立されていないため、求人サイトや転職エージェントへの依存が避けられず、結果として多額の費用と時間を要することもあります。
さらに、優秀な人材を採用できた場合でも、入社後すぐに退職されてしまうと、再び採用活動を行う必要があり、余計なコストや労力が発生してしまいます。
必要資金を抑えられる
法人設立において、設立者が1人の場合、複数人で始める場合と比較して初期費用を大幅に抑えられます。
仕事に必要なスペースや設備も自分自身の分だけで済むため、必ずしも広いオフィスを用意する必要がありません。
人数が増えると、それに応じた広さの事務所や人数分のパソコン、机、椅子といった備品が求められ、コストが膨らむのも事実です。
一方、1人であれば現在使っている設備をそのまま活用できることも多く、新たな投資をほとんどせずに済む可能性もあります。
また、オフィスを新たに借りる必要もなく、自宅を事務所として使用したり、バーチャルオフィスを活用することで、さらに経費を節約することも可能です。
株式会社設立の手続きの負担が少ない
株式会社を1人で設立する場合、手続きがシンプルになります。
複数人で設立を進めると、会社の基本方針や内部ルールを決める際に、意見が分かれてしまい、話し合いがスムーズに進まないことが挙げられます。
具体的に、株式会社設立にあたって発起人が決めなければならない項目は、以下が挙げられます。
- 商号(会社名)
- 本店の所在地
- 事業内容
- 資本金の金額
- 発行可能な株式の総数
- 発起人が引き受ける株式の数
- 会社の機関設計(取締役会の有無など)
- 設立時の取締役(役員)
- 事業年度
発起人が複数いる場合、すべてについて全員の合意が必要になります。
一方、発起人が1人であれば、こうした決定をスムーズに進めることができます。
株式会社を1人で設立することのデメリット
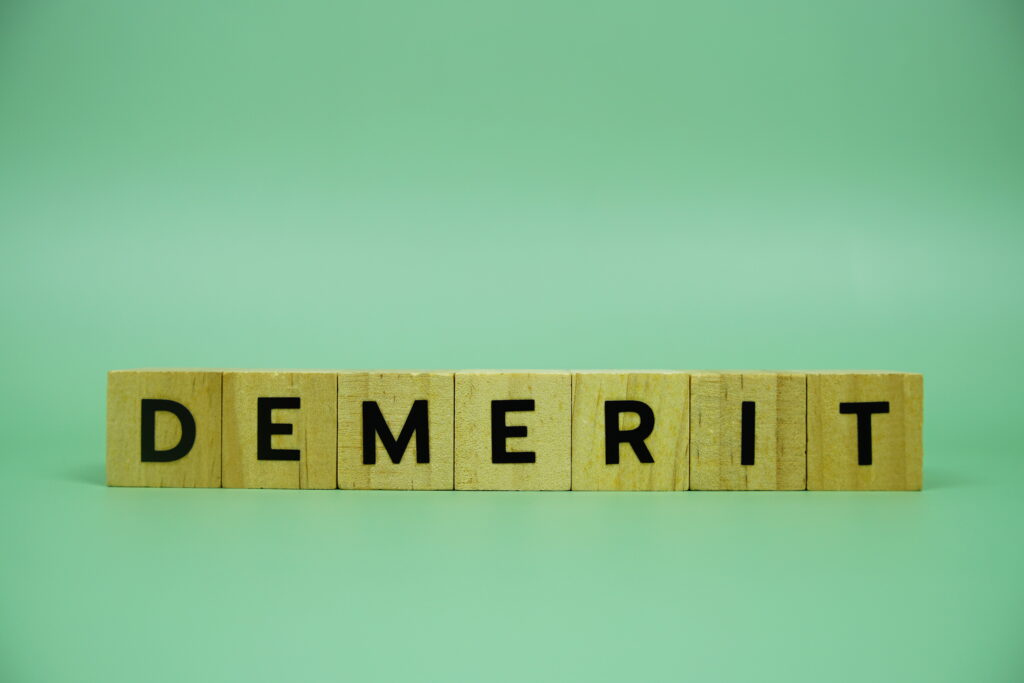
株式会社を1人で設立することのデメリットについては、以下の3つが挙げられます。
- 社会的信用度が低くなる
- 利益や売上の拡大がしにくい
- 負担が多くなる
それぞれのデメリットについて解説していきます。
社会的信用度が低くなる
1人で株式会社を設立する場合、組織の規模が小さいため、社会的信用において不利になるリスクがあります。
例えば、信用保証協会や金融機関では、企業の安定性を判断する際に「人的資源の投資状況」や「組織体制」を重要視する傾向があるとされています。
もちろん業種や取引内容によっては社員数が直接影響しないケースもありますが、一般的なイメージとしては、従業員数が多い会社の方が安定していると見られる傾向が強いといえるでしょう。
利益や売上の拡大がしにくい
株式会社を1人で設立するデメリットとして、利益や売上の拡大がしにくいことが挙げられます。
実際に、1人で事業を運営して売上や利益を伸ばしていくには、どうしても限界が存在します。
事業の内容によりますが、個人でこなせる業務量や時間には自然と制約がかかるので、ある一定の段階までは成長できたとしても、それ以上の飛躍を目指す場合には、人手を増やす必要が出てきます。
負担が多くなる
1人で会社を立ち上げる場合、日々の業務や責任を自分ひとりで担うことになるので、負担が多くなるデメリットが挙げられます。
また、1人で始める事業は、成功も失敗もすべて自分の力量にかかっています。
自分のペースで自由に物事を進められる一方で、成果や結果に対してもすべて自らが責任を負うことになります。
万が一、負担が多かったり不安を感じる場合は、外部に相談役やサポートをしてくれる専門家を確保しておくことをおすすめします。
株式会社設立に必要な手続き

株式会社設立に必要な手続きについては、以下の5つが挙げられます。
- 必要事項を決定する
- 定款を作成する
- 資本金の払い込みを行う
- 登記申請の必要書類を揃える
- 登記申請を実施する
それぞれの手続きについて解説していきます。
必要事項を決定する
株式会社を設立する際には、まず初めに重要な事項を決定しておく必要があります。
具体的に、事前に検討しておくべき必要事項は以下のとおりです。
- 商号(会社名)
- 本社所在地
- 事業目的
- 資本金と出資者
- 役員体制
- 設立日
- 事業年度
これらの項目は、会社設立時に作成する「定款」や「登記申請書」に記載しなければならないため、漏れなく決めておきましょう。
また、法人実印も重要です。
登記申請が完了すると、登記簿謄本や印鑑証明書が必要になりますが、これらには法人実印の押印が求められます。
法人実印は、外側に会社名、内側に「代表取締役印」などを彫刻した形が一般的です。インターネットや専門業者で注文可能ですが、作成には時間がかかるため、設立準備段階で早めに手配するのが賢明です。
登記申請の際には、法人印鑑の届出も併せて行い、登記完了後に印鑑証明書の発行を受けられるようにしておきましょう。
定款を作成する
次に、定款の作成と認証手続きを行います。
定款とは、先ほど決定した必要事項に加え、会社の運営方針やルールを明文化したものです。
株式会社を立ち上げるには、この定款を作成し、所轄の公証役場で認証を受けることが求められます。
定款には特定の書式はありませんが、細かな規定が多く、必要書類の中でも特に作成に手間がかかる部分とされています。
自身で作成することも可能ですが、誤りがあると無効になってしまうリスクも伴うため、時間や労力を節約したい場合には、専門家への依頼を検討するのも賢明な選択肢と言えます。
資本金の払い込みを行う
定款の作成と認証手続きが完了後は、資本金の払い込みを行います。
この時点では、まだ法人名義の銀行口座を開設することができないので、資本金は発起人自身の個人名義口座へ振り込むことになります。
かつてはゆうちょ銀行への払い込みが認められていませんでしたが、現在では利用可能になっています。
しかし、振込手数料が発生するので、あらかじめ確認しておくようにしましょう。
登記申請の必要書類を揃える
次に、登記申請に必要な書類をきちんと揃え、提出前に念入りな確認を行ってください。
登記手続きを進めるためには、次の書類を準備する必要があります。
- 登記申請書
- 定款(会社の基本ルールを定めた書類)
- 登録免許税分の収入印紙を貼付した台紙
- 発起人の決定書(発起人が複数いる場合は発起人会議の議事録)
- 代表取締役などの就任承諾書
- 設立時取締役の印鑑登録証明書
- 資本金の払込を証明する書類
- 印鑑届出書
登記申請書については、決まった書式が定められており、書き方に誤りや記載漏れがあると差し戻される可能性があるので、注意を払って作成するようにしましょう。
登記申請を実施する
必要書類がすべて整ったら、いよいよ登記手続きに進みます。
登記申請の方法には、以下の3つの選択肢があります。
- 直接法務局の窓口へ提出する
- 書類を郵送して申請する
- インターネットを利用してオンライン申請する
どの方法を選んでも、提出した書類に問題がなければ、通常受付から約10日ほどで登記が完了し、法人として正式に認められる流れです。
しかし、法務局から「登記完了」の通知は基本的に行っていません。
そのため、進捗を確認したい場合は、担当の法務局に直接問い合わせるか、法務局の公式サイトで登記完了予定日をチェックする必要があります。
株式会社を1人で設立する際の注意点

株式会社を1人で設立する際の注意点については、以下の3つが挙げられます。
- 経営判断の誤りに気づきにくい
- 経費が認められにくい傾向がある
- 事前の準備を入念にしておく
それぞれの注意点ついて解説していきます。
経営判断の誤りに気づきにくい
会社を1人で経営していると、自分の判断ミスに気づかず、誤った方向に進み続けてしまうリスクがあります。
しかし、取締役を複数名に増やすとなると、役員報酬の支払いや役員変更登記に伴う登録免許税などの費用が発生してしまう問題があります。
こうした場合には、経営と対等な立場で冷静な助言をしてくれる外部の専門家を活用することも、選択肢として考えておくことをおすすめします。
経費が認められにくい傾向がある
1人で株式会社を立ち上げた場合、経費として認められにくい支出が発生することがあります。
特に問題となりやすいのが、福利厚生費に関する取り扱いです。
役員が負担する社会保険料は必要経費として認められますが、それ以外の福利厚生費に該当する支出については、役員しか在籍していない場合、税務上認められにくい傾向があります。
福利厚生は本来、社員全員を公平に対象とするべきものとされており、役員しか在籍していない場合、その支出が経費と認められるのは難しい場合もあります。
例えば、家族のみで経営している場合、実態によっては社員旅行の費用を福利厚生費として認められないケースもあります。
事前の準備を入念にしておく
1人で株式会社を設立する場合は、登記申請や各種官公庁への届出といった設立手続きをすべて自分で進める必要があります。
また、設立後の経営においても、意思決定や重要事項の判断、資金管理などを1人で担うことになるため、相当な時間と労力が求められます。
加えて、開業資金も自力で調達しなければなりません。
そのため、会社運営をスムーズに行うためにも、事前の準備を入念にしておくことが重要です。
株式会社を1人で設立するか入念に検討しよう!

今回は、株式会社の設立人数について紹介しました。
1人で株式会社を設立する場合、初期コストを抑えやすいというメリットがある一方、業務の負担がすべて自身に集中してしまう点などに注意が必要です。
1人で株式会社を立ち上げるかどうかを決める際には、こうしたメリット・デメリットを総合的に踏まえつつ、起業予定の業種の特性も考慮して慎重に判断することが大切です。
今回の記事を参考にして、株式会社を1人で設立するか入念に検討してみてください。
‐免責事項‐
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。





