メニュー
起業・開業
起業資金は最低でもいくらかかる?必要な費用の項目や資金の集め方

読了目安時間:約 6分
これから起業しようと思っても、どれくらいの費用を想定すれば良いか分からず困っている方は多いのではないでしょうか。
特に、なるべく少ない資金で起業したい方にとっては気になるポイントです。
本記事では、起業に必要な資金の目安について解説します。
結論として、資金なしで起業することは可能ですが、初期費用に加えて月々発生するコストも考慮しなければならないため、ある程度の資金を用意しておく必要があるのです。
起業資金の調達方法についても詳しく説明しますので、起業後に事業を維持できるよう、必要な資金についてしっかり把握したうえで自身に合った資金調達方法を選択し、起業を成功させましょう。
目次
起業手続きにかかる費用
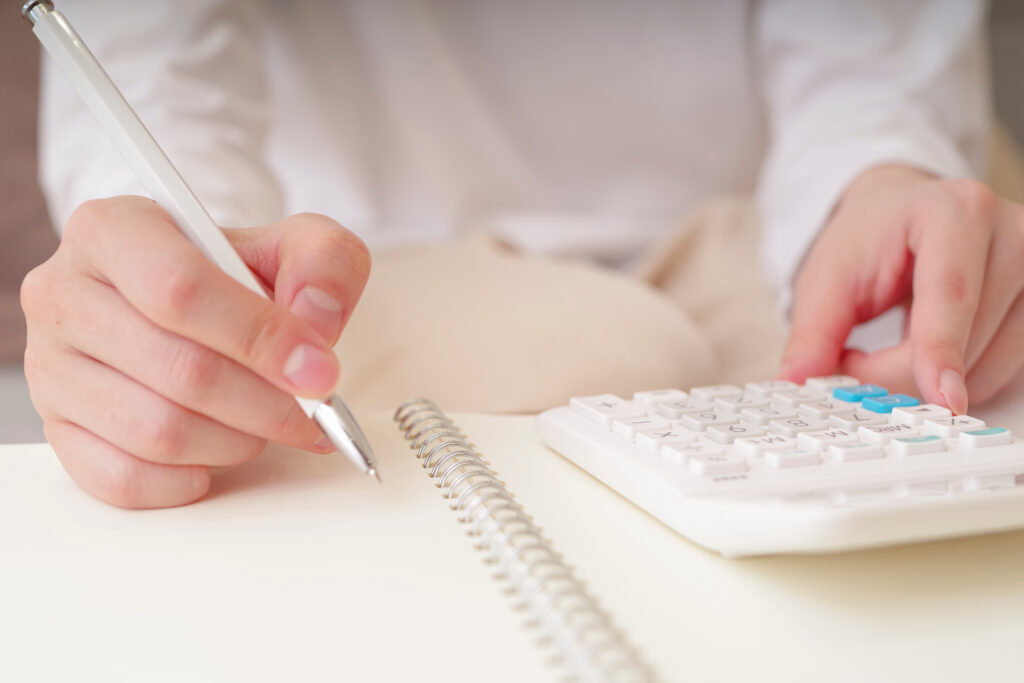
初期費用をなるべくかけず、手軽に起業したいと考えている方は多いかと思いますが、結論として、初期費用をほぼかけずに起業する「0円起業」は可能です。
ただし、起業時に必要な資金は業種や会社形態、事業規模、従業員をどのくらい雇うかなどによっても大きく異なります。
ここでは、起業時に最低限必要な金額について説明します。
個人事業主なら0円起業が可能
個人事業主の場合、開業手続きに費用がかからないため、0円で起業することが可能です。
税務署に開業届を提出すれば、個人事業主として事業を開始できます。
例えば、WEBデザイナーやWEBライター、動画撮影、編集などのように在宅完結型の仕事やオンラインビジネスを手掛けるフリーランスや個人事業主がスモールスタートで事業を始める際に、初期費用を抑えて起業するケースが多いです。
合同会社なら約6万〜11万円
合同会社を起業する場合、約6万〜11万円の費用が必要になります。
主な内訳は以下の通りです。
- 登録免許税:約6万円
- 登記時に必要な謄本手数料:約2,000円(1ページ250円)
- 定款に貼る印紙代:4万円 (※電子定款認証を行う場合は不要)
合同会社は一般的に株式会社よりも少ない資金で起業が可能となりますが、合同会社と株式会社との大きな違いは株式が発行できるかどうかです。
そのため、株式による出資を考えていない場合は手続きが簡易で登録免許税の低い合同会社を選んでも良いでしょう。
株式会社なら約21万〜26万円
会社形態として一般的な「株式会社」を起業する場合、約21万〜26万円の費用が必要になります。
主な費用内訳は以下の通りです。
- 登録免許税:約15万円
- 登記時に必要な謄本手数料:約2,000円(1ページ250円)
- 定款認証手数料:約5万円
- 定款に貼る印紙代:4万円 (※電子定款認証を行う場合は不要)
- その他雑費:約1万円( 会社の実印作成代、個人の印鑑証明書取得費、登記簿謄本の取得費 など)
株式会社の場合、株主は出資額に応じて議決権を持ち、経営は役員が行います。
設立に手間や費用がかかることから、合同会社よりも社会的な信用度が高い傾向にあります。
起業資金は最低いくら必要?

起業するには、手続きにかかる費用の他にもさまざまなコストがかかり、業種によって起業に必要な資金は大きく異なりますが、個人事業主で最低でも200万〜300万円程度、法人だと400万〜500万円程度は必要です。
日本政策金融公庫の「2023年新規開業実態調査」によれば、実際に起業でかかった開業資金の平均は1,027万円、中央値は550万円となっています。
開業時に必要となる資金は、大きく以下の2つに分けられます。
- 設備資金
- 運転資金
それぞれ詳しく説明します。
設備資金|事業に必要な設備を購入するための資金
設備資金は、開業のために必要な施設や機械、備品の導入にかかる費用を指します。
具体的には以下の項目です。
- 土地・建物、車両、機械の購入
- 備品購入資金(パソコン、OA機器、事務用品など)
- ホームページ作成、固定電話・FAX回線などの設置にかかる費用
- 賃貸物件の入居資金
- 事業所の改修・改装にかかる費用 など
設備資金は一度に多額の支出が発生するのが特徴で、それを回収するだけの収益を得るには、長い期間事業を継続する必要があります。
運転資金|事業を継続するために日常的にかかる費用
運転資金とは、事業を継続する上で必要となる資金で、以下の項目が挙げられます。
- 人件費(従業員への給与など)
- 事業所・店舗の維持費(家賃・光熱費・通信費・消耗品費など)
- 広告宣伝費(広告やスポンサー活動の資金)
- 商品の仕入代金
- 消耗品費
- 外注費(業務を外注した場合)
- 税金(法人税や消費税など)
一時的に発生する設備資金に対して、運転資金は継続的に発生するため、事業が軌道に乗るまでの間に事業を継続させるためにも、運転資金をある程度確保しておくのが望ましく、一般的に3ヶ月~6ヶ月分の運転資金を準備するのが目安です。
起業資金が足りない場合は資金調達が必要

起業に必要な資金が足りない場合、資金調達が必要になりますが、資金調達には以下のように融資や補助金・助成金、出資など、さまざまな方法があります。
- 政府系金融機関からの融資を受ける
- クラウドファンディングを活用する
- 出資を受ける
- 家族や親族から調達する
- 補助金・助成金を受ける
- 資産を売却する
- 退職金をもらう
どの資金調達方法が適しているかは、事業内容や規模によって異なります。
それぞれ詳しく説明しますので、参考にしてください。
政府系金融機関からの融資を受ける
創業者向けの融資制度を展開している、日本政策金融公庫などの政府系金融機関から融資を受けることを検討してみましょう。
日本政策金融公庫の「新規開業資金」では、無担保・無保証人で融資が可能で、自己資金要件もないため、より多くの起業家が融資を受けやすくなっています。
ただし、融資を行う立場からすると自己資金が多い事業主のほうが信頼をおけるため、起業への強い意思を示すためにもできる限りの自己資金を用意するのが望ましいです。
また、銀行や信用金庫などの金融機関から融資を受ける方法もありますが、創業融資の審査が厳しい傾向にあるため、審査落ちする可能性が高いです。
参考:日本政策金融公庫
クラウドファンディングを活用する
クラウドファンディングとは、インターネット上でプロジェクトを多数の支援者に公開し、共感や応援として資金を募集する仕組みです。
目標金額に上限がなく、比較的自由度の高い資金調達方法であるため、支援者を集めることができればより大きな資金で開業でき、調達後の資金を柔軟に活用できるメリットがあります。
また、開業前から認知度を拡大できたり、ファン作りができたりするため、開業後の事業運営を安定させやすいです。
ただし、集まる金額は不確定であり、資金を集めるには魅力的なアイディアとインターネット上でのアピールが求められます。
出資を受ける
個人投資家やベンチャーキャピタルなどから出資を受ける方法があります。
出資は、投資家が企業の株式を取得する代わりに資金を提供する方法で、借入金ではないため返済の必要がなく、支援者との繋がりができ、今後の事業展開に活かせるほか、起業に必要な知識を学習できるなどのメリットがあります。
一方、競争が激しく、出資者は出資した金額以上のリターンを期待するため、出資者が魅力を感じる事業でなければ、そもそも出資は成立しません。
そのため、資金を受ける側は出資者に対して相応のメリットを与えられるよう、事前の準備と計画が必要となります。
家族や親族から調達する
起業資金を親や親族、友人などから援助してもらう方法もあり、特に親から資金を出してもらって起業するケースはよくあります。
ただし、親から資金を受ける場合、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかる可能性を考慮しなければなりません。
また、資金を「借りる」場合には、金融機関から融資を受ける際に「自己資金」とはみなされないことが多いため注意が必要です。
補助金・助成金を受ける
補助金や助成金は、直接的または間接的に公益上必要があると政府が判断した場合に、事業者などに交付する給付金であり、原則として返済不要であるため、給付を受けられれば事業に大きなメリットとなります。
補助金と助成金はそれぞれ以下の特徴があります。
| 補助金 | 助成金 | |
|---|---|---|
| 受給条件 | 予算・件数に上限があり、抽選の場合がある | 条件を満たしていれば基本的に支給される |
| 難易度 | 難易度が高め | 難易度が低め |
| 金額 | 大きいことが多い | 小さいことが多い |
| 対象範囲 | 幅広い事業を対象とするものが多い | 雇用関係を対象とするものが多い |
助成金は比較的条件ハードルが低いですが、支給金額はあまり高くないケースが多く、一方、補助金はさまざまな事業が対象となり、支給金額も大きく設定されているケースが多いですが、その分難易度が助成金よりも高いです。
また、補助金も助成金も原則として「後払い」という点を理解しておきましょう。
資産を売却する
自身が所有している土地、車、有価証券などの資産を売却して得たお金も、起業時の自己資金として有効です。
買い手がいる場合はすぐに資金調達ができるほか、不動産の場合は維持管理費の削減にも繋がります。
ただし、買い手がいなければ資産とならず、売却の手間や手数料が発生するなどのデメリットもあります。
退職金をもらう
会社を辞めると、退職金や失業給付金が支給されるケースが多いですが、これらの資金を起業資金として活用することが可能です。
そのため、受け取った退職金をもとに起業する場合は、あらかじめ会社の労務規定を確認して退職金の金額や受給資格などを把握しておくと良いでしょう。
ただし、全額を起業資金に充てるのではなく、退職後の自身の生活に必要な資金とのバランスを考慮しながら充当する金額を決定する必要があります。
自己資金がないと起業が難しい?融資を受ける際の注意点

銀行から起業融資を受けるためには、基本的に「自己資金」が必要になります。
なぜなら、お金を貸す側はリスクを減らすために問題なく返済できるかどうかを審査するためです。
自己資金なしで融資を受ける場合、以下のデメリットがあります。
- 融資を受けにくい
- 融資額が少額になる可能性がある
- 金利が高くなる可能性がある
自己資金なし、もしくは少ない自己資金での起業は、資金面での信頼性が低く見られてしまうため、銀行融資の審査に通りにくくなる可能性があり、たとえ融資を受けられたとしても、融資額が少額になったり、金利が高くなったりする恐れがあります。
自己資金に含められるもの
基本的に、自分の財産のうち、出所がはっきりしているものに関しては自己資金と認められます。
具体的には以下が挙げられます。
- 退職金
- 生命保険の解約金
- 親族からの贈与金(返済不要であることが明確なもの)
- 相続金
- 資産を売却したお金(不動産や車などの)
- みなし自己資金
- 第三者割当増資
返済義務がない贈与も自己資金とみなされる場合があります。
また、お金の流れが把握できるものは自己資金と認められるため、起業を考えている方は、お金の管理は通帳で行うのが望ましいです。
自己資金と認められないもの
銀行融資の際に必要な自己資金は、手元にあるお金を指すわけではありません。
具体的には、以下のものは自己資金とはみなされないため、自己資金の計算に含めないようにしましょう。
- 他の金融機関からの融資金
- 親族や知人からの借入金
- タンス預金
- 出どころ不明の預貯金
返済義務のあるものはすべて自己資金としては認められず、お金の流れが不明瞭なものは見せ金とみなされる可能性があるため注意が必要です。
起業に必要な資金を把握しよう

開業時に必要な資金は、業種や事業規模、従業員の数などによって異なりますが、200万〜1,000万円程度は必要になってきます。
起業で失敗しないためにも、事前に自己資金や起業資金の額を把握し、万全の状態にしておきましょう。
起業資金が高額になる場合、全てを自己資金で賄うのが困難であるため、資金調達の方法を検討してみてください。
資金繰りに課題を感じている方、融資審査に通るか不安な方は、税理士などの専門家に依頼してアドバイスを受けるのが有効です。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。





