メニュー
起業・開業
電子定款を自分で作成・認証する手順とは?メリット・デメリットについても徹底解説

読了目安時間:約 7分
会社を設立する際には、企業名や所在地、事業内容などを明記した「定款」の作成が必要となります。
定款をPDF形式で作成した「電子定款」にすることで、紙の定款では必要な収入印紙代が不要になったり、手続きの手間が少なくなるメリットがあります。
本記事では、電子定款を自分で作成・認証する手順について紹介します。
他にも「電子定款を自分で作成・認証するメリット・デメリット」や「定款を作成する際の注意点」についても解説します。
ぜひこの記事を参考にして、電子定款を自分で作成・認証する手順について理解を深めてみてください。
電子定款を自分で作成・認証する手順
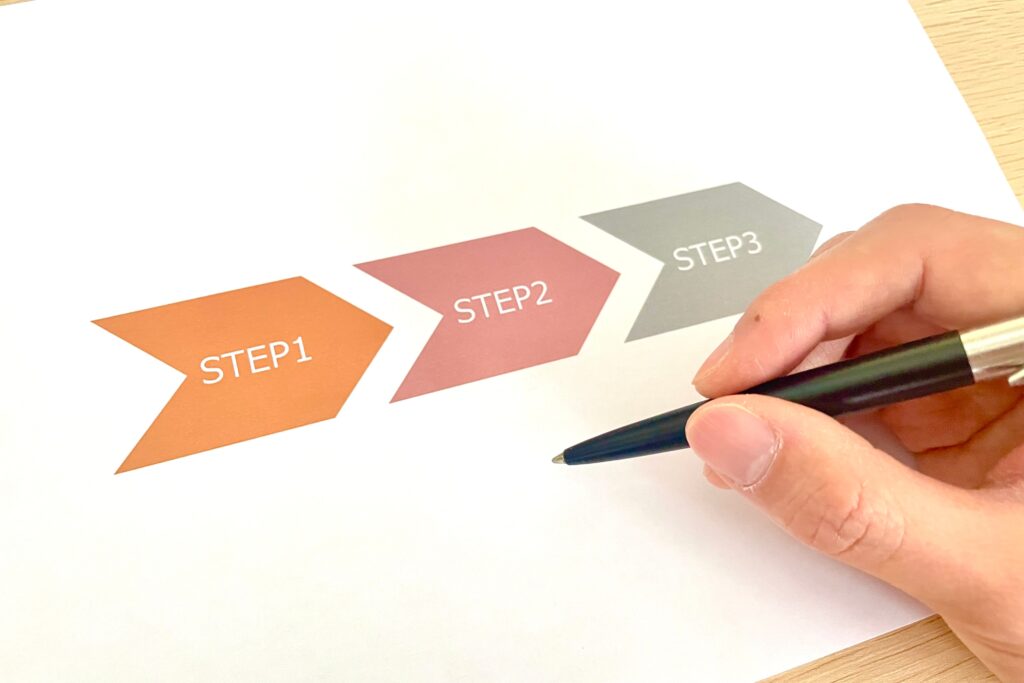
電子定款を自分で作成・認証する手順については、以下のとおりです。
- 電子定款に必要なものを準備する
- 定款の作成
- 定款をPDFに変換
- 電子署名の付与
- オンラインで提出
- 公証役場に予約する
- 公証役場に定款データを取りに行く
それぞれの手順について解説していきます。
電子定款に必要なものを準備する
自分で電子定款を作成・認証する場合は、以下の準備が必要です。
- 必要なもの①:電子証明書が記録されたマイナンバーカード
- 必要なもの②:ICカードリーダライター
- 必要なもの③:電子署名ソフト
- 必要なもの④:電子署名プラグインソフト
それぞれの項目について解説していきます。
必要なもの①:電子証明書が記録されたマイナンバーカード
マイナンバーカードとは、個人情報が入っているICチップが組み込まれたプラスチック製のカードです。
このカードの取得は、郵送、パソコン、またはスマートフォンからの申請が可能です。
また、カードの発行には一定の時間が必要になり、電子定款の提出などで利用を予定している方は、スケジュールに余裕を持って早めに申請手続きを進めることが大切です。
参考:マイナンバーカード
必要なもの②:ICカードリーダライター
電子証明書を活用して電子署名を行うには、専用のICカードリーダー(ICカードリーダライター)が必要です。
ICカードリーダーとは、マイナンバーカードや法人登記用の電子証明書など、ICカードに保存された情報を読み取るための機器で、通常はパソコンに接続して使用します。
また、ICカードリーダーには多様な機種があり、接続方法や対応するカードの種類がそれぞれ異なります。
そのため、利用する電子証明書のタイプや自身のパソコンの仕様に応じて、適切な機器を選定することが重要です。
さらに、ICカードリーダーを正しく動作させるには、必要に応じてドライバのインストールや設定の調整が必要となる場合があります。
詳しい手順については、製品に付属するマニュアルや製造元の公式サイトを確認し、手順に従って設定をおこなうようにしましょう。
必要なもの③:電子署名ソフト
PDF形式で作成された定款に電子署名を施すためには、専用のソフトウェアが必要になります。
一般的に利用されているのが「Adobe Acrobat」が挙げられます。
現在では、パッケージ版の販売は行われておらず、すべてサブスクリプション形式での利用となります。
無料版の「Adobe Acrobat Reader」には電子署名機能は一部制限があるため、あらかじめ注意が必要です。
必要なもの④:電子署名プラグインソフト
電子署名用プラグインソフトとは、PDF形式の定款に電子署名をするためのツールです。
Adobe Acrobatを使用している場合は、法務省が提供する「登記・供託オンライン申請システム」の対応プラグイン「PDF署名プラグイン」を導入することで、スムーズに電子署名を加えられます。
また、ソフトによっては、電子定款の作成と認証に対応しており、電子署名のための専用機材やソフトウェアを自分で用意するのが不要な場合もあります。
このように、選ぶソフトによって会社設立に必要な各種書類もまとめて作成できるので、手続きの手間やコストを大きく抑えることにつながります。
定款の作成
電子定款を自分で作成・認証する際には、「定款」の作成が欠かせません。
定款には、記載内容に応じて3つの分類があります。
| 定款の種類 | 内容 |
| 絶対的記載事項 | 必ず記載すべき事項。会社の名称、事業目的、本店の所在地、資本金の額など、会社の基本的な枠組みを定める項目です。 |
| 相対的記載事項 | 条件により記載が求められる事項。特定の事由や運営形態に応じて、定款への記載が必要になります。 |
| 任意的記載事項 | 任意で記載可能な事項。法的義務はないものの、会社独自の方針や運営ルールとして盛り込める項目です。 |
日本公証人連合会は、法務省と連携して「定款作成支援ツール」をリリースしています。
定款作成支援ツールは、発起人が3名以下のケースに限定されますが、必要事項を入力するだけで、簡単かつ迅速に定款が完成する仕組みになっているので、スピード感を重視する小規模企業の設立に適しています。
定款をPDFに変換
電子定款を自分で作成・認証するには、文書をPDF形式に変換する必要があります。
WordやGoogleドキュメントなどを使えばPDFファイルを簡単に作成できますが、電子定款として提出する際には、単にPDFにするだけでは不十分で、電子署名の付与が求められます。
この電子署名を施すには、署名機能が備わったPDF編集ソフトの使用が必要になります。
法務省のオンラインシステムと高い互換性を持つAdobe Acrobatは、信頼性と操作性の面からおすすめと言えます。
電子署名の付与
PDF形式で作成した定款に電子署名を施すには、マイナンバーカードに電子証明書があらかじめ搭載されている必要があります。
この電子証明書は、住んでいる自治体の窓口でマイナンバーカードを提示し、利用申請することができます。
また、より手軽な方法として、「マイナポータル」アプリを活用してスマートフォン用電子証明書の利用申請をオンラインでおこなうことも可能です。
電子証明書がカードに登録された後は、スマホで申請を進める場合はマイナンバーカード対応のスマホを、パソコンで操作する場合はICカードリーダライターを利用して、マイナンバーカードの情報を読み取る必要があります。
また、「登記・供託オンライン申請システム」から「PDF署名プラグイン」を入手し、公的個人認証サービスポータルサイトで提供されている「利用者クライアントソフト」をダウンロードすることで、PDFファイル形式の定款に対して電子署名を施す準備を整えることができます。
参考:マイナポータル
オンラインで提出
電子定款の提出は、自宅や職場からでも手軽にできる「登記・供託オンライン申請システム」や、デジタル庁が提供するマイナポータル内の「法人設立ワンストップサービス」経由でおこなえます。
しかし、一度電子的に定款を提出すると、その後に内容の誤りが見つかっても訂正や修正が原則できなくなってしまうので注意が必要です。
そのため、事前に作成した定款の内容を、公証役場にメールやFAXなどで送信し、記載内容に不備がないかをチェックしてもらうことをおすすめします。ただし、メールやFAXによる対応の可否は公証役場によって異なるため、事前に確認しましょう。
公証役場に予約する
電子申請システムを介して電子定款を提出すると、そのデータは公証役場に送信され、内容の認証手続きがおこなわれます。
認証後は、会社の本店所在地を所管する公証役場に足を運び、正式に認証された定款を受け取る必要があります。
しかし、公証役場は予約制を採っているので、事前に電話連絡をして予約を確保しておくようにしましょう。
認証時にテレビ会議方式を利用する場合、「登記・供託オンライン申請システム」を通じて定款データを提出できるので、公証役場に直接行く必要がなくなります。
そのため、登記・供託オンライン申請システムを選ぶことで、時間と手間の節約につながります。
公証役場で認証済みの定款を取りに行く
電子定款は電子媒体の提出ですが、合法的な認証の証明として公証役場で書面が発行されます。公証役場で定款を受け取るためには、あらかじめ準備しておくべき書類や持ち物がいくつかあります。
代表的なものとして、以下が挙げられます。
- 電子定款をプリントアウトしたもの
- 発起人全員分の印鑑登録証明書
- USBメモリ(記録媒体)
- 発起人の実印
- 本人確認書類
- 認証にかかる費用(おおよそ3万~5万円程度) など
上記のものを問題なく揃えたうえで定款原本の受け取りが完了すれば、電子定款の認証に関する一連の手続きは終了になります。
電子定款を自分で作成・認証するメリット

電子定款を自分で作成・認証するメリットについては、以下の2つが挙げられます。
- 紙の定款よりも費用を抑えられる
- 手続きの手間が少ない
それぞれのメリットについて解説していきます。
紙の定款よりも費用を抑えられる
電子定款を自分で作成・認証するメリットとして、紙の定款よりも費用を抑えることができます。
実際に、定款を紙で作成して提出する場合、4万円の印紙代が必要となります。
一方、電子定款を利用すれば、この印紙代は課されず、4万円分の費用を抑えることが可能です。
しかし、どちらの形式であっても、公証人に支払う手数料は3万円から5万円程度必要になるので、あらかじめ注意が必要です。
手続きの手間が少ない
電子定款を自分で作成・認証することで、手続きの手間が少ないメリットも挙げられます。
既に必要なツールや機材を所有している場合、電子定款を選択することで4万円の印紙税を節約でき、全体のコストを抑えられます。
一方で、電子定款を利用すれば、オンライン上の手続きが可能となり、テレビ会議システムを通じて認証を受けることができます。
さらに、定款には署名が必要ですが、紙定款では発起人全員の直筆署名が必要なのに対し、電子定款では代表者1名の電子署名のみで手続きが完了します。
このように、電子定款は発起人が一人でもスムーズに手続きを進められる、非常に効率的な手段と言えます。
電子定款を自分で作成・認証するデメリット
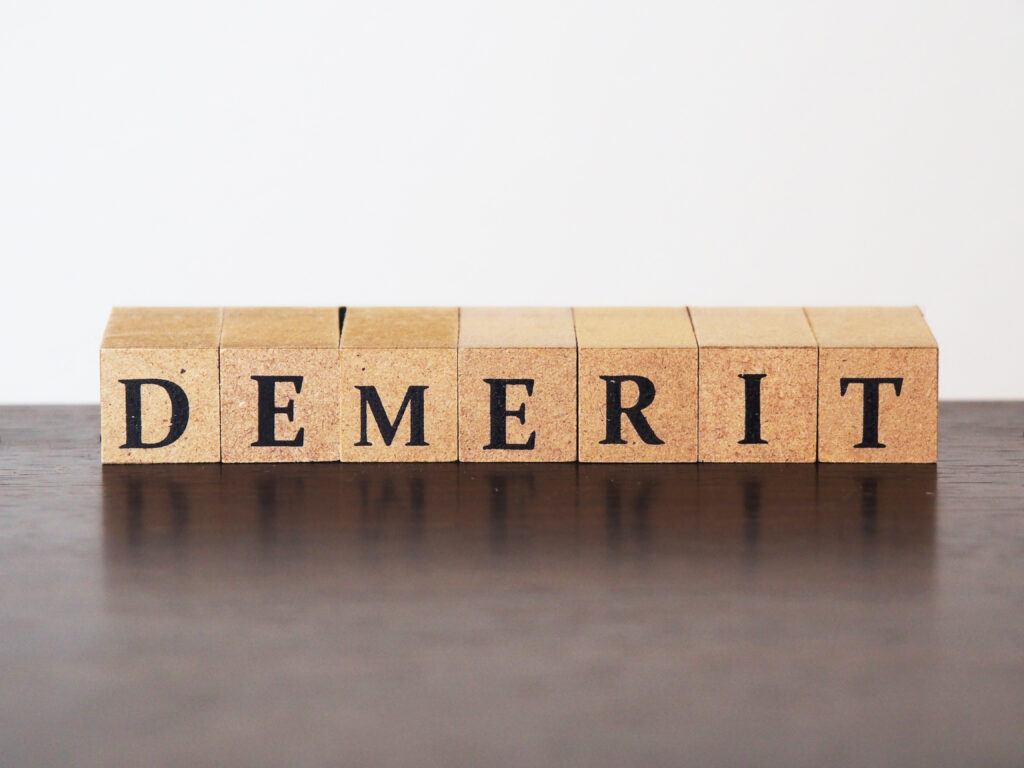
電子定款を自分で作成・認証するデメリットについては、以下の2つが挙げられます。
- 準備費用がかかる
- 申請後はデータ修正ができない
それぞれのデメリットについて解説していきます。
準備費用がかかる
電子定款を自分で作成・認証するデメリットとして、準備費用がかかることが挙げられます。
もしツールや機材をすでに所有している場合は、電子定款を選ぶことで4万円の印紙税が免除され、費用を抑えることが可能です。
しかし、ツールや機材がない場合には、準備するのに費用がかかるのはもちろん、手間や時間がかかってしまうデメリットがあるのも事実です。
そのため、自身の設備状況やコスト面を事前に確認し、どちらの方法がより適しているかを検討した上で、定款の作成手段を決定することが大切です。
申請後はデータ修正ができない
電子定款は、一度申請し認証されると内容の修正は基本的にできません。
万が一、修正が必要になった場合は、再度申請し直さなければならず、その際には定款認証にかかる手数料や保存手数料が再び必要となります。
そのため、電子定款の申請前に、公証役場へあらかじめ定款案を送付して確認してもらうことをおすすめします。
定款を作成する際の注意点

定款を作成する際の注意点については、以下の3つが挙げられます。
- 事業内容と目的を明確に記載する
- 正しい住所を記載する
- 事業内容をわかりやすく記載する
それぞれの注意点について解説していきます。
事業内容と目的を明確に記載する
会社が営むことのできる事業は、定款に明記された目的の範囲内に限られるので、将来的に展開を検討している事業についても、あらかじめ定款に含めておくことが重要です。
しかし、過度に多くの事業目的を盛り込みすぎると、会社の実態が見えにくくなり、審査の際に不利になるリスクもあります。
そのため、実際に行う見込みのない業務まで羅列するのは避けるようにしましょう。
また、事業目的を定める際には、第三者が見てもその内容が明確に理解できるよう、具体的で分かりやすい表現を用いることが求められます。
正しい住所を記載する
定款を作成する際には、正しい住所を記載するように注意が必要です。
具体的には、発起人や社員の住所は略さず、正式な住所表記「〇丁目〇番地〇号」の形式で記載することが求められます。
また、氏名や住所を記載する際には、印鑑登録証明書に記載されている情報と一致しているかどうかを必ず確認しておく必要があります。
このように、住所表記にハイフンを用いるなど、形式上のミスが起こりやすいため、定款を作成した後は丁寧に見直しをおこなうようにしましょう。
事業内容をわかりやすく記載する
会社設立時には、定款に記載する事業の内容を、誰にでも伝わるよう明瞭に記述することが重要です。
定款に記された情報は、法人登記後に登記簿謄本を通じて一般に公開されるので、外部の関係者が会社の活動内容を正確に把握できる資料となります。
事業内容の記述は、簡潔で明快な表現を心がけ、3文前後で要点を端的に示すのが効果的です。
さらに、特定の事業について法律上の許認可が必要となる場合は、定款にその許認可要件を反映させた記載をおこなう必要があります。
必要な許可を得ていないと、その事業を合法的に開始できなくなってしまうので注意が必要です。
そのため、該当する事業では、定款の目的欄において法的な要件を満たす表現が求められます。
電子定款を利用してスムーズに手続きを進めよう!

今回は、電子定款を自分で作成・認証する手順を紹介しました。
電子定款を活用することで、スムーズかつ効率的に手続きを進めることが可能です。
また、紙の定款で必要となる印紙代4万円が不要になるので、小規模な事業を始める方にとって大きな経済的メリットになります。
ただし、電子定款を自力で作成するには、PDF変換用の専用ソフトやマイナンバーカードの読み取り機器など、一定の準備が必要になります。
今回の記事を参考にして、電子定款を利用してスムーズに手続きを進めるようにしましょう。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。





