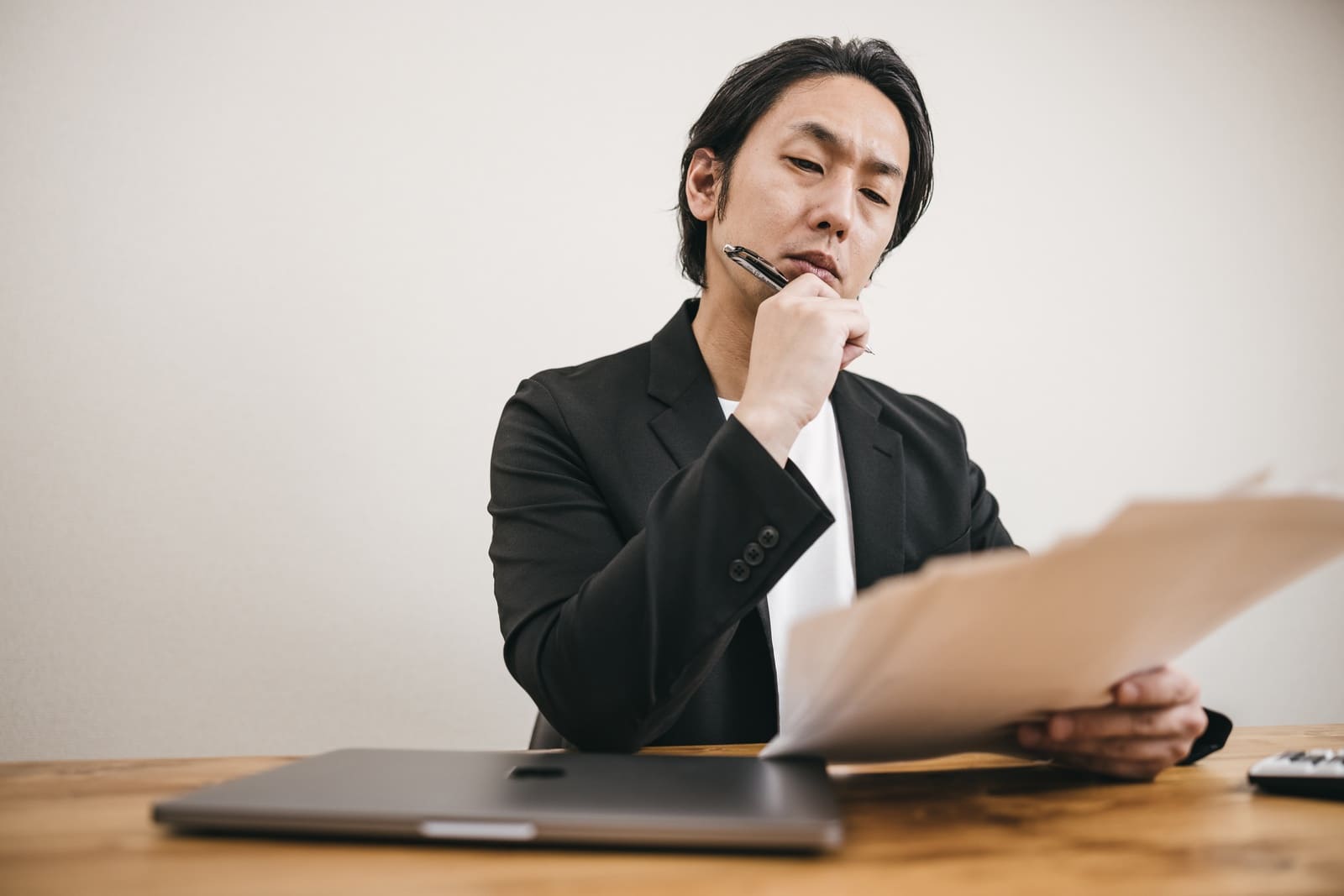メニュー
会社設立
法人化(法人成り)に必要な費用とは?運営・維持にかかる費用や節約するポイントも解説

読了目安時間:約 7分
法人化(法人成り)する際には、定款の作成費用や法人登記にかかる手数料、資本金の準備など一定の初期費用が必要になります。
また、法人として事業を運営していくと、法人住民税や法人税などの税金、社会保険料の負担といったコストが継続的に発生します。そのため、将来を見据えた資金計画を立てておくことが大切です。
本記事では、法人化に必要な費用について紹介します。
また、運営・維持にかかる費用や、負担を抑えるために検討できる工夫についても解説します。
ぜひ参考にしていただき、法人化に伴う費用への理解を深めていただければ幸いです。
目次
法人化に必要な費用とは?

法人化に際して必要となる主な初期費用として、以下の4つが挙げられます。
- 費用①:定款費用
- 費用②:登記費用
- 費用③:資本金
- 費用④:印鑑費用
費用①:定款費用
法人を設立する際には、まず定款と呼ばれる会社の基本ルールを記した書類の作成が求められます。
この手続きは株式会社や合同会社に共通の手続きで、紙媒体で定款を作成する場合は、収入印紙代として4万円の費用が必要となりますが、電子定款を利用すればこの印紙代は不要になります。
また、株式会社を設立する際には、定款を公証役場で認証してもらう必要があり、定款認証費用と謄本手数料がかかります。一方、合同会社の場合は認証手続きは不要です。
定款認証の料金は、おおよそ1万5千円から5万円程度で、資本金の額や会社の種類などによって金額が変わることがあります。また、認証された定款の謄本を取得する際には、1ページあたり約250円の謄本交付手数料が発生し、謄本の枚数によって費用は増減します。
参考:日本公証人連合会|会社の定款認証手数料の改定
費用②:登記費用
法人化を行う際には、その本店所在地を管轄する法務局に対して「会社設立登記」の申請を行う必要があり、登記を完了することで、会社が法的に成立したものと認められます。
この登記を進めるにあたっては「登録免許税」と呼ばれる税金の納付が求められます。
税額は会社の種類や資本金額によって決まりますが、株式会社の場合は最低でも15万円、合同会社では最低6万円が必要です。しかし、資本金に0.7%を掛けた金額がこれらの最低額を上回る場合には、高い方を納める必要があります。
参考:国税庁|登録免許税の税額表
費用③:資本金
法人を設立する際には、会社形態に応じて資本金を設定する必要がありますが、最低1円以上の資本金で設立することが可能です。ただし、資本金が少なすぎると、取引先からの信用や事業運営に必要な資金面で不安が生じる可能性があります。
資本金の払い込みは、通常、設立発起人(代表者)の個人口座を利用する方法が一般的です。その後、登記手続きにおいて「払込証明」として必要書類を添付する流れになります。
実際に準備すべき資本金の金額は、事業内容や今後の資金計画によって異なります。目安として、事業開始後の運転資金や初期費用を賄える程度の資本金を確保しておくことが望ましいでしょう。例えば、一定規模の事業を予定している場合は、数百万円単位の資本金を設定するケースも見受けられます。
費用④:印鑑費用
法人印(会社印)は、契約書や各種届出書類に使用される印鑑で、会社としての正式な手続きに用いられます。
主に以下の2種類があります。
- 代表者印(代表取締役印):会社を代表して使用する印鑑
- 社内用印(角印):社内文書や業務上の承認に使用する印鑑
会社印を新たに作成する場合、印鑑自体の購入費用や、印鑑登録に伴う手数料が必要です。
また、印鑑証明書にかかる費用は自治体によって異なりますが、1,000円前後である場合が多く、その印鑑が正式に登録されたものであることを証明する重要な書類であり、各種契約時に求められることがあります。
発行手数料は、おおよそ100円から1,000円ほどですが、申請する場所や方法によって異なるので、詳細については各自治体の窓口や公式サイトで確認するようにしましょう。
法人化による運営・維持にかかる費用

法人化にあたっては、運営や維持に一定の費用がかかります。主に考えられる費用としては、以下の通りです。
- 税金
- 社会保険料
- 決算公告費用
- 顧問契約費用
- その他費用
それぞれの費用について解説していきます。
税金
法人を設立すると、利益が出ていない場合でも、法人住民税の均等割など、一部の税金を支払う必要があります。
具体的に法人が負担する主な税金は以下の通りです。
| 税金の種類 | 内容 |
|---|---|
| 法人税 | 法人が得た利益(所得)に対して課せられる国の税金です。赤字の場合は基本的に支払いは発生しません。 |
| 法人住民税 | 会社を登記している都道府県・市区町村に納める地方税です。均等割と法人税割に分かれており、均等割は資本金や従業員数に応じた一定額が課されるため、赤字でも支払いが必要です。法人税割は利益に応じて算出され、赤字の場合は発生しません。 |
| 法人事業税 | 事業を行う都道府県に納める税金です。中小法人(資本金1億円以下)の場合、所得が課税対象となるため、赤字では基本的に課税されません。 |
| 特別法人事業税 | 法人事業税と併せて申告・納付する国税です。 |
| 消費税・地方消費税 | 商品やサービスの提供に伴って発生する税金です。原則として、受け取った消費税が支払った消費税を上回る場合、その差額を納税します。ただし、課税売上高が一定以下の法人は免税となる場合があります。 |
このように、法人化すると赤字経営でも一部の税金の支払い義務が生じる場合があります。特に法人住民税の均等割は赤字でも発生するため、設立前に注意が必要です。
社会保険料
法人を設立した場合、法人の規模や従業員の有無に応じて、健康保険や厚生年金への加入が必要となる場合があります。特に社員を雇用している法人では、これらの制度への加入が法律で義務付けられています。
また、労働者を雇用している場合は、労災保険や雇用保険への加入も必要です。さらに、被保険者の年齢や条件に応じて介護保険の加入が求められる場合があります。
社会保険料は原則として、会社と従業員で折半して負担します。経営者ひとりで法人を運営している場合は、会社が負担する分も実質的には経営者自身の負担となるケースがあります。
決算公告費用
法人化に伴い、運営・維持でかかる費用のひとつとして「決算公告費用」があります。
決算公告とは、企業が1年間の経営成績や財務状況を社会に向けて公表する手続きで、会社法に基づく義務です。最低限として貸借対照表の開示が求められます。
公告の方法と費用の目安は以下の通りです
- 電子公告:無料で対応可能なケースが多い
- 官報:おおよそ7万円から20万円程度
- 新聞(全国紙など):おおよそ50万円以上が相場
決算公告を怠ると、会社法第976条第2号に基づき「100万円以下の過料」が科される可能性があります。費用や方法を含め、適切に公告を実施することが重要です。
顧問契約費用
法人設立後、経営を円滑に進めるために、税理士・弁護士・公認会計士などの専門家と顧問契約を結ぶケースがあります。
これらの専門家に業務を依頼することで、法務や税務などの手続きを適切に進めやすくなる場合があります。
ただし、顧問契約には費用が発生し、その金額は依頼内容や契約条件によって異なります。契約前には、候補となる専門家に詳細な見積もりを依頼し、費用の内訳を確認しておくことが重要です。
その他費用
法人設立後には、以下のようにさまざまな運営コストが発生します。
- オフィスの賃料
- 電気・水道などの光熱費
- パソコンやデスクといった業務用の設備
- インターネットや電話などの通信に関する費用
- オフィス内の清掃やメンテナンス費用
- 企業のホームページを管理・更新するための費用
これらの経費は、企業の業態や規模、立地条件によって差があります。そのため、具体的な金額を把握するには、税理士や公認会計士などの専門家に相談し、見積もりや予算計画を立てることが重要です。
法人化にかかる費用を節約するポイント

法人化(法人成り)の際に発生する費用を抑えるポイントとして、以下の方法があります。
- 資本金を1,000万円以下にする
- 電子定款を作成する
- 電子公告を活用する
- 合同会社で設立する
資本金を1,000万円以下にする
法人化する際、資本金の額を1,000万円未満に設定すると、条件によっては税制上のメリットを受けやすくなる場合があります。
例えば、法人税については、中小企業者(資本金1,000万円以下)が一定の課税所得(概ね800万円以下)を得た場合、軽減税率15%が適用されることがあります。一方で、資本金1,000万円を超える場合は、軽減税率の適用を受けられず、通常の税率が適用されることがあります。
また、法人住民税の均等割は資本金や従業員数に応じて金額が決まります。資本金が小さい場合、年間7万円程度の最低額に抑えられるケースが多く、都道府県や市区町村によって多少の差があります。
さらに、消費税については、資本金1,000万円未満の法人であれば、原則として設立初年度と2期目に課税事業者となる必要がないため、消費税の納税が免除される場合があります。ただし、事業の内容や売上規模によって異なるため、事前に確認することが重要です。
参考:総務省|地方税制度|法人住民税
電子定款を作成する
定款を電子データとして作成すると、公証役場での認証時に通常必要な4万円の印紙税が不要になります。一方で、紙の定款では印紙税法に基づき課税文書となるため、4万円の費用が発生します。
電子署名のためには専用ソフトやICカードリーダーの準備が必要ですが、初期準備の手間や費用を考慮しても、印紙税の節約などのメリットが期待できます。
また、一度認証された後は内容の修正ができなくなるので、慎重な確認が必要です。
参考:法務省|オンラインによる定款認証及び設立登記の同時申請の取扱いを開始しました
電子公告を活用する
株式会社の決算情報の公開は、会社法に基づく重要な手続きです。決算公告は、官報や全国紙に掲載する方法と、会社のWebサイトを利用した電子公告の方法があります。
官報への掲載にはおおよそ6万円程度の費用がかかります。全国紙を利用する場合は、紙面の大きさや掲載文字数に応じて数十万円の費用が必要になることもあります。
自社Webサイトを活用することで、紙媒体に比べて掲載費用を抑えることが可能です。ただし、電子公告の場合も、公告内容は法律上一定期間(一般的に5年間)保存・閲覧可能な状態にしておく必要があります。
また、電子公告を利用する際には、情報を5年間継続して掲載し続けることが条件となっているので、導入の際はよく検討するようにしましょう。
参考:法務省|電子公告制度について
合同会社で設立する
株式会社と合同会社の設立費用を比較すると、一般的には合同会社の方が初期コストを抑えやすい傾向があります。
合同会社では、定款の公証人による認証が不要なため、公証手数料や謄本取得にかかる費用が発生しません。また、設立登記に際して納める登録免許税も、株式会社は原則として15万円、合同会社は6万円からとなっており、資本金が少額の場合には合同会社の方が低コストです。
ただし、登録免許税は「資本金×0.7%」と「最低税額(株式会社:15万円、合同会社:6万円)」のいずれか高い方が適用されるため、資本金の額によっては費用が変動します。設立前にあらかじめ確認しておくことをおすすめします。
参考:法務省|合同会社の設立手続について
個人事業主が法人化する際の注意点

個人事業主が法人化する際の注意点として、以下の3つが挙げられます。
- 資産移行は事前に試算しておく
- 事業税の支払いが必要になる
- 法人成りから個人成りは手間や費用がかかる
資産移行は事前に試算しておく
個人事業主が法人化する際には、事業用資産の移行方法を事前に整理し、税務面や会計処理への影響を十分に把握しておくことが重要です。主に以下の3つの方法があります。
| 項目 | 項目 |
|---|---|
| 売却(売買契約) | 個人事業主が自分の事業や所有する資産を法人に売却する方法です。手続きは比較的簡単で、売買契約書を作成するだけで進められるので、3つの中ではもっとも手軽な方法といえます。しかし、売却により所得が発生するので、税負担が伴う点には注意が必要です。 |
| 出資(現物出資) | 個人で所有する資産を会社設立時や増資の際に資本金として提供する方法です。この手段を選ぶと法人の資本金を増やすことができますが、出資額が500万円を超える場合には専門家による資産評価が求められます。 |
| 貸与(賃貸) | 個人の所有物を法人に貸し出すという方法もあります。形式上は法人が個人から資産を借りることになるので、契約は比較的シンプルです。しかし、家賃収入などが発生するので、個人側での確定申告が必要になります。 |
いずれの方法も税務上の扱いや手続きの複雑さが異なるため、事前にシミュレーションを行い、自分の事業状況に最適な方法を選ぶことが重要です。必要に応じて税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
事業税の支払いが必要になる
個人事業主が法人化する際には、事業税に関する手続きにも注意が必要です。
個人事業を廃業する場合、所得税の確定申告に加え、廃業届出の提出や都道府県による事業税の清算手続きが必要になる場合があります。手続きの期限や方法は都道府県によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
事業税は前年の所得を基に計算され、通常は8月頃に納付書が届きます。廃業後に支払う事業税は、原則としてその年の所得税の計算上、経費として扱うことはできません。ただし、一定の条件のもとで、将来支払う見込みの事業税を所得税の計算上の経費として計上できる場合もあります。
うした手続きを適切に進めるためにも、税務署や税理士に事前に相談しておくことをおすすめします。
参考:国税庁|個人事業の開業届出・廃業届出等手続
法人成りから個人成りは手間や費用がかかる
個人事業主から法人へ移行し、再び個人事業主として事業形態を戻す場合には、一定の手続きや費用が発生します。
法人を解散して個人事業主に戻るには、まず株主総会で会社解散の決議を行い、その後、税務署に解散届を提出して事業停止の手続きを進める必要があります。
また、法人登記の抹消や、会社が保有する資産の整理、残余財産の出資者への分配などの事務処理も発生します。
清算手続きでは、税務署への清算申告や官報への公告が必要になる場合があり、手続きにかかる費用は法人の規模や状況によって異なります。概ね数万円程度の費用が想定されますが、詳細は専門家に確認することをおすすめします。
参考:国税庁|異動事項に関する届出
法人化に必要な費用はあらかじめ確認しておこう!

今回は、個人事業主が法人化する際に必要な費用について解説しました。
法人を設立するには、設立時の定款作成費用や登記費用などの初期費用がかかるだけでなく、税金や社会保険料、顧問契約費用など、法人として事業を運営するうえで継続的なコストも発生します。
そのため、法人化を検討する際には、手続きや費用の種類・目安をあらかじめ把握し、事業の将来設計とあわせて経済的な負担をしっかり考慮することが重要です。
この記事を参考にして、法人化に必要な費用を事前に確認し、安心して法人運営をスタートできるよう準備しましょう。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。