メニュー
法人化
法人成り後も小規模企業共済は継続できる?継続することのメリット・デメリットも解説

読了目安時間:約 7分
小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模な会社経営者が将来の退職金に備えるための資金を積み立てられる制度です。
法人成り後であっても、一定の条件を満たし、中小機構に認められた場合には、加入を継続し、過去の掛金納付実績を引き継げるケースがあります。
本記事では、法人成り後に小規模企業共済を継続できるかどうかについて解説します。
あわせて「法人成り後の小規模企業共済の扱い方」や「継続した場合のメリット・デメリット」についても整理しました。
ぜひ参考にしていただき、法人成り後の小規模企業共済の仕組みを理解する一助としてご活用ください。
目次
法人成り後も小規模企業共済は継続できる?

法人成りをした場合でも、それまで加入していた小規模企業共済を継続できる場合があります。
ただし、すべてのケースで自動的に引き継げるわけではなく、中小機構が定める加入資格を満たす必要があります。そのため、法人成り後に共済を継続するには、条件を確認のうえ、所定の手続きを行うことが求められます。
一般的に、法人成り後に小規模企業共済を継続できるとされる主なケースは、次のようなものです。
- 個人事業を廃止したうえで法人を設立していること
- 従業員数が所定条件以下のこと
- 法人の役員として登記されていること
それぞれの条件について解説していきます。
個人事業を廃止したうえで法人を設立していること
法人成りを行う際には、必ずしも個人事業を廃止しなければならないわけではありません。ただし、個人事業を継続したまま法人を設立すると、小規模企業共済の「同一人通算」による継続利用が認められないケースがあります。
そのため、小規模企業共済を法人化後も継続したい場合には、
- 個人事業を廃業して法人へ切り替えたうえで「同一人通算」の手続きを行う
- 個人事業としてそのまま加入を続ける
といった対応が必要となります。状況により最適な方法が異なるため、加入条件や手続きについては事前に確認し、専門家へ相談することをおすすめします。
参考:共済サポートnavi|契約内容変更 – 掛金納付月数の通算(同一人通算)
従業員数が所定条件以下のこと
法人化後に小規模企業共済へ引き続き加入するには、法人の役員として加入要件を満たすことに加え、会社の規模が一定の範囲内であることが必要です。
具体的には、常時雇用している従業員数が以下の上限を超えないことが条件とされています。
| 事業の種類 | 従業員数の上限 |
|---|---|
| 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、宿泊業・娯楽業を含む一部のサービス業 | 20人以下 |
| 卸売業、小売業、上記以外のサービス業 | 5人以下 |
ここでいう「常時雇用の従業員」とは、原則として正社員として継続的に雇用されている方を指します。一般的には、パート・アルバイト・期間雇用の従業員、家族従業員、役員自身は含まれないとされています。
なお、加入後に従業員数が上限を超えた場合でも、直ちに加入資格を失うわけではなく、掛金を継続できる場合があります。ただし、最終的な取り扱いは中小機構(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)の判断に基づくため、状況によっては確認が必要です。
参考:共済サポートnavi|加入資格 | 小規模企業共済
法人の役員として登記されていること
法人成り後は、設立された会社の役員として登記されていることを確認する必要があります。
登記内容は「履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)」により客観的に確認できます。
提出や申請の際には、発行日から一定期間内の証明書であることを求められる場合があるため、最新の証明書を用意することが望ましいです。
参考:法務局|各種証明書請求手続 – 法務局 – 法務省
法人成り後の小規模企業共済のケース

個人事業主から法人へ移行した場合、小規模企業共済の取り扱いには主に3つの選択肢があります。それぞれ条件や手続きが異なるため、事前に確認することが重要です。
- 加入を継続する
- 準共済金を受け取る
- 解約手当金を受け取る
それぞれのについて詳しく解説していきます。
加入を継続する
法人成り後も、一定の条件を満たす場合には、個人事業主として加入していた小規模企業共済を法人契約として継続できるケースがあります。
この場合、「同一人通算」の手続きを行うことで、個人事業主として支払った掛金や加入期間を法人契約に引き継げる場合があります。
ただし、法人の役員であることや、会社の規模が小規模企業共済の加入要件を満たしていることなどが前提となるため、手続きの前に条件を確認することが重要です。
準共済金を受け取る
法人成り後の小規模企業共済では、解約して「準共済金」を受け取るケースがあります。
法人化により原則として個人事業主としての加入資格は失われますが、条件を満たす場合には、個人事業主時代の加入実績を引き継いで継続できる場合もあります(同一人通算制度)。
解約する場合、これまでに納付した掛金に応じて準共済金が支給されます。ただし、掛金の納付期間が12か月に満たない場合は、準共済金は支給されません。
また、共済契約に定められた条件を満たすことで、掛金の運用益に基づく付加給付金が支給される場合もあります。
参考:共済サポートnavi|共済金等請求・解約 | 小規模企業共済
解約手当金を受け取る
個人事業から法人へ事業を移行した場合でも、条件に応じて小規模企業共済の「解約手当金」を受け取れる場合があります。
ただし、掛金の納付期間や契約内容によって支給額は異なり、20年未満の納付期間では元本を下回ることもあるため注意が必要です。
支給率の詳細は、加入期間や契約内容に応じて変動します。おおよその目安としては、掛金の納付月数に応じて納付した掛金の80%から120%相当額です。具体的な支給額は制度の規程に基づき算定されます。
また、掛金の納付期間が1年未満の場合は、解約手当金は支給されないことがあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
参考:共済サポートnavi|解約手当金の額の算定方法 | 小規模企業共済
法人成り後に小規模企業共済を継続することのメリット

法人成り後に小規模企業共済を継続する場合、いくつかのメリットがあります。主なものとして、以下の点が挙げられます。
- 掛金の所得控除が可能
- 低金利貸付制度を利用できる
- 受取方法の選択肢がある
- 付加共済金が加算されることがある
- 掛金の運用による増加の可能性がある
掛金の所得控除が可能
法人成り後、条件を満たせば、小規模企業共済を継続して加入することが可能です。個人事業主として支払った掛金は、確定申告において所得控除の対象となるため、節税効果を通じて手元資金の確保に役立ちます。
掛金は月額1,000円から最大70,000円まで設定でき、事業の収支状況や資金計画に応じて柔軟に調整可能です。また、所得控除を活用することで、資金の使い道を計画的に考えることができます。
ただし、法人化後の継続加入には一定の条件があるため、具体的な手続きや税務上の取り扱いについては、税理士など専門家に相談することをおすすめします。
低金利貸付制度を利用できる
法人成り後も小規模企業共済を継続することで、掛金の範囲内で利用できる「低金利貸付制度」の活用が可能です。
この制度では、一定の条件を満たせば、比較的低い金利で事業資金を借り入れることができます。融資の上限額や金利は制度改定により変動する可能性があるため、利用時には最新情報の確認が必要です。
また、融資の用途についても所定の条件がありますが、事業資金として柔軟に利用できる場合があります。共済制度を上手に活用することで、低金利の資金調達手段の一つとして検討することが可能です。
参考:独立行政法人 中小企業基盤整備機構|制度の概要
受取方法の選択肢がある
法人成り後も、小規模企業共済の共済金は、契約内容に応じて受け取り方法を選択できる場合があります。
主な受け取り方法には、まとまった金額を一度に受け取る「一括受取」、一定期間に分けて受け取る「分割受取」、および「一括と分割の併用」の三通りがあります。受け取り方法は、納付期間や加入期間などの条件によって制限される場合があります。
例えば、一括受取を選べば、まとまった資金を一度に手に入れられるため、新たなビジネスへの投資や自己成長のための支出など大きな目標に活用しやすくなります。また、分割受取を選ぶことで、老後の安定収入として計画的に資金を得られ、生活設計に安心感が生まれる場合があります。
このため、将来の資金計画やライフプランに応じて、どの受け取り方法が適しているかを事前に確認しておくことが重要です。
参考:独立行政法人 中小企業基盤整備機構|制度の概要
付加共済金が加算されることがある
法人成り後に小規模企業共済を継続する場合、加入状況によっては付加共済金が上乗せされることがあります。
付加共済金とは、共済金の運用収益等に基づき、中小企業基盤整備機構が定める計算方法で算出される金額で、基本共済金に追加して支給されるものです。
なお、付加共済金も基本共済金と同様に、各区分ごとに算出され、退職や脱退の際にまとめて受け取ることができます。ただし、解約手当金の計算には含まれませんので、あらかじめご注意ください。
参考:共済サポートnavi|共済金の額の算定方法 | 小規模企業共済
掛金の運用による増加の可能性がある
法人成り後も小規模企業共済を継続することで、掛金の積立に伴う資金運用が行われます。運用は中小企業基盤整備機構が責任をもって実施しており、元本が安全に管理されるよう配慮されています。
そのため、長期にわたって積み立てることで、将来的に預けた掛金を上回る共済金を受け取れる可能性があります。
ただし、運用利回りは確定していないため、受け取る金額が掛金を下回る場合もあります。銀行の普通預金と比べると、過去の実績としては高めの利回りとなる傾向がありますが、あくまで参考情報としてご理解ください。
法人成り後に小規模企業共済を継続することのデメリット
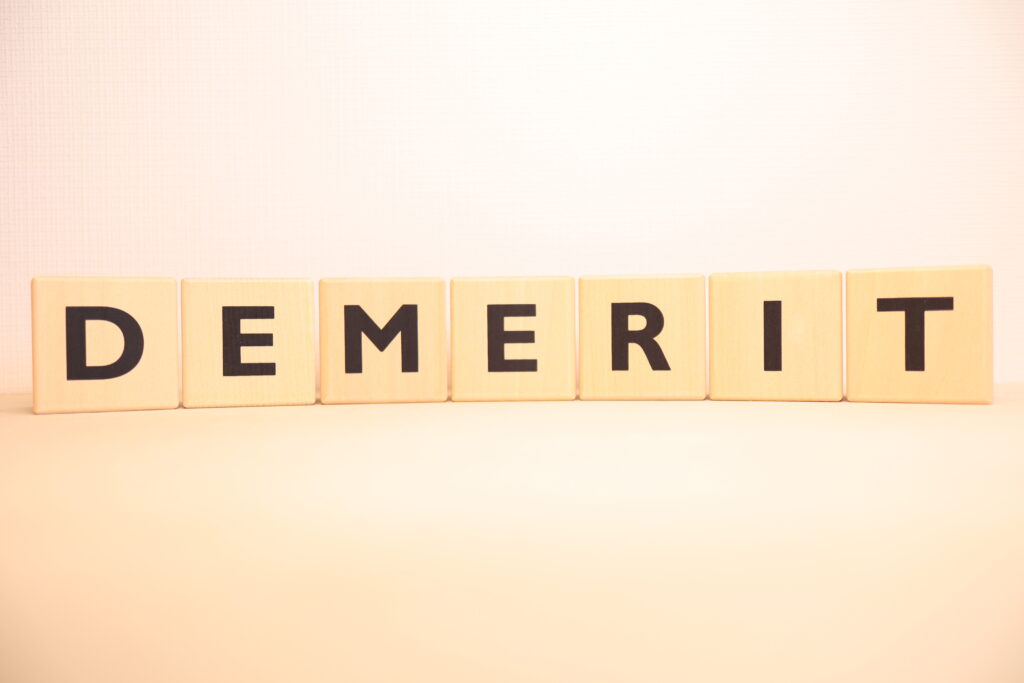
法人成り後に小規模企業共済を継続する場合、いくつか留意すべき点があります。主なデメリットとしては、以下の3つが挙げられます。
- 掛金は経費に算入できない
- 支払期間が短いと受け取れる共済金が少なくなる可能性がある
- 共済金の受け取り時に課税される場合がある
掛金は経費に算入できない
法人成り後に小規模企業共済を継続する場合の注意点の一つとして、掛金は法人の経費としては認められないことが挙げられます。
法人の役員として加入を継続した場合、掛金は個人事業主時代の所得控除の対象ではなくなり、法人の損金算入もできません。そのため、法人の課税所得を直接減らす効果は期待できません。
こうした特性を踏まえ、掛金の支払いを含めた資金運用や事業資金の配分について、計画的に検討することが重要です。資金に余裕のある範囲で継続することで、長期的な退職金準備やリスクヘッジの一助として活用できます。
支払期間が短いと受け取れる共済金が少なくなる可能性がある
小規模企業共済に加入してから掛金の納付期間が短い段階(例えば6か月未満)で、廃業や死亡などの請求事由が発生した場合、原則として支払済み掛金の全額が共済金として戻らないことがあります。
また、準共済金や解約手当金についても、納付期間が1年未満の場合には支給対象外となることがあるため、注意が必要です。
そのため、法人化のタイミングや掛金の支払状況は慎重に確認することが重要です。特に、加入から間もない段階で法人化を予定している場合は、掛金の納付期間や共済制度の条件を十分に理解し、将来的な損失を避けるための計画的な対応が求められます。
さらに、法人化後の事業運営方針も踏まえ、これまでの掛金が有効に活用できるよう検討することが望ましいでしょう。
参考:共済サポートnavi|解約手当金の額の算定方法 | 小規模企業共済
共済金の受け取り時に課税される場合がある
共済金を受け取る際には、所得税の課税対象となる場合があります。
受け取り方法によって税務上の扱いが異なり、一括で受け取る場合には「退職所得」として計算され、一定の控除を受けられることがあります。一方、分割して受け取る場合でも、原則として「退職所得」として扱われますが、契約内容や受取方法によっては一時所得として扱われ、課税対象となるケースもあります。
受け取りのタイミングや金額により課税額が変動する場合があるため、事前に税理士など専門家に相談して適切な手続きを確認することが重要です。
参考:共済サポートnavi|小規模企業共済の掛金
法人成り後に小規模企業共済を継続する手続き

法人成り後も小規模企業共済を継続して利用する場合は、一定の条件を満たしたうえで所定の手続きを行う必要があります。具体的には、以下の手順で手続きを進めます。
- 必要書類を中小機構の連携団体や金融機関の窓口に提出する
- 手続き完了のお知らせを受け取る
それぞれの項目について解説していきます。
必要書類を中小機構の連携団体や金融機関の窓口に提出する
小規模企業共済における「同一人通算」の手続きを進めるには、以下の書類を、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)と提携している指定団体または金融機関の窓口に提出する必要があります。
- 個人事業の廃業届の写し
- 法人登記に関する書類
- 納付月数通算申出書兼契約申込書(同一人通算用)
この申出は、個人事業の廃業や法人設立などの「事由発生」から1年以内におこなう必要があるため、期限には注意が必要です。
参考:共済サポートnavi|掛金納付月数の同一人通算又は承継通算手続き | 小規模企業共済
手続き完了のお知らせを受け取る
必要書類に不備がなく受理されると、中小企業基盤整備機構(中小機構)から以下の書類が送付されます。
- 納付月数通算(同一人)手続き完了のお知らせ
- 契約内容確認書
これらの書類が届いた時点で、手続きは完了となります。届いた書類の内容をよく確認し、契約内容に誤りや記載漏れがないかチェックしておくことが重要です。
もし申請内容に不備があった場合には、書類の差し戻しや追加提出が求められることがあります。その場合は、必要な修正や補足を行ったうえで、再度書類を提出してください。
自分自身の状況に合わせて継続か解約を判断しよう!

今回は、法人成り後の小規模企業共済の継続について解説しました。
法人成りした場合でも、所定の条件を満たすことで、個人事業主として加入していた期間を引き継ぐ「同一人通算」によって、共済契約を継続することが可能です。ただし、この手続きを行わない場合や条件を満たさない場合は、契約を引き継ぐことはできません。
また、個人事業と法人を同時に運営する場合には、個人事業を廃業しないと同一人通算は適用されないため、注意が必要です。
小規模企業共済には、将来の資産形成支援、税制上の所得控除、低金利貸付制度などのメリットがあります。一方で、掛金の納付期間が短い場合は共済金を受け取れない可能性がある点や、掛金が全額損金として扱えない可能性がある点には注意が必要です。
本記事を参考に、ご自身の状況に合わせて継続の可否を慎重に判断していただけたら幸いです。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。





