メニュー
創業融資
ブラックリストに載っても借入はできる?借入する方法から注意点について徹底解説
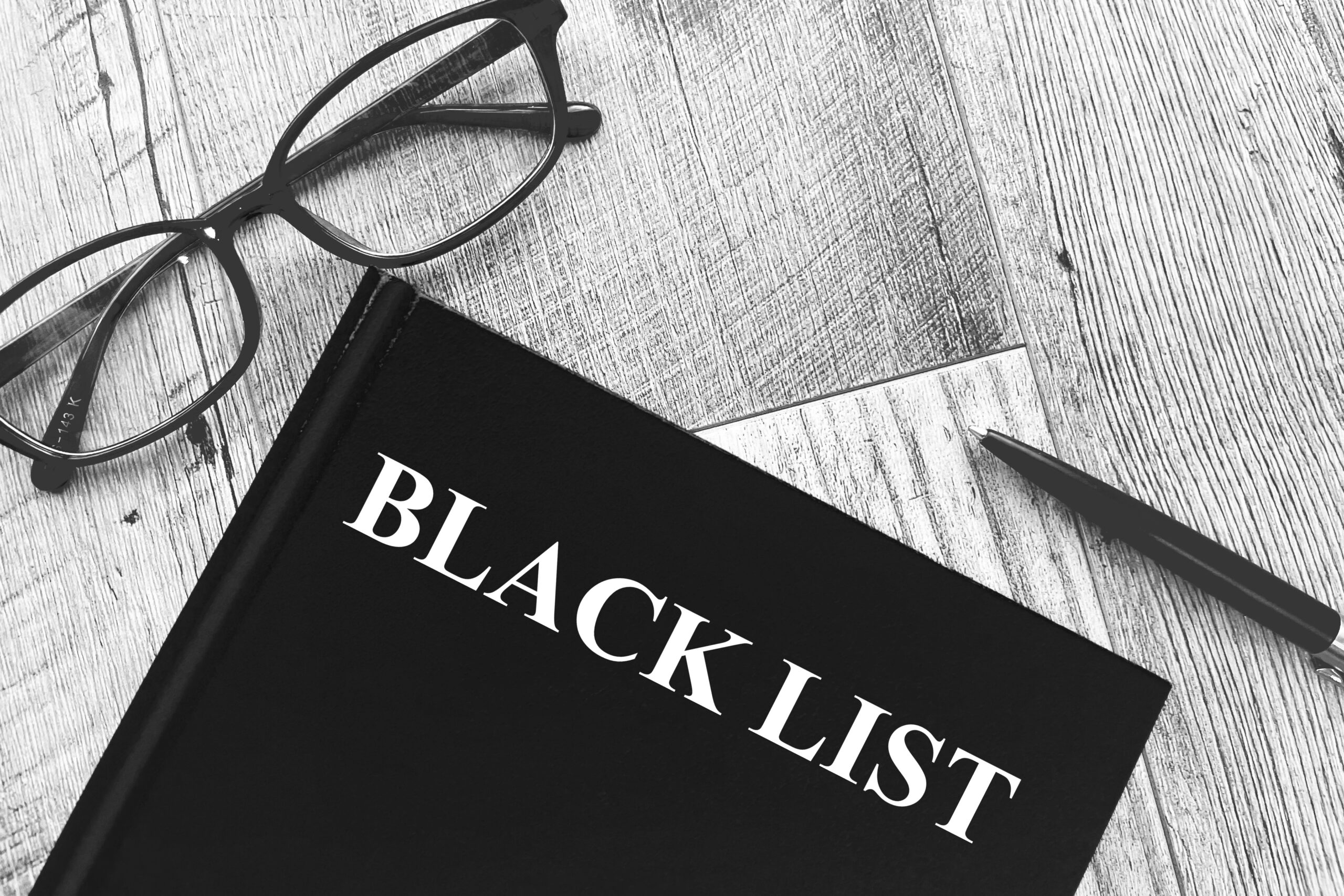
読了目安時間:約 7分
「ブラックリストに載る」という言葉が一般的に使われますが、正確には信用情報機関に延滞や債務整理などの金融事故情報が登録されることを指します。
通常、個人でカードローンや住宅ローンを申し込む場合、信用情報に事故情報があると審査に通過するのは難しいとされています。
一方で、法人が事業資金を借入する場合には、審査基準が個人ローンと異なるケースがあります。もっとも、金融機関は法人の財務内容だけでなく、代表者の信用情報を確認することが一般的であり、事故情報があるからといって必ずしも借入ができないとは限りません。
本記事では、信用情報に事故情報がある場合の借入の可否や、注意しておくべきポイントについて解説します。借入を検討する際の参考にしていただければ幸いです。
目次
ブラックリストに載っても借入はできる?

ブラックリストに載っても借入できる可能性はあります。
信用情報機関に延滞や債務整理、自己破産といった金融事故の記録が残っている場合、ローンやクレジットカードの審査に大きな影響を及ぼします。
一般的には、こうした記録があると新たな借入を行うことは非常に困難とされています。
俗に「ブラックリストに載る」と言われる状態は、この信用情報に金融事故の履歴が登録されていることを指し、金融機関は審査の際に信用情報を参照するため、延滞や債務整理の記録があると否決されるケースが多いのです。
一部の金融機関では、独自の基準や担当者の判断によって例外的に融資が行われる場合もあります。ただしこれはあくまで限定的なケースであり、「必ず借入できる」という意味ではありません。
借入を検討する際には、信用情報の状況を正しく把握し、返済計画を立てたうえで無理のない資金繰りを行うことが重要です。
ブラックリストで借入する方法

ブラックリストに載っている場合、金融機関の審査に影響することがあります。その中でも、当事者が取れる選択肢があり、具体的には以下の通りです。
- 日本政策金融公庫の融資
- 金融機関の融資
- クレジットカード
- 従業員貸付制度
それぞれの方法について解説していきます。
日本政策金融公庫の融資
日本政策金融公庫は、中小企業や個人事業主向けに多様な融資制度を提供している公的な金融機関です。
同公庫は信用情報機関である全国銀行個人信用情報センター(KSC)や株式会社シー・アイ・シー(CIC)などに加盟しており、融資審査では一般的に申込者の信用情報を確認します。
ただし審査は信用情報だけで決まるものではなく、過去の決算書や確定申告の内容、現在の財務状況、将来の事業計画などを総合的に評価します。
そのため、信用情報に問題がある場合でも、事業計画や返済能力が十分に評価されれば融資が認められるケースもあります。ただし、信用情報に重大な問題があると審査が厳しくなる点には注意が必要です。
参考:日本政策金融公庫|融資制度を探す
金融機関の融資
保証人を求めないタイプの事業融資であっても、信用情報に延滞や債務整理などの記録がある場合、審査は厳しくなります。ただし、法人の財務内容や事業計画が健全であれば、融資の可能性が残されているケースもあります。
金融機関の事業融資は大きく2つに分類されます。
| 金融機関の融資種類 | 内容 |
|---|---|
| プロパー融資 | 金融機関が企業の信用力を直接評価し、保証人や保証協会の保証を前提とせずに行う融資 |
| 信用保証協会付き融資 | 信用保証協会が保証を行い、その保証を基に金融機関が貸し付ける融資 |
いずれの場合も、審査では法人の財務状況や将来の事業計画といった実態が重視されます。決算内容が堅実で、成長戦略が明確であれば、融資の実現可能性は高まります。
参考:信用保証協会連合会|初めての融資と信用保証
クレジットカード
クレジットカードを保有している場合、「請求書カード払い」サービスを活用することで、請求書の支払いをカードで行い、実際の資金の引き落としまでに一定の猶予を確保できる場合があります。
これにより、資金繰りに一定の余裕が生まれる可能性があります。
利用にあたっては、手数料や審査条件がサービスごとに異なるため、事前に確認することが重要です。また、信用情報に応じて利用できない場合もあるため、注意が必要です。
従業員貸付制度
従業員向け貸付制度がある企業では、勤務状況や社内での評価に基づき、個人の信用情報とは別に融資の検討が行われる場合があります。
そのため、外部の金融機関とは異なる基準で融資の可否が判断されることがありますが、審査が全くないわけではありません。一般的には、社内での勤務年数や勤務態度などが、貸付の判断材料となることがあります。また、制度の内容は企業ごとに異なり、貸付対象者の条件、貸付限度額、返済方法などは事前に確認が必要です。
企業による貸付制度のメリットとしては、比較的低金利である場合が多い点や、給与天引きなどで返済管理がしやすい点が挙げられます。
多くの場合、こうした制度は正社員を対象としており、勤続年数に一定の条件が設けられていることもあります。
参考:厚生労働省|勤労者の福利厚生について
ブラックリストで借入以外の資金調達方法

ブラックリスト登録などで金融機関からの借入が難しい場合でも、資金調達の方法はいくつかあります。ただし、各方法には条件や注意点がありますので、状況に応じて専門家と相談しながら検討することが重要です。
主な資金調達手段として、以下が挙げられます。
- ファクタリング
- 補助金・助成金
- クラウドファンディング
- 質入れ
それぞれの資金調達方法について解説していきます。
ファクタリング
ファクタリングとは、自社が保有する売掛金を専門のファクタリング会社に売却し、早期に現金化する資金調達の方法です。
この仕組みでは、資金を提供する会社は売掛先の信用状況を中心に審査を行うため、場合によっては自社の信用情報に課題があっても利用できることがあります。
審査の手続きは比較的簡単で、スピーディーに進む場合もあり、条件によっては申し込み当日中に資金を受け取れるケースもあります。
ただし、銀行融資と比べると手数料が高めに設定される場合が多く、特に「3社間ファクタリング」を利用する場合は、売掛先の企業にファクタリングを利用している事実が通知されることがあるため注意が必要です。
参考:金融庁|ファクタリングの利用に関する注意喚起
補助金・助成金
中小企業の経営支援を目的として、政府や地方自治体では「補助金」や「助成金」が用意されています。
これらは、企業が厳しい経営状況にあっても、条件を満たせば活用できる可能性があります。
金融機関からの融資とは異なり、原則として返済の必要はありません。ただし、申請にあたっては各種要件を満たす必要があり、過去の税務・社会保険の状況なども確認される場合があります。
また、補助金と助成金には以下のように性質の違いがあります。
- 助成金:所定の要件を満たしていれば支給されることが多いが、予算や申請時期によっては受給できない場合もある
- 補助金:審査によって採択される必要があり、申請しても必ず支給されるわけではない
参考:補助金とは | 経済産業省 中小企業庁 – ミラサポPlus
クラウドファンディング
クラウドファンディングとは、特定のプロジェクトに共感した人たちから資金を募る仕組みで、支援者にはその見返りとして商品やサービスなどが提供されるケースが多いです。
支援者の共感を得られれば、一定の期間内でまとまった資金を集められる可能性があります。ただし、プロジェクトが必ず成功するわけではなく、成功後も商品の配送やサービス提供に伴う労力やコストが発生する点には注意が必要です。また、クラウドファンディングで得た資金は、場合によって所得税や法人税の課税対象となることがありますので、資金調達を検討する際には税務面についてもあらかじめ確認しておくことが重要です。
自社の商品やサービスに自信がある場合には、資金調達の手段のひとつとしてクラウドファンディングを検討することも可能です。
質入れ
質入れとは、自分が所有する品物を担保として預け、その評価額に応じて資金を借りる方法です。カードローンのような無担保融資とは異なり、担保付き融資の一種となります。
一般的には、査定された評価額の70〜80%程度を現金として受け取ることが可能です。ただし、質屋によって受け取れる額は異なります。
質屋では審査が簡略化されている場合もありますが、身分証の提示など必要な手続きは行われます。
また、返済が難しくなった場合は、預けた品物を質流れ(処分)させることで借入金の清算が行われます。ただし、契約条件によっては注意が必要で、信用情報に影響する場合もあります。
ブラックリストで借入する際のコツ

信用情報に問題がある場合でも、資金繰りを改善するためには、合法的で安全な方法を検討することが重要です。
具体的には、以下のような対策が考えられます。
- 借入金額を抑える
- 属性を高める
それぞれについて解説していきます。
借入金額を抑える
必要以上に高額な金額を申請すると、審査の負担を増やす可能性があります。金融機関は借入額が大きいほど慎重に審査を行う傾向があるため、借入を検討する際は、自身の資金計画に基づき、必要最低限の金額を検討することが望ましいとされています。
ただし、借入の可否は金融機関の審査基準によって決まるため、必ずしも希望通りに借入できるわけではありません。計画的な資金管理や返済計画を立てることが重要です。
参考:日本政策金融公庫|新規開業・スタートアップ支援資金
属性を高める
借入時に金融機関が重要視する「属性」とは、申込者の収入や勤務状況など、返済能力を判断するための情報のことを指します。
具体的には、次のような項目が含まれます。
- 年齢
- 会社の規模
- 勤続年数
- 年収
- 現在の住居での居住期間
- 配偶者の有無
金融機関は、これらの情報をもとに貸付金額や審査可否を判断します。属性が安定している場合、審査において有利に働くことがありますが、必ずしも審査通過を保証するものではありません。
なお、属性は一朝一夕で大きく変えることは難しいため、借入を検討する際は自身の状況を把握した上で計画的に準備することが大切です。
ブラックリストで借入する際の注意点

資金調達を検討する際には、信用情報や金融商品の特性を理解しておくことが重要です。
特に過去に延滞や債務整理などがある場合は、無理な借入は避け、以下の点に注意しましょう。
- 短期間に複数の消費者金融を申し込まない
- 虚偽の年収を申告しない
- 悪質業者には注意する
それぞれの注意点について解説していきます。
短期間に複数の消費者金融を申し込まない
短期間に複数の消費者金融へ申し込みを行うと、信用情報上で「短期間に複数の照会がある」と判断され、審査に影響する場合があります。
信用情報機関には、金融会社からの照会記録が一定期間残る仕組みがあります。そのため、短期間に多くの照会履歴が残ると、金融機関によっては審査時に慎重に判断されることがあります。
一般的に、このような記録は数か月で消えるとされていますが、過度な多重申し込みは避け、計画的に借入や申請を行うことが望ましいでしょう。
参考:指定信用情報機関のCIC
虚偽の年収を申告しない
個人の金融取引においては、年収や勤務状況などの情報を正確に把握し、申告することが重要です。金融機関は、申込者の返済能力を確認した上で融資を判断します。返済能力の評価には、年収が重要な指標のひとつとして用いられます。
また、貸金業法の総量規制によると、現在は年収の3分の1を超える金額を借りることはできないとされています。
このため、申込者は正しい情報を申告する責任があり、虚偽の申告は融資の審査に影響するだけでなく、法律上の問題を引き起こす可能性があります。税務や金融に関する正確な情報管理は、トラブル防止の観点からも非常に重要です。
参考:日本貸金業協会|お借入れは年収の3分の1までです
悪質業者には注意する
ブラックリストに登録されている利用者の立場につけ込み、不適切な条件で貸付をおこなう業者も存在する可能性があります。
貸金業者を利用する際には、業者が正式に登録されているかどうかを確認することが重要です。具体的には、貸金業者が取得している「登録番号」の確認や、電話番号が固定回線であるかの確認などが有効です。
また、金融庁が提供している「登録貸金業者情報検索サービス」を活用すれば、検討中の業者が正規に認可を受けているかどうかを簡単に確認できます。
違法な取り立てや不当な条件での契約を避けるため、こうした情報を確認したうえで、慎重に判断することが推奨されます。
参考:金融庁|登録貸金業者情報検索サービス
借入する際には自身の財務状況を冷静に見直そう!

ブラックリストに登録されている場合、金融機関からの借入は原則として難しくなります。
そのため、安易に借入を検討するのではなく、まずは自身の収支状況や負債の状況を正確に把握することが重要です。
借入を検討する際には、無理のない返済計画が立てられるかどうかを慎重に確認し、必要であれば専門家に相談することをおすすめします。
今回の記事を参考にして、借入を検討する際には自身の財務状況を冷静に見直すようにしましょう。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。





