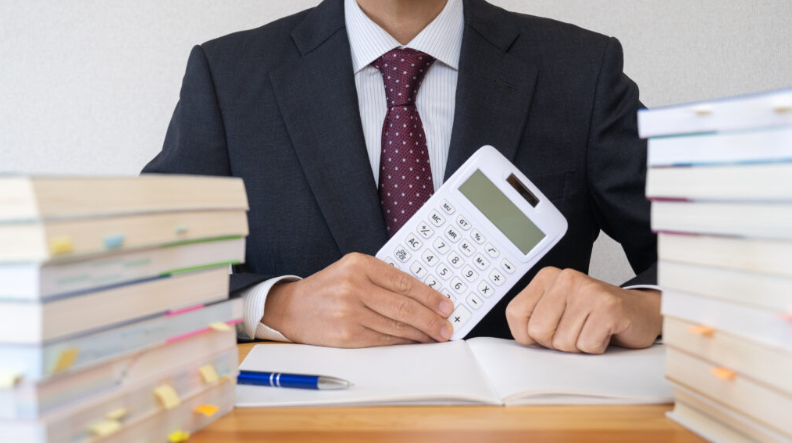メニュー
会社設立
創業と設立の違いとは何か?混同しやすい用語から設立日を選ぶ際の注意点を紹介

読了目安時間:約 7分
創業と設立は似た言葉ですが、それぞれ意味や文脈に明確な違いがあります。
創業とは、事業活動を開始することを指す言葉で、個人事業主としての開業も含まれます。税務上の取り扱いにおいても、創業時期を基準に青色申告や各種控除の適用が判断されることがあります。
一方、設立は、法人格を有する会社や組織を登記によって正式に立ち上げることを指します。設立日や資本金、定款の内容などは、法人の税務申告や各種手続きに直接関わる重要な要素です。
このように、言葉の意味や適用される文脈が異なるため、正しく理解し、状況に応じて使い分けることが大切です。
本記事では、創業と設立の違いを解説するとともに、「創業・設立と混同しやすい用語」や「設立日を決める際の注意点」についても解説します。税務や法務の観点から正確に理解する参考としてご覧ください。
目次
創業と設立の違いとは何か?

創業とは、個人事業であれ法人であれ、事業活動を開始することを指す概念です。
一方、設立は法人として法的に組織を立ち上げる手続きを意味します。具体的には、法務局での登記申請が完了した日が設立日となり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)にもこの設立年月日が記載されます。
新たに法人を起こす場合、創業日と設立日が同じになることもありますが、もともと個人事業を営んでいた場合は、創業が先にあり、法人化した日が設立日となることがあります。
このように、創業は事業開始全般を広く指す概念であり、設立は法人登記という法的手続きに限定される点で区別されます。
参考:法務局|登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です
創業・設立と混同しやすい用語

創業・設立と混同しやすい用語については、以下の4つが挙げられます。
- 用語①:創立
- 用語②:開業
- 用語③:起業
- 用語④:独立
それぞれの用語について解説していきます。
用語①:創立
「創立」は、新たな組織や機関を作ることを指す言葉で、学校や研究機関、社会団体など、一定の組織体に対して使われるのが一般的です。一方、個人が事業を始めた場合には、組織としての形態が伴わないため、「創業」と表現するのがより適切です。
また、「創立」は法人登記や開業届の提出を必ず必要とするものではなく、法的な意味での「設立」とは区別されます。
このように、組織や法人の有無、法的手続きの有無によって、「創立」「創業」「設立」の使い分けがされています。
用語②:開業
開業とは、個人または法人が新たに事業や店舗を開始し、営業活動をスタートすることを指します。
創業とほぼ同義で使われることもありますが、特に個人事業主や独立して活動する専門職の方に用いられることが多い表現です。例えば、医療・法律・美容・飲食業など、幅広い業種で自らのビジネスを開始する際に開業という言葉が用いられます。
開業にあたっては、以下のような準備が必要です。
- ビジネスの計画立案
- 資金の確保
- 適切な立地の選定
- 必要な許認可の取得
- 各種登録手続き
- 顧客獲得の戦略づくり
また、個人事業を始める場合は、税務署に「個人事業の開廃業届出書」を提出することが求められます。
このように、開業は自らの力で収益を上げることを目指し、経営者としての一歩を踏み出す重要な節目といえます。
参考:国税庁|A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
用語③:起業
起業とは、新たに事業やビジネスを始めることを指す言葉です。
創業や開業と似ていますが、起業は個人事業主としての小規模な事業開始から、法人としての新規事業の立ち上げまで幅広く使われます。
例えば、自宅で小規模に事業を始める個人事業主や、法人を設立して新たなサービスや製品を提供する会社など、事業を始めた人を「起業家」と呼びます。
起業には必ずしも革新性や大規模な挑戦が必要なわけではなく、新しい価値やサービスの提供を目的として事業を始めるすべてのケースを含みます。
用語④:独立
独立とは、会社などの組織に所属して働いていた人が、その組織を離れ、自らの力で生計を立てることを指す場合が一般的です。
具体的には、企業に雇用されていた方が自身で事業を開始したり、フリーランスとして活動を始めたりするケースが該当します。ただし、最初から組織に所属せずに事業を開始する場合や、会社員として在籍しながら副業を行う場合もあり、独立の形態は一律ではありません。
税務や社会保険の手続き上は、独立の状況によって必要な届出や対応が異なるため、具体的なケースに応じた確認が重要です。
創業日よりも設立日が重要な理由

企業活動において、法的な観点から特に重要とされるのは設立日です。
創業日とは、開業届や法人登記の有無にかかわらず、事業を開始した日として当事者が記録する日を指します。税務上や助成金申請などでは創業日が基準となる場合もありますが、法務上の法人格の取得に関しては設立日が基準となります。
設立日は、会社が登記を通じて法人格を取得した日であり、登記事項証明書にも明記されます。登記申請が受理された日が、法人として法的に認められた日となるため、会社運営や契約、登記上の手続きにおいては設立日が重要です。
このように、法的な手続きの基準日としては設立日が基本となる一方、事業開始日としての創業日も状況によって活用されることを理解しておくことが大切です。
参考:法務局|各種証明書請求手続
会社を設立するメリット
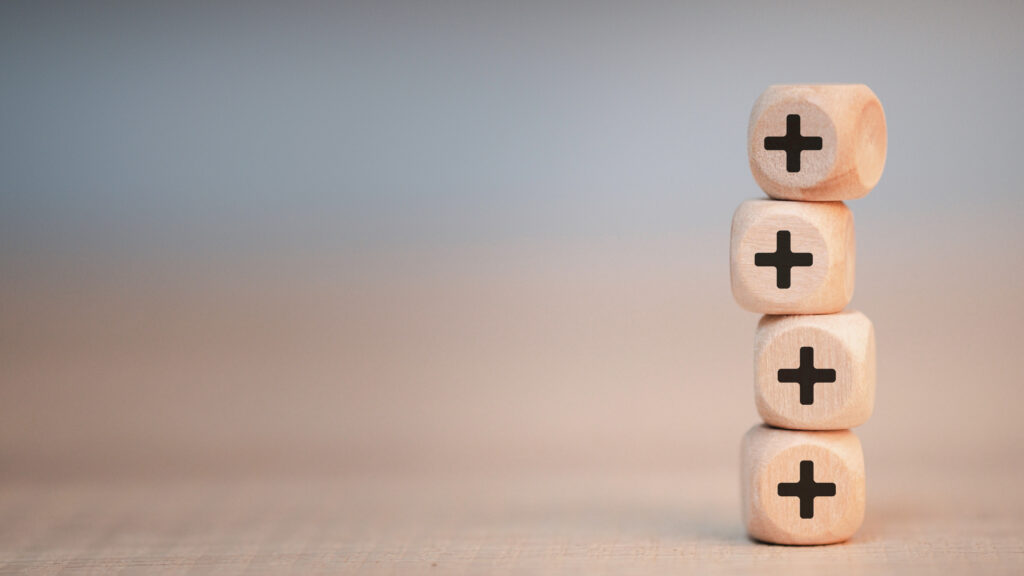
会社を設立するメリットについては、以下の5つが挙げられます。
- 社会的信用が高まる
- 資金調達がしやすくなる
- 節税効果が期待できる
- 有限責任になる
- 事業承継がスムーズにおこなえる
それぞれのメリットについて解説していきます。
社会的信用が高まる
法人を設立することで、状況によっては個人事業主に比べて社会的信用が高まり、取引先との信頼関係構築に有利に働く場合があります。
特に企業間取引では、信用力が重要視されることも多く、法人格を持つことで名刺や公式書類に株式会社・合同会社などの法人名を記載でき、初対面の相手に対して安心感を与えやすくなるケースがあります。
そのため、信用力が売上や契約獲得に影響するビジネスでは、法人化によって会社を設立することが有効な選択肢となることがあります。
資金調達がしやすくなる
創業時に資金調達を検討する場合、法人を設立することで金融機関からの信用評価が得やすくなるケースがあります。
法人では会計や財務管理の体制が整備されていることが多く、金融機関が経営状況を把握しやすいというメリットがあります。ただし、融資の可否や条件は、事業計画や事業規模、経営者の信用状況など複数の要素によって決まるため、法人化=必ず有利というわけではありません。
参考:日本政策金融公庫|融資制度を探す
節税効果が期待できる
法人設立には、個人事業主に比べて活用できる税務上の制度が増えるというメリットがあります。
例えば、法人では経費として計上できる範囲が個人事業よりも広く、経営者自身への給与も役員報酬として法人の損金に計上することが可能です。また、個人の所得税と法人の法人税では税率体系が異なるため、利益規模や経営状況によっては、法人化により税負担が軽減される場合があります。
さらに、個人事業主が加入する生命保険料は原則として事業経費にはできませんが、法人が契約者となる生命保険の場合、一定の条件のもとで損金算入が可能となるケースがあります。ただし、保険の種類や契約内容によって取り扱いが異なるため、具体的には税理士など専門家への確認が必要です。
このように、法人化によって利用できる制度や節税の方法が広がるため、事業の規模や収益状況に応じて法人化を検討することが有効です。
有限責任になる
事業における責任の範囲は、個人事業主と法人で大きく異なります。
個人事業主の場合、事業に関する債務や義務は基本的に事業主本人が負うことになります。事業と個人の財産の区別は法人に比べて明確ではないため、事業の損失が個人の財産に影響を及ぼす可能性があるのです。
一方、法人の場合は有限責任の仕組みを持っており、通常は出資した資金の範囲内で責任を負うことになります。ただし、役員保証や法令違反など特定の状況では、個人が責任を問われるケースもあり得ます。
このように、事業に対するリスクの負担の仕方は、個人事業と法人で異なるため、事業形態を選ぶ際には注意が必要です。
参考:J-Net21中小企業ビジネス支援サイト|有限責任と無限責任について教えてください。
事業承継がスムーズにおこなえる
法人として事業を行っている場合、代表取締役が死亡した際も、会社名義の銀行口座は法人の財産として扱われます。事業を継続するためには、法務局での代表者変更登記や銀行への届出などの手続きが必要ですが、適切に対応することで事業活動を継続することが可能です。
一方、個人事業主の場合、事業主が亡くなると、事業用の預金口座や契約の名義人が不在となるため、金融機関や関係先の手続きにより支払いなどが一時的に制限されることがあります。このため、個人事業を継続する場合には、相続や事業承継の準備が重要となります。
参考:法務局|商業・法人登記の申請書様式 – 法務局
会社を設立するデメリット

会社を設立するデメリットについては、以下の3つが挙げられます。
- 設立と維持に費用がかかる
- 会計処理が複雑になる
- 社会保険加入が義務付けられる
それぞれのデメリットについて解説していきます。
設立と維持に費用がかかる
会社を設立する際には、一定の費用が発生することを理解しておくことが重要です。
個人事業主として開業する場合は、税務署への「開業届」の提出だけで事業を始められます。一方、法人を設立する場合は、定款の作成や登記などの手続きが必要で、それに伴いさまざまな費用がかかります。
たとえば、株式会社の設立では、定款認証手数料や登録免許税などを合わせて一般的に20万円前後の初期費用がかかるケースが多く、必要に応じて専門家への報酬が発生することもあります。
また、法人を維持するには継続的なコストもかかります。法人住民税の均等割は赤字でも課税されるのが一般的です。さらに、社会保険への加入義務があり、従業員を雇用する場合や役員のみの場合など、状況によって保険料の負担が発生します。
会社を設立・維持するには一定の経済的負担が伴うことを、あらかじめ把握しておくことが大切です。
参考:法務局|商業・法人登記申請手続
会計処理が複雑になる
法人として事業を運営する場合、会計や税務は個人事業主よりもルールが厳格になるため、取り扱う項目や手続きが増える傾向があります。
個人事業主であれば自分で帳簿を作成し、確定申告を行うことも可能ですが、法人では決算書の作成や帳簿の整備など、正確さが求められる作業が増えるため、税理士などの専門家に相談・依頼するケースが一般的です。
また、法人では社会保険や労働保険に関する届出や手続きも継続的に必要となります。こうした業務は事務負担として認識されますが、専門家に依頼することで効率的に対応できます。
法人設立を検討する際は、会計・税務・社会保険などの管理業務を含めた運営体制を事前に整えておくことが大切です。
社会保険加入が義務付けられる
法人を設立した場合、会社の形態を問わず、原則として社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられています。これは、法人が「強制適用事業所」として法律上定められているためです。
設立後は、設立日または適用事由が生じた日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」および「被保険者資格取得届」などを日本年金機構に提出する必要があります。
手続きを怠ると、後日遡って保険料の徴収を受ける場合や、未加入期間の是正指導を受けることがあるので注意してください。
なお、法人であっても、役員報酬を支払っていない場合や従業員を雇用していない場合には、その時点で被保険者資格が発生しないため、実務上は保険料が発生しないケースもあります。ただし、法人そのものは引き続き「社会保険の強制適用事業所」であるため、今後報酬支給や雇用が始まった場合には、速やかに加入手続きを行いましょう。
参考:日本年金機構|健康保険・厚生年金保険の保険料関係
設立日を選ぶ際の注意点

設立日を選ぶ際の注意点については、以下の2つが挙げられます。
- 設立日で法人住民税均等割の負担金額が変わる
- 設立日は法務局に登記申請をおこなった日
それぞれの注意点について解説していきます。
設立日で法人住民税均等割の負担金額が変わる
会社設立の日付によっては、法人住民税の計算に影響が出る場合があります。法人住民税は、法人税割と均等割の2つの要素で構成されます。
法人税割は法人税額に基づいて算出されるのに対し、均等割は資本金の額や従業員数などに応じて一定額が課されます。均等割は、事業が赤字の場合でも原則として納税義務が生じます。
均等割の算定方法については、事務所の所在地自治体や活動月数によって計算方法が異なる場合がありますので、具体的な金額や計算方法については設立前に自治体や税理士に確認することが望ましいです。
設立日によって年間の税負担額が変動することがあるため、会社設立にあたっては税務面も含めたスケジュール検討が必要です。
参考:総務省|地方税制度|法人住民税
設立日は法務局に登記申請をおこなった日
会社の設立日に関しては、「登記が完了した日」ではなく、「法務局に登記申請をおこなった日」が正式な設立日になるとされています。
法人設立の手続きでは、必要な登記書類を整えて法務局に申請することが第一ステップです。
申請に問題がなければ、通常1週間から10日ほどで登記手続きが完了しますが、登記の法的効力が発生するのは申請書類を提出した日にさかのぼることを理解しておくことが重要です。
提出手段により所要日数が異なる場合がありますので、スケジュールに余裕を持って手続きを進めましょう。
| 提出方法 | 設立日として扱われる日 |
| 窓口提出 | 申請を行った日 |
| 郵送提出 | 書類が法務局に届いた日 |
| オンライン提出 | 申請が正式に受理された日(通常は送信日と同日だが、システム障害などにより遅延する可能性あり) |
参考:法務局|商業・法人登記申請手続
創業と設立の違いを正しく理解しよう!

今回は、創業と設立の違いについて解説しました。
創業とは、法人・個人を問わず、事業活動を開始すること全般を指します。たとえば、店舗の営業開始やサービス提供の開始などが該当します。
設立とは、法人格を取得するために法務局で登記を行う手続きを指します。法人として事業を始める場合、創業日と設立日が同じ場合もありますが、個人事業として始めた後に法人化した場合は、創業日が設立日より前になることがあります。
企業として外部に自社を紹介する場合は、創業年と設立年が異なるケースがあることを正しく理解し、適切に表記することが重要です。
創業と設立の違いを理解することで、事業計画書や契約書、会社案内などの記載に誤解を生じさせず、正確な情報提供につながります。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。