メニュー
起業・開業
フリーランスと自営業の違いとは?メリット・デメリットや必要な手続きについても解説

読了目安時間:約 8分
フリーランスと自営業は、どちらも自分の責任で事業を行う働き方ですが、その形態や契約の仕組みには違いがあります。
一般的にフリーランスは、企業や個人と業務委託契約を結び、個人のスキルや経験を活かして仕事を請け負うスタイルを指します。一方、自営業は、店舗運営やサービス提供などを通じて独立して事業を営むケースも含まれます。
本記事では、税務上の視点も交えながら「フリーランスと自営業の違い」をわかりやすく解説します。
さらに、「それぞれの働き方のメリット・デメリット」や「開業時に必要な手続き」についても詳しく紹介します。
ご自身に合った働き方を選ぶ際の参考にしてください。
目次
フリーランスと自営業の違いとは?

フリーランスとは、企業などの雇用関係に属さず、自分のスキルや専門性を活かして業務委託などの形で仕事を請け負う人を指します。
必ずしも個人事業主に限らず、法人を設立して業務を請け負う場合でも、働き方の性質が自由業に近ければ一般的に「フリーランス」と呼ばれることがあります。
一方、自営業は、自らの責任で独立して事業を運営する人を広く指す言葉です。
その中には、税務署に開業届を提出して活動する「個人事業主」や、会社を設立して経営をおこなう「法人経営者」などが含まれます。
このように、「フリーランス」は働き方を指す言葉であり、「自営業」は事業運営の形態を表す言葉という点が大きな違いです。
次の章では、両者の特徴や具体的な違いについて詳しく解説します。
フリーランスとは?
フリーランスとは、企業や団体に雇用されず、個人の裁量で業務を受託して働くスタイルを指します。
主に業務委託契約を結び、成果や業務の遂行内容に応じて報酬を受け取るのが一般的です。
なお、法人を設立して代表を務めている場合でも、契約の主体が個人であればフリーランスとして扱われることがあります。ただし、法人名義で業務を請け負っている場合は、一般的に「法人事業者」として区別されます。
業務委託契約では、雇用契約のような労働時間や勤務場所の制限が比較的少なく、柔軟な働き方がしやすい点が特徴です。
一方で、フリーランスは原則として労働基準法の保護対象外となるため、最低賃金や残業代などの保障を受けられないケースが多く、契約内容を十分に確認しておくことが重要です。
参考:厚生労働省|フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
自営業とは?
自営業とは、企業や団体に雇われるのではなく、自ら事業を営む働き方です。
主に個人事業主やフリーランスなど、自分の名前または屋号で取引を行う人が該当します。
一方で、法人を設立して代表を務める場合は、一般的には「会社経営者」と呼ばれますが、事業を自ら運営している点では自営業と共通する部分もあります。
実際には、飲食業や小売業、サービス業など、地域に根ざした事業を展開するケースが多く見られます。
フリーランスとして働くメリット

フリーランスとして働く主なメリットには、次の3つが挙げられます。
- 自分の裁量で働ける自由度の高さ
- スキルアップにつながる
- 成果次第で高収入を目指せる
それぞれのメリットについて解説していきます。
自分の裁量で働ける自由度の高さ
フリーランスとして働くメリットのひとつに、働き方の柔軟性が挙げられます。
企業や団体に属さずに業務をおこなうため、勤務時間や作業場所、休暇の取り方などをある程度自分で調整できる場合があります。
例えば、平日の昼間にしかできない手続きや用事を済ませやすくなることや、自分の生活リズムに合わせて作業時間を工夫できる点がメリットとして挙げられます。ただし、案件や納期の都合により必ずしも自由に調整できるわけではなく、自己管理が重要となります。
このように、フリーランスは自身の働き方を工夫することで、仕事とプライベートのバランスを取りやすくすることも可能です。
参考:厚生労働省|第5章 自営業者における労働時間と働き方に関する 調査
スキルアップにつながる
フリーランスとして活動するメリットの一つは、組織に縛られない立場から、さまざまな分野の案件に関わる機会がある点です。
案件によっては、特定のスキルを深めたり、新しい知識を学んだりすることができ、実務を通じて多様な経験を積む機会となります。
また、継続的な収入を目指す場合は、複数の依頼主と良好な関係を保つことが役立つことがあります。
さらに、仕事の進行に伴う質問対応や報酬の交渉、打ち合わせなどを通して、対人能力やコミュニケーションスキル、交渉力といった実践的な力を身につけることができる場合もあります。
こうした日々の経験を通して、自ら学び成長する姿勢を意識することが、フリーランスとしての活動の幅を広げることにつながる可能性があります。
成果次第で高収入を目指せる
フリーランスとして働くことで、場合によっては会社員よりも高い収入を得ることも可能です。
フリーランスは、自ら仕事を見つけて実行する働き方であり、個人のスキルや行動力が収入に影響します。
たとえば、営業力や専門的な知識・技術がある場合には、より高単価の案件を受注できる可能性があります。ただし、収入は案件や業界の状況、経験年数などによって変動するため、安定的な収入を得るには計画的な案件選びや自己管理が重要です。
フリーランスとして働くデメリット

フリーランスとして働く際に考慮すべきポイントとして、以下のようなものがあります。
- 収入の変動が生じやすい
- 確定申告などの事務手続きが必要
- 所得に応じた税負担が生じる
それぞれについて詳しく解説していきます。
収入の変動が生じやすい
フリーランスという働き方は、個人のスキルや実績によって高収入を目指せるメリットがあります。一方で、収入は案件の単価や受注数によって変動しやすく、収益が安定しにくい場合もあります。
フリーランスの仕事は主に業務委託契約で進められるため、契約終了後に次の案件が見つかるまで収入が減少することもあります。そのため、資金計画や貯蓄、契約のタイミングなどをあらかじめ考慮しておくことが重要です。
また、収益が安定しにくい状況では、必要な設備投資や事業の拡大に十分な資金を充てるのが難しいケースもあるため、資金管理には注意が必要です。
確定申告などの事務手続きが必要
給与以外の所得が年間で20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。開業届の提出有無にかかわらず、事業所得や雑所得など、対象となる所得に応じて適切に申告を行う必要があります。
フリーランス、自営業、個人事業主などの働き方にかかわらず、所得税の納税義務は原則として共通です。ただし、控除や所得の種類によって申告不要となるケースもあります。
また、日々の売上や経費を整理して帳簿を作成し、領収書や請求書などの証憑類を保存しておくことが望ましいとされています。所得の規模や帳簿の形式によっては、簡易的な記録で足りる場合もあります。
参考:国税庁|所得税の確定申告
所得に応じた税負担が生じる
フリーランスとして収益が増えると、所得税は累進課税制度に基づくため、所得が増えるほど税率が高い部分に課税されます。
現行の所得税制度では、例えば課税所得が900万円を超える部分には33%の税率が適用される、といったように、課税所得に応じて税率が段階的に上がります。
一方、法人税については、中小企業の場合は一定の所得までは軽減税率が適用され、所得が増えても法人税率が一定の範囲内で安定する仕組みになっています。ただし、事業税や住民税などを加味すると、実効税率は変動します。
そのため、所得が一定水準を超える場合は、法人化することで税負担の面でメリットが出ることもあるでしょう。ただし、法人化には設立・維持コストや社会保険の負担、会計処理の手間なども伴うため、税理士に相談して総合的に判断することが重要です。
参考:国税庁|No.2260 所得税の税率
自営業として働くメリット
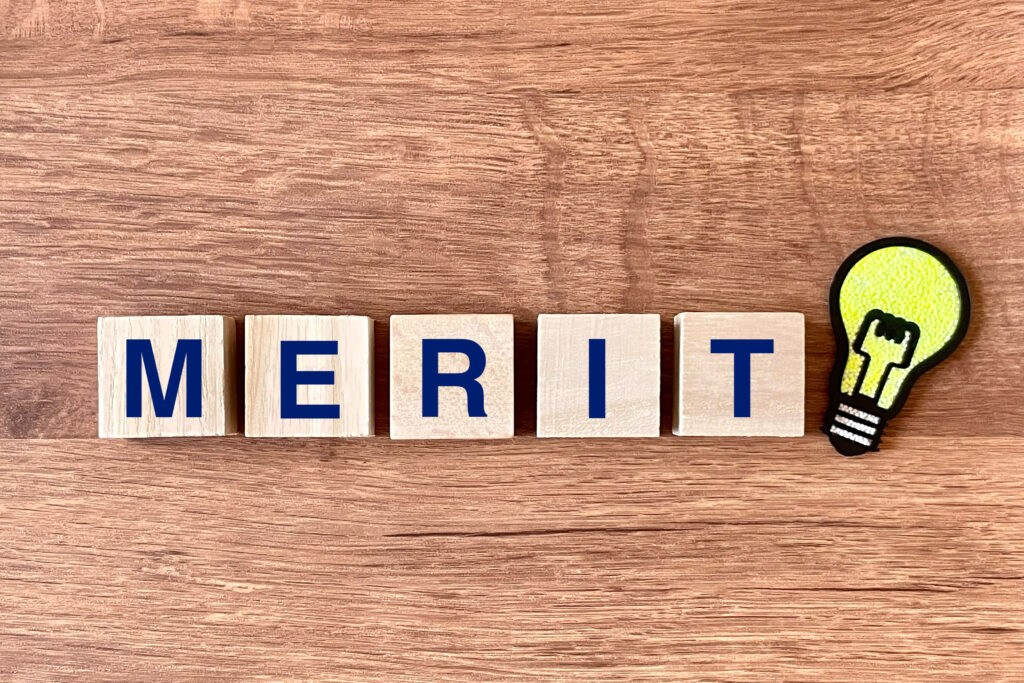
自営業として働くメリットとして、以下の3つが挙げられます。
- 定年退職がない
- 経費計上できる幅が広がる
- 成果に応じた収入を得られる
それぞれのメリットについて解説していきます。
定年退職がない
自営業には法的な定年がないため、体調や意欲がある限り、年齢に関係なく働き続けることが可能です。業務内容や働き方を自分で設計できるため、得意分野や興味のある分野に取り組みながら、長期的に仕事を続けやすい点がメリットのひとつです。
もちろん、事業の収入は変動することもありますが、安定した事業基盤を築ければ、経済面だけでなく精神的な充実感も得やすくなります。
一方、会社員や公務員には一般的に定年制度があります。再雇用制度を利用して働き続ける場合もありますが、給与や仕事内容が変わるケースがあり、将来の生活設計に備えることが重要です。
このように、自営業は年齢に縛られず柔軟に働ける可能性がある働き方ですが、収入の変動リスクや将来の資金計画にも注意しながら、長く働く環境を整えることが大切です。
参考:厚生労働省|第7章 定年、退職及び解雇
経費計上できる幅が広がる
自営業として働く場合、事業に関わる支出を経費として計上できる点がメリットのひとつです。
たとえば、業務に関連する出張の移動費は「旅費交通費」として計上できる場合があります。また、取引先との打ち合わせ費用については、税法上一定の条件を満たす場合に「接待交際費」として経費計上できることがあります。
自宅を仕事場として使用している場合も、家賃やインターネット代、水道光熱費などの一部を業務使用分として按分し、経費に含めることが可能です。
ただし、経費として認められるのはあくまで業務に使用した分のみです。プライベートな利用分とは明確に区分して管理するようにしましょう。
参考:国税庁|No.2210 必要経費の知識
成果に応じた収入を得られる
自営業として働く場合、業務の多くを自らの裁量で進めることになります。そのため、営業活動やスキルの向上が収入に影響するケースもあります。努力や成果が売上に反映されやすい環境で働きたい方にとっては、自営業は選択肢のひとつと言えるでしょう。
一方、会社員の場合、給与体系や評価制度によっては、成果が給与や昇給に直接反映されにくいこともあります。ただし、企業によっては成果に応じて賞与や昇給に反映される制度を採用している場合もあります。
このように、自営業も会社員もそれぞれ収入に関する特徴があり、自分の働き方や目指す収入スタイルに応じて選択することが重要です。
自営業として働くデメリット
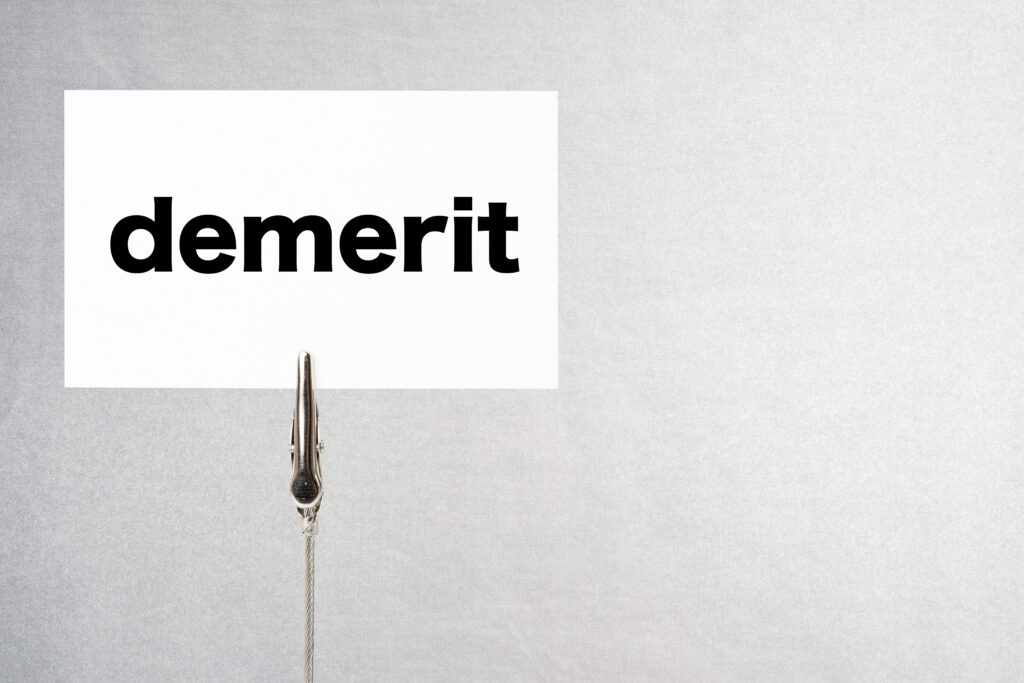
自営業として働く際に考慮すべきポイントとして、以下のようなものがあります。
- 金融機関の融資審査が慎重になることがある
- 労働法上の適用範囲が異なる
- 長時間労働や過重な業務負担につながることがある
それぞれのデメリットについて解説していきます。
金融機関の融資審査が慎重になることがある
開業直後の自営業者は、事業の実績が少ないため、社会的信用の面で会社員と比べて金融機関からの評価に影響を与える場合があります。
特に、収入が安定していない場合、住宅ローンや事業用クレジットカードの審査で注意が必要なケースがあります。
銀行や信販会社は、給与所得が定期的にある会社員と異なり、収入の変動や返済能力を評価する際に参考となる情報が限られるため、審査が慎重になることがあるのです。
そのため、開業時には自己資金の確保や信用力のある取引先との関係構築など、金融面での準備やリスク管理を意識する必要があります。
労働法上の適用範囲が異なる
自営業者は、労働基準法などの労働関連法の直接的な適用対象にはならないため、会社員とは異なる形で働くことになります。
そのため、雇用保険や労災保険といった公的保険制度は原則として自動的には適用されません。
また、仕事が減少した場合や受注が途切れた場合に、会社員のような失業手当はありません。ただし、各種助成制度や国の支援策を活用することでリスクをある程度緩和することが可能です。
このように、自営業者は会社員とは異なる保障体系の下で働くことになるため、経済面や保険制度について事前に理解しておくことが重要です。
参考:厚生労働省|雇用・労働雇用保険制度
長時間労働や過重な業務負担につながることがある
自営業者は、働き方の自由度が高いというメリットがあります。その一方で、業務量やスケジュールの管理が十分でない場合、長時間労働や過重な業務負担につながることもあります。
特に開業初期は、仕事を受けやすい状況から業務が集中しやすくなる傾向があります。
そのため、計画的な業務管理や適切な休息を意識することが重要です。必要に応じて、税務や経理のアウトソーシングも検討すると、負担軽減につながります。
フリーランス・自営業を始めるために必要な手続き

フリーランスや自営業を始める際に、多くの方が必要とする代表的な手続きには、以下のものがあります。
- 開業届の提出
- 青色申告承認申請書
- 健康保険・年金の加入手続き
それぞれの手続きについて解説していきます。
開業届の提出
開業届とは、個人で事業を始めたことを税務署に届け出る書類で、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。所得税に関する国税書類の一つで、居住地などの管轄税務署に提出します。
原則として、事業開始日から1か月以内に提出することが望ましいとされています。開業日とは、事業を開始した本人が「事業を開始した日」として設定する日で、特別な審査はありません。ただし、帳簿や売上実績などと整合性を持たせることが重要です。
提出が1か月を過ぎても刑事罰や罰金は課されませんが、青色申告承認申請書や各種助成制度などの手続きに影響する場合があります。そのため、なるべく早めの提出をおすすめします。
参考:国税庁|A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
青色申告承認申請書
青色申告を希望する場合は、開業届とは別に「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出する必要があります。
この申請書には提出期限があり、通常はその年の3月15日までです。ただし、1月16日以降に事業を開始した場合は、開業日から2か月以内が提出期限となります。
確定申告の直前になって青色申告を検討しても、申請が間に合わない場合がありますので、できるだけ早めに手続きを行うことが望ましいです。
なお、提出期限を過ぎてしまった場合や開業届のみを提出して青色申告承認申請書を提出していなかった場合は、原則として白色申告での申告となります。青色申告で認められる特別控除や損失の繰越といったメリットを活用するには、開業届とあわせて青色申告承認申請書を提出することをおすすめします。
参考:国税庁|A1-8 所得税の青色申告承認申請手続
健康保険・年金の加入手続き
会社を退職して個人事業主として独立する場合、健康保険と年金に関する手続きが必要です。
一般的には、会社員時代に加入していた社会保険(健康保険・厚生年金)から、国民健康保険および国民年金への加入に切り替えることが多くなります。この手続きは、退職日翌日からなるべく早めに、住民票のある市区町村の役所で行うことが推奨されています。
ただし、健康保険については一定の条件を満たせば「任意継続被保険者制度」を利用することも可能です。これにより、退職後も最大2年間、以前加入していた健康保険を継続して利用できます。任意継続を希望する場合は、退職日の翌日から20日以内に、従来加入していた健康保険組合や協会けんぽに申請手続きを行う必要があります。なお、保険料の支払いや手続きの可否には条件があるため、事前に確認しておくことが重要です。
参考:日本年金機構|健康保険・厚生年金保険の保険料関係
自分の事業に最適な開業形態を検討しよう!

今回は、フリーランスと自営業の違いについて解説しました。
フリーランスと自営業は、どちらも組織に属さずに働く点で共通しています。一般的には、フリーランスは個人で案件を受けて働く「働き方」を指すことが多く、一方の自営業は、店舗や事業を運営する「事業形態」に焦点を当てた言葉として使われます。
税務上は、フリーランスも開業届を提出すれば個人事業主として扱われ、開業手続きや所得税の計算方法などは基本的に共通しています。ただし、事業規模や業種によって、適用される制度や控除の内容が異なる場合もあります。
自分の働き方や事業内容に合った開業形態を検討する際は、この記事を参考にしつつ、必要に応じて税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。





