メニュー
会社設立
会社役員とは?種類から決める際の注意点について徹底解説

読了目安時間:約 7分
会社役員とは、会社法上、取締役・監査役・会計参与など、企業経営に関する意思決定や監督を担う立場の人を指します。
役員を選任する際は、株主総会での決議など、会社法に基づいた正式な手続きが必要です。
また、役員報酬の決定方法についても、税法上の「定期同額給与」などの要件を満たす必要があり、一般の給与体系とは異なるルールが適用されます。
本記事では、会社役員の基本的な仕組みや役割をわかりやすく解説し、あわせて役員の種類や選任時の注意点についても紹介します。役員制度を正しく理解したい方はぜひ参考にしてください。
目次
会社役員とは?
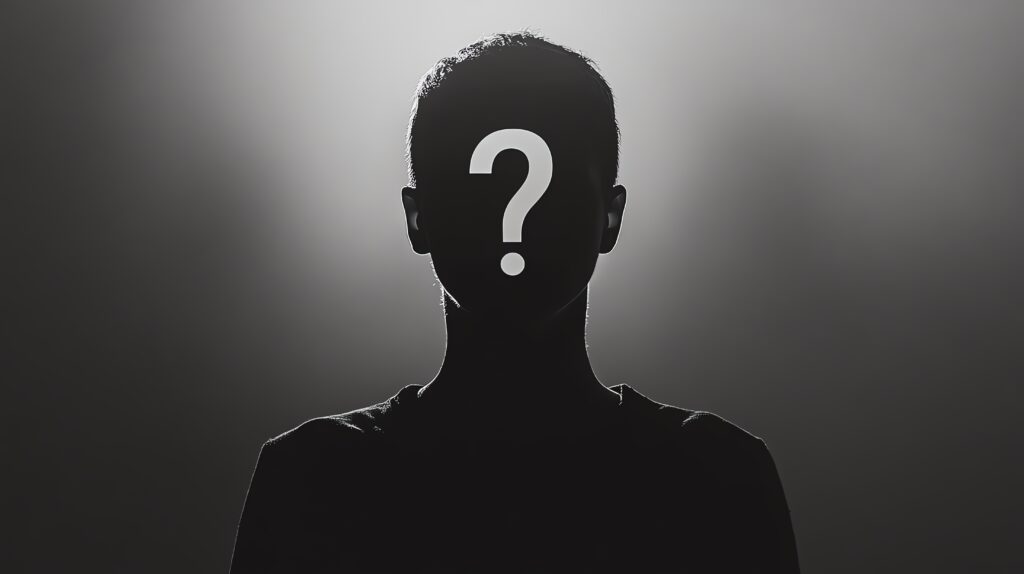
役員とは、企業経営に関する重要な方針や意思決定に関わる立場を担う人を指します。
日本の会社法上、役員は株主から会社の経営を委ねられ、善管注意義務や忠実義務をもって職務を遂行することが求められています。
このように、役員は会社経営において重要な意思決定を担う責任ある立場であり、その判断は企業の方向性に大きな影響を与えるのです。
また、取締役などの業務執行に関わる役員には、経営方針を示すだけでなく、従業員が円滑に業務を行えるよう組織運営を管理・支援する役割も求められます。
参考:国税庁|第1款 役員等の範囲
会社役員と一般社員との違い
役員と社員は、企業内での立場や契約形態において明確な違いがあります。
役員は会社の経営に携わる立場であり、事業運営の方向性を決定し推進する責任を負っています。一方、社員は労働者として、組織の指揮命令のもとで働き、労働力を提供する役割を果たします。
社員は労働基準法上の「労働者」として扱われ、会社と雇用契約を結びますが、役員は一般的に「任用契約(委任契約)」を会社と締結し、その職務にあたります。
そのため、役員は原則として通常の雇用関係には該当せず、労災保険や雇用保険の対象外となります。
ただし、代表取締役などの役職にあっても、実際の業務内容が従業員と同様である場合には、「使用人兼務役員」として一部の業務に限り、労働保険の適用対象と認められるケースもあります。
この判断は、所轄の労働基準監督署や労働局が個別に行うため、加入の可否については専門家への確認が望まれます。
このように、役員と社員の違いは、会社における立場や契約上の位置づけによって区別されているのが一般的です。
会社役員と執行役員との違い
役員は、会社法に基づき設けられる正式な役職であるのに対し、執行役員は会社法上に定めのない、企業が独自に設置できる任意のポジションです。ただし、会社法で定義される「執行役(会社法第402条の2)」とは異なる制度である点に注意が必要です。
執行役員の主な役割は、取締役などの経営陣が策定した経営方針や業務計画を、実際の業務レベルで遂行することです。経営層と現場をつなぐ橋渡し役として、円滑な組織運営を支える重要なポジションといえます。
また、経営陣が経営判断に専念できる体制を整える目的で、執行役員を置く企業も多く見られます。多くの場合、管理職など一定の責任を担う社員の中から執行役員が選任されます。
名前に「役員」が含まれていますが、法的には通常の社員と同様に扱われ、労働基準法の適用対象となります。
参考:国税庁|商法改正に伴い導入された「執行役」制度等を巡る税務上の諸問題
会社役員の種類

会社役員には、主に次のような種類があります。
- 種類①:取締役
- 種類②:代表取締役
- 種類③:監査役
- 種類④:会計参与
以下では、それぞれの役割や特徴について解説します。
種類①:取締役
取締役は、会社法で定められた役職の一つで、会社の業務を円滑に進めるための重要な意思決定を行います。
2006年の会社法改正以前は、株式会社の設立には取締役会の設置が必須で、取締役は3名以上、監査役は1名以上選任する必要がありました。しかし、改正後は取締役1名でも会社を設立できるようになり、柔軟な体制が可能となっています。
株式会社では、株主が会社の所有者として経営方針の承認などの権限を持ち、実務的な経営は取締役や取締役会が担います。株主総会では、前年度の事業や決算の報告、次期の経営方針の承認などが行われますが、日常の経営判断は取締役の責任で進められます。
参考:e-Gov 法令検索|会社法
種類②:代表取締役
代表取締役は、会社法に基づき設置される取締役の中から選ばれ、会社を代表して業務執行を行う権限を持つ役職です。
取締役と混同されることがありますが、代表取締役は複数の取締役の中から選出され、法人を代表して契約を締結したり、会社の意思決定を実行したりする役割を担います。
選任方法は、会社の形態によって異なります。取締役会を置く会社では取締役会の決議により選任されますが、取締役会を置かない会社では株主総会で選任される場合もあります。
また、会社によっては「代表取締役社長」として社長職を兼ねるケースや、複数の代表取締役を置くケースもあります。
種類③:監査役
監査役は、企業内部において取締役および会計参与が適切に職務を遂行しているかを監督する役割を担う重要なポジションです。
取締役会を設置している株式会社においては、監査役の設置が法律上求められる場合があります。
監査役は、取締役や会計参与に対して業務の報告を求め、会社の運営が法令や定款に従って行われているかを監査・調査する責任があります。必要に応じて、問題が認められた場合には取締役会や株主総会への報告が求められます。
監査役の設置は、企業におけるガバナンス体制の強化や経営の透明性向上に寄与する可能性があります。
一方で、取締役会を設けていない会社や非公開会社では、監査役の設置は法律上必須ではありません。
参考:J-Net21中小企業ビジネス支援サイト|監査役の役割について教えてください。
種類④:会計参与
会計参与とは、企業の会計に関する書類の作成や管理に専門的知識をもって関与する役員です。
就任資格は公認会計士または税理士に限定されており、顧問税理士が任命されることもあります。
会計参与は、他の役員と協力して財務諸表や計算書類を作成し、株主総会や債権者からの求めに応じて会計に関する説明や資料の開示を行う責務があります。
任期は原則として取締役と同様で、再任される場合には「重任登記」の手続きが必要です。
また、業務遂行にあたっては、経営陣と協働しつつも、一定の独立性を保った立場で職務を行います。
参考:日本税理士連合会|会計参与制度
会社法で会社役員として定められていない役職

会社法上、正式に定められた役員の種類は限られています。一方で、企業によって独自に設置される役職もあります。代表的なものとして、以下のような役職があります。
- 役職①:会長
- 役職②:社長
- 役職③:専務・常務
それぞれの役職について解説していきます。
参考:国税庁|第1款 役員等の範囲
役職①:会長
会長は、企業において社内で象徴的・統括的な役割を担うことが多い役職です。社長を退任した人物が就く場合もありますが、会社によっては現社長や外部の人物が会長に就任することもあります。
会社法上、会長という役職は定義されていませんが、会社の定款や就業規則に基づき、税法上の役員に該当する場合があります。この場合、取締役と同様に「役員報酬」として報酬が支払われることがあります。
役職②:社長
社長とは、企業の経営を統括し、業務全体の運営を主導する役職です。一般的には、企業の経営責任者として社内外から認識される存在とされています。
代表取締役と混同されることがありますが、両者は必ずしも同一ではありません。代表取締役は、会社法に基づき取締役会や株主総会の決議により任命され、会社を法的に代表する立場です。
一方、社長という役職は会社法上の法定役職ではなく、商慣習に基づいて企業内で経営責任者として位置づけられる役割です。
多くの企業では「代表取締役社長」という形で両方の肩書きを兼ねることが一般的ですが、会社によっては代表取締役と社長を別々に設置している場合もあります。
また、代表取締役は複数名設置されることがありますが、社長は慣習的に1社につき1人が任命されるケースが多く見られます。
役職③:専務・常務
専務とは、正式には「専務取締役」や「専務執行役」と呼ばれることがあり、社長を補佐しつつ企業の経営に関わる役職です。主に業務全般の管理や指導を担当することが多く、経営に関する判断にも関与する場合があります。
ただし、専務という役職は会社法で明確に定められているものではなく、呼称や職務範囲は企業ごとに異なります。常務も同様に法的な定義はなく、企業内で一般的に使用されている肩書きです。
一般的な傾向として、専務は会社全体の経営方針や戦略に関わることが多く、常務は日常業務や現場の運営管理など実務的な役割を担う場合が多いとされます。しかし、役職の名称や職務内容は企業によって異なるため、必ずしもこの限りではありません。
会社役員の選任方法

会社を円滑かつ健全に運営するためには、役員の選任方法を適切に理解しておくことが重要です。
役員の選任手続きは、会社が取締役会を設置しているかどうかなど、組織形態によって異なります。
そのため、自社の機関設計に応じた選任手続きを事前に確認しておくことが望ましいでしょう。
以下では、取締役会を設置する場合と設置しない場合のそれぞれの選任手続きについて解説します。
参考:J-Net21中小企業ビジネス支援サイト|取締役会の権限等について教えてください。
取締役会を設置するケース
取締役会を設置する株式会社では、原則として取締役を3名以上置く必要があります。また、監査役については、会社の規模や定款によって設置が求められる場合があります。監査役は取締役と兼任できないため、必要に応じて独立して選任することになります。
取締役の選任は株主総会で行われ、一般的な手順は以下の通りです。
- 定款に取締役の人数や選任に関する事項を記載する
- 株主に向けて株主総会の招集通知を送付する
- 総会にて、取締役候補者の選出について承認を得る
- 承認された者から正式な就任の承諾を受ける
- 法務局にて登記手続きを行う
このように、定款の整備から登記まで一連の手続きを順を追って行うことが求められます。
取締役会を設置しないケース
取締役会を設置しない株式会社では、取締役が1名いれば会社運営が可能であり、監査役を必ず設置する必要はありません。
設立時には、定款であらかじめ指名された者が取締役として職務に就きます。個人が会社を設立する場合には、代表取締役として自ら就任することで設立手続きを行うことが可能です。その後、取締役の増員や交代が生じた場合は、株主総会で新たに選任する形となります。
なお、取締役会を設置しない株式会社は、一般的に従業員数や資本金が少ない中小規模の企業で採用されるケースが多いとされています。
会社役員の役員報酬の決め方

会社法では、役員報酬は定款に記載するか、株主総会の決議により決定する必要があると定められています。
中小企業の場合、定款に報酬規定が設けられていないことも多く、その場合は株主総会の決議で金額が決まることが一般的です。
役員報酬とは、取締役や監査役など会社の役員に対して支払われる報酬を指し、従業員に対する給与とは性質が異なります。従業員の給与は労働の対価として支給されるため原則として全額を損金算入できますが、役員報酬を損金に算入するには一定の条件を満たす必要があります。
具体的には、事業年度開始後3か月以内に株主総会で報酬額を決議することが基本とされており、この期間を超えた場合は原則として損金算入が認められない可能性があります。ただし、臨時改定や業績悪化に伴う改定など、例外的に認められる場合もあります。
参考:国税庁|No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
会社役員を決める際の注意点

会社役員を決める際には、以下のポイントに注意することが重要です。
- 会社役員も社会保険への加入義務がある
- 会社方針に適した人材を選任する
- 上場企業は社外取締役の選任が義務化されている
それぞれの注意点について解説していきます。
会社役員も社会保険への加入義務がある
会社から報酬を受け取る役員は、その報酬をもとに厚生年金保険・健康保険・介護保険などの社会保険への加入が原則として義務付けられます。
従業員と同様の取り扱いとなりますが、報酬が支払われていない場合には、これらの保険への加入義務は生じません。
ただし、報酬額が社会保険料の算定基準となる最低額を下回る場合は、社会保険に加入できないことがあるため注意が必要です。
なお、役員は法律上「労働者」には該当しないため、労災保険や雇用保険の対象には基本的に含まれません。ただし、労災保険については、条件を満たすことで役員も「特別加入」という形で加入できる場合があります。
会社方針に適した人材を選任する
役員の選任にあたっては、会社の経営方針や組織体制に適した人材を選ぶことが重要です。
具体的には、法令に基づく資格要件や、会社の業務内容に応じた経験・知識などを総合的に考慮して判断することが求められます。
役員は経営の意思決定に関わる重要な立場であり、その行動や発言は企業の信用や業務運営に影響を与えるため、慎重な選任が必要です。
また、一度任命された役員を変更する場合には、株主総会での決議や登記手続きなど、所定の法的手続きを経る必要があります。
そのため、役員の選任は目先の事情だけでなく、中長期的な経営方針や組織の安定性を見据えておこなうことが望ましいといえます。
上場企業は社外取締役の選任が義務化されている
上場企業においては、社外取締役の選任が義務付けられています。社外取締役とは、会社の内部から独立した立場で経営の監督や意思決定に対して客観的な視点を提供する取締役のことです。
上場企業は、会社法や東京証券取引所の上場規則に基づき、一定人数以上の社外取締役を選任することが義務とされています。これにより、経営の透明性向上や利害関係の調整、外部の専門的意見の反映が期待されます。
また、法律上の義務がない非上場企業であっても、経営の透明性を高めたり、外部の専門家の視点を取り入れたりする目的で、任意に社外取締役を設置することも可能です。
参考:法務局|社外取締役及び社外監査役の要件等の改正について
会社役員の選任は慎重に決めよう!

会社運営において、会社役員は経営の意思決定や業務監督を担う重要な役職です。
取締役は、株主からの委任を受け、会社の方向性を示すとともに、業務の実行状況を把握・監督する責任があります。
会社役員と従業員では、業務内容や契約上の立場などに違いがあります。
個人で会社を設立する場合には、発起人が株主であり取締役を兼任することもありますが、その際も法律に基づく手続きや条件を遵守する必要があるでしょう。
会社役員の選任や報酬の決定については、設立前に法的ルールを正しく理解しておくことが重要です。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。





