メニュー
会社設立
合同会社が節税になる理由とは?節税効果を高めるコツや節税以外のメリットも紹介

読了目安時間:約 8分
合同会社は、出資者(社員)が自ら事業の運営に関わることができる法人形態のひとつです。
法人化することで、経費として計上できる範囲が広がる場合があるほか、役員報酬や退職金などを活用した税務上の調整がしやすくなる場合もあります。
ただし、実際に税負担の軽減につながるかどうかは、収益規模や支出内容、役員報酬の設定方法などによって大きく異なります。
そのため、設立前に節税効果について理解し、自身の事業規模や所得状況に応じたシミュレーションを行うことが重要です。
本記事では、「合同会社で節税効果が見込めるケース」や「節税以外のメリット」について解説します。
ぜひ参考にして、法人化を検討する際の判断材料としてお役立てください。
合同会社が節税になる理由とは?

合同会社は、場合によっては個人事業主として活動するよりも税負担を抑えられることがあります。
その主な理由として、以下の8つのポイントが挙げられます。
- 理由①:法人税が適用される
- 理由②:役員報酬を経費計上できる
- 理由③:役員報酬に給与所得控除が適用される
- 理由④:赤字繰越を利用できる
- 理由⑤:経費幅が広がる
- 理由⑥:役員退職金を経費にできる
- 理由⑦:消費税の免税事業者になれる可能性がある
- 理由⑧:相続税や贈与税を抑えられる可能性がある
それぞれの理由について解説していきます。
理由①:法人税が適用される
合同会社を設立すると、事業所得に対しては「法人税」が課されます。
法人税は、所得税のように細かい段階で税率が変わる仕組みではなく、資本金や所得金額などに応じて一定の税率が適用されるのが一般的です。
たとえば、資本金1億円以下の中小法人など一定の要件を満たす場合、年800万円までの所得に対しては15%の軽減税率が適用され、それを超える部分には23.2%の税率が適用されます。
一方、個人事業主として活動している場合には、所得に対して「所得税」が課されます。所得税は累進課税制度を採用しており、所得が増えるほど税率が上がり、最高税率は45%と高く設定されています。
そのため、所得が一定水準を超えるようになった場合、法人化によって税率が下がり、結果的に税負担が軽減されることもあります。ただし、役員報酬や社会保険料などを総合的に考慮する必要があり、必ずしもすべてのケースで節税になるとは限りません。
理由②:役員報酬を経費計上できる
合同会社を設立して役員報酬として収入を得る場合、一定の条件を満たせば、その報酬は会社の経費として認められる場合があります。
課税対象となる所得は、売上から必要経費を差し引いて算出されます。
そのため、役員報酬を適切に経費計上することで、課税所得を抑えられるケースもあり、結果として個人事業のときより税負担が軽くなる可能性があります。
参考:国税庁|No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
理由③:役員報酬に給与所得控除が適用される
個人事業主として得た収入は原則として全額が所得税の課税対象となります。一方、合同会社の役員報酬は「給与所得」として扱われるため、所得税を計算する際には「給与所得控除」を適用できます。
この控除により、課税対象となる所得額を一定程度圧縮できる可能性があるため、個人として納める所得税の負担が軽減される場合があるのです。
そのため、法人化することで、場合によっては法人・個人双方での税負担を調整しやすくなるケースがあります。
参考:国税庁|No.1410 給与所得控除
理由④:赤字繰越を利用できる
法人として事業を進める中で赤字が発生した場合、一定の条件のもとで損失を翌年度以降に繰り越すことができます(現行制度では最長10年間)。
この繰越控除を利用することで、将来利益が出た際に過去の赤字と相殺し、課税対象となる利益を抑えることが可能です。
創業初期は収支が安定せず赤字となる場合もあるため、繰越控除制度を活用した税務上の戦略は、長期的な事業運営の計画において重要な意味を持ちます。
この制度は、合同会社に限らず株式会社などすべての法人に適用されるため、法人設立時には税務上のメリットとして検討する価値があります。
参考:国税庁|No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
理由⑤:経費幅が広がる
個人事業主から法人化することで、経費として計上できる範囲が広がるため、条件次第では法人税の節税につながる場合があります。
法人として経費計上が認められる主な支出には、以下のようなものがあります。
- 経営者本人への給与や賞与
- 健康診断にかかる費用
- 社宅の家賃および関連する費用
- 出張時の手当
- 将来の退職金
特に社宅費用は金額が大きくなりやすく、適切に制度を活用すれば節税効果が期待できます。ただし、経費として認められるかどうかは、支出の内容や金額、法人の規程などに応じて税務上の判断が必要です。
参考:国税庁|No.2210 必要経費の知識
理由⑥:役員退職金を経費にできる
合同会社を設立すると、役員に対して支払う退職金を、一定の条件を満たす場合に会社の経費として計上することが可能です。
退職金を経費に計上するには、退職金規程を整備し、支給額が妥当であることを示す必要があります。
この制度を活用することで、法人税の課税所得を抑えることができ、法人化による税務面でのメリットの一つとして位置付けられます。
また、法人化することで、事業主自身も退職金を受け取ることが可能となり、税務面でのメリットだけでなく、将来の生活資金を準備する手段としても有効です。
参考:国税庁|第7款 退職給与
理由⑦:消費税の免税事業者になれる可能性がある
個人事業主が新たに法人を設立した場合、法人としての売上実績がないことから、設立後の一定期間(最長で2年間)について消費税の納税義務が免除される「免税事業者」となる可能性があります。
個人事業主として消費税を納めていた場合でも、法人化により一定期間は消費税の納税負担が軽減されるケースがあります。ただし、インボイス制度の導入に伴い、適格請求書発行事業者として登録している場合などは、この免税措置が適用されない場合があります。
そのため、法人設立時に消費税の免税適用条件や例外事項について、税理士など専門家に相談し、制度の詳細を十分に確認することが重要です。
参考:国税庁|No.6501 納税義務の免除
理由⑧:相続税や贈与税を抑えられる可能性がある
合同会社を通じて事業を行っている場合、その会社が保有する不動産などの資産は、会社の財産として管理されるため、原則として相続や贈与の対象から外れます。
特に、事業の後継者が家族以外である場合には、会社名義の財産が相続財産に該当しないことから、事業承継の方法によっては、相続税や贈与税の負担を軽減できる可能性があります。
ただし、税制は非常に複雑で、資産の種類や事業形態、承継の方法によって税額が大きく変わるため、具体的な対応は税理士などの専門家に相談することが重要です。
参考:国税庁|No.4105 相続税がかかる財産
合同会社で節税効果を高めるコツ

合同会社における節税対策としては、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。個々の状況によって効果は異なりますが、一般的に次のような点が参考になります。
- 役員報酬の設定を検討する
- シミュレーションをおこなう
- 目的に合った会社形態を選ぶ
- 専門家に相談する
それぞれについて解説していきます。
役員報酬の設定を検討する
合同会社での節税を考える際には、役員報酬の設定が重要なポイントの一つです。
所得税は累進課税制度が採用されており、所得が増えるほど税率が高くなります。そのため、役員報酬の金額によって法人税の負担や個人の所得税・社会保険料への影響が変わってきます。
役員報酬を極端に高額に設定すると、法人税の節税になる可能性がある一方で、受け取る本人には高い所得税が課される場合があり、加えて社会保険料の負担が大きくなることがあります。さらに、税務署から「妥当性を確認する必要がある」と判断される場合があり、税務調査の対象となる可能性もあります。こうした場合、追加の税金が発生することがあるので注意が必要です。
そのため、役員報酬を決める際には、法人税と所得税・社会保険料のバランスを考慮しつつ、事業規模や同業他社の水準などを参考に、妥当な金額を設定することが大切です。必要に応じて税理士に相談し、客観的に適正と判断される金額を設定することをおすすめします。
シミュレーションをおこなう
合同会社で節税効果を検討する際は、シミュレーションをおこなうことが重要です。
税金の負担額は、所得や家族構成、控除の有無などによって個々に異なるため、自分の状況に応じたシミュレーションが役立ちます。
例えば、同じ年収でも扶養家族の有無によって適用される控除が変わるため、納める税額に差が生じることがあります。
節税効果を正確に把握するには、事業所得や経費の内容、扶養関係などを踏まえた上で、法人化した場合に発生する法人税・住民税・社会保険料などを個別に確認することが望ましいです。
必要に応じて、税理士など専門家に相談しながらシミュレーションすることをおすすめします。
目的に合った会社形態を選ぶ
合同会社で節税効果を検討する際には、事業開始時点で自身の経営方針や将来のビジョンに合った会社形態を選ぶことが重要です。
合同会社と株式会社では、設立費用や運営の柔軟性、資金調達の方法などに違いがあります。
それぞれの特徴や利点・注意点を理解した上で、事業内容や将来の計画に応じて最適な形態を選択することが大切です。
参考記事:株式会社と合同会社の違いは何?設立するならどっちを選ぶべき?
専門家に相談する
専門家に相談することで、合同会社設立に伴う税務面や経営面での対応を適切に進めやすくなり、節税対策についても相談できます。
会社設立のサポートを行う専門家には、税理士・行政書士・司法書士などがいます。特に税務や経営面の相談に強いのが税理士です。
税理士に相談することで、次のようなメリットが期待できます。
- 法令に基づいた節税や資金計画に関する具体的なアドバイスが受けられる
- 業種や事業内容に応じた適法な節税策の検討が可能
- 融資や資金調達を踏まえた資本金設計の検討ができる
また、税理士は設立支援の経験を活かして、業界特有の税務上の留意点について助言できる場合があります。これにより、適切な税務戦略や経営判断の参考になります。
合同会社の節税以外のメリット

合同会社には、節税以外にも以下のようなメリットがあります。
- 柔軟な経営運営が可能
- 決算公告の義務がない
- 役員の任期に制限がない
それぞれのメリットについて解説していきます。
柔軟な経営運営が可能
合同会社は、出資者自身が経営に携わるケースが多いため、意思決定の柔軟性が高く、迅速な経営判断が可能です。
株式会社の場合、重要事項を決定する際には株主総会や議事録の作成が必要になる場合がありますが、合同会社では定款で定めた方法に従って意思決定が行えるため、経営のスピード感を重視する方に向いています。
また、合同会社では利益の分配方法を定款で柔軟に定めることができます。出資比率に関わらず配分ルールを設定できる点は、事業内容やメンバー構成に応じた柔軟な運用が可能です。
決算公告の義務がない
決算公告とは、会社の財務状況を株主や取引先などに知らせるため、決算内容を官報や新聞などの媒体で公表する手続きです。
株式会社では、会社法により決算公告が義務付けられており、公告の掲載には一定の費用がかかります。また、公告情報は一般に閲覧可能です。
一方、合同会社には決算公告の義務がありません。そのため、公告にかかるコストを抑えることができ、経営状況の情報公開に関して柔軟性が高いといえます。
この点は、情報公開の範囲やコストを抑えたい事業者にとって検討の一つとなる特徴です。
参考:法務省|電子公告制度について
役員の任期に制限がない
合同会社には、株式会社のような役員任期に関する法律上の制限が設けられていません。そのため、同じ人物が長期間にわたり役職を務めることが可能です。役職名や氏名に変更が生じない限り、登記の変更手続きは必要ありません。
一方、株式会社では会社法第332条により、役員の任期は原則2年と定められており、非公開会社でも最長10年までとなっています。
このため、合同会社では役員任期の制限がないことにより、登記手続きにかかる手間を一定程度軽減できる特徴があります。
参考:e-Gov 法令検索|会社法
合同会社を設立する際の注意点
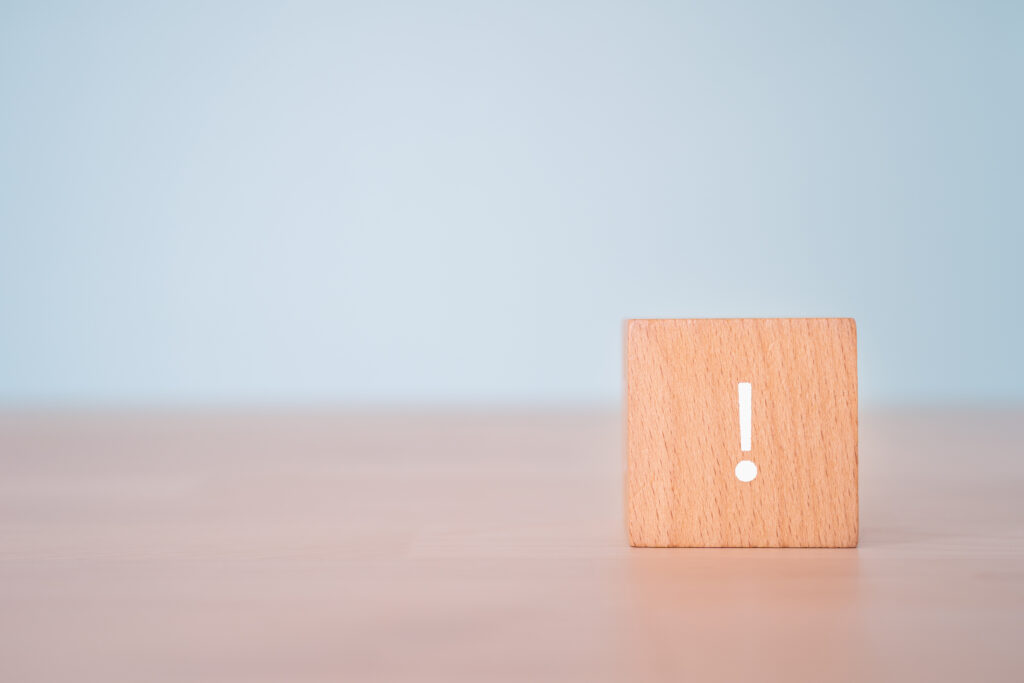
合同会社を設立する際に注意すべきポイントとしては、以下のような点があります。
- 取引先による認知度や信用度の違い
- 従業員同士のトラブル
- 設立手続きや費用の理解
- 法人としての事務負担
それぞれの注意点について解説していきます。
取引先による認知度や信用度の違い
合同会社は、株式会社と比べると知名度や一般的な認知度や信用度の面で差がある場合があります。
そのため、金融機関からの融資や大手企業との取引ができなかったり、追加の説明や資料の提出を求められたりすることも考えられます。
特に、将来的に大規模な資金調達や上場を視野に入れている場合には、制限が大きな障壁となる場合があるため、設立時に自社の事業計画や経営方針を踏まえて最適な形態を検討することが重要です。
従業員同士のトラブル
合同会社を設立する際には、社内の意思決定の方法についてあらかじめ整理しておくことが重要です。
合同会社は社員全員が出資者であるため、意思決定の権限が平等に与えられる仕組みになっています。このため、意見の対立が生じた場合には話し合いに時間がかかることもあります。自由度の高い経営が可能である一方で、社内の意思統一を図るためのルールづくりが経営上の安定に寄与します。
具体的には、定款に「社員の過半数による決議」などの意思決定方法を定めておくことで、運営をスムーズに行いやすくなるでしょう。
設立手続きや費用の理解
合同会社を設立する場合、定款の作成や法務局での登記申請など、一定の手続きが必要です。登記には登録免許税が発生し、最低でも6万円程度かかります。
本業と並行してこれらの作業を行う場合、手間がかかることもあります。そのため、設立手続きをスムーズに進めるために、税理士や司法書士などの専門家に相談することも一つの方法です。
参考:国税庁|No.7191 登録免許税の税額表
法人としての事務負担
合同会社を設立すると、個人事業主としての申告に比べ、法人としての税務・決算業務が増えるため、手続きがやや複雑になります。
具体的には、法人税の申告に加え、役員報酬を受け取っている場合は所得税の申告も必要です。また、決算の際には損益計算書や貸借対照表といった財務諸表の作成が求められます。
これらの手続きを適切に行うことで、税務上のリスクを回避できるほか、取引先や金融機関からの信用維持にもつながります。初めての法人運営の場合は、税理士に相談することでスムーズに対応できるでしょう。
参考:国税庁|貸借対照表作成の手引き
合同会社で節税効果を高めよう!

今回は、合同会社の設立によって想定される節税の仕組みについて紹介しました。
合同会社は、法人税の仕組みや経費計上の柔軟性などから、場合によっては節税の効果が期待できるケースもあります。ただし、すべての事業主に当てはまるわけではなく、所得状況や支出内容によって結果は大きく異なります。
そのため、法人化を検討する際には、事前に具体的なシミュレーションを行い、個別の状況に応じた判断をすることが重要です。
また、合同会社としての節税効果を最大限に活かすには、役員報酬の設定などの方法について、税務の専門家に相談しながら検討することが推奨されます。
この記事を合同会社の設立を検討する際の参考にしてください。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。





