メニュー
法人化
法人の青色申告承認申請書の書き方とは?青色申告するメリットも解説

読了目安時間:約 7分
法人が青色申告を採用すると、欠損金の繰越控除や少額減価償却資産の特例など、税務上の優遇措置を受けられる場合があります。
ただし、これらの制度を適用するためには、あらかじめ「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を受けておく必要があります。提出期限を過ぎると、その年度は青色申告が認められないため注意が必要です。
本記事では、法人の青色申告承認申請書の書き方を中心に、提出期限や青色申告のメリット・デメリットについても解説します。
法人で青色申告を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
法人の青色申告承認申請書の書き方

法人の青色申告承認申請書には、主に以下の13項目を記入します。
それぞれの項目がどのような内容を示しているか、一般的なポイントを整理してみましょう。
- 項目①:日付
- 項目②:宛名欄
- 項目③:納税地
- 項目④:法人名・法人番号
- 項目⑤:代表者氏名・代表者住所
- 項目⑥:事業種目
- 項目⑦:資本金又は出資金額
- 項目⑧:自令和年月日〜至令和年月日
- 項目⑨:事業初年度から青色申告を開始するか否かのチェック欄
- 項目⑩:帳簿組織の状況
- 項目⑪:特別な記帳方法の採用の有無
- 項目⑫:税理士が関与している場合における関与度合
- 項目⑬:税理士署名
それぞれの項目別に解説していきます。
参考:国税庁|C1-19 青色申告書の承認の申請|国税庁
項目①:日付
青色申告承認申請書に記載する「日付」欄は、税務署へ提出する実際の提出日を記載する重要な項目です。
この日付は、申請の受理時期や承認の対象年度に関わるため、正確に記入する必要があります。
提出方法によっても記入日が異なります。
たとえば、郵送で提出する場合は「発送日」を、税務署の窓口に持参する場合は「持参日」を記入しましょう。
なお、提出期限を過ぎてしまうと、その年分では青色申告の承認を受けられないことがあります。
その場合は、翌年以降からの適用となるため、必ず期限内に提出できるよう日付を確認しておくことが大切です。
項目②:宛名欄
青色申告承認申請書の宛名欄には、法人の本店所在地を所管する税務署の正式名称を記入します。
税務署名を誤って記載しても、内容に誤りがなければ受理される場合もありますが、処理の確認や照会が必要になることがあり、手続きが遅れるおそれがあります。
そのため、申請前に国税庁の「税務署の所在地などを検索」ページなどで、正確な管轄税務署名を確認しておくと安心です。
税務署名は地域によって似た名称が多いため、記入時には正式名称を確認するようにしましょう。
参考:国税庁|税務署の所在地などを知りたい方
項目③:納税地
青色申告承認申請書の「納税地」欄には、法人が税金の申告や納付を行う際の基準となる所在地を記入します。
原則として、法人の本店所在地を登記簿の内容と同一に記載することが望ましいです。市区町村名から番地までを正確に記入し、建物名がある場合も、登記に記載されていれば同様に記載しましょう。
登記内容と住所の表記が異なる場合、税務署側で確認や修正対応が必要になることがあり、処理が遅れる可能性もあります。
また、電話番号欄には、税務署からの問い合わせに対応できるよう、日中に連絡が取れる番号を記載しておくと安心です。
項目④:法人名・法人番号
青色申告承認申請書の「法人名等」の欄には、設立した法人の正式名称を正確に記載してください。
法人番号については、申請書提出時点でまだ付与されていない場合は、記入せず空欄のままでも差し支えありません。
法人番号が付与された後は、国税庁が運営する「法人番号公表サイト」で簡単に検索・確認できますので、正確な情報を確認して記入するようにしましょう。
参考:国税庁法人番号公表サイト
項目⑤:代表者氏名・代表者住所
青色申告承認申請書の「代表者氏名・代表者住所」の欄には、法人の代表者の氏名を正確に記入し、フリガナも忘れずに記載しましょう。
印鑑欄には、法人の実印を押印する必要があります。株式会社の場合は「代表取締役印」、合同会社の場合は「代表社員印」など、法人形態に応じた印鑑を使用するのが一般的です。
代表者の住所は、基本的に代表者本人の居住地を記載します。自身の住居を事業所として使用している場合には、納税地と同じ住所を記載するケースもあります。
項目⑥:事業種目
青色申告承認申請書の「事業種目」の欄には、法人の定款に記載されている事業目的の中から、主な事業内容を抜粋して記載します。
複数の事業を展開している場合は、代表的な事業や申告の中心となる事業を記載するケースが多いですが、必要に応じて複数の事業を併記することも可能です。
項目⑦:資本金又は出資金額
青色申告承認申請書の「資本金又は出資金額」の欄には、法人が実際に用意した金額を正確に記載しましょう。
この情報は、法人の財務基盤や事業規模を示す基本的な情報として重要です。申請書を確認する税務署にとっても、法人の概要を把握する参考として活用されることがあります。
項目⑧:自令和年月日〜至令和年月日
青色申告承認申請書の「自令和〇年〇月〇日 ~ 至令和〇年〇月〇日」の欄には、青色申告を適用したい会計期間を正確に記載します。
この期間は法人の事業年度(会計年度)に基づき、どの年度から青色申告を希望しているかを税務署に明示するための重要な情報です。
初年度から青色申告の適用を希望する場合は、事業年度に合わせて誤りのない期間を記入することが大切です。
記載内容に不備があると、承認手続きが遅れる可能性がありますので、注意して記入しましょう。
項目⑨:事業初年度から青色申告を開始するか否かのチェック欄
「事業初年度から青色申告を開始するか否かのチェック欄」は、該当する法人が記入すべき重要な項目です。
特に、設立初年度から青色申告を適用したい場合は、この欄を正確に記入することが求められます。
設立日を誤って記載すると、申請手続きが遅れたり、税務署から確認を求められたりする可能性があるので注意が必要です。
設立日の確認には、「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」を利用し、手元で正確に転記することをおすすめします。
項目⑩:帳簿組織の状況
青色申告承認申請書の「帳簿組織の状況」欄には、法人が日常的に使用している帳簿の種類や管理方法を記載します。
これは、法人が財務をどのように記録・管理しているかを税務署に示すための情報です。
帳簿の名称には、通常「仕訳帳」「総勘定元帳」を中心に記載し、必要に応じて「現金出納帳」や「預金出納帳」なども併せて記載します。
保存形式は、クラウド会計ソフトや専用ソフトを利用している場合は「会計ソフト」、紙やExcelで管理している場合は「紙」「Excel」といったように、実際の運用に合わせて記入します。
記帳の頻度については、「毎月」「毎週」「随時」など、帳簿を記入・更新する予定のタイミングを示します。あくまで現時点での予定を記入する欄であり、実際の運用に応じて変更することも可能です。
項目⑪:特別な記帳方法の採用の有無
青色申告承認申請書の「特別な記帳方法の採用の有無」の欄は、法人が通常の記帳方法とは異なる帳簿記帳方法を採用しているかどうかを税務署に報告するための欄です。
特別な記帳方法を導入している場合には、重要な情報として正確に記載する必要があります。
近年、一部の企業では会計処理の効率化や正確性の向上を目的として、クラウド型会計システムや専用の会計ソフトを利用しています。これらのツールは、取引入力から集計、帳票作成までを支援し、場合によっては業務時間の削減や入力ミスの防止に役立つことがあります。
こうした電子的な方法で帳簿を作成している場合には、申請書の「電子計算機利用」にチェックを入れることが必要です。このチェックによって、税務署は法人が電子計算機による帳簿管理を行っていることを把握しやすくなります。
項目⑫:税理士が関与している場合における関与度合
青色申告承認申請書の「税理士が関与している場合における関与度合」の欄は、法人が税理士に税務関連の業務をどの程度委託しているかを記載する項目です。
税理士に関与してもらっている場合は、実際に委託している業務内容と範囲を簡潔に明示することが望ましいです。
例えば、経理の全般を任せている場合は「伝票整理から決算書作成まで委託」といった形で記載できます。また、一部業務のみ委託している場合は「年末調整のみ依頼」「決算書作成のみ委託」など、具体的な内容を示します。
記載内容は税理士と事前に確認し、正確かつ誤解のない形でまとめることが重要です。これにより、税務署は法人と税理士の役割分担を把握しやすくなります。
項目⑬:税理士署名
青色申告承認申請書を作成する際、法人が税理士に依頼している場合は、申請書に税理士の署名を記載してもらう必要があります。
税理士が関与している場合、署名や押印をもらうことで、法人側としても内容が専門家のチェックを経ていることを示す目安になります。
署名や確認を受けることで、法人として申請書の内容を慎重に整えて提出したことを示すことができ、税務署にとっても一定の安心材料となります。
法人の青色申告承認申請書の提出期限

法人が青色申告を行うには、所定の期限までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
特に、設立初年度の法人の場合は、原則として設立日から3か月以内に申請を行う必要があります。ただし、設立後3か月を待たずに最初の事業年度が終了する場合は、事業年度終了日の前日までに提出することが求められます。
すでに設立されている法人が青色申告への変更を希望する場合は、適用を希望する事業年度の開始日の前日までに申請書を提出する必要があります。
これらの期限は税法に基づいて定められており、延長は原則認められていません。そのため、事前にスケジュールを確認し、余裕をもって申請を行うことが重要です。
参考:国税庁|A1-8 所得税の青色申告承認申請手続
法人の青色申告承認申告書の提出先

法人が青色申告の承認を受けるには、申請書を所轄の税務署に提出する必要があります。提出先は、法人の登記上の本店所在地を管轄する税務署で決まるため、事前に確認しておくことが大切です。
申請書の提出方法には、税務署への直接持参と郵送の2通りがあります。郵送で提出する場合は、税務署に到着するまでの日数を考慮し、余裕をもって準備すると安心です。
提出先や手続きに不安がある場合は、税務署に事前に問い合わせることでスムーズに手続きを進めることができます。また、税理士に相談すれば、正確かつ効率的に申請を行うことが可能です。
参考:国税庁|税務署の所在地などを知りたい方
法人で青色申告するメリット
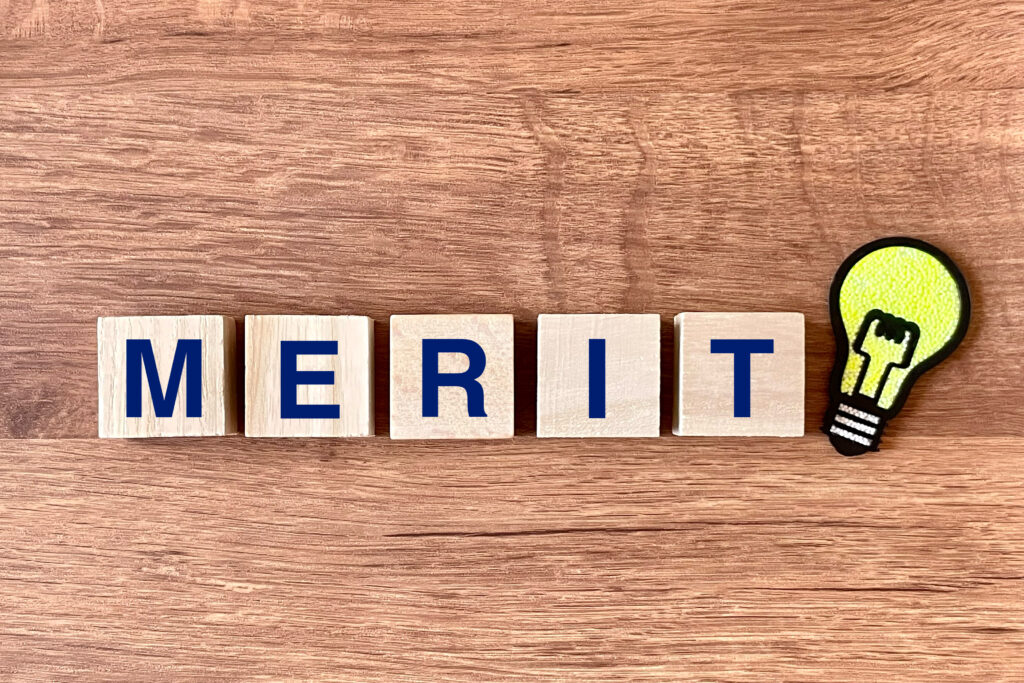
法人が青色申告を行うことによる代表的なメリットには、次のようなものがあります。
- 30万円未満の減価償却資産を一括で経費計上できる
- 支払い済みの税金の還付を受けられる
- 欠損金の繰越控除ができる
- 中小企業投資促進税制を利用できる
それぞれのメリットについて解説していきます。
30万円未満の減価償却資産を一括で経費計上できる
青色申告をおこなっている中小企業は、取得価格が30万円未満の設備や備品などを購入した場合に、その費用を一度に経費として計上できる「少額減価償却資産の特例」を利用できます。
この制度は、中小企業の定義(資本金や従業員数などの条件に該当する事業者)に限り適用されます。適用対象となる資産は、事業のために2026年3月31日までに取得されたもので、1年間に経費として計上できる合計額は最大300万円です。
この特例を活用すると、購入した年度に全額を経費計上できるため、会計処理が簡便になります。ただし、節税効果の大きさは事業の規模や所得状況によって異なりますので、具体的な適用方法については税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
参考:国税庁|No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
支払い済みの税金の還付を受けられる
青色申告の承認を受けている法人は、一定の条件を満たす場合に「欠損金の繰戻しによる還付制度」を利用できます。
この制度は、赤字が生じた年度の損失を前の年度にさかのぼって適用することで、過去に納めた法人税の一部を還付してもらえる仕組みです。実際の適用には、法人の申告状況や制度の要件を満たす必要があります。
例えば、前年度に法人税を支払った後、翌年度に赤字が出た場合、条件を満たせば前年度にさかのぼって損失を反映し、還付を受けられる可能性があります。具体的な計算方法や手続きについては、税理士に相談することをおすすめします。
参考:国税庁|No.5763 欠損金の繰戻しによる還付
欠損金の繰越控除ができる
青色申告を行う法人には、注目すべきメリットの一つとして「欠損金の繰越控除」があります。
事業年度に赤字が発生した場合、将来の黒字と相殺することが可能な制度です。法人の場合、原則として発生した欠損金を最長10年間にわたって繰り越し、翌年以降の利益と相殺することで税負担を軽減できます。
個人事業主でも繰越控除は利用可能ですが、適用期間は3年間と短めです。そのため、長期的な節税の可能性という観点では、法人での青色申告が有効な場合があります。
なお、この制度を活用するには、欠損金が発生した年度に青色申告による確定申告書を提出することに加え、その後も毎年欠かさず確定申告書を提出し続けることが必要です。
参考:国税庁|No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
中小企業投資促進税制を利用できる
法人が青色申告の承認を受けると、一定の条件を満たすことで「中小企業投資促進税制」と呼ばれる設備投資向けの優遇措置を活用できる場合があります。
この制度は、事業に必要な設備を導入した際に、通常の減価償却に加えて、取得価格の一部を特別償却として計上したり、税額控除を受けたりできる仕組みです。たとえば、青色申告を適正におこなっている法人が製造用機械を導入した場合、取得価格の一定割合を一括で償却できる「特別償却」や、一定の税額控除の適用を受けられるケースがあります。
青色申告とあわせてこれらの制度を活用することで、設備投資にかかるコストの軽減や資金繰りの改善につなげることが可能です。
参考:国税庁|No.5433 中小企業投資促進税制
法人の確定申告は青色申告をしよう!
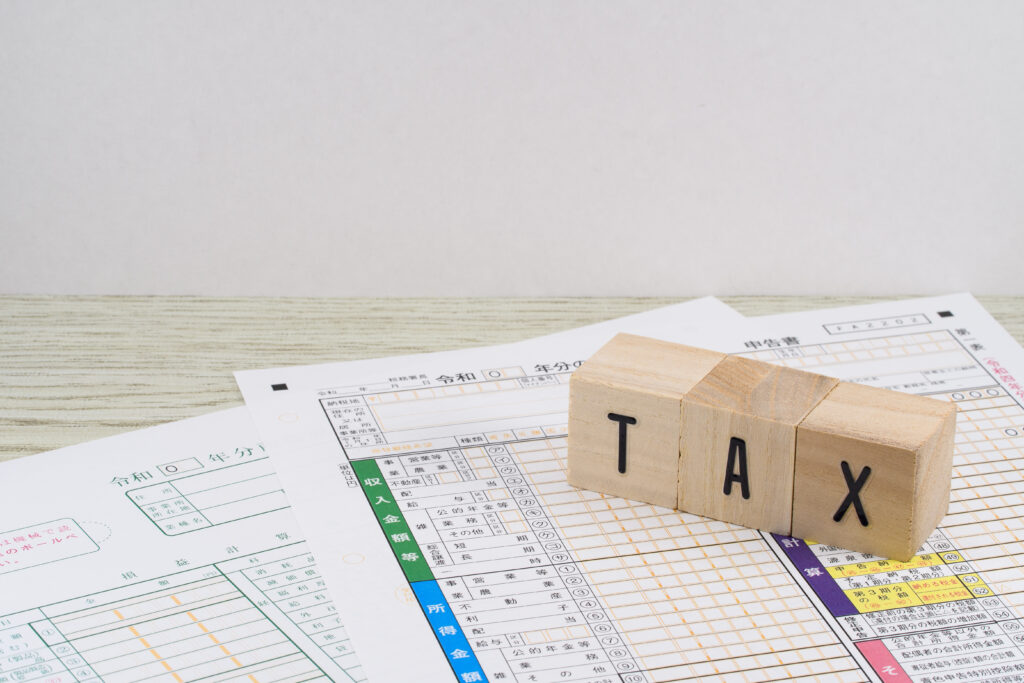
今回は、法人の青色申告承認申請書の書き方について解説しました。
法人が青色申告をおこなうと、赤字が出た年の損失を翌年以降に繰り越したり、前年度にさかのぼって還付を受けられたりと、税務上の優遇措置を活用できる場合があります。ただし、すべての法人で必ず節税になるわけではないため、自社の状況に応じた判断が必要です。
青色申告を希望する場合は、所定の期限内に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出し、承認を受ける必要があります。期限を過ぎると、その年度は青色申告の特典が適用されず、通常の申告方式となります。
会社を設立した際は、青色申告の承認申請を早めに行うことで、将来的に利用できる控除や繰越の制度をスムーズに活用しやすくなります。今回の記事を参考に、法人の申告方法を検討してみてください。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。





