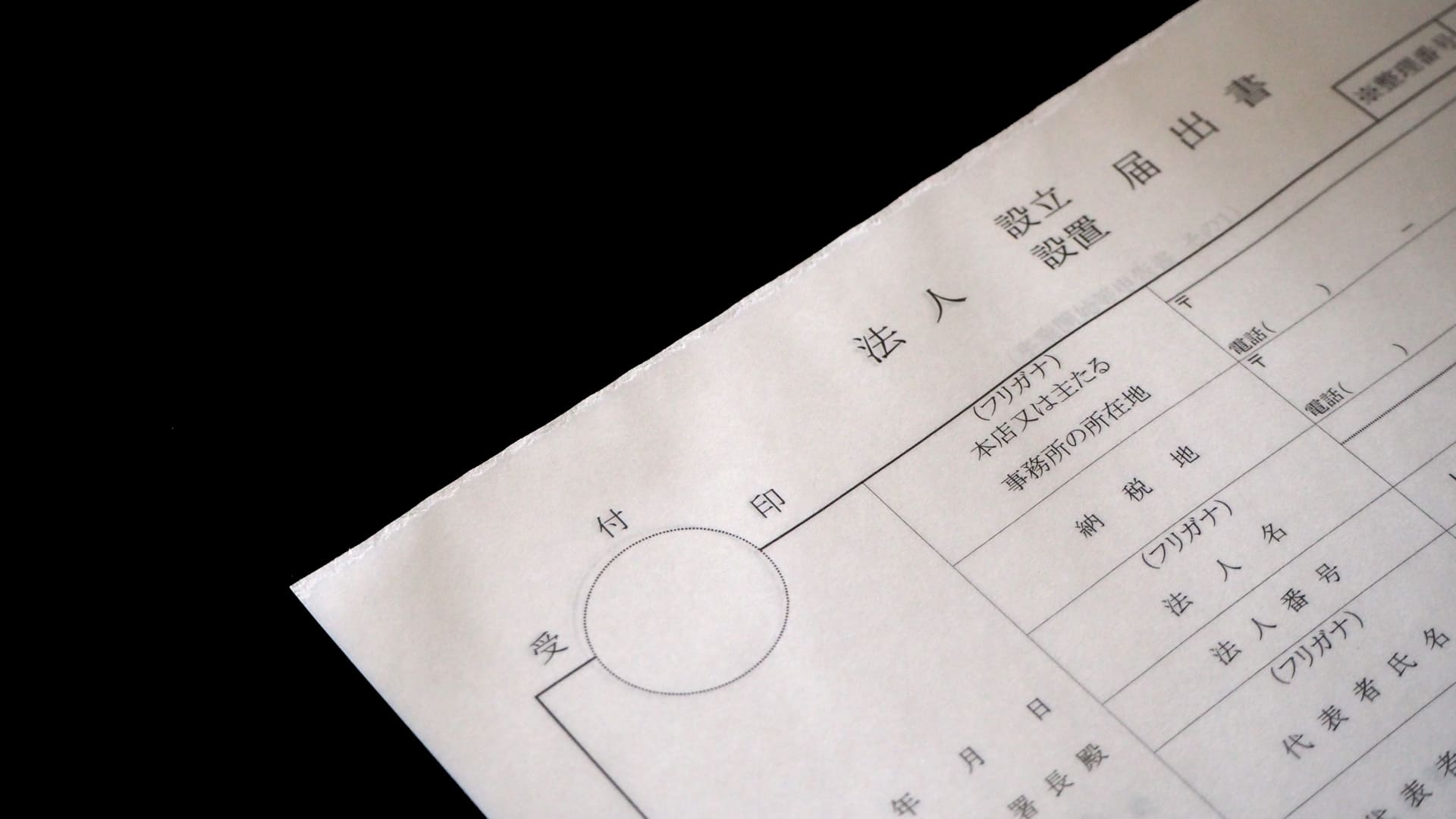メニュー
会社設立
定款の事業目的とは何か?設定する必須要件や記載するコツについても徹底解説
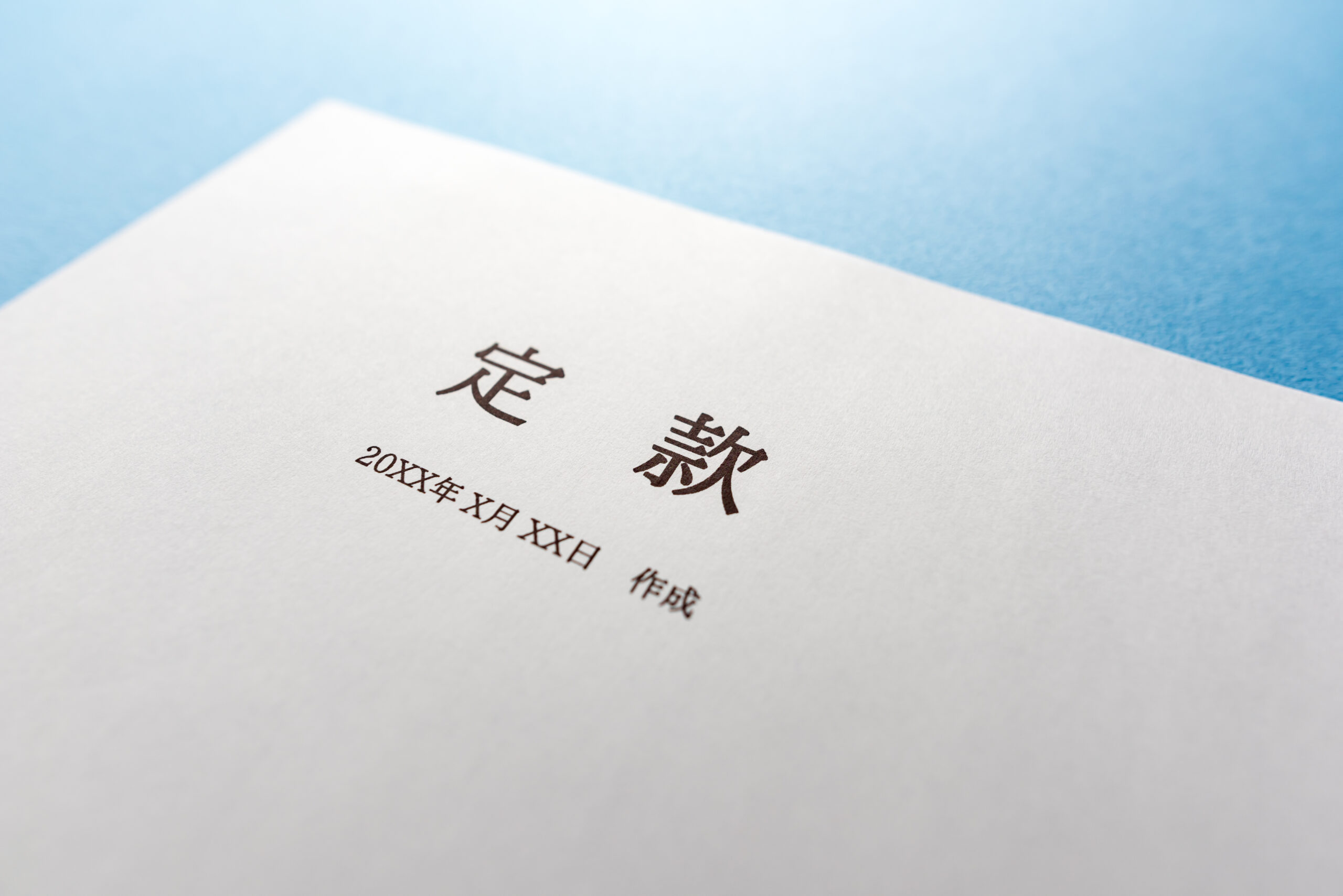
読了目安時間:約 6分
定款に記載する「事業目的」は、会社法第27条において定められている、必ず記載すべき基本事項の一つです。
この項目は、企業がどのような事業活動を行うのかを示すものであり、登記官や取引先など外部の関係者にも理解できるよう、具体的かつ明確に記載することが求められます。
本記事では、「定款の事業目的」とは何かをわかりやすく解説するとともに、設定時のポイントや記載の注意点についても紹介します。
定款の作成や見直しを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
定款の事業目的とは何か?

定款の事業目的とは、会社法で定められた「絶対的記載事項」のひとつであり、会社の基本的なルールの中でも重要な項目です。
会社を設立する際には、その企業がどのような事業を展開するのかを、定款に明確に記載する必要があります。
定款は会社設立における中心的な書類の一つであり、内容を適切に整えるためには一定の手間と慎重な確認が求められます。
また、定款に記載された事業目的は、取引先や金融機関などの外部機関が会社の信頼性を確認する際の参考資料のひとつとなる場合もあります。
そのため、事業内容を他者が容易に理解できるよう、明確で正確な表現を心がけることが大切です。
定款の事業目的を設定する必須要件

定款に記載する事業目的を定める際には、次の3つの点を満たしていることが望ましいとされています。
- 要件①:違法でないこと(適法性)
- 要件②:営利性(法人の性格に応じた目的であること)
- 要件③:明確性
それぞれの項目について解説していきます。
要件①:違法でないこと(適法性)
法的な観点から見て、違法行為を事業の目的とすることは認められていません。
例えば、法律に反する取引や詐欺行為など、社会的に不正とされる活動を定款に記載することはできません。
また、弁護士や司法書士など、特定の国家資格を有する者にのみ認められた業務については、資格を持たない者がその業務を事業目的に掲げることも許されません。
さらに、金融機関からの融資や新たな取引先との契約に際して、登記簿謄本の提示を求められることがあります。
このとき、実際の事業内容が定款に記載されていないと、信用評価に影響を与え、融資審査や取引交渉で不利に働く可能性があるため注意が必要です。
参考:法務局|登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です
要件②:営利性(法人の性格に応じた目的であること)
会社は、利益を生み出すことを目的とした法人組織であるため、定款に記載する事業目的も基本的には収益性を前提とした内容であることが求められます。
そのため、ボランティア活動や寄付など、営利を直接の目的としない活動だけを事業目的として記載することは一般的には適していません。
一方で、企業が社会的責任(CSR)の一環として行う公益的な取り組みについては、主な事業との関連を明示した上で、補足的に事業目的に記載することが可能です。
参考:厚生労働省|労働政策全般:CSR(企業の社会的責任)
要件③:明確性
事業目的を記載する際には、誰が読んでも内容を把握しやすいように、分かりやすく具体的な表現を用いることが大切です。
特に、一般の方にも事業内容がイメージしやすいよう、平易で明瞭な言葉を選びましょう。
なお、業界特有の専門用語やカタカナ語、新しいサービス名称などを使用する場合は、一般的な認知度を確認しておくことが望ましいです。
用語の意味が分かりにくい場合には、括弧書きで日本語の補足説明を添えるとより親切です。まだ広く認知されていない場合でも、説明を添えることで、登記上認められるケースがあります。
ただし、登記上の可否については、最終的に法務局の判断によります。
不安がある場合は、司法書士や専門家に確認してから記載内容を決定すると安心です。
定款の事業目的を適切に記載するコツ

定款の事業目的を適切に記載するポイントとして、以下の5点が挙げられます。
- 分かりやすく記載する
- 許認可の要件を確認する
- 同業他社の定款を参考にする
- 将来的な事業拡大も視野に入れる
- 「前各号に附帯関連する一切の事業」を入れる
それぞれについて詳しく解説していきます。
分かりやすく記載する
定款の事業目的を定める際は、会社が行う事業の内容を明確かつ具体的に記載することが基本です。
記載内容は定款に反映され、登記後は「登記事項証明書」に記載されるため、銀行口座の開設時や新規取引先による会社情報の確認などで活用されます。
事業内容が曖昧な場合、信用に影響することもあるため注意が必要です。
また、一般的には、定款の事業目的で最初に記載する項目は、会社の中心的な事業を示す内容にすることが望ましいとされています。
許認可の要件を確認する
ビジネスの分野によっては、開業前に行政機関から特別な「許認可」を取得する必要があります。
許認可の申請では、会社の定款に記載する「事業目的」が申請内容に沿っていることが重要です。
定款の記載内容が不十分である場合、許認可手続きに支障が出る可能性があるため、事業目的は慎重に検討し、正確かつ分かりやすい表現を用いましょう。
主な許認可が必要な業種と申請先の例は以下の通りです。
| 業種 | 必要な許認可 | 申請先機関 |
|---|---|---|
| 飲食業 | 食品営業許可 | 保健所 |
| 酒類販売業 | 酒類販売業免許 | 税務署 |
| 建設業 | 建設業許可 | 都道府県庁 |
| 不動産業 | 宅地建物取引業免許 | 都道府県庁 |
| 貸金業 | 貸金業登録 | 財務局または都道府県庁 |
| リサイクルショップ | 古物商許可 | 警察署 |
| スナック・キャバレー | 風俗営業許可 | 警察署 |
| 旅行業 | 旅行業登録 | 都道府県庁 |
| 運送業 | 一般貨物自動車運送事業許可(大型トラックなど) 貨物軽自動車運送事業届出(軽トラックなど) | 運輸支局 |
上記の業種で開業を検討する場合は、定款の事業目的や申請要件を事前に確認し、申請手続き全体の流れを把握しておくことが重要です。必要に応じて、専門家(税理士や行政書士など)に相談することもおすすめです。
参考:厚生労働省|健康・医療営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報
同業他社の定款を参考にする
定款を作成する際には、他社の定款の記載例を参考にすることも実務上有効です。ただし、内容をそのままコピーすることはできないため、自社の状況に合わせて参考にする点に注意が必要です。
なお、定款そのものは原則として株主や債権者など限られた人しか直接請求できません。しかし、定款に記載された「事業目的」は登記事項証明書に反映されます。この登記事項証明書は、所定の手数料を支払えば、法務局の窓口や郵送、オンラインサービスを通じて誰でも取得可能です。
また、上場企業の場合は、法令に基づき定款を自社ウェブサイトで公開していることがあります。たとえば、東京証券取引所に上場している企業の多くは、東証の公式サイトを通じて定款を閲覧できます。ただし、一般企業では公開されていないことがほとんどです。
参考:法務局|登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です
将来的な事業拡大も視野に入れる
定款に記載されていない事業を行うことは原則として認められていません。罰則が直接科されるわけではありませんが、登記事項と実態が異なる場合には、金融機関との取引や許認可手続きで支障が生じる可能性があります。
そのため、現時点で実施予定がなくても、将来的に取り組む可能性のある事業はあらかじめ定款に盛り込んでおくことが望ましいとされています。
定款に記載できる事業目的の数に法的な制限はありませんが、実態に即した適切な範囲での記載が推奨されます。大手企業では多くの事業目的を掲げる例もありますが、中小企業や新設法人の場合は、主力事業に加え関連業務を含め、合計で5件から10件程度を目安に定めるのが無理のない範囲とされています。
「前各号に附帯関連する一切の事業」を入れる
定款に記載されていない業務を開始する場合、後々トラブルになる可能性があります。そのため、多くの企業では事業目的の末尾に「前各号に附帯または関連する一切の業務」といった文言を加えることがあります。
この文言を加えることで、明確に列挙されていない事業であっても、既存の目的に関連性がある場合は、会社の事業範囲として扱われる場合があります。ただし、すべての事業が自動的に認められるわけではなく、主たる事業との関連性が前提です。
また、許可や認可が必要な業種については、包括的な文言だけでは足りず、定款に具体的な事業内容を明記する必要があります。定款の記載内容と実際の事業内容を適切に整合させることが重要です。
定款の事業目的を記載する際の注意点
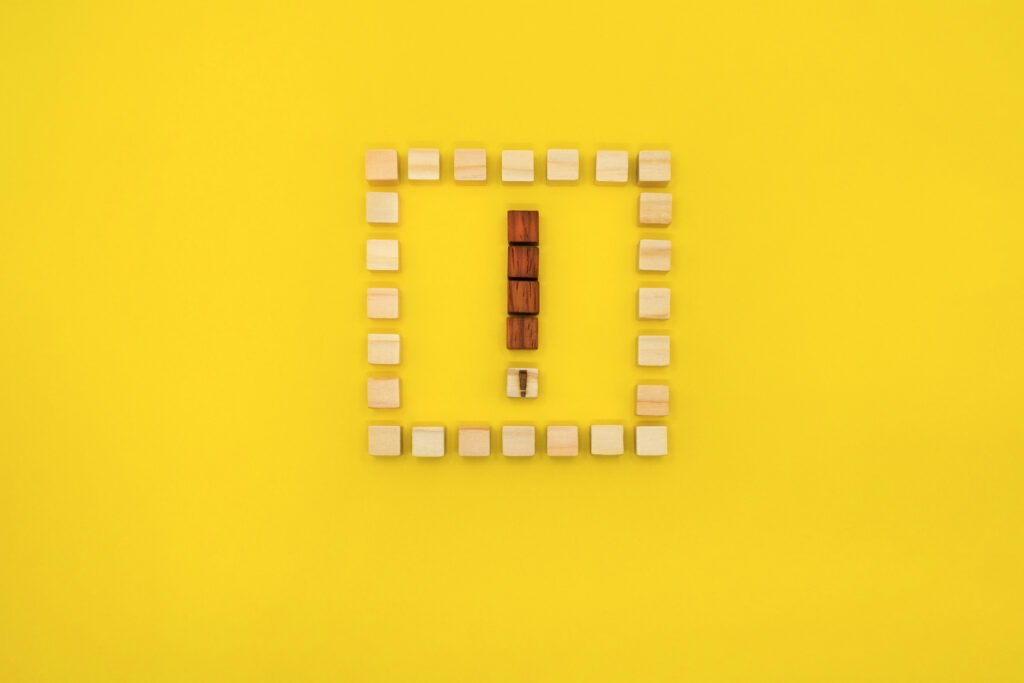
定款の事業目的を記載する際には、以下の3点に注意することが重要です。
- 記載数を適切にする
- 将来的にやりたい事業も記載する
- 不安がある場合は専門家に相談する
それぞれの注意点について解説していきます。
記載数を適切にする
事業目的の記載に法的な上限はありませんが、項目が多くなりすぎると、会社の主要な事業内容が分かりにくくなる場合があり、取引先や金融機関から確認される場合があります。
そのため、会社設立時には、まずは今後3〜5年以内に実際に着手する予定の事業に絞って記載することが実務上は一般的です。
将来的に取り組む可能性のある事業も含めることは可能ですが、あまりに多くの目的を列挙すると、登記簿を確認する第三者にとって事業の重点が把握しにくくなる点に留意しましょう。
将来的に行う可能性のある事業も視野に入れる
事業目的には、会社設立直後に行う予定の業務だけでなく、将来的に取り組む可能性のある事業を記載することも可能です。
あらかじめ将来の事業を見越して定款に盛り込むことで、事業目的を追加・変更する際に必要な「変更登記」の手続きや登録免許税(3万円)の負担を軽減できる場合があります。
ただし、あまりにも幅広く抽象的な内容を記載すると、取引先や金融機関から疑念を持たれる可能性がありますので、具体性と柔軟性のバランスを考慮して記載することが重要です。
参考:法務省|スマート変更登記のご利用方法
不安がある場合は専門家に相談する
定款の事業目的を記載する際に少しでも不安がある場合は、早めに専門家へ相談するのが望ましいです。
特に、許認可が必要な業種や高度な専門知識が求められる分野では、定款に記載する表現にも慎重な配慮が必要です。
相談先としては、会社設立や定款作成に詳しい行政書士・司法書士が一般的ですが、税務面の視点も含めて税理士に確認しておくと、将来の事業展開や会計上の影響も踏まえた適切なアドバイスを受けられます。
専門家の意見を取り入れることで、記載内容の正確性を高められるだけでなく、他社事例や将来的な事業拡大も見据えた判断が可能になります。
定款の事業目的を追加・変更する際の手続き

企業が事業拡大に伴い新しい分野へ進出したり、一部の事業を縮小・撤退したりする場合、定款に記載された事業目的の見直しが必要になるケースがあります。
定款の事業目的を追加・変更する際には、原則として以下の手続きが必要です。
- 株主総会での決議
- 法務局への定款変更登記申請
それぞれの項目について解説していきます。
株主総会での決議
事業目的を定款上で変更する場合には、株主総会での特別決議が必要です。
特別決議とは、議決権の過半数を有する株主の出席があり、かつ出席株主の3分の2以上の賛成によって成立する決議を指します(会社法第309条)。
このため、議案として「定款の一部変更(事業目的の追加・変更)」を明確に提示し、株主に内容を十分に説明することが求められます。
参考:e-Gov 法令検索|会社法
法務局への定款変更登記申請
株主総会で定款変更が承認された後は、原則としてその内容に基づき法務局への登記申請をおこないます。
登記申請の際に通常必要となる書類は、以下の通りです。
- 株主総会議事録(定款変更が決議されたことを証明するもの)
- 変更後の定款(またはその一部)
- 登記申請書
- 登録免許税の納付証明(株式会社の場合は原則として3万円)
提出方法は、法務局の窓口・郵送・オンライン申請のいずれにも対応可能です。
必要に応じて、税理士などの専門家に手続きを依頼することもできます。
事業に合った目的を設定しよう!

今回は、定款に記載する「事業目的」について解説しました。
定款の事業目的は、会社の取引や金融機関からの融資申込みなど、会社活動の基盤となる重要な情報です。そのため、事業目的を設定する際には、適法性・営利性・明確性の3点を意識することが必要です。
また、将来的な事業拡大や方向性の変更に対応できるよう、ある程度の幅を持たせた表現にしておくことも有効です。ただし、内容があまりに広範すぎたり不明瞭だと、金融機関や行政手続きでの確認に時間がかかる可能性があるため、適切な具体性を持たせることが望ましいです。
本記事を参考に、会社の事業内容や将来の展望に合った目的を定款に設定しましょう。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。