メニュー
起業・開業
起業・開業する際の資金調達方法とは?ポイントや注意点についても解説

読了目安時間:約 7分
起業や開業を検討する際には、設備投資や当面の運転資金など、一定の資金を確保する必要があります。
そのため、事前にどのような資金調達方法があるのかを理解しておくことが、事業を安定的にスタートさせるうえで重要です。
本記事では、起業・開業時に利用できる主な資金調達の手段をわかりやすく紹介します。
併せて、「資金調達を進める際のポイント」や「注意しておきたい点」についても解説します。
資金計画をしっかり立てることで、開業後の資金繰りを安定させることができます。ぜひ参考にしてみてください。
目次
起業・開業する際の資金調達方法

起業や開業の際に利用できる主な資金調達方法としては、次の6つが挙げられます。
- 日本政策金融公庫からの融資
- 自治体などが実施する制度融資
- 銀行によるプロパー融資
- 出資(個人投資家やベンチャーキャピタル等による)
- クラウドファンディング
- 補助金・助成金
それぞれの資金調達方法について解説していきます。
日本政策金融公庫からの融資
起業や開業を検討している方、または事業を開始してから7年以内の方は、日本政策金融公庫の「新規開業資金」を利用できる可能性があります。
日本政策金融公庫は、政府が全額出資する公的な金融機関であり、一般の金融機関からの融資が難しい中小企業や個人事業主、創業希望者を対象に、さまざまな融資制度を提供しています。
「新規開業資金」では、一定の条件を満たす場合、金利や返済期間について特例措置が設けられているケースもあります。
たとえば「再挑戦支援資金」では、過去に廃業経験がある方などが再度起業する際に、通常よりも長期の返済期間が設定できる場合があります。
詳細な条件や申込手続きについては、日本政策金融公庫の公式ウェブサイト内「新規開業資金」ページをご確認ください。
参考:日本政策金融公庫|新規開業・スタートアップ支援資金
自治体などが実施する制度融資
起業や開業を検討する際には、自治体・金融機関・信用保証協会が連携して実施する「制度融資」と呼ばれる資金支援制度を利用できる場合があります。
制度融資は、信用保証協会が新規開業者や中小企業などの借入に対して保証を行うことで、金融機関からの融資を受けやすくする仕組みです。
信用保証協会による保証が付くことで、金融機関が融資を検討しやすくなるとされており、状況によっては一般的な融資と併用して資金調達の幅を広げられる場合もあります。
また、信用保証協会では中小企業向けの経営相談を実施しているところもあり、融資と併せて経営面のアドバイスを受けられるケースもあります。
一方で、融資までに一定の期間を要したり、保証料の負担が発生したりする点には注意が必要です。
制度の内容や利用条件は自治体によって異なるため、開業予定地域の自治体窓口や信用保証協会に早めに確認しておくと安心です。
銀行によるプロパー融資
プロパー融資とは、信用保証協会などの保証を付けずに、銀行や信用金庫などの金融機関が独自の判断で実行する融資を指します。
創業や開業直後の事業者の場合、まだ実績や財務データが十分でないことが多く、金融機関が単独でリスクを負うプロパー融資の審査は、ややハードルが高い傾向にあります。
金利水準については、保証料が不要な分、条件次第では有利になる場合もありますが、事業の信用度や返済能力によって大きく変動します。
このように、プロパー融資は事業の成長段階に応じて慎重に検討すべき選択肢の一つといえるでしょう。
参考:J-Net21中小企業ビジネス支援サイト|プロパー融資と保証協会付き融資の違いについて教えてください。
出資(個人投資家やベンチャーキャピタル等による)
出資による資金調達とは、ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家などから資金提供を受ける代わりに、自社の株式や持分の一部を引き渡す形でおこなわれる資金調達方法です。
この方法では、出資契約に基づき出資者が経営に関与する権利を持つ場合があり、利益配分に関する権利が生じることもあります。そのため、出資契約の条件や株式・持分の評価、投資家との協業関係、自社の成長戦略との整合性を慎重に確認することが重要です。
また、ベンチャーキャピタルは出資先企業の新規株式公開(IPO)やM&Aの実現による株式価値の上昇を通じて利益を得ることを目的としています。初期段階の企業は金融機関からの融資が難しい場合でも、出資を通じて必要な資金を確保できるケースがあります。
クラウドファンディング
クラウドファンディングは、個人や企業がアイデアや事業を実現するためにプロジェクトを立ち上げ、インターネットを通じて多数の人々から資金提供を募る仕組みです。
主な形態は以下の3つです。
| 形態 | 内容 |
|---|---|
| 購入型 | 支援者が資金を提供する代わりに、そのプロジェクトが生み出す商品やサービスを受け取る形態。 |
| 寄付型 | 支援者が応援の気持ちで資金を提供し、見返りを求めない形態。 |
| 金融型 | 出資や貸付などの形で資金提供を行い、将来的なリターンを見込む形態。 |
クラウドファンディングは、比較的小規模な資金を多数の人から集められる点が特徴で、銀行融資や投資による資金調達が難しいケースでも活用しやすいです。また、事業の実現性や市場の関心を把握する一つの指標としても活用できます。
ただし、すべてのプロジェクトが目標額に達するわけではなく、資金を受け取れない場合もあります。また、手数料や広報活動が必要な場合もあるため、慎重な計画と戦略が重要です。
補助金・助成金
地方自治体では、創業支援を目的とした補助金・助成金制度が整備されている場合が多く、国でも生産性向上や技術革新など特定のテーマに沿った事業を支援する制度があります。ただし、これらの支援金はそれぞれ明確な支給目的や要件が定められており、条件を満たさなければ申請は受け付けられません。
申請にあたっては、募集要項に基づく審査が行われ、事業計画書や各種書類の作成など一定の準備が必要です。また、補助金・助成金は原則として事業実施後に支給される「後払い」の仕組みであるため、申請の際には自己資金や融資などで資金を確保しておくことが重要です。
税理士は、補助金・助成金の申請書作成や資金計画の立案をサポートすることが可能です。制度の目的や条件を事前に確認したうえで、計画的に申請を進めることをおすすめします。
起業・開業する際に資金調達をおこなうポイント
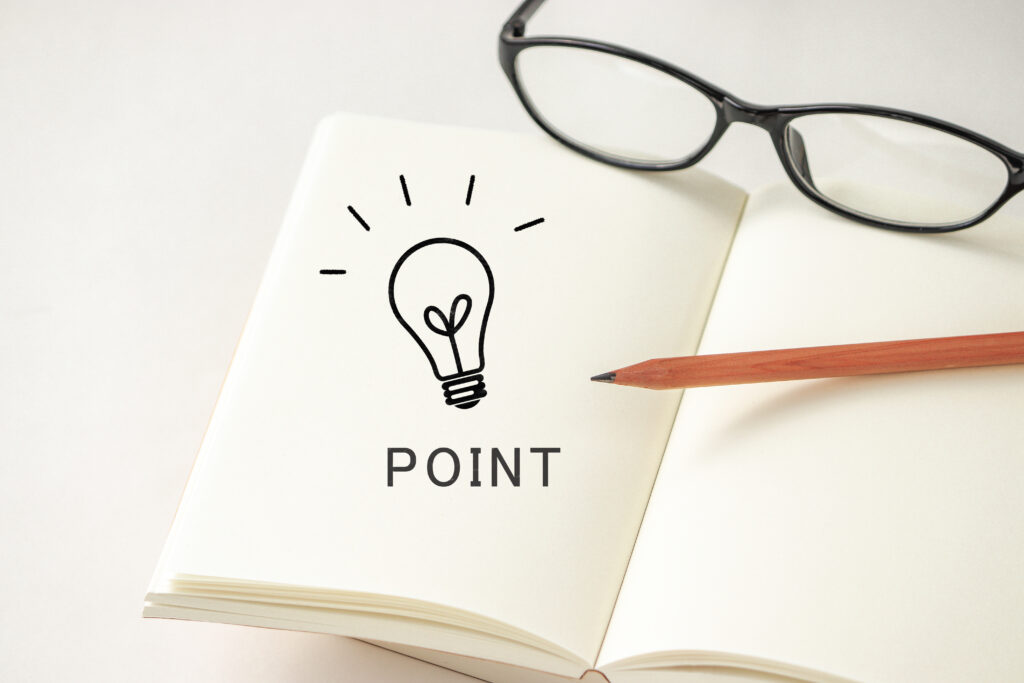
起業・開業時に資金調達を行う際には、次の3つのポイントを意識することが重要です。
- 自社の状況に適した資金調達方法を選ぶ
- 必要な資金額を明確にする
- 金融機関や投資家からの信頼を確保する
それぞれのポイントについて解説していきます。
自社の状況に適した資金調達方法を選ぶ
資金調達を行う際には、自社の状況に最も適した手段を選定することが重要です。
具体的には、必要な資金の額や時期、用途を明確にし、それに基づいて慎重に検討する必要があります。創業期と事業がある程度軌道に乗った段階では、適した資金調達方法が異なる場合があります。
また、法人・個人事業主の別、事業規模、資金を必要とするタイミングなど、さまざまな要素によって選択すべき手段は変わります。資金調達を検討する際には、必要な資金の目的や条件を整理し、計画的に検討することが望ましいでしょう。
また、法人・個人事業主の別、事業規模、資金を必要とするタイミングなど、さまざまな要素によって選択すべき手段は変わります。資金調達を検討する際には、必要な資金の目的や条件を整理し、計画的に検討することが望ましいでしょう。
参考:日本政策金融公庫|融資制度を探す
必要な資金額を明確にする
スムーズな資金調達には、必要な資金の額をできるだけ正確に見積もることが重要です。
借入額は、審査のハードルや金利、返済計画に影響するため、計画的に設定することが望まれます。
特に創業初期の段階では、金融機関からの評価がまだ十分でない場合もあるため、希望額通りの調達が難しいケースもあります。
そのため、まずは必要最低限の資金を確保することを念頭に置きつつ、事業の将来性や成長計画に応じて、設備投資など追加の資金調達を検討するのが良いでしょう。
金融機関や投資家からの信頼を確保する
融資や補助金・助成金といった外部資金を活用する際には、事業の信頼性が審査の重要な要素となります。
他社との差別化や自社の強みを整理し、具体的に説明できる資料を用意しておくことが、審査の理解を得やすくするポイントのひとつです。
信頼性を高める方法としては、事前に市場環境や競合の動向を調査し、自社のビジネスモデルや戦略の根拠を客観的に整理しておくことが有効です。
これらの情報を整理した上で、申請書類を丁寧に準備することで、審査の過程をスムーズに進める手助けとなります。
起業・開業に必要な資金調達の相談先

起業・開業にあたって資金調達の相談を行う際には、以下の窓口や専門家が参考になります。
- 日本政策金融公庫
- 商工会
- 商工会議所
- よろず支援拠点
- 税理士
それぞれの相談先について解説していきます。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は、政府が設立した公的な金融機関で、中小企業や個人事業主をはじめ幅広い事業者に対して、融資を中心とした支援を行っています。
資金面のサポートに加え、経営に関するアドバイスや情報提供も積極的におこなっており、電話相談のほか、東京・名古屋・大阪に設置された「ビジネスサポートプラザ」や「創業サポートデスク」などの対面窓口でも相談が可能です。
起業や開業準備中の方、経営に関して情報収集を行いたい事業者にとって、活用できる公的な支援機関の一つです。
参考:日本政策金融公庫
商工会
商工会は、町村部を中心に設置されている、地域商工業の振興を目的とした公的団体です。
地域の企業や商店などが会員として参加し、それぞれの事業の発展や地域経済の活性化を目指して、さまざまな活動を展開しています。
また、商工会は小規模事業者向けの国や都道府県の支援施策の一部を受託して実施しており、経営相談や実務上のアドバイスなど、幅広いサポートを提供しています。
全国には約1,700か所の商工会があり、経営や事業運営に関して悩みや相談がある場合は、最寄りの商工会に問い合わせることで、地域に密着した支援を受けることができます。
参考:全国商工会連合会
商工会議所
商工会議所は、主に市単位で設置される公的な団体で、「商工会議所法」に基づきさまざまな事業者支援を行っています。
中小企業や個人事業主を対象に、以下のような支援や相談が可能です。
- 創業支援
- 起業準備
- 事業拡大
- 事業承継
これらのサービスは多くの場合無料で提供されていますが、一部有料のセミナーや専門相談もあります。支援内容や相談の方法は各商工会議所ごとに異なるため、利用を検討する際は該当する商工会議所の公式サイトで最新情報を確認することをおすすめします。
参考:日本商工会議所
よろず支援拠点
よろず支援拠点は、全国に設置された国の公的な経営相談窓口で、中小企業や小規模事業者の経営支援を目的としています。
原則として、相談は無料で受けることができ、起業準備や資金繰り、経営課題の見直しなど、幅広いテーマに対応しています。
各課題に応じて専門家への連携も行う「ワンストップ型」の相談体制が整っており、経営に関するさまざまな悩みについて幅広くアドバイスを受けることが可能です。
相談を希望する場合は、最寄りのよろず支援拠点の公式サイトで掲載されている方法に従って予約してください。
参考:よろず支援拠点全国本部
税理士
税理士をはじめとする専門家に相談することで、独立・起業に向けた準備をより効率的に進めることが可能です。
特に融資を検討している場合には、金融機関の審査の流れや申請書類のポイントに詳しい専門家の支援を受けることで、準備の精度を高めることが期待できます。
また、会社設立に関する実務に詳しい専門家であれば、融資だけでなく、補助金・助成金の申請や出資など、事業の状況に応じた資金調達の方法についてアドバイスを受けることも可能です。
起業・開業する際に資金調達する際の注意点

起業や開業の際に資金調達を行う場合、事業の安定と税務上のリスク管理の観点から、以下の3点を押さえておくことが重要です。
- 資金調達の目的を明確にする
- キャッシュフローを正確に把握する
- 資金繰り計画を立てる
それぞれの注意点について解説していきます。
資金調達の目的を明確にする
資金調達を円滑に進めるためには、資金を「何のために、どのくらい必要か」を明確にしておくことが重要です。
具体的には、創業時の準備費用や新規事業への設備投資、日々の運転資金など、目的に応じた必要額をあらかじめ見積もっておくことが望まれます。
たとえば新店舗の立ち上げでは、物件取得費や設備導入費、内装・外装工事費など、具体的な支出項目を整理しておくと、金融機関や投資家への説明がスムーズになります。
資金の使途とその根拠を整理しておくことは、計画的な資金管理や資金調達の判断に役立ちます。税理士などの専門家に相談することで、より適切で現実的な資金計画を立てやすくなるでしょう。
キャッシュフローを正確に把握する
資金調達、特に借入を行う場合は、返済義務や利息負担が発生するため、手元資金の流れを適切に管理することが重要です。
そのため、現在のキャッシュ・フローの状況を正確に把握し、将来の資金の動きについても予測しておくことが望まれます。
例えば、「キャッシュ・フロー計算書」を活用することで、営業活動・投資活動・財務活動それぞれによる現金の出入りを明確に把握できます。損益計算書のように非現金項目を含む資料とは異なり、実際の現金の動きを確認できる点が特徴です。
あわせて、日々の入出金予定を整理した「資金繰り表」を作成し、支払いや入金のタイミングを定期的に確認する仕組みを整えることも、健全な資金管理には有効です。
参考:厚生労働省|キャッシュ・フロー計算書原則
資金繰り計画を立てる
起業・開業時には、資金繰り計画を作成して資金の流れを把握しておくことが望ましいとされています。
資金繰り計画とは、今後の入金や支出の予測に基づき、資金を管理するための計画書です。
銀行からの融資申請時には作成が求められることが多いですが、補助金や助成金の活用時でも、計画をもとに資金の動きを確認しておくことで経営の安定につながります。
また、返済不要の資金であっても、経営状況を定期的に確認し、将来的な課題や資金不足のリスクを把握するために、資金繰りの見通しを作成しておくことが有効です。
資金調達で起業・開業を成功させよう!

今回は、起業・開業する際の資金調達方法について解説しました。
創業時には、利用できる資金調達の手段がいくつかありますが、それぞれにメリット・注意点があり、融資を受けるために条件を満たす必要がある場合もあります。
まずは、資金の用途や必要額を明確に整理したうえで、自社の状況や目的に最も適した資金調達方法を検討することが大切です。
本記事を参考に、計画的な資金調達の一助として活用してください。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。





