メニュー
法人化
個人事業主とは?メリット・デメリットや開業の流れをわかりやすく解説
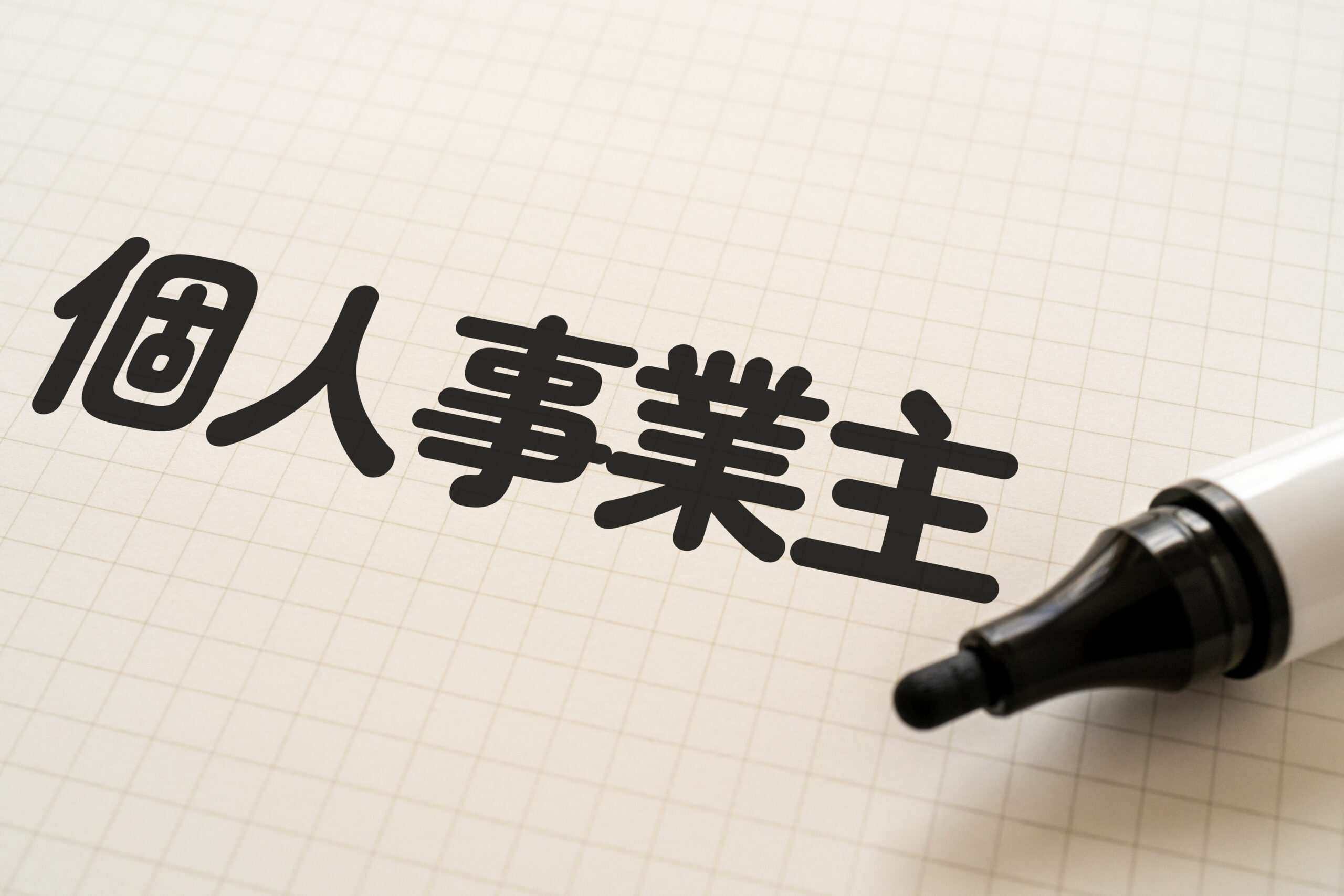
読了目安時間:約 8分
「自分の力で仕事をしたい」「副業からビジネスを広げたい」そのようなときに検討できるのは「個人事業主」という働き方です。
個人事業主は、法人(会社)を設立せずに、個人として事業を行う形態のことを指し、開業届を提出するだけで始められるため、費用や手続きのハードルが低いのが特徴です。
一方で、税金の仕組みや経費計上、確定申告など、事業主として知っておくべきポイントも多くあります。また、所得が増えてきた段階では、税負担や信用力の観点から「法人化」を検討すべき場合もあります。
本記事では、個人事業主とは何かという基本から、メリット・デメリット、開業の流れ、税金・申告方法、法人化を考えるタイミングまで、詳しく解説します。これから開業を考えている方はぜひ参考にしてください。
目次
個人事業主とは

個人事業主とは、法人を設立せずに個人の名前で事業を行う人のことを指します。
開業手続きが比較的簡単で、資本金なども必要ないため、スモールスタートに適した働き方です。近年は副業の広がりや働き方の多様化により、デザイナー・ライター・EC販売・サロン経営・飲食業など、幅広い業種で個人事業主として働くケースが増えています。
一方で、税金の計算方法や責任の範囲、信用力などは法人と異なるため、事業の規模や将来の展望に応じて適切な形態を選ぶことが重要です。ここでは、個人事業主の特徴と仕組みについて説明していきます。
参考:国税庁|個人事業
法人との違い
個人事業主と法人の大きな違いは、「事業の主体が誰になるか」という点です。
個人事業主は事業主本人が主体となり、事業の利益や債務はすべて個人に帰属します。一方、法人は法的に独立した「会社」という人格が主体となり、代表者個人とは分離して扱われます。
そのため、法人は有限責任であり、原則として会社の資産をもとに責任を負いますが、個人事業主は事業の損失や債務を個人資産でカバーする必要がある(無限責任)点が大きな違いです。
また、税金面では、個人事業主は所得に応じた累進課税、法人は法人税率が適用されます。事業の規模や利益状況に応じて、どちらが有利かは異なります。
フリーランスとの違い
「個人事業主」と「フリーランス」は混同されることが多い言葉ですが、意味は異なります。個人事業主は法的な区分であり、開業届を提出して税務署に事業者として登録されている人を指します。一方、フリーランスは働き方を示す言葉で、企業や組織に所属せず、案件ごとに仕事を受けるスタイルを表します。
つまり、「フリーランスとして働く個人事業主」もいれば、「自営業店舗を運営する個人事業主」も存在します。
税務や社会保険の扱いを明確にするためにも、フリーランスで仕事をしている人でも、必要に応じて開業届を提出し、青色申告を活用することで節税や経費処理の柔軟性が高まります。
開業届を提出するだけで始められる仕組み
個人事業を始める際には、「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を税務署に提出するだけで手続きが完了します。
資本金・設立登記・公証役場での定款認証などは必要なく、初期コストがほとんどかからないことが特徴です。
また、同時に「青色申告承認申請書」を提出することで、最大65万円の特別控除や赤字の繰越など、節税効果を得られるため、多くの個人事業主が青色申告を選択しています。
開業届を出さずに個人で収入を得ることも可能ですが、その場合は青色申告の特典が使えず、事業者としての信用性も弱くなるため、開業を明確にするメリットは大きいといえます。
参考:国税庁|A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
個人事業主になるメリット

個人事業主は、法人を設立するのに比べて手続きがシンプルで、事業をスモールスタートしやすい点が大きな特徴です。事業内容や働き方を柔軟に変えられるため、副業として始めたい場合や、初めは小規模に始めて徐々に事業を拡大したい場合などにも適しています。
ここでは、個人事業主として活動することで得られる具体的なメリットを解説します。
設立手続き・維持コストが少ない
個人事業主は基本的に、開業届を税務署に提出するだけで事業を始められます。会社設立のように定款認証や法務局での登記手続きは不要で、設立時の費用・時間・手間がかかりません。
また、法人の場合は毎年の決算公告や法人住民税などの維持コストが必要ですが、個人事業主にはこれらの負担がありません。
帳簿付けも比較的シンプルで、会計ソフトを活用すれば自分で管理することも可能です。事業を始める段階では、資金やリスクを抑えてスムーズにスタートしやすい点が大きな特徴です。
利益が少ないうちは税負担が抑えられる
個人事業主の所得税は、所得額に応じて税率が上がる「累進課税」が採用されています。
事業を始めたばかりで利益が少ない場合は、税率も低くなるため、税負担が比較的軽いことが特徴です。また、青色申告を選択することで、最大65万円の青色申告特別控除や、家族への給与を経費として認められる「青色事業専従者給与」、赤字の繰越控除など、節税につながる制度を活用することもできます。
そのため、利益が小さいうちは個人事業主として運営し、売上や利益の増加に合わせて法人化を検討することで、税負担をバランスよく調整することができます。
参考:国税庁|No.2260 所得税の税率
事業内容や働き方を柔軟に変えやすい
個人事業主は、事業内容、屋号、働き方、取引先などを自由に変更できる柔軟性が高い働き方です。
例えば、デザイナーとして事業を始めた後に、Web制作、コンサルティング、物販などに事業を広げることも可能です。また、働く場所や時間も自分で決められるため、育児・介護・副業などとの両立もしやすい点がメリットです。
一方、法人の場合は事業目的の追加や組織変更などに手続きが必要になることが多く、柔軟性は制限される場合があります。そのため、将来の方向性を模索しながら成長したい場合、個人事業主は相性の良い形態といえます。
個人事業主のデメリット・注意点

個人事業主は、始めやすく柔軟性の高い働き方ができる一方で、注意すべき点やデメリットも存在します。
メリットとデメリットの両面を理解し、状況に応じて法人化を含めた最適な選択を検討することが大切です。ここからは、個人事業主として働く場合のデメリットや注意点を説明します。
所得が増えると税率が高くなりやすい
個人事業主の所得税は「累進課税制度」が採用されており、所得が増えるほど税率も高くなる仕組みです。
具体的には、所得税率は5%〜45%まで段階的に上がり、住民税も合わさるため、利益が大きくなってくると税負担が急激に重くなりやすい点に注意が必要です。
特に、事業が軌道に乗り売上・利益が増えた場合には、個人事業主のままでは節税の選択肢に限りがあり、結果として手元に残るお金が減ることもあります。そのため、一定の利益水準(目安として年間所得500〜800万円以上)に達した段階で、法人化を検討することで節税と資金管理がしやすくなるとされています。
事業の責任を個人が負う必要がある
個人事業主は、事業に関する損失や負債をすべて個人が負う「無限責任」となります。つまり、事業で借入を行ったり、取引先とのトラブルが発生したりした場合、その責任は事業と個人の区別なく自身の資産で対応する必要があります。
一方、法人は「法人格」として独立しており、原則として会社の資産の範囲で責任を負う「有限責任」です。小規模事業のうちは大きな問題にならないことも多いですが、設備投資や取引額が増えるにつれ、リスク管理の観点から法人化の必要性が高まることがあります。
事業規模に応じて、適切な責任の持ち方を検討することが重要です。
参考:J-Net21中小企業ビジネス支援サイト|有限責任と無限責任について教えてください。
社会的信用度・資金調達力は法人より低い
一般的に、個人事業主より法人の方が社会的信用力は高く評価される傾向にあります。
例えば、取引先との契約、融資審査、補助金・助成金の申請などにおいて、法人であることが有利に働くケースが少なくありません。また、金融機関や投資家から見ると、法人は決算書や組織体制が整っているため、将来の事業継続性や返済能力を評価しやすいという背景があります。
個人事業主でも実績や帳簿管理の徹底により信用を築くことは可能ですが、事業拡大や資金調達を視野に入れる場合には、法人化が選択肢となることが多いです。
個人事業主になるための手続き

個人事業主として事業を始めるためには、基本的に税務署へ書類を提出するだけで手続きは完了します。
法人設立のような登記や資本金は必要なく、準備コストを抑えてスムーズにスタートしやすい点が大きな特徴です。
開業初期から青色申告のメリットを活用できるよう、開業届と併せて「青色申告承認申請書」も提出することがおすすめです。また、事業のブランド名となる「屋号」を決めることで、請求書や口座名義に統一感が生まれ、取引の信用性も高まります。
ここでは具体的な手続きの流れを解説します。
開業届の提出(提出先・必要書類・期限)
個人事業を始める際には、「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を所轄の税務署へ提出します。
必要書類は原則この1枚のみで、手数料もかかりません。提出期限は、事業を開始した日から1か月以内とされていますが、期限を過ぎても提出自体ができなくなるわけではありません。
ただし、開業届を提出しない場合、青色申告が利用できず、控除や節税のメリットを受けられない可能性があるため、事業開始と同時に提出するのが一般的です。
提出は窓口のほか、郵送やe-Taxを利用したオンライン提出にも対応しています。必要事項は比較的シンプルで、事業内容や事業開始日、屋号などを記載するだけで完了します。
参考:国税庁|A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
青色申告承認申請書の提出とそのメリット
開業届と同時に提出しておきたいのが「青色申告承認申請書」です。
青色申告を選択することで、帳簿を適切に作成していることを前提に、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。また、家族に支払う給与を経費にできる「青色事業専従者給与」や、赤字を翌年以降に繰り越せる「損失の繰越控除」など、事業運営に有利な制度が多数あります。
提出期限は原則として開業から2か月以内、またはその年の3月15日までです。特に節税効果が大きいため、多くの個人事業主が青色申告を選択しています。
青色申告と白色申告の違い
確定申告には「青色申告」と「白色申告」があります。青色申告は複雑な帳簿の作成が必要になりますが、節税メリットが大きいのが特徴です。一方、白色申告は帳簿の作成義務が緩やかで手続きが簡単ですが、青色申告に比べて控除がほとんどありません。
そのため、長く事業を継続し、利益を確保していくことを考えると、多くの個人事業主にとって青色申告がおすすめといえます。
参考:国税庁|No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度
屋号(ビジネス名)の決め方
屋号とは、事業で使用する「ビジネス上の名称」です。
必ず設定する必要はありませんが、請求書・名刺・銀行口座などで統一感が生まれ、取引先からの信用性が高まるため、設定する個人事業主も多いです。
屋号は自由に決められますが、同業他社と著しく紛らわしい名称や、商標権を侵害する可能性のある名称は避けることが望ましいです。シンプルで覚えやすく、事業内容がイメージしやすい名称にするとブランディングに役立ちます。
また、屋号名義で銀行口座を開設できるため、事業用とプライベートの資金を分けやすくなり、帳簿管理もスムーズになります。
個人事業主の税金と確定申告

個人事業主は、事業で得た利益をもとに所得税や住民税、場合によっては消費税を納めます。
これらの税金を正しく計算するためには、日々の取引を帳簿に記録し、1年分の収支をまとめて確定申告を行う必要があります。
特に、青色申告を活用すれば控除や損失繰越などの節税メリットが期待できるため、早い段階で帳簿の付け方や申告方法を理解しておくことが重要です。
ここでは、個人事業主に必要な税金知識と確定申告の基本を整理します。
参考:国税庁|所得税の確定申告
所得税の計算方法と必要な帳簿
個人事業主の所得税は、「売上から必要経費を差し引いた利益」に対して課税されます。
具体的には、「所得 = 売上 − 経費」で求められ、その所得額に応じて累進課税により税率が決まります。この計算を正しく行うためには、日々の入出金や取引内容を帳簿に記録することが必要です。
帳簿付けは、会計ソフトを使うことで効率的に管理できます。また、青色申告を行う場合は複式簿記に対応した帳簿が必要ですが、帳簿を整えることで最大65万円控除が受けられるため、初期段階から整備しておくことが望ましいです。
経費にできるもの・できないもの
経費とは、事業のために必要な支出のことをいいます。
例えば、仕入れ費用、仕事用のパソコンや備品、事務所家賃、通信費、交通費、広告費、外注費などは経費として計上できます。
ただし、「事業に関連していること」が条件となるため、プライベートの支出や私的利用が明らかに高いものは経費にできません。自宅兼事務所の家賃や光熱費など、事業と私生活が混在する支出は、使用割合に応じて按分して計上します。
経費の判断は税務調査でも重要なポイントとなるため、領収書の保管や支出目的の明確化が大切です。
参考:国税庁|No.2210 必要経費の知識
個人事業主から法人化を検討すべきタイミング

個人事業主として事業を続けていく中で、売上が伸びたり、取引先が増えたりすると、法人化を検討するタイミングが訪れます。
法人化には手続きが必要となりますが、税率・信用力・事業の継続性といった面でメリットが大きく、一定の規模に達した事業にとっては有利に働く場面が多くあります。
「いつ法人化すべきか」は事業の状況により異なりますが、主に利益額、事業規模、取引状況が判断のポイントとなります。
ここでは、法人化を検討するべき代表的なタイミングと、そのメリットについて解説します。
売上・利益が増えてきたとき
個人事業主の所得税は累進課税のため、利益が増えるほど税率が上がりやすく、税負担が大きくなります。
所得税率は最大45%まで上昇し、住民税を含めると実効税率はさらに高くなる可能性があります。一方、法人税は利益額にかかわらず一定の税率が適用されるため、利益が大きくなるほど法人化の方が税負担が軽くなる場合が多いという特徴があります。
一般的な目安として、年間の課税所得が500〜800万円を超えるあたりで法人化を検討することで、手取りが増えやすくなります。また、法人化すると役員報酬の設定によって所得分散ができ、節税の幅が広がる点も大きな利点です。
参考:国税庁|No.5759 法人税の税率
事業拡大や信用力が必要になったとき
取引先が増えたり、大型案件や融資を利用した設備投資が必要になったりすると、法人であることが信用力の面で有利に働くことが増えてきます。
法人は決算書や組織形態が明確で、事業の継続性や経営体制が評価されやすいため、金融機関からの融資審査でもプラスに作用する場合があります。
また、取引先の中には「法人との取引を前提」としているケースもあり、法人化することで契約や営業活動の幅が広がることもあります。
そのため、事業規模が広がり始めたタイミングは、信用力強化のための法人化を考える良い時期といえます。
個人事業主は始めやすいが、成長段階で法人化も検討を

個人事業主は、開業届を提出するだけで気軽に事業をスタートでき、初期費用や維持コストが少ないのが大きな魅力です。
副業からの延長や、小さなビジネスをまず形にしたい場合にも向いています。一方で、所得が増えると税負担が重くなりやすい点や、取引先や金融機関からの信用は法人に比べて弱いといった側面もあります。
売上が伸びてきたり、事業の幅を広げたいと考える段階では、法人化によって節税や信用力向上の効果が期待できる場合があります。
そのため、「今の事業規模に合った形態は何か」を判断することが大切です。将来的な展望を踏まえながら、適切なタイミングで法人化を検討していきましょう。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。





