メニュー
創業融資
国民政策金融公庫とは?日本政策金融公庫の事業内容から注意点について紹介

読了目安時間:約 9分
国民政策金融公庫とは、国がつくった金融機関で、主に中小企業や個人事業主、これから会社を始めたい人に対して、必要な資金を公的に支援していた機関です。
民間の銀行とは違い、低い金利で借りられたり、担保や保証人がいらないことが特徴です。
本記事では、国民政策金融公庫について紹介します。
他にも「日本政策金融公庫の事業内容」や「日本政策金融公庫の注意点」についても解説していきます。
ぜひこの記事を参考にして、国民政策金融公庫について理解を深めてみてください。
目次
国民生活金融公庫とは?

「国金」の略称で親しまれていた国民生活金融公庫は、中小企業金融公庫とともに、政府が設立した公的金融機関の一つとして広く知られていました。現在では、こうした組織は再編され、「国民生活金融公庫」という名称の機関は存在していません。
その役割は現在、日本政策金融公庫が引き継いでおり、国の全額出資により運営される政策金融機関として、中小企業や起業家への融資支援を積極的におこなっています。
日本政策金融公庫は、2008年に国民生活金融公庫・農林漁業金融公庫・中小企業金融公庫および国際協力銀行(国際金融等業務)の4機関が統合されて発足しました。
目的は、一般の金融機関が行う金融を補完しつつ、産業の成長促進や国民生活の安定に寄与することです。特に、民間の金融機関では取り扱いが難しいとされる高リスク分野や、政策上重点が置かれる分野に対して柔軟な融資を提供し、公的な立場から金融支援をおこなっています。
参考:国民生活金融レポート
日本政策金融公庫の国民生活金融公庫以外の特殊法人

日本政策金融公庫の国民生活金融公庫以外の特殊法人は、農林漁業金融公庫と中小企業金融公庫が挙げられます。
これら二つの公庫は、国民生活金融公庫と同様に2008年に実施された政府系金融機関の統合により、それぞれの役割を日本政策金融公庫に引き継ぐ形で統合されました。
それぞれの特殊法人について解説します。
農林漁業金融公庫
農林漁業金融公庫は、農業・林業・漁業などの第一次産業および食品産業に関わる者を主な支援対象としていた政策金融機関です。
農林漁業経営体や食品関連事業者が、農業用ハウス・畜産施設・漁船・共同利用施設などの設備を導入したり、長期の事業資金を確保したりする際に、長期・低利・固定金利の融資を通じて支援していました。特に、投下資本の回収に長期間を要し、天候・自然条件に左右されやすい農林漁業分野において、民間金融機関では対応が難しい長期資金を供給することが主要な役割でした。
その目的は、農村・山村・漁村地域の生産基盤・生活基盤の整備を進めつつ、生産性の向上と経営の安定を図り、国内の食料供給体制の維持・強化に資することにありました。こうした公的な資金支援は、収入が不安定になりやすい第一次産業分野において、事業の安定と継続にとって重要な位置付けを有していたと言えます。
中小企業金融公庫
中小企業金融公庫は、製造業・卸売業・小売業・サービス業など、幅広い分野で事業をおこなう中小企業者を支援するために設立された政策金融機関です。
中小企業は日本経済の大部分を支える存在である一方、担保や企業規模の面で民間金融機関から十分な長期資金の供給を受けにくいという構造的な課題を抱えていました。中小企業金融公庫は、こうした中小企業者に対し、設備投資や事業再編、新分野進出等に必要となる長期・固定金利の事業資金を供給することで、成長や新規事業への挑戦、雇用の維持・創出を支える役割を果たしていました。
また、業績悪化時の資金繰りを支えるセーフティネット的な融資や、信用保証・信用保険制度との連携を通じて、民間金融機関からの融資を受けやすくする「信用補完」の機能も担っており、中小企業金融を補完する政策金融機関として位置付けられていました。
日本政策金融公庫の事業内容

日本政策金融公庫の事業内容については、以下の3つが挙げられます。
- 事業内容①:国民生活事業
- 事業内容②:農林水産事業
- 事業内容③:中小企業事業
それぞれの事業内容について解説していきます。
事業内容①:国民生活事業
国民生活事業では、小規模事業者向けに事業資金の貸付をおこなったり、子どもの進学に必要な教育資金(「国の教育ローン」)など暮らしに密着した融資を通じて、国民の生活基盤を支える役割を担っています。
創業を目指す方々に加え、海外市場への進出を考える企業や地域の課題解決に取り組むビジネス、事業の再構築や事業承継に取り組む事業者に対しても、それぞれの状況に応じた資金支援をおこない、幅広いニーズ対応しています。
また、自然災害や社会情勢の変化などにより経営資金の確保が難しくなった場合にも、セージてぃねっと貸付などを通じて資金調達の支援をおこない、緊急時の支えとなっています。地域密着型の支援体制も特徴で、地域金融機関や商工会議所、税理士などの専門家と連携しながら、地域経済を支える小規模事業者の経営支援に力を入れています。
事業内容②:農林水産事業
農林水産事業では、農業・林業・漁業および食品関連産業に従事する事業者に対して資金面の支援を実施しており、国内の食料供給体制の安定化や、品質の高い食料品の安定した生産・流通を後押ししています
この分野の特性として、天候や気象条件に左右されやすく収益が不安定になりやすいことや、初期投資に対して収益化までに時間を要するケースが多いことが挙げられます。こうしたリスク要因により、民間金融機関からの融資が難しい場合も少なくありません。
また、農地や山林、漁船といった資産は、担保としての評価が難しい場合もあります。
そうした背景を踏まえ、日本政策金融公庫は、民間では対応しきれないニーズに応え、農林漁業を営む人々が持続可能な経営を続けられるように、長期資金やセーフティネット資金など柔軟な融資体制を整えて支援をおこなっています。
事業内容③:中小企業事業
中小企業事業では、主に中小企業を対象とした長期的な事業資金の融資をおこなっています。具体的には、企業の事業拡大、新たなビジネスの創出、設備投資などを支援するための資金提供をしています。
中小企業事業は、一般の金融機関が供給することが難しい長期資金を中心に取り扱う一方で、短期の運転資金については、民間金融機関等による調達と組み合わせることが想定されています。いわゆる短期のつなぎ資金や日常的な運転資金のニーズについては、他の制度や融資手段も含めて検討する必要があります。
また、中小企業事業は「信用補完制度」にも関与しています。
信用補完制度は、中小企業者等・金融機関・信用保証協会から成る「信用保証制度」と、信用保証協会と日本政策金融公庫による「信用保険制度」の総称であり、信用保証協会が日本政策金融公庫に保険料を支払い、日本政策金融公庫が代位弁済額の一定割合を保険金として支払う仕組みによって、保証協会のリスクを軽減し、中小企業向け融資の円滑化を図る制度です。
この仕組みによって、信用保証協会および金融機関のリスク分散が可能となり、結果として中小企業者が金融機関から融資を受けやすくなる効果が期待されているのです。
日本政策金融公庫と銀行の違い

日本政策金融公庫と銀行の違いについては、以下の2つが挙げられます。
- 信用保証協会の保証の有無
- 預金業務の取り扱いの違い
それぞれの違いについて解説していきます。
信用保証協会の保証の有無
銀行から融資を受ける場合、多くは信用保証協会の保証を付けて資金を借りる形になります。
これは、銀行が融資を行う際に万一の返済不能リスクを軽減するために用いられる仕組みで、「信用保証付き融資」として広く浸透しています。
民間金融機関である銀行にとって、リスク管理の一環として欠かせない制度となっています(なお、銀行には保証を付けない「プロパー融資」も存在します)。
一方、日本政策金融公庫は、政府が政策目的のために設立した公的金融機関であり、民間銀行とは法的性質が異なります。公庫は信用保証協会の保証を利用せず、融資に伴う信用リスクは原則として公庫自身が負担します。
なお、公庫には銀行の信用保証とは異なる制度として、国(中小企業信用保険公庫を含む政府系機関)が信用保証協会を財政的に支える「信用補完制度」が存在しますが、これは保証を付与する仕組みではなく、保証協会の損失補填を行う国の制度であり、公庫独自の保証制度ではありません。
この点を混同しないよう注意が必要です。
預金業務
銀行は、営利を目的とした民間の金融機関であり、顧客から預金を受け入れ、その資金を元にして貸し付けをおこなう「預金と融資を両輪としたビジネスモデル」を採用しています。
顧客の資金を安全に管理しつつ、それを活用して利益を生み出す仕組みで運営されています。
一方、日本政策金融公庫は、国の政策に基づいて設立された非営利の公的機関であり、預金を取り扱う業務はおこなっていません。
営利追求ではなく、政策的な目標の実現を目的としているので、融資のための原資は預金ではなく、国からの出資や借入といった公的資金によってまかなわれています。
また、日本政策金融公庫を利用して資金を借り入れる際には、返済や振込などの手続きに必要となる民間金融機関の預金口座が別途必要になります。
日本政策金融公庫の貸付制度

日本政策金融公庫の貸付制度については、以下の5つが挙げられます。
- 一般貸付
- 特別貸付
- 新企業育成貸付
- 企業活力強化貸付
- 生活衛生貸付
それぞれの貸付制度について解説していきます。
一般貸付
一般貸付は、多くの業種で事業を営む方々が幅広く活用できる融資制度であり、大きく分けて「無担保型」と「担保付き」の2種類の融資形態があります。
無担保型の融資は、設備投資や事業運営に必要な資金として利用可能で、融資の限度額は最大4,800万円となっています。
返済期間については、設備資金であれば最長10年、運転資金の場合は最長7年以内と定められています。
また、経済環境の変化やその他の事情によって、事業内容の変更や新たな商品分野への対応を求められた事業者に対しては、通常の貸付よりも条件が優遇された「特定設備資金」が用意されています。
特定設備資金では、最大7,200万円までの資金調達が可能なので、事業転換を支援するための有力な手段となっています。
特別貸付
特別貸付には、利用者の状況や目的に応じて多様な融資制度が設けられており、事業の段階や取り組みに応じた支援が受けられるようになっています。
例えば、新企業育成貸付は、新規で事業を始める方や創業からおおよそ7年以内の事業者が対象となっており、スタートアップ期の支援に適しています。
「企業活力強化貸付」では、事業の成長や効率化を目指す事業者、事業承継やM&Aに挑む方、社会的な課題をビジネスで解決しようとする方、海外への展開を進める企業などが利用できます。
さらに、「資本性ローン(挑戦支援資本強化特別貸付)」は、財務基盤の強化を目的とする融資制度となっています。
このように、さまざまな支援をおこなっているので、自社に合った融資制度を利用してみることをおすすめします。
新企業育成貸付
新企業育成貸付は、日本経済の活力を高め、持続的な成長や新たな雇用の創出を後押しするために設けられた制度です。
この制度では、革新的な技術の活用や独自性のある商品・サービスを通じて、新しい市場の創造や開拓に取り組み、将来的に大きな成長が見込まれる中小企業を対象に支援を行います。
この融資を受けるには、「成長新事業育成審査会」において、事業の新しさや成長の可能性について一定の評価を得る必要があり、革新性と将来性の両方が認められることが条件となります。
また、2つの融資タイプがあり、ひとつは「新規開業資金」で、新たに起業する方や事業を始めてからおおむね7年以内の事業者が対象です。
もうひとつは「新事業活動促進資金」と呼ばれ、既存事業の枠を超えて新たな分野に進出したり、事業の転換を通じて第二創業を目指すような取り組みを支援しています。
企業活力強化貸付
企業活力強化貸付は、事業の合理化や生産体制の改善など将来的な成長に向けた設備投資を支援するための融資制度です。
他企業との連携を強化したい事業者や業務プロセスの見直しを進めたいと考えている事業者にとって、有効な資金調達手段と言えます。
この制度にはさまざまな資金が用意されており、対象となる業種や取り組み内容に応じて選択することができます。
例えば、卸売・小売業、食品関連の製造小売業、飲食業やサービス業、一定の条件を満たした不動産賃貸業を営む事業者が、店舗の新設や改装、設備導入などに取り組む場合には「企業活力強化資金」が活用できます。
また、事業承継や企業買収(M&A)を進めるにあたり、株式や事業用資産を取得する場合には「事業承継・集約・活性化支援資金」の利用が可能です。
さらに、社会的な課題に取り組む事業に対しても支援が行われており、NPO法人、保育・介護事業者、または地域や社会の問題解決を目的とした活動を行う事業者は「ソーシャルビジネス支援資金」を通じて融資を受けられます。
生活衛生貸付
生活衛生貸付は、生活衛生に関わる業種を営む方が、店舗の改装や設備導入などに必要な資金を調達するために設けられた公的な融資制度です。
この制度が対象としているのは、飲食業・理容・美容業・宿泊業・クリーニング業など日常に欠かせないサービスを提供する業種が該当します。
こうした業種で独立開業や事業の拡張を目指す際には、店舗の賃借費用や内装工事、機器の導入など多くの初期投資が求められます。
しかし、これらをすべて自己資金でまかなうのは現実的に難しく、多くの事業者にとって大きなハードルとなりがちなのも事実です。
そのため、生活衛生貸付はこのような資金面の課題を軽減し、スムーズな事業開始や規模拡大を可能にするための資金的な後押しをしています。
日本政策金融公庫のメリット
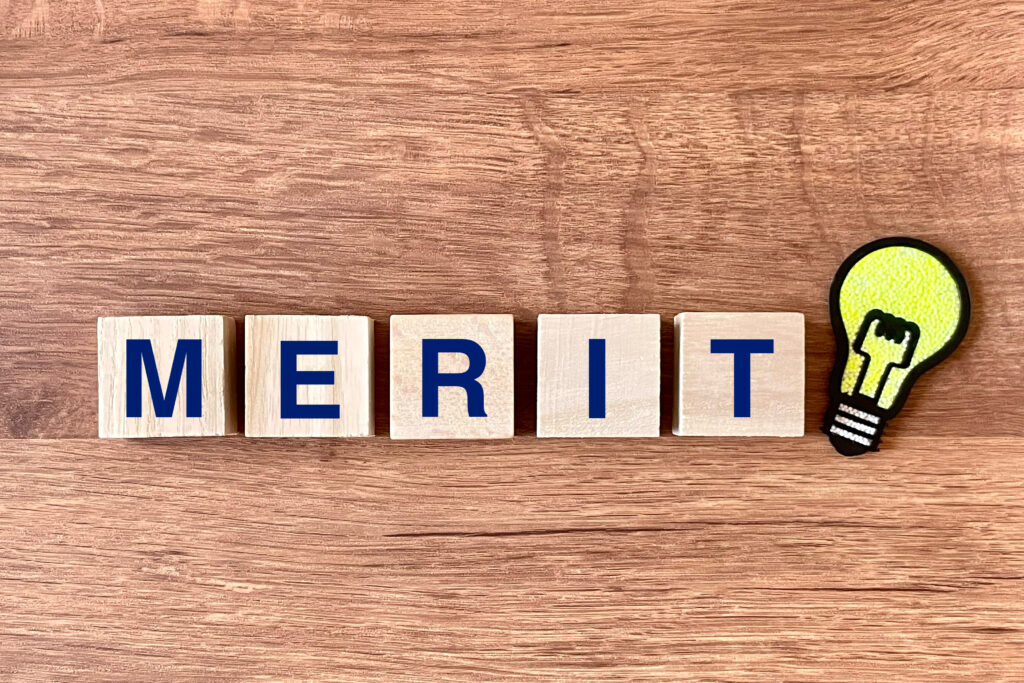
日本政策金融公庫のメリットについては、以下の3つが挙げられます。
- 審査が通りやすい
- 返済期間を長くできる
- 金利が低い
それぞれのメリットについて解説していきます。
審査が通りやすい
日本政策金融公庫は、中小企業やこれから事業を始める人々を支援する目的で設立された公的な金融機関であり、民間の銀行と比べて、比較的融資を受けやすいとされています。
特に、創業間もない企業や事業の規模が小さい個人事業主など一般の金融機関では融資の審査に通りにくい場合でも、公庫では支援の対象となるケースがあります。
さらに、日本政策金融公庫からの融資を受けた実績があることによって、他の金融機関からの信頼性が高まる傾向もあります。その結果として、将来的に民間の銀行や信用金庫などからの資金調達がスムーズになる可能性もあります。
もっとも、「審査が通りやすい」と一律に評価できるものではなく、事業計画や自己資金、返済能力等に基づき厳正な審査が行われます。会社設立後や個人事業から法人化したばかりのタイミングであっても、条件次第では融資の対象となり得るため、まずは具体的な計画を整理したうえで相談することが重要です。
返済期間を長くできる
日本政策金融公庫が提供する融資は、制度の内容によって返済期間が異なりますが、7年から20年程度と比較的長期にわたる設定がされています。
民間の金融機関では運転資金の返済期限が1年以内に定められている場合もあることを考えると、事業の収支が安定するまでに余裕をもって返済を進められる点で大きなメリットと言えます。
しかし、返済期間が延びることで、利息の支払額もその分増加してしまうので、結果として最終的な返済総額が多くなる可能性があるので注意が必要です。
そのため、返済期間をどう設定するかは、資金繰りの計画や将来的な事業展開を踏まえ、慎重に判断することが重要です。
金利が低い
日本政策金融公庫のメリットの一つとして、民間の金融機関からの事業性融資と比べて、比較的低い金利で資金を調達できる場合があることが挙げられます。
金利が高いと、返済時の負担が増え、総返済額も大きくなることから、不安を感じる方も少なくありません。
しかし、低金利であれば資金繰りの計画が立てやすく、前向きな気持ちで融資に踏み出せる可能性が高くなるメリットが挙げられます。
ただし、金利が低くても、返済期間が長くなるほど利息負担は累積するため、最終的な返済総額が増える可能性がある点には注意が必要です。事前に返済シミュレーションをおこない、現実的なプランを立てることが重要です。
日本政策金融公庫の注意点
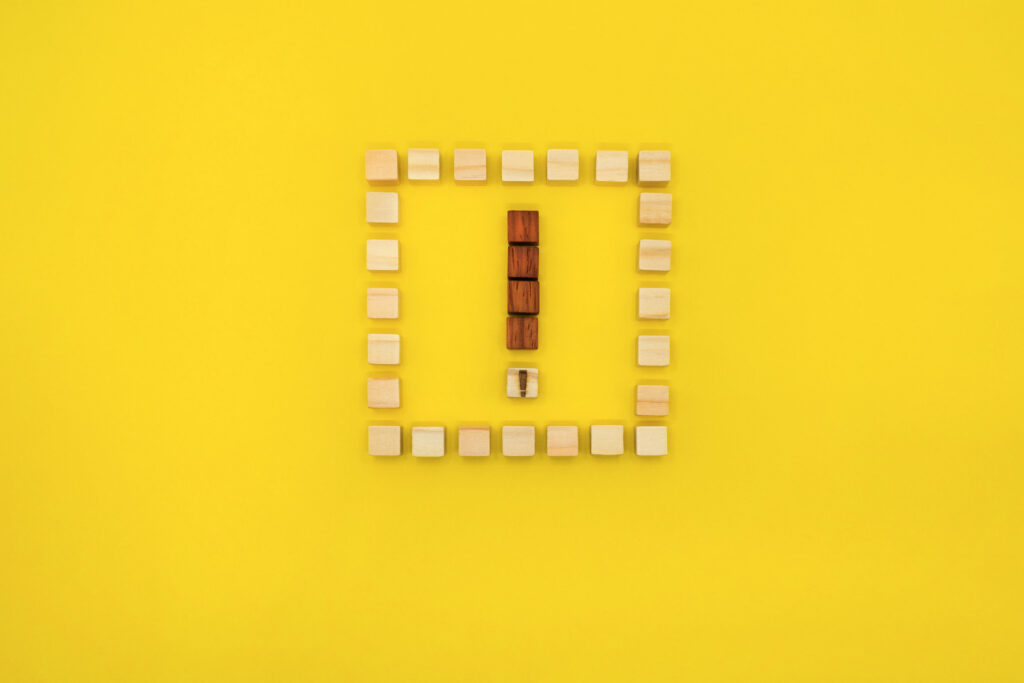
日本政策金融公庫の注意点については、以下の2つが挙げられます。
- 融資を受けるまでの期間が比較的長い
- 必要な書類が多い
それぞれの注意点について解説していきます。
融資を受けるまでの期間が比較的長い
日本政策金融公庫からの融資は、審査に一定の時間がかかる傾向があり、資金が実際に手元に届くまでにある程度の期間を要します。
通常、審査結果が出るまでには約2週間から1か月程度を要することもあるとされており、1週間前後で結論が出る民間金融機関の審査と比べて長めと言えます。
こうした審査期間の違いは、両者の審査の進め方に起因しています。
民間の金融機関は、顧客の取引口座の動きを日常的に把握しているので、企業の資金状況や信用度を迅速に判断できます。
一方、日本政策金融公庫には口座情報の閲覧権限がないので、申請者の提出書類に基づき、個別に口座の入出金履歴や資金の流れを丁寧に確認する必要があります。
そのため、日本政策金融公庫に融資を申し込む際には、審査結果が出るまでの時間を考慮し、余裕を持ったスケジュールで計画的に手続きを進めることが重要です。
参考:よくあるご質問 事業を営む方 個人・小規模企業の方|日本政策金融公庫
必要な書類が多い
日本政策金融公庫を利用する際のハードルの一つとして、提出が求められる書類の多さが挙げられます。具体的には、以下のような資料の提出が必要です。
- 事業計画書(創業計画書を含む)
- 資金繰りに関する資料
- 賃貸借契約書の写し(店舗・事務所を賃借する場合など)
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の原本(法人の場合)
- 自己資金の内容を証明する書類(預金通帳等)
- 借入申込書
- 本人確認書類
すでに事業を営んでいる場合は、確定申告書や決算書といった過去の収支が分かる書類の用意も求められます。
これらをすべて整えるには手間や時間的な負担がかかる一方で、これらの書類を通じて自社の実態や将来の見通しを整理することができるため、事業運営上のプラスにもなり得ます。これらの準備にかかる負担を軽減したいという方は、税理士などの相談することもおすすめです。
日本政策金融公庫の融資申し込みを検討してみよう!

今回は、国民政策金融公庫について紹介しました。
国民生活金融公庫は、個人事業主や中小企業の経営者、これから事業を始めようとする人々を対象に、資金提供をおこなっていた公的な融資機関です。
また、日本政策金融公庫が提供する融資制度は、起業や新たな事業を始める際の資金調達手段として広く活用されています。
特に、民間の金融機関では審査が厳しく融資が難しいとされるケースでも、日本政策金融公庫であれば資金を確保できる可能性があるので、起業を検討している方にとっては有力な選択肢の一つと言えます。
今回の記事を参考にして、日本政策金融公庫の融資申し込みを検討してみてください。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。





