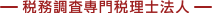BLOG
税務調査における質問検査権とは。拒否した場合は罰則が科せられる?
この記事の監修
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏
(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。
多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。


税務調査時には、調査官には質問検査権が与えられています。そのため、税務調査の際に「質問検査権に基づいて帳簿の提示を求めます」と調査官に資料の開示を求められるケースもあります。
質問検査権があるといわれれば、内容について詳しく知らない場合でもそのような権利があるのであれば、従わなければならないのかと思うことも多いでしょう。では、質問検査権とはどのような権利で、質問検査権には従わなければならないのでしょうか。
今回は、税務調査における質問検査権について詳しくご説明します。
目次
質問検査権とは
質問検査権とは、税務調査において納税義務者に対し、質問や帳簿書類などの検査、提示、提出などを求められる調査官の権利のことです。質問検査権は、国税通則法第74条の2~6において、調査官の権利として認められています。
国税通則法第74条の2に定められている質問検査権
国税通則法第74条の2の条文では、質問検査権について次のように示しています。
「国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときには、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他物件もしくは輸出物品又はこれらの帳簿書類を検査し、または当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。」
この条文から分かるように、税務調査時には調査官に対して次の行為を認めるとしています。
・質問
・帳簿等の検査
・帳簿等の提示
・帳簿等の提出
質問検査権が指す調査と調査対象者、調査対象書類
国税通則法第74条の2でいう「調査」とは、国税に関する法律の規定に基づき行われる調査で、税務調査のほか、再調査決定や申請等の審査のための行為も含まれています。
また、質問検査の対象となるのは、所得税や法人税などの納税義務者だけではありません。調査のために必要がある場合には代理人や使用人などにも及ぶとされています。
そのほか、帳簿書類その他物件には、記帳や保存をしなければならないとされている帳簿書類のほか、正しい税額を調査するために必要と認められる帳簿書類も含まれます。
質問検査権を拒否することはできる?
調査官には質問検査権があることが分かりましたが、税務調査時に調査官の質問や書類の検査などを拒否することはできるのでしょうか。
質問検査権を拒否すると罰則が科せられる
質問検査権は法的な権利であり、質問検査権を拒否した場合、納税者には罰則が科せられます。
国税通則法第128条では、正当な理由なく、調査官の質問検査権を示している第74条の2~6に違反した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されると示されています。
したがって、税務調査時に正当な理由なく、次のような行為をした場合は罰則の対象となるのです。
・調査官の質問に答弁しなかった
・調査官の質問に虚偽の回答をした
・調査官に帳簿の提出を求められたが応じなかった
・偽りの内容を記載した帳簿を提示した
質問検査権があるからこそ任意調査でも拒否はできない
税務調査には、任意調査と強制調査の2種類があり、一般的な税務調査は任意調査に該当します。任意調査というからには、任意で受ければよい調査なのではと考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、任意調査であっても納税者は税務調査を拒否することはできません。なぜなら、税務調査の調査官には、国税に関する質問や帳簿の提出、提示などを求める質問検査権が認められており、質問や調査を拒否した場合には罰則が科せられるからです。
税務調査には受忍義務があるとされている背景には、この質問検査権が関係しているのです。
質問検査権の質問・検査・提示・提出・留置きについて
税務調査における質問検査権とは、調査官が納税者に質問、検査、提示、提出を求める権利です。では、税務調査時には、具体的に質問検査権を行使し、どのようなことが行われるのでしょうか。質問検査権に含まれる質問や検査等の意味することを具体的にご説明します。
税務調査での質問とは
納税額についての調査を行うためには事業方針や事業の概要などについても理解しておく必要があり、質問内容は帳簿の記載内容だけにはとどまりません。税務調査の目的とは全く関係のない質問に対しては、質問検査権は認められてはいませんが、事業を深く理解するうえで必要だと考えられる質問については、納税者に回答する義務があります。
また、仕入や売上、帳簿などに関する質問のほか、従業員の状況についても質問が行われます。従業員の給与の支払い方や支払額、源泉徴収、扶養控除の状況なども、税額の計算に密接に関わってくるためです。
税務調査における検査とは
検査とは、帳簿や契約書、見積書、領収書、請求書などを調べることです。検査の対象となるのは、紙の書類だけではありません。データで管理しているものがあれば、パソコン内のデータや記録媒体も検査の対象となります。
ただし、検査の対象となるのは、税務調査に必要な書類やデータに限られます。万が一、税務調査とは関係のない書類やデータの閲覧を希望された場合には拒否することが可能です。
税務調査における提示
提示とは、調査官の求めに応じて帳簿や契約書、領収書などの書類、データを開示することです。調査官が確認できる状態にすることを提示といいます。紙ではなく、データで管理している場合にはパソコンのディスプレイ上に表示させることになります。
税務調査における提出
提出とは、調査官に求められた書類を提出し、調査官が手に取って確認できる状態にすることを指します。紙ではなく、データの場合には、プリントアウトして調査官に渡すことで対応します。
税務調査における留置き
税務調査では、留置きという言葉が用いられることがあります。留置きとは、帳簿等の書類を税務署に持ち帰ることを指す言葉です。提示・提出は、税務調査時に調査現場で書類を見せることを指すのに対し、留置きは書類の持ち帰りを意味します。
実地調査だけで十分に調査を終えられなかった場合や詳細に確認したい点がある場合などは、留置きの申し出があり、帳簿等の持ち帰りについての承諾を求められるケースがあります。ただし、帳簿のコピーなどを調査官に渡し、調査官がコピーを持ち帰る行為は留置きには当たらないため、該当箇所のコピーのみを調査官が税務署に持ち帰るケースも少なくありません。
留置く際には預かり証が交付され、留置く必要がなくなった時には遅滞なく返還されます。また、提出者から返還要請があった場合には特段の支障がない限り速やかに返還しなければならないとされています。
まとめ
税務調査の調査官は、納税者に対して税に関する質問や検査、帳簿等の提示、提出を求める権利を有しており、この権利を質問検査権といいます。質問検査権は国税通則法で定められている調査官の権利であり、質問検査権に基づいた質問に応じなかったり、帳簿の提示や提出などに応じなかったりした場合は、罰則が規定されています。
質問検査権は、任意調査であっても税務調査には応じなければならない受忍義務があることの法的根拠となるものでもあります。質問検査権の内容について事前にしっかりと把握しておけば、質問検査権に該当する行為や該当しない行為の判断も可能になり、安心して税務調査時に臨めるようになるでしょう。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税理士法人松本は
国税局査察部、税務署のOB税理士が
所属する税理士事務所です。
全国からの税務調査相談実績
1,000件以上
- 現在、税務調査が入っているので困っている
- 過去分からサポートしてくれる税理士に依頼したい
- 税務調査に強い税理士に変更したい
- 自分では対応できないので、税理士に依頼したい
といったお悩みを抱えている方は、
まずは初回電話無料相談をご利用ください。
税務調査の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 税務署目線、税理士目線、お客様目線の三方良しの考え方でアドバイス
- 過去の無申告分から現在まですべて対応可能
- 査察案件から税務署案件までの経験と実績が豊富にあります
- 顧問税理士がさじを投げた案件も途中から税理士変更対応できます
いますぐ電話で無料相談
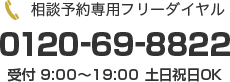
24時間いつでも受付
メールでご相談税務調査の専門家に初回電話相談無料
相談予約後、お近くの拠点より
折り返しご連絡します!
税務調査専門税理士法人松本
関連記事
相談実績1,000件以上
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属
税務調査に精通している
「税理士法人松本」が
税務調査の専門家として
あなたをサポートします!
- 現在、税務調査が入っているので
困っている - 過去分からサポートしてくれる
税理士に依頼したい - 税務調査に強い税理士に変更したい
- 自分では対応できないので、
税理士に依頼したい
税務調査専門税理士法人松本