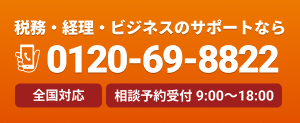メニュー
- 融資
運転資金の計算方法とは?何ヶ月必要かの目安や資金の考え方までわかりやすく解説

事業を営む中で「今月の資金が足りるだろうか」と不安になったことはありませんか?
経営者にとって、日々の事業運営に必要な「運転資金」の確保は常に頭を悩ませる問題です。特に創業間もない企業や事業拡大期には、売上の変動や予期せぬ出費によって資金繰りが逼迫することも少なくありません。
経営する中で、「必要な運転資金はどのくらいなのか」「どうやって計算すれば良いのか」という疑問を持つ経営者は多いでしょう。
そこで今回は「運転資金の計算方法」について解説します。「運転資金の基本的な考え方」や「運転資金の不足を防ぐための実践的な方法」まで紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
運転資金とは?何ヶ月分が目安になるのか解説

運転資金とは、企業が事業を継続させるために必要な資金のことです。具体的には仕入れ代金や人件費、家賃、光熱費などの経費を支払うために必要な資金を指します。
まずは運転資金とは何なのか、以下にわけて詳しく見ていきましょう。
- 運転資金の基本的な考え方
- 必要な運転資金の目安
- 設備資金との違い
- 運転資金が不足するとどうなる?
運転資金の基本的な考え方
運転資金を考える際に重要なのは「お金の入りと出のタイミングのズレ」です。例えば、商品を仕入れてから販売して代金を回収するまでには時間差があります。この期間、仕入れ代金や諸経費の支払いが発生するため、その分の資金を確保しておかなくてはいけません。運転資金は、その間を埋めるための資金です。
以上の点から業種によって必要な運転資金の額は異なります。小売業では商品の回転率が比較的早いため少ない運転資金で済むことがある一方、製造業では原材料の仕入れから製品の販売・入金までの期間が長いため、より多くの運転資金が必要になる場合が多くあります。
後払いの掛け取引が主流なのもあって、運転資金は重要な資金なのです。
必要な運転資金の目安
一般的に、必要な運転資金の目安は「月間の固定費 × 6ヶ月分」と言われています。日本政策金融公庫によると、事業が軌道に乗り、黒字化するまでには平均して半年以上かかるそうです。3ヶ月程度など甘い見積もりはしない方が良いでしょう。
ただし、この目安はあくまで一般論です。実際には業種や事業規模、取引条件などによって大きく異なるため、自社の状況に合わせた計算が必要になります。特に創業間もない企業や事業拡大期には、予測よりも多めの運転資金を確保しておくと安心です。
設備資金との違い

運転資金と混同されやすいのが「設備資金」です。設備資金は工場や機械設備、店舗内装など、長期的に使用する固定資産を購入するための資金を指します。一方、運転資金は日々の事業運営に必要な経常的な支出をカバーするための資金という違いがあります。
設備資金に該当する代表的なものを見てみましょう。
- 製造設備
- 工場機械
- 店舗内装
- 土地 / 建物
- 車両
- OA機器
- システム関連費用
- WebサイトやECサイトの構築費用
設備資金は1度に大きな支出が発生しますが、長期間にわたって効果を得られます。対して、運転資金は光熱費や人件費など継続的に必要となる資金で、毎月発生します。
融資を受ける際にも、両者は区別して考えられるため、明確にわけて管理するようにしましょう。
運転資金が不足するとどうなる?
運転資金が不足すると、様々な問題が発生します。最も深刻なのは、仕入れや給与の支払いができなくなることです。結果として取引先からの信用を失ったり、従業員のモチベーション低下を招いたりする可能性があります。
また、資金繰りが悪化すると、急な支払いに対応するために高金利の借入を行わざるを得なくなることも。積み重なると金利負担が増大し、さらに資金繰りを圧迫するという悪循環に陥ってしまいます。
最悪の場合、「黒字倒産」という事態に至る可能性もあります。利益を出していて、現金の流れがうまく回らず、支払いができなくなるのです。実際、中小企業の倒産の中には、決算書上は黒字であっても資金ショートによって事業継続が困難になるケースが見受けられます。
こうした点から見ても、運転資金は企業にとって重要な資金といえます。
初心者でもわかる運転資金の計算方法

運転資金の計算方法は、それほど難しくありません。以下の手順に沿って進めてみましょう。
- 売上債権・棚卸資産・仕入債務を洗い出す
- それぞれの金額を計算する
- 計算式に当てはめて運転資金を算出する
Step1.売上債権・棚卸資産・仕入債務を洗い出す
運転資金を計算する前に、まずは以下の3つの項目を洗い出しましょう。
- 売上債権:売掛金や受取手形など
- 棚卸資産:商品や原材料、仕掛品など、まだ販売していない在庫
- 仕入債務:買掛金や支払手形など
これらの項目を正確に把握しておくと、実際にどれくらいの資金が企業内でどのような形で動いているかが見えてきます。
運転資金の計算でも使う数値なので、必ず計測しておきましょう。
Step2.それぞれの金額を計算する
次に、それぞれの金額を具体的に計算します。Step1.で出した数値を、以下の式に当てはめてみましょう。
売上債権の計算:月間売上高 × 平均回収期間(月) = 売上債権
月間売上高が500万円で、平均して1.5ヶ月後に回収されるなら、 500万円 × 1.5 = 750万円が売上債権の金額となります。
棚卸資産の計算:月間売上原価 × 平均在庫期間(月) = 棚卸資産
月間売上原価が300万円で、平均して1ヶ月在庫を持つなら、 300万円 × 1 = 300万円が棚卸資産の金額となります。
仕入債務の計算:月間仕入高 × 平均支払期間(月) = 仕入債務
月間仕入高が250万円で、平均して0.5ヶ月後に支払うなら、 250万円 × 0.5 = 125万円が仕入債務の金額となります。
計算式は非常にシンプルなので、すぐに割り出せるでしょう。
Step3.計算式に当てはめて運転資金を算出する
最後に、Step2で割り出した数値を計算式に当てはめて運転資金を算出します。基本的な計算式は以下の通りです。
運転資金 = 売上債権 + 棚卸資産 – 仕入債務
先ほどの例を使うと、 運転資金 = 750万円 + 300万円 – 125万円 = 925万円となります。つまり、事業を円滑に運営するために必要な運転資金が約925万円であることがわかります。
ここまでがAです。実際にやってみましょう。
運転資金の目安となる金額を算出する4つの方法

運転資金の目安となる金額は、大きくわけて4種類あります。どのようなものか、それぞれ詳しく見ていきましょう。
- 経常運転資金
- 増加運転資金
- 減少運転資金
- 季節性運転資金
経常運転資金
経常運転資金とは、通常の事業活動を維持するために継続的に必要となる資金のことです。先ほど説明した「売上債権 + 棚卸資産 – 仕入債務」の計算式で求められる金額が該当します。
季節変動や特殊要因がない平常時の事業運営に必要な基本的な資金であり、長期的な視点で確保しておくべき金額です。企業経営において正確に把握しておきたい運転資金といえるでしょう。
経常運転資金を正確に把握できていれば、安定した資金計画の基礎を作れます。最低でも6ヶ月分の経常運転資金を目安にしておきましょう。
増加運転資金
増加運転資金とは、事業拡大や売上増加に伴って追加で必要となる運転資金を指します。例えば、新規取引先の獲得や新商品の発売によって売上が増加する場合、それに比例して運転資金も増加します。企業の成長において必ずかかる運転資金といえるでしょう。
そんな増加運転資金の計算式は以下の通りです。
増加運転資金 = 売上債権 + 棚卸資産 – 買入債務
例えば、売上債権が500万円、棚卸資産が300万円、買入債務が100万円だった場合、500万円 + 300万円 – 100万円で700万円となります。
これがもしそれぞれ倍になったとすると、1,000万円 + 600万円 – 200万円で1,400万円となり、700万円も運転資金が増加しています。
もし増加運転資金を用意できていないと、利益が出ているのにも関わらず黒字倒産してしまう可能性があるため、注意しましょう。
減少運転資金

減少運転資金とは、事業不振で売上が減少している際に必要になる運転資金です。売上が減っていたとしても、支払わなければいけない人件費や固定費に対して使います。そのため、経常運転資金をそのまま当てはめてください。
例えば業績が不振になった際は、減少運転資金をつなぎにしつつ、キャッシュフローを回して売上を増やし、人件費や固定費を削減していきます。経営を建て直すための基本的な方法です。
自転車操業が長く続くと、減少運転資金がショートして経営不振に陥る可能性があります。常に意識したい運転資金といえるでしょう。
季節性運転資金
季節性運転資金とは、毎年決まった季節に必要な運転資金です。以下のようなイベントが該当します。
- 賞与
- クリスマス
- バレンタイン
- 夏休み
賞与のように従業員へ支払うボーナスも季節運転資金に含まれます。その他、業種によってはクリスマスやバレンタイン商戦に参加したり、夏休みに旅行客を迎えたりといったケースもあるでしょう。
季節性運転資金は毎年続けていると、ある程度の金額が見えてくるので、それを目安にしてみてください。サービス業の場合、1年を通した商売サイクルを把握しているだけでも効果的です。
運転資金の不要な借入を減らす6つの方法

運転資金の不要な借入を減らすためには、以下の6つの方法が有効です。
- 資金繰り計画の精度を向上させる
- 売上債権を早期回収する
- 在庫管理を最適化する
- 仕入債務を見直す
- 経費を削減する
- 補助金や助成金を活用する
資金繰り計画の精度を向上させる
資金繰り計画の精度を高めて必要な運転資金を正確に把握し、過剰な借入を避ける方法があります。まずは数字を見える化し、現状を直視するところから始めます。何となくで資金繰りを計画していた場合、真っ先に着手した方が良いでしょう。その際は月次ではなく週次や日次での資金繰り表を作成し、より細かな資金の動きを把握すると効果的です。
また、過去の実績データを分析して季節変動や特殊要因を考慮した予測も立ててみてください。予測と実績の差異を定期的に検証し、計画の精度を高めていきましょう。
売上債権を早期回収する
売上債権の回収期間を短縮しても、運転資金の負担を減らせます。売上債権が多いと黒字倒産が発生する可能性が高くなるため、有効な方法です。以下のような方法を使って、対策をしていきましょう。
- 回収条件を見直す(現金取引への切り替えや手形期間の短縮など)
- 売上代金の回収を早める(締日と入金日の前倒し)
- 請求漏れのチェック
- 定期的な入金状況の確認と督促
大口取引先との交渉は難しい面もありますが、新規取引先との契約時には回収条件を慎重に検討しておくと効果的です。
在庫管理を最適化する

在庫管理を最適化する方法も効果があります。在庫は資金が形を変えた状態なので、過剰在庫は運転資金を圧迫します。在庫管理を最適化するためには、以下のような取り組みを実践してみましょう。
- 在庫の適正水準を設定し、定期的にチェックする
- 売れ筋商品と滞留商品を分析し、発注量を調整する
- 在庫回転率を高めるための販売促進策を実施する
- 発注ロットやタイミングの見直し
- 定期的に棚卸をする
- 余った在庫は廃棄
不要な在庫は早期に処分するなど、思い切った対策が必要な場合もあります。短期的には損失が発生しても、長期的には運転資金の効率化につながると意識しましょう。
仕入債務を見直す
仕入債務を見直すのも重要なポイントです。支払条件を見直すことで、運転資金の負担を軽減できる可能性があります。以下のような対策を取ってみましょう。
- 支払期日の延長交渉
- 仕入数を適正まで減らす
- 支払条件に応じた仕入先の選定
仕入れ数が増えると在庫を圧迫するので、適正な数を維持できるかが重要です。定期的に見直し、適正な数値を維持するようにしましょう。
ただし、支払条件の見直しは取引先との信頼関係に影響する可能性があります。双方にとってメリットのある提案を心がけてください。
経費を削減する
固定費や変動費を見直して削減する方法も、運転資金の負担軽減につながります。以下のような取り組みを実践してみましょう。
- 不要なサブスクやサービスの解約
- 電気・ガス・水道などの使用量の見直し
- 業務効率化による残業削減
- 外注業務の内製化
ただし、品質やサービスレベルの低下につながる過度な経費削減は避けてください。長期的な視点で、本当に必要な経費と削減可能な経費を見極めていきましょう。1度実験的に試し、難しそうなら元に戻すといった方法も有効です。
補助金や助成金を活用する
国や地方自治体、各種団体が提供する補助金や助成金を活用して運転資金の負担を軽減する方法もあります。以下の活用も検討しましょう。
- 新規開業資金
- 新事業活動促進資金
- 中小企業経営力強化資金
こうした補助金や助成金は制度は定期的に内容が変わるため、最新情報を常にチェックして、自社の事業内容や計画に合った制度を探すようにしましょう。
運転資金の計算方法を知って安定した経営を実現しよう

運転資金は事業継続の生命線とも言える重要な要素です。一般的には最低6ヶ月分は必要とされています。今回紹介した計算方法を活用して金額を確保し、資金ショートのリスクを回避するようにしましょう。
‐免責事項‐
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は 国税OB・元税務署長 が所属し、 確定申告・相続・会社設立・融資サポート・労務手続きなど 幅広いサービスを提供する税理士法人です。
全国からの 税務・労務相談実績 年間1,000件以上
税理士法人松本の強み
- 税務署目線、税理士目線、お客様目線の三方良しの考え方でアドバイス
- 過去の無申告分から税務調査、相続、会社設立まで幅広く対応可能
- 融資や助成金、補助金の申請など資金調達サポートにも豊富な実績
- 顧問税理士が対応に困った案件も途中からサポートできます
30秒で完了かんたん融資診断