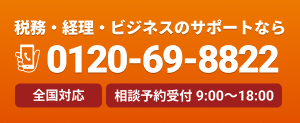メニュー
- 融資
事業を始める資金の調達方法は?開業時に使える融資や成功率を高めるポイントを解説

事業を始めるには、設備資金や諸費用などの開業資金が必要です。
特に設備資金など多くの投資が必要な事業者は自己資金が足りなかったり、足りたとしても、資金繰りが難しくなり経営がうまくいかなくなったりする可能性もあります。
開業を検討している人の中には、どのように資金調達をすれば良いか悩んでいる方もいるでしょう。
そこで本記事では、開業資金の融資を受ける方法やその他の資金調達方法を解説します。
また、資金調達の相談をする際に注意すべきポイントについても説明していきますので、ぜひこの記事を参考に資金調達の手段を知り、自社の状況に合った適切な方法を選択して対策をとりましょう。
目次
開業資金はいくら必要?

新しく事業をはじめる際には、開業費用が必要になるケースがほとんどです。
開業にかかる資金は、業種や会社形態、規模などによっても大きく異なりますが、目安としては以下の金額が必要になります。
- 士業・コンサルタントなど:30万円~1,000万円
- 飲食店:100万円~1,500万円
- カフェ・喫茶店:100万円~1,000万円
- 美容院:500万円~3,000万円
開業費用には、設備や仕入れにかかる費用のほか、開業後数ヶ月は利益が出ないことも多いため、当面の生活費や税金なども入れて考える必要があります。
自己資金なしでも起業できる?
自己資金がない場合でも起業自体は可能です。
しかし、一般的には開業するにあたってさまざまな費用がかかります。
また、起業したとしても、すぐに利益を上げられるとは限らず、その間も様々な費用がかかるため、これらの費用負担をどうするのか考える必要があるのです。
このように、自己資金だけでは足りない場合や開業後に資金繰りが苦しくなる恐れがある場合には、融資などの資金調達が必要となります。
開業資金の融資を受ける方法

開業資金を調達する方法として、借入や融資が考えられますが、具体的には以下の通りです。
- 銀行からの融資
- 日本政策金融公庫|新規開業資金
- 日本政策金融公庫|挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)
- 地方自治体の制度融資
- ビジネスローン
これから開業する事業者や、開業して間もない事業者の場合、実績がなく信用力が乏しいなどの理由から、審査の厳しい民間の金融機関からの融資が受けられない可能性が高いです。
この場合は、開業した方、開業して間もない方を対象とした融資制度の利用も検討してみましょう。
開業時に利用できる融資について、それぞれ詳しく説明していきます。
銀行からの融資
最もポピュラーな方法として、銀行から資金を借り入れる資金調達方法があります。
審査にさえ通れば求める額の資金が調達でき、経営の介入がなく多額の借り入れができる点がメリットです。
ただし、審査が厳しく希望の融資金額にならない恐れがあることや、開業したばかりの事業者では利用が難しいなどのデメリットがあります。
開業時に銀行からの融資を検討している場合は、大手銀行よりも地方銀行の方が対応してくれる可能性が高いです。
日本政策金融公庫|新規開業資金
開業における融資でまず検討したいのが、日本政策金融公庫の新規開業資金です。
日本政策金融公庫は、民間金融機関を補完する目的で国が運営している金融機関で、起業・開業する方への融資を積極的に行っています。
日本政策金融機関が提供している新規開業資金は、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が利用できる制度で、原則として無担保・無保証人で融資が受けられるなどのメリットがあるのです。
また、この制度には自己資金要件はないため、幅広い方の創業・スタートアップをサポートしています。
【新規開業資金の概要】
|
対象者 |
新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 |
|
資金用途 |
設備資金、運転資金 |
|
融資限度額 |
7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
|
返済期間 |
設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金:10年以内(うち据置期間5年以内) |
日本政策金融公庫|挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)

日本政策金融公庫には、「挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)」という、融資における特例制度もあります。
主に、スタートアップや新事業展開・海外展開・事業再生等に取り組む方の財務体質を強化するなど、ベンチャーキャピタル・民間金融機関などからの資金調達の円滑化を支援するための制度です。
また、資本性ローンであるため、金融機関の資産査定では借入金が自己資本とみなされるのが特徴となっています。
【挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)の概要】
|
対象者 |
以下のいずれかの融資制度の対象となる方
・新規開業資金 ・新事業活動促進資金 ・海外展開 ・事業再編資金 ・事業承継・集約・活性化支援資金 ・企業再建資金 ・ソーシャルビジネス支援資金 その他条件として以下のすべての要件も満たす方 ・地域経済活性化にかかる事業を行うこと ・税務申告を1期以上行っている場合、原則として所得税等を完納していること |
| 資金用途 |
設備資金、運転資金 |
|
融資限度額 |
7,200万円 |
| 返済期間 |
5年1ヵ月以上20年以内 |
地方自治体の制度融資
都道府県や市区町村といった地方自治体の制度融資を活用するのもおすすめです。
制度融資とは、地方自治体と金融機関と信用保証協会の3つの機関が連携して実行する融資制度で、中小企業や個人事業主が対象となります。
制度融資には、以下のようにさまざまなメリットがあります。
- 比較的審査に前向きで実績のない企業でも審査に通りやすい
- 低金利で長期間借りられる
- 元本を返済しない据置制度がある
ただし、こちらの制度は都道府県によって対象者や利用条件に違いがあるほか、全ての自治体で行われているわけではないので、開業する地域に制度融資があれば検討してみると良いでしょう。
ビジネスローン
ビジネスローンは、銀行や信販会社、消費者金融が提供している事業資金専用のローンを指します。
法人または個人事業主が対象となり、借入金は運転資金や設備資金、新規事業の立ち上げ資金などに利用できるものです。
ビジネスローンには融資までの期間が比較的短いというメリットがありますが、融資上限額が比較的低いことや、金利が高い傾向にあるなどのデメリットもあるため、特徴をしっかり把握したうえで利用する必要があります。
融資以外で資金調達する方法

開業資金を調達する方法として、融資以外にも以下の方法があります。
- 自治体の補助金・助成金を使う
- ベンチャーキャピタル
- クラウドファンディング
- 退職金・失業給付金を使う
中小企業や個人事業主が利用できる資金調達の方法を詳しく説明していきます。
自治体の補助金・助成金を使う
自治体によっては、制度融資とは別に会社設立時に利用できる補助金や助成金制度を実施している場合があります。
補助金や助成金は、融資とは違い返済が不要な点がメリットとなりますが、利用対象や条件が厳しい傾向にあります。
また、自治体によって補助金・助成金制度の種類や対象者、補助・助成内容などがそれぞれ異なるため、開業する自治体のホームページを確認してみるのがおすすめです。
ベンチャーキャピタル
ベンチャーキャピタル(Venture Capital)とは、将来有望なベンチャー企業やスタートアップ企業に出資する組織です。
今後成長が見込まれる企業の事業将来性を見極めて、出資やビジネス支援を行うため、金融機関からの融資が受けられない場合でも、資金調達できる可能性があります。
さらに、ベンチャーキャピタルから受けた出資金は借入金とはならないため、返済の必要がありません。
ただし、あくまでも「出資」であるため、出資者の意図に合わなかったり、成長が見込めないと判断されたりすると、撤退され、資金調達がうまくいかなくなるケースもあるので注意しましょう。
クラウドファンディング
近年増えている資金調達方法にクラウドファンディングがあります。
クラウドファンディングは、事業計画や目的などをインターネット上に公表し、それに賛同してくれた不特定多数の方から資金を集める方法です。
少額から出資できる場合が多いため、多くの人から資金を集められるというメリットがあります。
融資を受けるのが難しい場合でも資金調達ができる可能性が高いだけでなく、店舗や商品、サービスの宣伝にもなりますが、目標額に到達しなければ資金を集められない点に注意しましょう。
退職金・失業給付金を使う
現在勤めている会社を辞めて起業する場合、その際に支払われる退職金や失業給付金を企業資金として活用することができます。
退職金は会社の労務規定を、失業給付はハローワークの窓口から金額や受給資格などから把握しておきましょう。
また、退職金は退職日から1週間~1ヶ月位の間で支払われるのが一般的ですが、こちらも確認しておくのがおすすめです。
資金調達の相談をする際のポイント
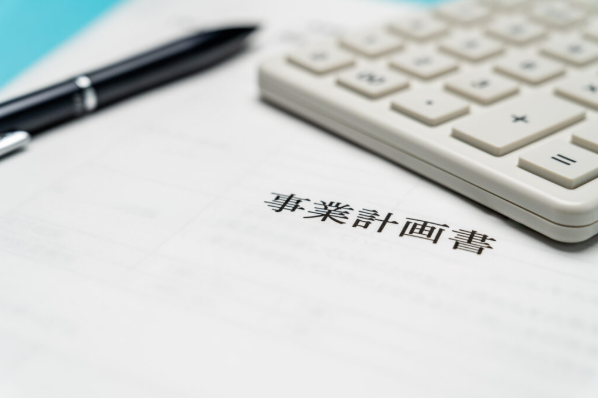
事業を始めるにあたって利用できる融資や資金調達方法はさまざまありますが、実際に資金を得るためには、事前に対策をとっておかなければ失敗する可能性が高いです。
ここでは、資金調達を相談する前に準備しておくものや心掛けることを説明していきます。
必要な資金調達額を明確にする
資金調達をする際に注意しなければならないのが資金調達額です。
資金調達額は多ければ多いというわけでなく、金額によって金利や審査の難易度が変わるほか、返済プランにも影響が生じます。
特に、開業したばかりの事業者であれば、必要以上に多く見積もると審査で不利になってしまう恐れがあるので注意しましょう。
このように、資金調達の目標金額の算定を誤ってしまうとやがて大きなトラブルを招いてしまう恐れがあるので、資金調達を考えるときにはまず、あらかじめ目標金額を明確に決めておくことが望ましいです。
自社に合った資金調達方法を選ぶ
資金調達成功のポイントは、自社の目的やタイミングに合った効果的な調達方法を選択することです。
ご紹介した通り、資金調達にはさまざまな用途や方法があり、誤った手段を選ぶと、キャッシュフローの悪化につながり、資金繰りが苦しくなるケースもあります。
自社の目的やタイミングに合った資金調達を行えば、事業拡大の大きなチャンスとなるため、必要に応じて資金調達の専門家である税理士やコンサルタント等に相談しながら、効果的な資金調達方法を選択しましょう。
綿密な事業計画を準備する
綿密な事業計画を立てることで資金調達がしやすくなり、事業の成功にも繋がります。
融資を提供する側はその企業に資金が本当に必要なのか、事業で利益を出せるのかを事業計画書で確認するため、事業者に融資の必要性があるのかをしっかりと訴えることが重要です。
また、融資する側は返すあてがない企業に対してお金を貸せないため、融資の申し込みをする前に、事業計画やキャッシュフローについて綿密に組み立てておく必要があります。
【事業計画に必要な要素】
- 会社の基本情報
- 事業の概要
- 経営者の経歴・起業の動機
- 経営理念・目標・ビジョン
- 事業概要(コンセプト・サービス内容)
- 市場環境・競合状況
- 自社の強みや成長性
- 人員計画や実施体制
- 収支計画 など
返済計画を提示する
たとえ融資を受けたとしても、返済が行き詰まってしまえば経営に悪影響が出る恐れがあるため、事前に返済計画や返済期間をしっかり考え、返済計画を提示することが重要です。
資金調達方法には、補助金や助成金のように返済不要なものもあれば、融資などのように利息と共に返済しなければならないものがあり、資金調達した後は資金繰りをきちんと行い、無駄な支出を抑え、お金を増やして借入金を返済していかなければなりません。
そのため、資金調達を行う際は、事前に余裕を持った返済計画を立てておきましょう。
開業資金は自社の目的別に適した手段を選ぼう

資金調達は企業経営において大切なプロセスです。
ご紹介した通り、資金調達にはさまざまな方法がありますが、起業時には制度融資や公庫融資の活用、クラウドファンディングで広く出資を募るなど、自社の目的や状況に応じて最適な手段を選ぶことが重要です。
また、中小企業や小規模事業者が創業する際の融資では審査が厳しくなる傾向にあるため、あらかじめ綿密な事業計画や返済計画を立て、事業の成功につながる明確な根拠を示しましょう。
また、税理士に資金調達の相談をすれば、自社のニーズに合った方法を選択できるほか、金融機関や投資家からの信頼を得られるような事業計画書の作成ができ、資金調達の成功率が向上するため、専門家のサポートも検討してみてください。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は 国税OB・元税務署長 が所属し、 確定申告・相続・会社設立・融資サポート・労務手続きなど 幅広いサービスを提供する税理士法人です。
全国からの 税務・労務相談実績 年間1,000件以上
税理士法人松本の強み
- 税務署目線、税理士目線、お客様目線の三方良しの考え方でアドバイス
- 過去の無申告分から税務調査、相続、会社設立まで幅広く対応可能
- 融資や助成金、補助金の申請など資金調達サポートにも豊富な実績
- 顧問税理士が対応に困った案件も途中からサポートできます
30秒で完了かんたん融資診断