メニュー
起業・開業
開業届を提出するタイミングとは?提出するメリット・デメリットについても徹底解説
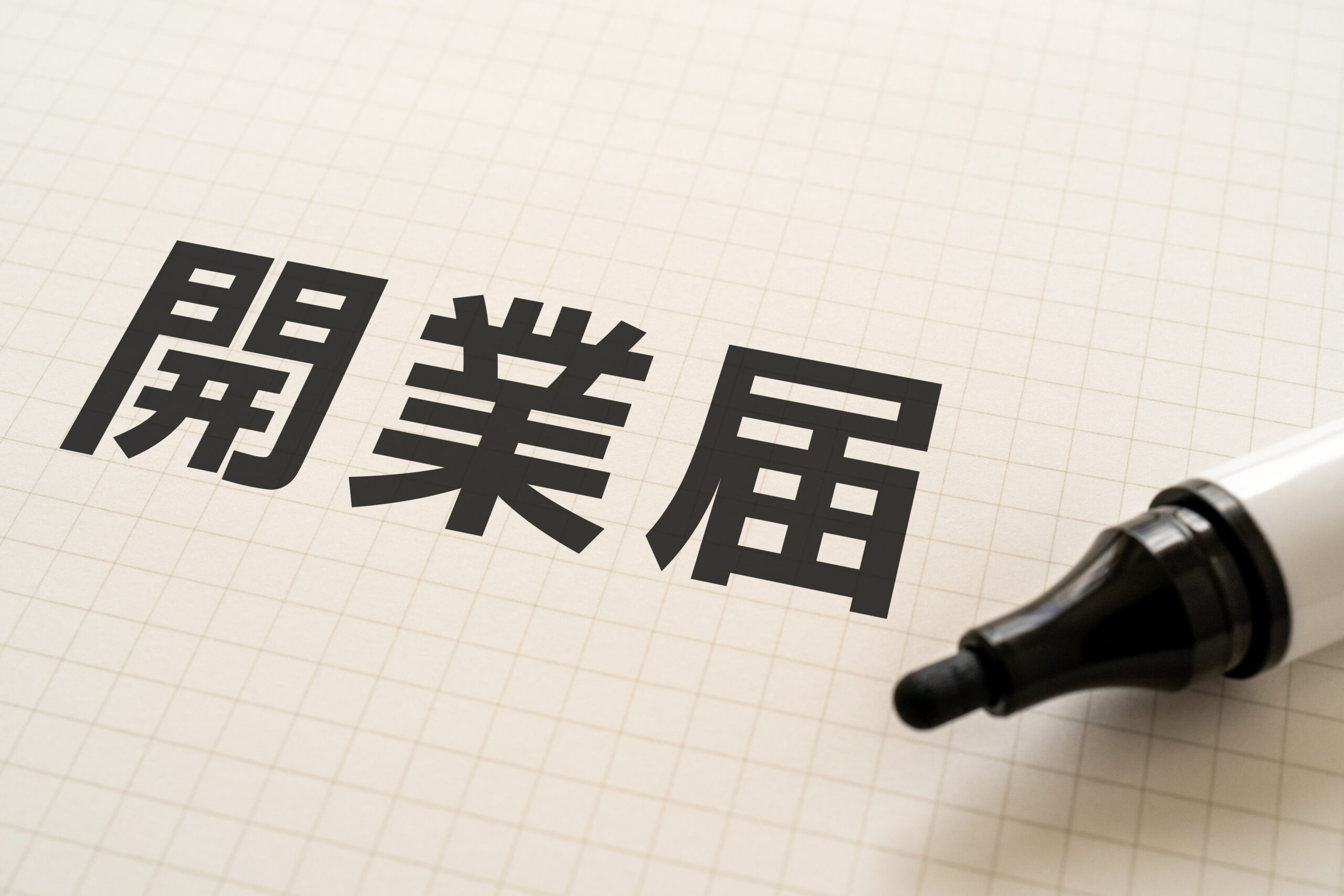
読了目安時間:約 7分
開業届とは、事業所得などを得る際に必要となる手続きの一つであり、提出しない場合は青色申告の申請ができなくなります。
また、節税や融資の面で損をしてしまうリスクがあるので、提出するタイミングが重要です。
本記事では、開業届を提出するタイミングについて紹介していきます。
他にも「開業届を提出することのメリット・デメリット」や「開業届の提出方法」についても解説していきます。
ぜひこの記事を参考にして、開業届を提出するタイミングについて理解を深めてみてください。
目次
開業届を提出するタイミングとは?

開業届を提出するタイミングについては、以下の5つが挙げられます。
- 年間所得が48万円を超えた
- 年内に事業所得がある
- 副業から本業になった
- 再就職手当を受けたい
- 縁起の良い日を開業日にしたい
それぞれのタイミングについて解説していきます。
年間所得が48万円を超えた
開業届を提出するタイミングとして、年間所得が48万円を超えたタイミングが挙げられます。
基礎控除は一律48万円で、この金額までは課税所得から控除されるため、所得税の課税対象から外れます。
一方、年間の事業所得がこの額を超える場合、その超過分に対しては課税が行われ、税金の支払いが必要になります。
開業届を提出し、確定申告を青色申告の形式で行うことで、「青色申告特別控除」を利用できます。
この制度により、条件を満たせば55万円または最大で65万円の控除が受けられ、税負担の軽減につながります。
年内に事業所得がある
年内に事業所得がある場合は、年内に開業届を提出するようにしましょう。
翌年以降に届け出を行うと、前年分の青色申告特別控除が受けられないことがあります。
開業届を提出する際には、あわせて「青色申告承認申請書」も出しておくと、青色申告に必要な手続きがスムーズに整います。
この制度を利用するには、開業から2か月以内、もしくは青色申告を適用する年の3月15日までに申請書を提出する必要があります。
参考:青色申告制度|国税庁
副業から本業になった
開業届を提出するタイミングとして、副業から本業になったタイミングが挙げられます。
会社勤めの方が副業で収入を得ている場合でも、事業性が認められる程度の継続性や規模があれば、税務署から開業届の提出を求められるケースがあります。そのため、副業収入が一定以上ある場合は、税務署や税理士に確認のうえ、開業届の提出を検討することが望ましいでしょう。
一般的に、副業での収益は「雑所得」として扱われることが多く、この場合は青色申告による最大65万円の控除を受けることができません。一方、「本業」としての活動に移行する際には、開業届と同時に青色申告承認申請書も提出し、青色申告ができる状態にしておくとよいでしょう。
このように、収入の主体が事業所得として認められるようになった段階で、開業手続きを行うことが望ましいと言えます。
参考:通達目次 / 所得税基本通達|国税庁、事業所得の課税のしくみ(事業所得)|国税庁
再就職手当を受けたい
開業届を提出するタイミングとして、再就職手当を受けたい時が挙げられます。
退職後に「再就職手当」の支給を希望する場合には、退職時に「開業届」の提出を検討するようにしましょう。
理由として、再就職手当が他社への就職だけでなく、自ら事業を立ち上げる「個人事業主としての開業」も対象として認められていることが挙げられます。
しかし、ハローワークでの失業認定を受ける前に開業届を提出してしまうと、再就職手当の支給対象から外れてしまうので、あらかじめ注意が必要です。
具体的に、開業届を出して再就職手当を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。
- 事業を1年以上継続する見込みがあること
- 雇用保険の被保険者であったこと
- 7日間の待機期間を経てから開業していること
- 前職の勤務先と業務上の深いつながりがないこと
- 失業手当(基本手当)の支給残日数が全体の3分の1以上あること
- 過去3年間に再就職手当または常用就職支援手当を受けていないこと
- 再就職手当の支給日までに雇用されていないこと
このような要件を確認のうえ、開業のタイミングと手続きに注意すれば、個人事業としての再スタートでも支援を受けることが可能です。
参考:再就職手当のご案内|厚生労働省、雇用保険法|厚生労働省
縁起の良い日を開業日にしたい
開業届を提出するタイミングの一つとして、縁起の良い日を開業日にしたいことが挙げられます。
個人事業主としての第一歩を踏み出す開業届の提出日は、将来への覚悟や新たなスタートを象徴する特別な日と言えます。
そうした節目を迎えるにあたって、縁起のよい日を選んで提出することも一つの考え方です。
日本の伝統的な吉日には、以下が挙げられます。
- 一粒万倍日
- 天赦日
- 寅の日
これらの吉日は、新しい物事を始めるのに適しているとされており、開業のタイミングとして選ばれることも少なくありません。
あらかじめ暦を確認し、これらの吉日に合わせて開業届を出すことをおすすめします。
開業届を提出することのメリット

開業届を提出することのメリットについては、以下の4つが挙げられます。
- 社会的信用力が増す
- 融資を受けやすくなる
- 確定申告時に青色申告が使える
- 赤字繰越ができる
それぞれのメリットについて解説していきます。
社会的信用力が増す
開業届を提出することで、個人事業主としての活動を税務署に届け出た証明になります。
法人と異なり、個人事業主は法務局で登記を行わないため、事業実態を第三者に公的に示す手段が限られています。
開業届を提出しておけば、取引先や金融機関に対して事業開始の証明書類として提示できるため、取引や契約の場面で信用を得やすくなる場合があります。ただし、開業届の有無だけで信用力が決まるわけではなく、実際には取引実績や事業内容、納税実績なども含めた総合的な要素で判断されます。
開業届の手続きを済ませておくことで、取引先や関係者からの信頼を得やすくなり、ビジネスを円滑に進めることにつながります。
融資を受けやすくなる
個人事業主として開業届を提出すると、屋号名義で事業専用の銀行口座を作成できるようになります。
事業専用口座を持つことで、資金の流れが明確になり、事業の実態を公的に示せるため、銀行や日本政策金融公庫などでの融資申請時に有利に働く可能性があります。
ただし、実際に融資が受けられるかどうかは、事業計画や返済能力、金融機関ごとの審査基準などを総合的に判断して決定されます。そのため、開業届を提出しただけで必ず融資が通るわけではない点には注意が必要です。
また、事業専用口座を持つことで資金管理の透明性が高まり、融資審査においてプラスに働くケースもありますが、条件や金利は金融機関によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
確定申告時に青色申告が使える
開業届を提出して「青色申告承認申請書」を期限内に提出することで、青色申告が利用可能になります。青色申告を選択すると、最大65万円(一定条件を満たさない場合は55万円)の特別控除が適用でき、課税所得を減らすことができます。
ただし、この控除を受けるためには、複式簿記による記帳やe-Taxによる電子申告、または電子帳簿保存などの条件を満たす必要があります。
また、青色申告の承認申請は、開業から2か月以内または青色申告を希望する年の3月15日までに提出が必要なため、期限管理が重要です。
参考:e-Tax
赤字繰越ができる
青色申告を選択した場合、事業で発生した赤字は翌年以降に繰り越して、将来の黒字と相殺することが可能です(最長3年間)。
これにより、起業初期の赤字を将来の税負担軽減に活用でき、資金繰りの面でも有利に働く場合があります。
ただし、この制度を利用するには青色申告の承認を受けていることが前提であり、白色申告では適用されません。事業が安定する前に開業届と青色申告の準備を整えておくことが推奨されます。
開業届を提出することのデメリット
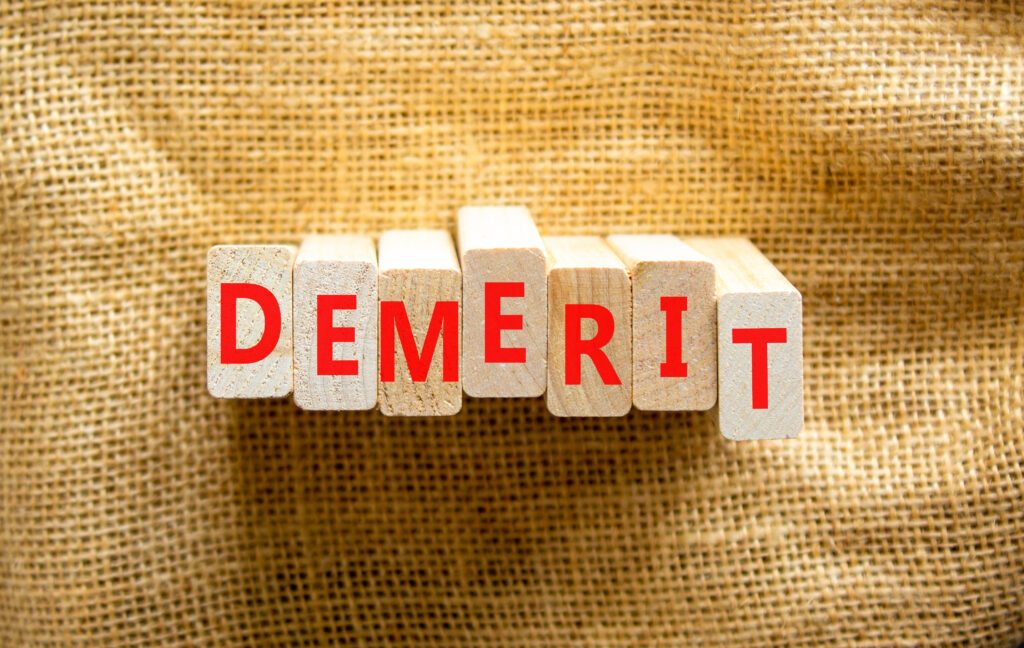
開業届を提出することのデメリットについては、以下の3つが挙げられます。
- 失業手当が受けられない場合がある
- 帳簿付けなどの手間がかかる
- 健康保険の被扶養者から外れる可能性がある
それぞれのデメリットについて解説していきます。
失業手当が受けられない場合がある
開業届を提出すると、ハローワークでは「今後、就職する意志がない」と受け取られ、失業給付の対象外となる場合があります。
失業手当の受給には「働く意思と能力」が前提条件として求められています。
開業届を出すという行為は、自らの意思で会社に雇われず、独立して事業を始めるという選択を意味していると見られてしまいます。
そのため、現在失業手当を受給中の方や、これから受給を予定している方は、開業届をいつ提出するかについて慎重に検討することが大切です。
ただし対象外となるか否かは状況により異なりますので、提出前に必ずハローワークに相談することを推奨します。
帳簿付けなどの手間がかかる
開業届を提出して、青色申告を選ぶ際には、記帳作業などに一定の手間が伴ってしまうデメリットが挙げられます。
特に、65万円の控除を受けるためには、電子帳簿による記録・保存とe-Taxを利用した申告が必要です。
また、55万円の控除でも複式簿記での記帳が条件となります。
しかし、開業していても収入が少ない場合には、白色申告を選んだり、青色申告でも10万円の控除を受ける方法もあるので、自分に合った方法を選ぶようにしましょう。
健康保険の被扶養者から外れる可能性がある
開業届を税務署に提出すると、家族や配偶者の健康保険における「被扶養者」資格を失ってしまうデメリットが挙げられます。
健康保険組合ごとに扶養の認定基準が異なりますが、収入が少なくても、事業を営んでいるという理由だけで扶養の対象外とされるケースもあります。
また、年間の収入や所得が一定の基準を超えると、扶養から除外されることもあります。
被扶養者としての資格を失った場合、自ら健康保険の脱退手続きと、国民健康保険への加入手続きを進める必要があります。
現在家族の健康保険に扶養されている方は、あらかじめ加入している保険組合の扶養条件をしっかりと確認しておくことが大切です。
開業届の提出時に必要な書類

開業届の提出時に必要な書類については、以下の3つが挙げられます。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- マイナンバーカード
- 本人確認書類
それぞれの書類について解説していきます。
個人事業の開業・廃業等届出書
個人事業の開業・廃業等届出書とは、個人で事業を始める際に提出が求められる届出書のことを指します。
この届出書は、税務署や市役所・区役所などの役所窓口、あるいは国税庁の公式サイトから入手可能です。
紙で提出する場合は、手書きもしくはパソコンで作成して印刷したものを準備し、税務署の窓口に直接持参するか郵送で送付します。
一方、オンラインで手続きしたい場合は、e-Taxを利用することで電子申請が可能です。e-Taxの「開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」にアクセスし、必要な情報を入力するだけで、届出書が簡単に作成・提出ができます。
参考:e-Tax
マイナンバーカード
開業届を提出する際には、マイナンバーの記入が求められるので、マイナンバーカードや個人番号が記載された書類の準備が必要になります。
具体的には、通知カードやマイナンバー入りの住民票などがその証明書類として使えます。
さらに、e-Taxを利用してオンラインで提出する場合には、マイナンバーカードが必須となります。
そのため、未取得の方は、あらかじめ発行手続きをおこなっておくことをおすすめします。
参考:マイナンバーカード
本人確認書類
開業届を提出する際には、本人確認の手続きが必要となるため、身分証明書の提示が求められます。
マイナンバーカードを持っている場合は、顔写真付きで氏名や住所などの情報が記載されているので、マイナンバーだけで本人確認が可能です。
一方、マイナンバーカードを持っていない場合には、マイナンバーの記載がある通知カードや住民票のほかに、運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの身分証明書をもう一つ用意し、計二種類の書類を提示する必要があります。
窓口で提出する際にはこれらを直接提示し、郵送の場合にはコピーを同封するようにしましょう。
また、e-Taxを利用してオンラインで提出する場合は、マイナンバーカードによる電子認証を行うため、本人確認書類を別途用意する必要はありません。
開業届を提出できるように準備しておこう!

今回は、開業届を提出するタイミングについて紹介しました。
開業日は実際に業務を開始した日を指し、その日から1か月以内に開業届を出すことが求められます。
期限を過ぎても届出自体は受理されますが、青色申告を希望する場合には注意が必要です。
青色申告承認申請書は、開業日から2か月以内に提出しなければ、初年度の青色申告ができなくなってしまうのであらかじめ注意が必要です。
今回の記事を参考にして、計画的に準備を進め、開業届の提出時期を逃さないようにしましょう。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。





