メニュー
法人化
マイクロ法人とは?メリット・デメリットや設立する手順についても徹底解説

読了目安時間:約 7分
マイクロ法人とは、代表者1名で事業を行い、従業員を持たない小規模な法人形態を指します。
個人事業主としての活動と比べて、法人化することで税務上の取り扱いや社会保険の加入方法が異なる場合があり、節税や社会保険料の負担軽減につながるケースもあるため、それを見越して設立を検討する人もいます。
また、法人設立には一定のコストや会計・事務処理の手間が発生することもある点に注意が必要です。
本記事では、マイクロ法人の概要や、メリット・デメリット、設立手順などについて解説します。ぜひこの記事を参考に、自分に合った働き方を選択していただけたら幸いです。
目次
マイクロ法人とは?

マイクロ法人とは、代表者自身が1人で事業運営を行う、小規模な企業形態のことを指します。
一般的には個人事業主やフリーランスが、法人化による税務上のメリットや社会保険制度への対応のために設立するケースが多いです。
設立可能な法人形態には、株式会社や合同会社などがあり、法的に認められた形で運営できます。
ただし、合資会社や合名会社の場合は社員の人数や責任範囲に制限があるため、代表者1人だけでの設立はできません。設立前に注意が必要です。
マイクロ法人と一般法人との違い
マイクロ法人と一般法人の主な違いは、組織規模や運営形態にあります。
一般法人は、株主からの出資を受けて資金を調達し、役員や従業員を雇用して事業を拡大し、利益を株主に分配するケースが多く見られます。
一方、マイクロ法人は、少人数で運営されることが多く、代表者自身が出資者および役員を兼ねる形で事業を運営することが一般的です。外部の従業員を雇用せずに事業を行う場合もありますが、必ずしも制限されるわけではありません。
どちらの法人形態も法律上は「法人格」を有しており、会社法に基づいた設立登記が必要である点は共通しています。
マイクロ法人と個人事業主との違い
マイクロ法人と個人事業主との違いとして、主に以下が挙げられます。
- 起業時の手続き
- 税金の取り扱い
- 経費の使い方
個人事業主として開業する場合は、税務署に「個人事業の開業届」を提出するだけで手続きは完了します。
一方、法人を設立する場合は、定款の作成や法務局での登記などが必要となるため、準備に一定の時間と費用がかかります。ただし、設立後は法人としての各種税制上のメリットを活用できる場合があります。
また、法人と個人事業主では課税の方法や種類が異なるため、所得の額や経費の使い方によって、納める税金に差が生じることがあります。どの形態が最適かは、事業規模や収入の見込み、将来の事業計画などに応じて判断することが重要です。
参考:国税庁|個人事業の開業届出・廃業届出等手続
マイクロ法人を設立するメリット

マイクロ法人を設立する場合、以下のようなメリットが考えられます。
- 経費の範囲が広くなる
- 社会的信用度が高くなる
- 税金を抑えられる
- 消費税の免税事業者になれる可能性がある
- 社会保険料の節約につながる
経費の範囲が広くなる
マイクロ法人を設立するメリットの一つとして、個人事業主に比べて経費として計上できる範囲が広がることが挙げられます。
例えば、法人の代表者が受け取る役員報酬は、一定の条件を満たすことで法人の経費として計上できます。これにより、法人の課税所得を適切に調整することが可能です。
また、法人契約の退職金や生命保険料の一部、出張時の日当なども、条件を満たせば経費として計上できる場合があります。
このように、マイクロ法人を活用することで、経費の計上範囲が広がり、税務面で柔軟な対応が可能になります。
参考:国税庁| 必要経費の知識
社会的信用度が高くなる
マイクロ法人を設立することで、法人格を持つことによる一定の信用力向上が期待できます。
法人を設立する際には、法務局で会社の設立登記を行い、会社名・所在地・資本金などの基本情報を公式に登録します。この登記情報は一般に公開され、法人としての責任が明確になることで、取引先や金融機関に対して信頼性の目安となる場合があります。
また、法人格を持つことで、金融機関からの融資制度の利用や、法人を対象とした助成金・補助金への申請など、資金調達の選択肢が個人事業主より広がる場合があります。ただし、条件や審査基準は制度ごとに異なるため、必ずしも自動的に利用できるわけではありません。
税金を抑えられる
マイクロ法人を設立することで、場合によっては税負担の軽減につながる可能性があります。
個人事業主として事業を行う場合、利益には「所得税」がかかります。所得税は所得に応じて段階的に税率が上がる累進課税制度が採用されており、税率は5%から最大45%まで、7段階に分かれており、一般的に収入が増えるほど税率も高くなる仕組みです。
個人で事業を行っている場合、得た利益に対しては「所得税」がかかります。
この所得税は段階的に税率が上がっていく累進課税制度が採用されており、税率は5%から最大45%まで、所得の額に応じて7つの区分に分かれて、収入が増えるほど税率も高くなる仕組みです。
一方、法人として事業を行う場合には「法人税」が課されます。法人税は原則として23.2%ですが、資本金1,000万円以下の法人で、課税所得が800万円以下の部分については軽減税率15%が適用されます。
そのため、一定の収益規模や経費状況によっては、個人事業として運営するより法人化した方が税負担を抑えられる可能性があります。ただし、実際の税額は収入や経費の内容によって異なるため、法人化による節税効果は個別に確認することが重要です。
参考:国税庁|法人税の税率
消費税の免税事業者になれる可能性がある
マイクロ法人を設立することで、一定の条件を満たす場合には、消費税の免税事業者として扱われる可能性があります。
消費税の「免税事業者」とは、基準期間における課税売上高が1,000万円未満の事業者が対象となり、消費税の納税義務が免除される制度です。
ただし、消費税対策を目的としてマイクロ法人を作る行為は、税務署から租税回避や意図的な脱税行為として見なされるリスクがあるため注意が必要です。
参考:国税庁|納税義務の免除
社会保険料の節約につながる
マイクロ法人を設立した場合、法人の代表者は健康保険および厚生年金に加入することが法律で義務付けられています。保険料は原則として役員報酬の金額に基づき計算されます。
個人事業主から法人化することで、場合によっては社会保険料や税負担のバランスを調整できるケースもあり、仮に報酬を最低限に抑えると、それに比例して健康保険・厚生年金の負担額も軽くなります。
ただし、効果は事業の規模や報酬額によって異なるため、専門家と相談して判断することをおすすめします。
参考:全国健康保険協会|都道府県毎の保険料額表
マイクロ法人を設立するデメリット
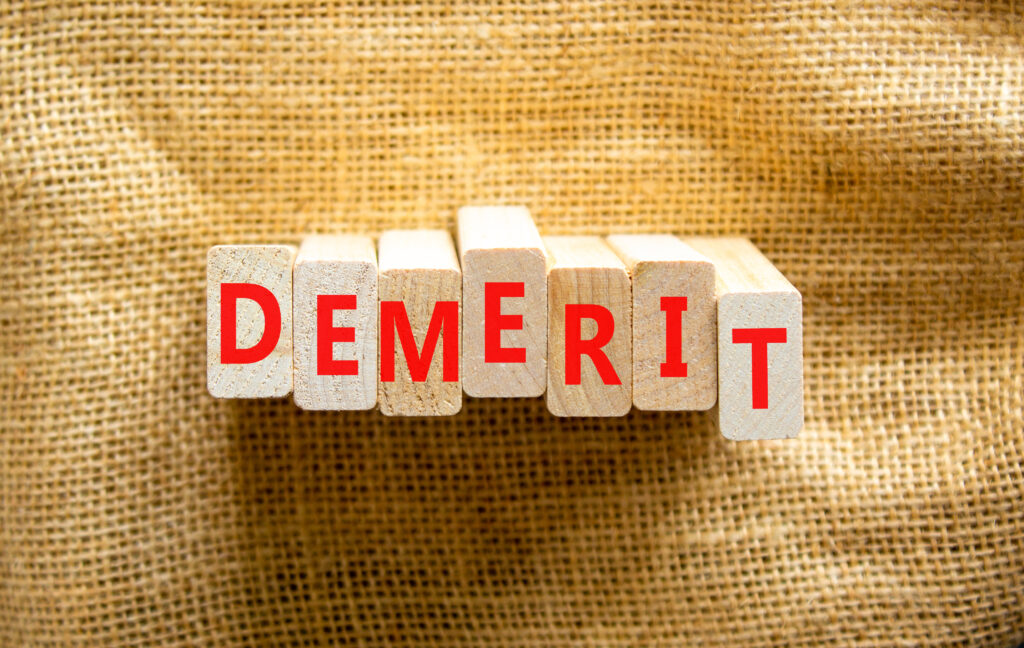
マイクロ法人を設立するデメリットとして、以下の3つが挙げられます。
- コストがかかる
- 赤字でも法人住民税の支払いが必要になる
- 事務作業が複雑になる
コストがかかる
マイクロ法人の設立には、初期費用や維持費といったコスト面の負担が増えてしまうデメリットが挙げられます。
例えば、株式会社を設立する場合は、登記費用や定款認証費用などで20万円~万円程度かかるケースがあります。また、法人として活動を継続する場合、法人住民税などの固定費が毎年発生します。
さらに、決算書類の作成や税務申告を税理士などの専門家に依頼する場合は、別途費用が必要となることがあります。
赤字でも法人住民税の支払いが必要になる
マイクロ法人を設立すると、たとえ経営が赤字であっても「法人住民税の均等割」という税金の支払い義務が発生します。
この均等割は、会社の資本金などに応じて金額が異なりますが、最低でも都道府県に2万円、市区町村に5万円、合計で年間7万円の納税が必要になります。
そのため、収益が出ていない個人事業主がマイクロ法人へ切り替えた場合、住民税の負担が増加し、結果的にコストがかさむ場合がある点に注意が必要です。
参考:総務省|地方税制度
事務作業が複雑になる
マイクロ法人を設立すると、個人事業主として活動していた場合と比べて、事務作業や会計処理の範囲が広がる点に注意が必要です。
個人事業主であれば、年に一度の確定申告を済ませれば基本的な手続きは完了しますが、法人を設立した場合には、貸借対照表や損益計算書、株主資本等変動計算書といった財務諸表が求められます。さらに、勘定科目内訳明細書や法人事業概況説明書など、提出すべき書類が増えるため、会計業務の範囲が広がることになります。
参考:国税庁|貸借対照表作成の手引き
マイクロ法人を設立する手順

マイクロ法人を設立する主な手順は、以下のとおりです。
- 基本事項の決定
- 定款作成
- 出資金の払い込み
- 登記申請
- 各種の届け出
基本事項の決定
マイクロ法人を設立する際には、まず会社の基本事項を明確にしておくことが重要です。
基本事項には、以下の項目が含まれます。
- 法人の種類
- 名称
- 事業の目的
- 所在地
- 資本金
- 決算期
法人形態としては、一般的に株式会社や合同会社が選ばれます。合名会社や合資会社も法律上は設立可能ですが、実務ではほとんど利用されません。
また、法律上は資本金に最低金額の定めはなく、1円からでも設立は可能です。しかし、社会的な信頼性や取引先との関係を考慮すると、ある程度の資本金を設定することが望ましいとされています。
会社設立にあたっては、これらの基本事項を事前に検討・決定しておくことで、スムーズな設立手続きにつながります。
定款作成
次に、基本的なルールを定める「定款」を作成することが求められます。
特に、法律で必ず盛り込むよう定められている「絶対的記載事項」は、定款の有効性に直結する重要な要素になります。
これらが欠けている場合、定款そのものが無効と判断されるおそれがあるため、十分な注意が必要です。
具体的に、法人を設立する際に記載が義務づけられている絶対的記載事項には、以下の5つが挙げられます。
- 会社の事業目的
- 商号(会社の名称)
- 本店の所在地
- 出資される資産の額、もしくはその最低金額
- 発起人の氏名・名称および住所
この認証手続きは、株式会社を設立する際にのみ必要になり、合同会社・合名会社・合資会社を設立する場合には不要です。
参考:定款の作り方 | 起業マニュアル – J-Net21 – 中小機構
出資金の振り込み
マイクロ法人の設立するには、出資金の振り込みを行う必要があります。
出資金の振込が完了したら、その事実を証明できる資料を用意するようにしましょう。例えば、以下の資料のコピーが必要です。
- 通帳の表紙
- 裏表紙(支店名、口座番号、名義人の氏名が確認できる部分)
- 振込日と振込金額が記載された取引ページ
また、通帳がない場合やインターネットバンキングを利用している場合には、金融機関名、口座名義、入金日、入金額が表示されている画面の印刷でも代用可能です。
これらの資料は、法人登記の際に添付書類として必要になるので、紛失しないように保管しておきましょう。
登記申請
マイクロ法人を設立する際には、必要な書類を整えた上で、本店所在地を管轄する法務局にて登記申請をおこなう必要があります。
具体的に、提出が求められる主な書類は以下のとおりです。
- 本人確認が可能な身分証明書の写し
- 出資金の払込を証明する書類
- 印鑑届書
- 法人登記申請書
- 会社の定款
- 発起人の同意を証明する書類
- 初代代表取締役の選任に関する証明書
- 設立時取締役の就任承諾書
また、定款の内容や会社の形態によって、提出が必要な書類が変わる場合がありますので、事前に最新情報を確認することが重要です。
各種の届け出
最後に、税務署や市役所・町村役場などの公的機関で必要な届け出や申請をおこなう必要があります。例えば、開業届の提出や社会保険関連の申請などが該当します。
実際に、個人事業主であれば、基本的に税務署へ開業届を提出するだけで完了しますが、マイクロ法人を設立する際は、より多くの手続きが必要です。
特に、青色申告承認申請書のように、提出期限に注意しなければならない書類もあるので、スケジュール管理も重要です。
参考:国税庁|所得税の青色申告承認申請手続
マイクロ法人設立時の注意点

マイクロ法人設立時の注意点として、以下の2つが挙げられます。
- 脱税を疑われないように注意する
- 会社員は社会保険料を節約できない
脱税を疑われないように注意する
マイクロ法人を設立する際には、税務署から不正な節税や脱税を疑われないよう、十分な配慮が求められます。
特に、個人事業と並行してマイクロ法人を運営する場合には、両者の業務内容をしっかりと区別しておくことが重要です。
特に、活動内容が酷似していると、意図的に利益を分散させて税負担を軽くしようとしていると受け取られるリスクがあるので注意が必要です。
参考:国税庁|令和6年度 査察の概要
会社員は社会保険料を節約できない
会社員がマイクロ法人を設立する場合、社会保険料の削減効果は必ずしも期待できないことがあります。
すでに勤務先で社会保険に加入している場合、自身の法人から役員報酬を受け取ると、保険料が追加で発生することもあります。
また、複数の事業で社会保険に加入する場合には、勤務先に通知が行くケースがあるため、事前に勤務先の就業規則や社会保険の取り扱いを確認しておくことが望ましいでしょう。
マイクロ法人設立はさまざまな観点から検討しよう!

今回は、マイクロ法人について紹介しました。
マイクロ法人とは、代表者1人で運営される小規模な会社形態で、従業員を雇わずに事業をおこなう法人です。
個人事業主がマイクロ法人を設立する場合、所得の分散や経費計上の方法によって、所得税や住民税の負担を軽減できるケースがあります。また、役員報酬の設定次第では社会保険料の負担が変わることもあります。
一方で、マイクロ法人の設立には登記費用や定款作成費用などの初期費用がかかり、税務や会計の手続きも個人事業より複雑になります。
そのため、マイクロ法人のメリットだけに注目するのではなく、デメリットやリスクについても理解した上で、自分のビジネスにとって最適な形を検討することが重要です。
今回の記事を参考にして、マイクロ法人設立をさまざまな観点から検討しましょう。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。





