メニュー
法人化
法人成り後に個人事業主を廃業しないメリット・デメリットとは?注意点についても解説

読了目安時間:約 6分
法人成り後であっても、事業内容や状況によっては、個人事業を継続することも可能です。
個人事業を廃業しないことで一定のメリットが得られることもありますが、廃業手続きを行わずに放置すると、税務署や自治体への申告漏れ、二重課税のリスクなどが生じる可能性があります。
本記事では、法人成り後に個人事業を廃業しない場合のメリット・デメリット、注意点、そして廃業手続きの流れについて解説します。
目次
法人成り後に個人事業主を廃業しないメリット

法人成り後に個人事業主を廃業しないメリットとして、以下の3つが挙げられます。
- 所得税の負担を軽減できる
- 損益通算を活用した節税効果が期待できる
- 不動産所得の税務申告で控除できる場合がある
所得税の負担を軽減できる
法人成り後に個人事業主を廃業せず残しておくことで、場合によっては個人事業としての税制上の仕組みを引き続き利用できる可能性があります。
たとえば、個人事業に限り認められている「青色申告特別控除」や「青色事業専従者給与控除」は、法人化した会社には適用されません。そのため、個人事業を並行して継続している場合に限り、こうした制度を活用できる余地があります。
ただし、個人事業を廃業しないことで必ずしも税負担が軽くなるとは限りません。法人と個人の双方で申告や納税義務が発生するため、事務負担や社会保険料などを含めると、むしろ不利になるケースもあります。したがって、個人事業を残すか廃業するかは、事業の内容・所得の状況・将来の見通しなどを踏まえ、専門家に相談した上で判断することが重要です。
参考:国税庁|青色申告特別控除
損益通算を活用した節税効果が期待できる
法人成り後も個人事業を廃業せずに残しておくことで、その個人事業で発生した赤字を、一定の所得と損益通算できる可能性があります。
損益通算とは、事業で出た赤字を他の所得と相殺して、課税される所得を減らせる仕組みです。例えば、個人事業で赤字が出た場合に、不動産所得や譲渡所得などがあれば、それらの黒字と通算して課税所得を圧縮でき、結果として税負担が軽くなることがあります。
ただし注意が必要なのは、法人から受け取る役員報酬(給与所得)は損益通算の対象外という点です。つまり、法人化して役員報酬を得ている場合でも、その給与所得と個人事業の赤字を直接相殺することはできません。
それでも個人事業を残しておけば、不動産所得や一時的な資産売却益などとの損益通算による節税余地があるため、廃業せずに維持するメリットが出るケースもあります。
参考:国税庁|損益通算
不動産所得の税務申告で控除できる場合がある
法人成り後に個人事業主を廃業しないことで、不動産所得が生じた場合に控除を活用できる場合があります。そのため、法人成り後でも、個人として不動産収入がある場合は、個人事業の廃業届を提出するタイミングについて慎重に検討する必要があるでしょう。
例えば、自宅の一部を利用して飲食業を営んでいた方が法人化した場合、法人に店舗部分を賃貸することで、個人として家賃収入を得られるケースがあります。この場合、事業所得はなくなりますが、新たに不動産所得が発生します。
不動産所得についても、一定の要件を満たせば青色申告特別控除などの制度を活用できる可能性があります。ただし、事業所得と不動産所得では収入や経費の区分や必要な帳簿の作成方法が異なるため、申告にあたっては注意が必要です。
参考:国税庁| 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
法人成り後に個人事業主を廃業しないデメリット
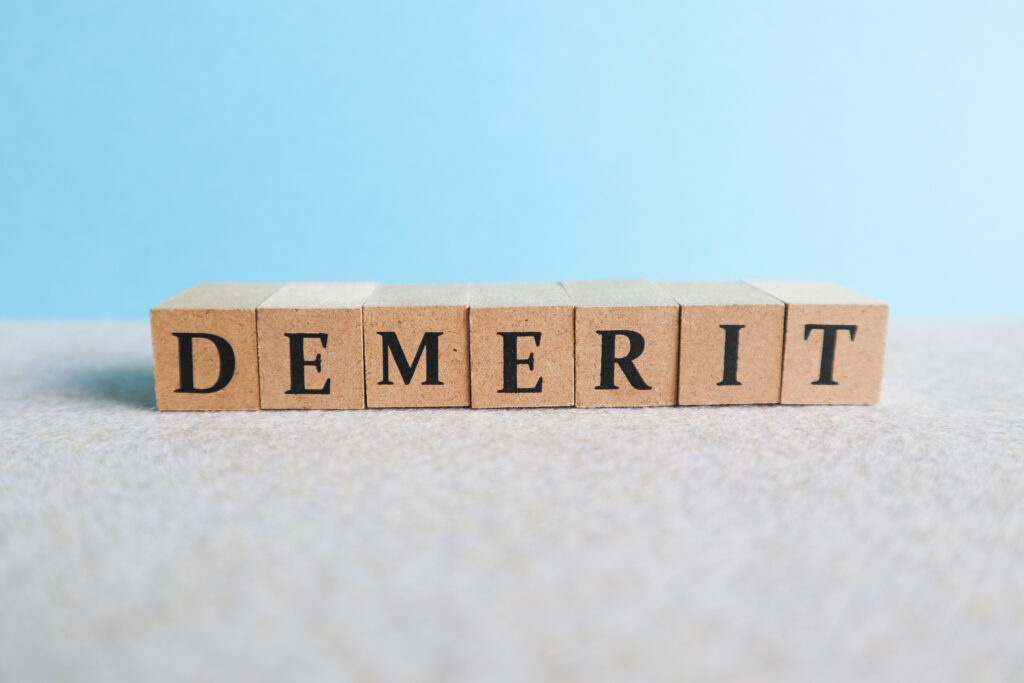
法人成り後に個人事業主を廃業しないデメリットとして、以下の5つが挙げられます。
- 法人と個人事業の売上が少なくなる
- 融資審査で不利になる可能性がある
- 事務作業の手間が増える
- 利益相反取引のリスクがある
- 取引先を混乱させてしまう要因になる
法人と個人事業の売上が少なくなる
法人成り後に個人事業主を廃業しない場合のデメリットの一つとして、収益の見え方が分散してしまう点が挙げられます。
具体的には、個人事業と法人を並行して運営すると、売上や利益がそれぞれに分かれて計上されるため、法人単体での事業規模が小さく見えることがあるのです。
その結果、金融機関からの融資や取引先からの評価において、法人としての事業実績や信用力を十分に示しにくくなるケースもあるため注意が必要です。
融資審査で不利になる可能性がある
法人成り後に個人事業主を廃業しないことによって、融資の際に不利になる場合があります。
法人成り後も個人事業を継続する場合、法人と個人事業は形式上別の存在として扱われるため、融資審査もそれぞれに対して行われます。
法人成りによって一部の売上が法人へ移行するケースがあり、その結果、個人事業の売上規模が以前より小さく見えることがある点に注意が必要です。ただし、融資審査では売上の推移も参考にされることがありますが、評価は売上だけでなく、資産状況や返済能力、事業計画など複数の要素を総合して判断されます。そのため、売上が一時的に減少しても、必ずしも不利になるとは限りません。
事務作業の手間が増える
デメリットの一つとして、記帳や税務申告の手間が増える点が挙げられます。
法人と個人事業を同時に運営する場合、それぞれ別に帳簿を管理する必要があるため、売上や経費の仕訳が複雑になりがちです。また、法人は決算申告、個人事業は確定申告を行う必要があるため、経理・税務関連の事務作業は増加します。
この負担を軽減するために税理士へ依頼する場合、法人・個人事業それぞれのサポートが必要となることがあり、費用が増える可能性があります。具体的な金額は業務量や契約内容によって異なるため、事前に確認することが重要です。
参考:国税庁|所得税の確定申告
利益相反取引のリスクがある
法人成り後に個人事業主を廃業せずに運営する場合、法人と個人事業で同じ人物が関与する取引では、利益相反の可能性が生じることがあります。
例えば、法人とその代表者が個人事業主として物品の売買や不動産の賃貸を行う場合、双方の利害が対立する可能性があります。その結果、どちらの利益を優先すべきかの判断が難しくなり、取引の公正性や透明性を確保できないことがある点に注意が必要です。
法人においては、利益相反取引を行う際には、株主総会での事前承認などの手続きが求められる場合があります。このような手続きを踏むことで、取引の適正性を確保することが可能です。
参考:厚生労働省|利益相反への対応に関する基本的な考え方
取引先を混乱させてしまう要因になる
法人成り後に個人事業を継続し、法人と個人の両方で同じ事業を展開する場合、取引先が「どちらと契約すべきか」と判断に迷うことがある点に注意が必要です。
特に、新規の取引先にとっては、法人と個人事業の区別が明確でない場合、取引の契約条件や責任の所在について不安を感じる可能性があります。
なお、事業の内容や対象が明確に分かれている場合は問題が生じにくいですが、同一の業務を両方で行う場合は、契約関係や取引先への説明方法を工夫することが重要です。
法人成りで個人事業主を廃業しない際の注意点

法人成りで個人事業主を廃業しない際の注意点として、以下の3つが挙げられます。
- 法人と個人事業が同じ事業をやらない
- 許可書は法人へ引き継がれない
- 記録を分けて管理する
法人と個人事業が同じ事業をやらない
法人成り後に個人事業を廃業せずに続ける場合は、法人と個人事業の事業内容が重複しないよう注意が必要です。
たとえば、同じ業種で双方が同じ取引を行い、それぞれ請求書を発行すると、税務署から誤解を受ける可能性があります。
そのため、個人事業を継続する場合には、業種や取扱商品・サービスを分けるなど、法人と個人事業の活動範囲を明確に区別して運営することが望ましいです。
許可書は法人へ引き継がれない
法人成りに際して個人事業主を廃業せず事業を継続する場合、行政から取得した許可や資格は、原則として法人に自動的に引き継がれません。
業種によっては、営業許可や各種資格の名義を個人から法人に変更する手続きが必要となる場合があります。
そのため、「法人名義で取得するのか」「個人名義で継続するのか」を事前に確認し、適切な手続きを行うことが重要です。
参考:厚生労働省|健康・医療営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報
記録を分けて管理する
法人と個人の活動を並行して行う場合は、それぞれの取引や記録を明確に区別して管理することが大切です。
具体的には、会計データや銀行口座、請求書・領収書などを混同せず、法人用と個人用で別々に管理しましょう。たとえば、ひとつの通帳で法人と個人の入出金をまとめたり、経費を共通で使用することは避けるのが望ましいです。
取引をきちんと分けて記録しておくことで、税務申告の際に資料として活用しやすくなり、外部からの信用も向上します。
参考:国税庁|法人税及び地方法人税の申告(法人税申告書別表等)
法人成りで個人事業主を廃業する流れ

法人成りにあたり、個人事業主を廃業する場合の主な流れは以下の通りです。
- 法人設立日を決める
- 廃業届を提出する
- 自治体へ届け出をする
- 消費税の事業廃止届出書を提出する
- 廃業年分の確定申告をおこなう
①法人設立日を決める
法人成りにあたり個人事業主を廃業する際、まず考えるべきは「会社をいつ設立するか」という日付の設定です。
設立日(法人登記日)は、個人事業の終了時期や各種手続きを進めるタイミングに関わる重要な要素です。
月の初めや月末など区切りの良い日を設立日として検討すると、個人事業と法人の会計期間が整理しやすく、税務処理をスムーズに進めやすくなる場合があります。
ただし、最適な設立日は事業内容や収支状況によって異なるため、事前に税理士に相談して判断することをおすすめします。
②廃業届を提出する
個人事業を廃業する場合は、所轄の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。提出は、廃業日から原則1か月以内に行うことが望ましいとされています。
この届出書は、税務署の窓口で受け取るほか、国税庁の公式サイトからもダウンロード可能です。
届出書には、マイナンバーや事業内容、廃業日などの必要事項を記入して提出します。なお、提出期限を過ぎても罰則は基本的にありませんが、手続きを早めに行うことで、税務上の手続きや今後の控除・申告の準備がスムーズになります。
参考:国税庁|個人事業の開業届出・廃業届出等手続
③自治体へ届け出をする
個人事業を廃業する際には、業種や地域によって、都道府県や市区町村への手続きが必要になることがあります。
例えば、飲食業や古物商など、営業許可・登録が必要な事業を行っていた場合は、許可の返納や関連書類の提出が求められることがあります。また、個人事業主の場合は、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。
必要な手続きや書類の詳細は自治体によって異なるため、事前に該当する市区町村や税務署の公式Webサイトで最新情報を確認することが重要です。
④消費税の事業廃止届出書を提出する
個人事業主として消費税を納めていた方が法人化を行う場合、所轄の税務署へ「消費税の事業廃止届出書」の提出が必要です。この届出を提出しない場合、法人化後も個人として消費税の納税義務が生じるケースがあります。
また、法人化後はインボイス制度などの影響により、法人として課税事業者に該当するかどうかを確認する必要があります。
このような判断は状況により異なるため、税理士などの専門家に相談しながら手続きを進めることが、トラブルを防ぐ上で大切です。
参考:国税庁|事業廃止届出手続
⑤廃業年分の確定申告をおこなう
個人事業を廃業した年であっても、その年に発生した収入については、個人として確定申告を行う必要があります。
収入や必要経費を整理して所得を算出し、所得税および住民税を納めます。
また、廃業と同時期に法人を設立した場合は、個人事業と法人それぞれの所得について別々に申告が必要となることがあります。申告スケジュールを事前に確認し、計画的に準備することが重要です。
確定申告の提出期限は原則として翌年の3月15日までですので、廃業後も期限を意識して余裕をもって準備を進めましょう。
参考:国税庁|所得税の確定申告
廃業するかどうか慎重に判断しよう!

今回は、法人成り後に個人事業主を廃業しない場合のメリット・デメリットについて解説しました。
事業を法人化した後も、一部の事業を個人事業として継続することは法律上可能です。
個人事業主を廃業しないことで、場合によっては所得税の負担軽減や損益通算を活用した節税の効果が期待できるケースもあります。
一方で、金融機関による融資の審査や、税務署の調査対象となる可能性がある点にも注意が必要です。
法人成り後に個人事業を継続するか廃業するかは、税務面・資金面を踏まえて慎重に判断することをおすすめします。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。





