メニュー
法人化
ホステスが法人化(法人成り)するタイミングとは?メリット・デメリットや手順も紹介

読了目安時間:約 7分
ホステスなど接客業に携わる方でも、一定の収入規模や事業の将来性を見据えて法人化(法人成り)を検討するケースがあります。
法人化には、節税効果や取引先・金融機関からの信用力向上といったメリットが期待できる一方、設立や維持にかかるコストや手続きの複雑さといった注意点もあります。法人化の判断をする際には、収入規模や事業計画に加えて、税務・社会保険の負担を総合的に考慮することが重要です。
この記事では、接客業を営む個人事業主の方が法人化を検討する際のタイミングやメリット・デメリット、手続きの流れについて解説します。
目次
ホステスが法人化(法人成り)するタイミング

事業を法人化(法人成り)するタイミングについては、一般的に以下のような目安が挙げられます。
- 年間利益が600万円を超えたタイミング
- 売上が1,000万円を超えるタイミング
- 事業を拡大するタイミング
それぞれの項目について解説していきます。
年間利益が600万円を超えたタイミング
年間利益が600万円を超えてくると、個人事業主のままよりも法人化した方が、税制面で有利になるケースが見られます。
個人事業主は累進課税が適用され、所得が増えるにつれて税率が上がり、最高で45%に達します。
一方、法人の場合は、法人税・地方法人税・法人住民税・事業税などを合算した実効税率が適用され、一定の所得を超えると税率がほぼ一定になります。ただし、法人化に伴い社会保険料の負担が発生することや、経費計上の可否などによって実際の有利・不利は異なります。
そのため、利益が600万円前後となった段階は、法人化を検討する一つの目安と捉え、専門家に相談しながら判断することをおすすめします。
参考:財務省|法人課税に関する基本的な資料
売上が1,000万円を超えるタイミング
個人事業主が法人化(法人成り)するタイミングとして、年間の課税売上高が1,000万円を超えるケースが挙げられます。
年間の課税売上高が1,000万円を超えると、原則としてその2年後から消費税の納税義務が発生します。例えば、2年前の売上が1,000万円を超えていれば、今年は消費税を納める必要があるという仕組みです。
一方で、新たに法人を設立した場合は、個人事業の売上実績は原則引き継がれないため、法人としての消費税の納税義務判定は設立後の売上を基準に行われます。ただし、2023年10月に導入されたインボイス制度やその他の要件によっては、売上が1,000万円以下でも課税事業者として登録が必要になる場合があるため注意が必要です。
参考:国税庁|納税義務者
事業を拡大するタイミング
事業を法人化(法人成り)することで、法人を対象にした取引の機会が広がったり、金融機関からの融資や資金調達の選択肢が増えたりと、事業発展につながるメリットがあります。
実際に、取引条件として「法人格を有していること」を求める企業も見られるため、法人化が新たなビジネスチャンスにつながる可能性があります。
また、法人という形態は、個人事業に比べて第三者から一定の信用を得やすい傾向があるため、営業活動や銀行との交渉でプラスに作用するケースもあります。
このように、事業の成長や規模拡大を目指している場合には、法人化を検討する価値があるでしょう。
ホステスが法人化(法人成り)するメリット

ホステスが法人化(法人成り)するメリットについてとしては、以下の4つが挙げられます。
- 節税対策になる
- 社会的信用度が高くなる
- 有限責任に限定される
- 社会保険に加入できる
それぞれのメリットについて解説していきます。
節税対策になる
法人化には、場合によって節税効果が期待できるメリットがあります。
個人事業主として所得が増えると、所得税は累進課税により税率が上がります。一方で、中小法人の場合、法人税には軽減税率が適用されるため、利益規模によっては法人化することで税負担が軽くなるケースがあります。
また、法人化して役員報酬として給与を支給する場合、給与所得控除を受けられるなど、個人事業主では利用できない税制上の仕組みを活用できる場合があります。
ただし、法人化には設立費用や社会保険料の負担なども伴うため、必ず節税になるわけではありません。事業規模や収益状況に応じて、専門家に相談することが重要です。
社会的信用度が高くなる
株式会社などの法人形態には、個人事業主と比べて一定の社会的信用度があるとされています。
例えば、金融機関からの資金調達においては、法人名義での申し込みが審査上有利になるケースも見られます。
また、一部の取引先やサービスでは、法人向けの契約条件や料金体系が適用される場合もあります。
このように、法人化することで、事業上の信用や取引条件において個人事業主と比べてメリットが得られる可能性があります。ただし、業種や取引先によって状況は異なるため、具体的な影響については専門家に相談することが望ましいです。
有限責任に限定される
法人化すると、原則として経営者個人の責任は有限となります。
具体的には、法人が負う債務については、法人の資産の範囲内で返済義務が生じます。一方、個人事業主の場合は、事業上の借入れや債務に対して個人資産も含めて返済責任を負うことになります。
このため、法人化により個人資産の保護が可能となり、リスクを管理しながら事業活動を行いやすくなる点がメリットとして挙げられます。
社会保険に加入できる
法人化した場合、原則として社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必要になる場合があります。
ただし、役員1人の法人や従業員がいない場合など、加入義務の有無は条件によって異なりますので注意が必要です。
社会保険に加入すると、従業員の医療費負担や老後の生活を支える仕組みを整えることができます。また、加入することで職場環境の整備や従業員の安心感の向上につながる可能性があります。
このように、社会保険への加入は企業運営や人材確保の一助となる場合がありますが、効果の程度は企業の状況によって異なります。
参考:厚生労働省|社会保険加入のメリットや手取りの額の変化について
ホステスが法人化(法人成り)するデメリット
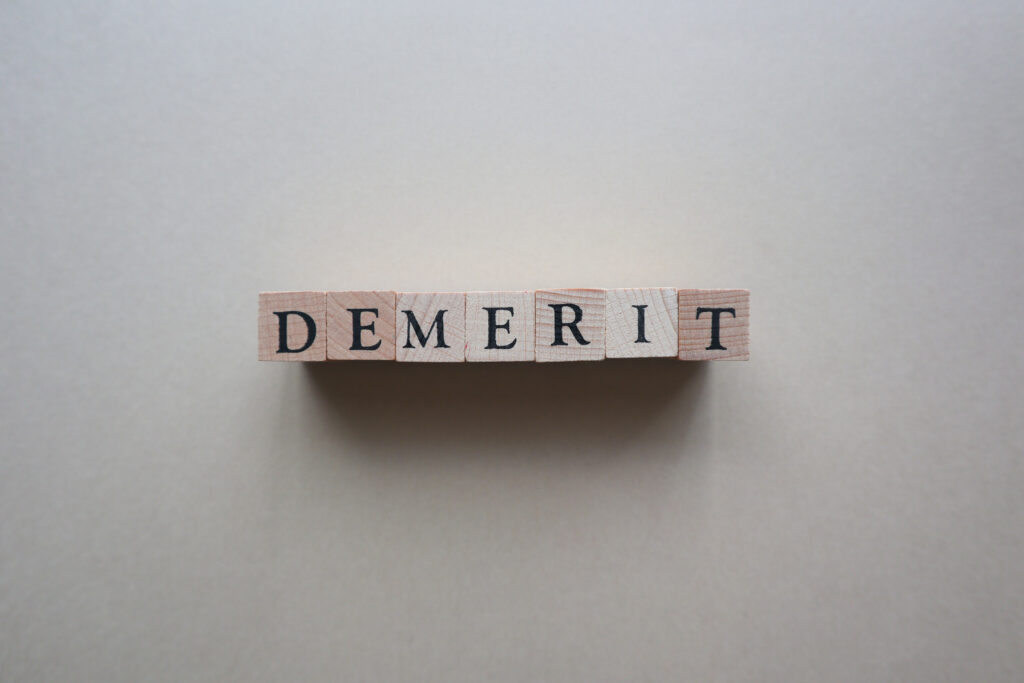
ホステスが法人化(法人成り)するデメリットとして、以下の3つが挙げられます。
- コストがかかる
- 赤字でも税金を支払う必要がある
- 事務作業の負担が増える
それぞれのデメリットについて解説していきます。
コストがかかる
法人化には、設立に伴うコストや事務負担がある点に注意が必要です。
具体的には、定款の作成・認証、法務局への登記申請など複数の手続きを行う必要があります。株式会社の場合は、登録免許税や公証役場での定款認証料などがかかり、設立時の初期費用が合同会社よりも高くなる傾向があります。
設立費用の目安としては、合同会社で6万円〜10万円、株式会社で20万円〜30万円程度が一般的です。なお、資本金は別途準備が必要です。
また、法人化すると経理や税務申告、法務手続きが複雑化するため、税理士や会計士など専門家に依頼することで、正確かつ効率的に業務を進めることができます。専門家への報酬は別途必要になりますが、適切な運営や節税の観点からは有益な投資といえます。
参考:法務局|商業・法人登記申請手続
赤字でも税金を支払う必要がある
ホステスが法人化する場合のデメリットの一つとして、赤字であっても一定の税金負担が発生することが挙げられます。
個人事業主であれば、事業が赤字の場合は所得税や住民税の課税は基本的に発生しません。しかし、法人の場合は事業年度の損益が赤字であっても、「法人住民税の均等割」と呼ばれる固定的な税金が課されます。金額は規模や所在地によって異なりますが、目安として年間数万円から十数万円程度となることがあります。
このため、まだ安定的な利益が見込めない事業者が法人化を検討する場合は、こうした固定コストもあらかじめ考慮して判断することが重要です。
参考:総務省|地方税制度|法人住民税
事務作業の負担が増える
法人化すると、毎年決算を行い、それに基づいて法人税の申告書を作成する必要があります。法人税の申告は、個人の確定申告よりも手続きや計算の範囲が広くなるため、専門知識があると安心です。そのため、多くの法人では税理士に依頼し、顧問契約の形で決算や税務申告をサポートしてもらうことが一般的です。
すでに個人事業の段階で税理士に確定申告を依頼していた場合でも、法人化に伴い税務処理の範囲が広がることがあります。その場合、税理士のサポート内容によっては報酬が増えることもありますが、事前に相談して見積もりを確認することで安心につながります。
ホステスが法人化(法人成り)する手順
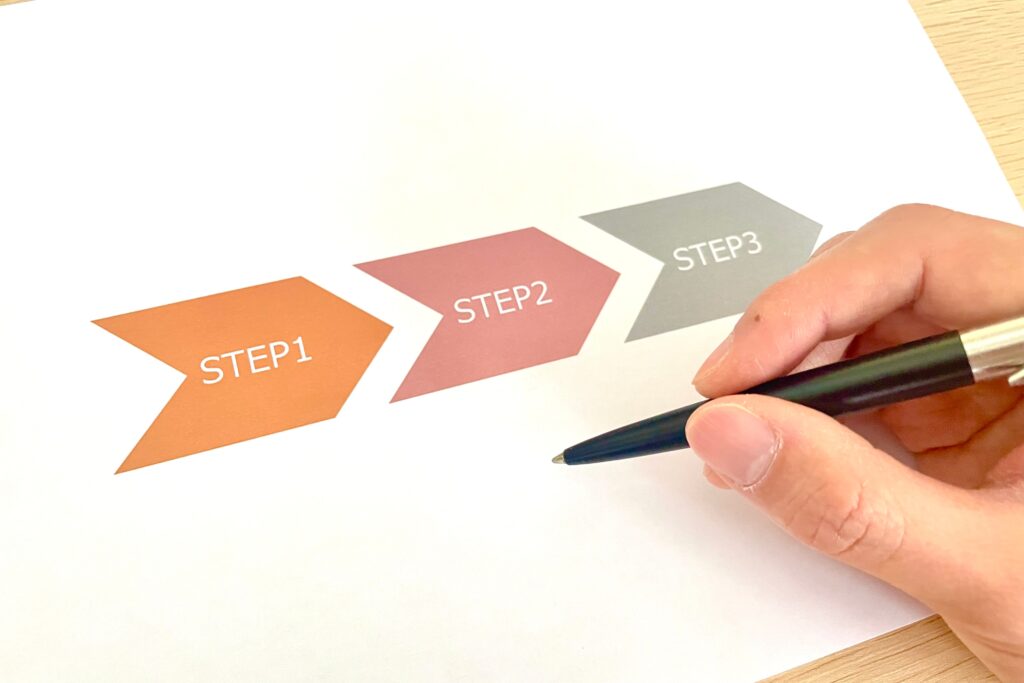
ホステスがが法人化(法人成り)する際の一般的な手順は、以下のように進めます。
- 基礎事項を決める
- 定款作成と認証を受ける
- 資本金の払い込みをおこなう
- 法務局に登記申請をする
それぞれの手順について解説していきます。
①基礎事項を決める
個人事業主が法人化する際には、手続きをスムーズに進めるため、あらかじめ決めておくべき基本事項があります。
具体的には、以下の項目が挙げられます。
- 法人化のタイミング
- 資本金の額
- 会社内部の組織体制や意思決定機関の構成
- 設立する会社の名称(商号)と使用可能性の確認
- 法人としての事業内容(事業目的)
これらを事前に整理しておくことで、設立手続きの途中で迷うことが少なくなり、スムーズに進めやすくなります。
特に定款に記載する事業目的は重要で、不明確な記載の場合には登記手続きにおいて補正が必要となることがありますので、慎重に検討してください。
また、資本金の額や設立時の費用は、法人設立後の均等割の税額や初期の運営コストに影響する場合があります。事前に十分に検討することをおすすめします。
②定款作成と認証を受ける
基礎事項を決定した後、それらの内容をもとに 定款と呼ばれる書面を作成し、公証役場での正式な認証手続きを行います。
定款とは、会社の運営や組織に関する基本的なルールをまとめた書面で、会社の目的、商号(会社名)、本店所在地などの重要事項が記載されます。
従来は紙で作成するのが一般的でしたが、現在では電子データでの作成も認められており、一定の条件を満たせばオンラインでの手続きも可能です。ただし、電子署名や認証手数料など、専門的な手続きが必要となります。
定款はご自身で作成して認証を受けることもできますが、内容や手続きの正確性を重視する場合には、行政書士や司法書士などの専門家に相談・依頼する方法もあります。
参考:日本公証人連合会|定款等記載例(Examples of Articles of Incorporation etc)
③資本金の払い込みをおこなう
次に、会社設立時には事業の運転資金となる「資本金」を用意する必要があります。
資本金は、会社設立の法的要件を満たすために発起人が払い込む資金であり、払い込みが行われたことを証明する書類の作成が求められます。
具体的には、発起人が自身の資金を用意し、設立予定の会社に対して払い込みを行うことで、払い込み証明書を作成することが可能です。この証明書は、設立登記申請時に提出する重要な書類のひとつとなります。
④法務局に登記申請をする
最後に、会社設立の手続きとして法務局に登記申請を行います。
登記申請の際に必要となる主な書類は以下の通りです。
- 登記申請書
- 定款(会社の基本ルールを定めた文書)
- 発起人による決議書
- 資本金の払込を証明する書類
- 印鑑証明書
- 印鑑届出書
会社の形態や運営体制によって、提出書類が追加で必要となる場合がありますので、事前に確認しておくことが重要です。
登記申請は、所轄の法務局窓口に直接提出する方法のほか、郵送での申請も可能です。
申請後、通常は1〜2週間程度で手続きが完了し、会社設立が正式に認められます。
ホステスが法人化(法人成り)をスムーズに進めるポイント

ホステスが法人化(法人成り)をスムーズに進めるポイントとして、以下の2つが挙げられます。
- 税理士などの専門家に相談する
- 各種ツールを活用する
それぞれのポイントについて解説していきます。
税理士などの専門家に相談する
法人化をスムーズに進めるためには、税理士などの専門家に相談することが有効です。
会社設立に関わる手続きは多岐にわたり、書類作成や法務手続きなどを個人だけで進めるのは容易ではありません。
そのため、税務・法務・社会保険など、それぞれの分野に精通した専門家のサポートを受けることをおすすめします。
専門家に依頼すると一定の費用は発生しますが、煩雑な手続きの負担を軽減でき、確実かつ効率的に法人設立を進められるというメリットがあります。
参考:税理士法人松本
各種ツールを活用する
法人化すると、個人事業主に比べて手続きや事務作業が増えるため、設立時から効率化を意識して準備することが重要です。
例えば、日々の経理業務や税務処理には、会計ソフトの導入が有効です。こうしたソフトを活用することで、日常の記帳作業を効率化したり、年度末の申告準備をスムーズに進めたりすることができます。
また、会社設立に関わる書類作成についても、法人設立支援ソフトを併用することで、定款の作成や登記申請書の作成を補助することが可能です。ただし、社会保険の手続きや法的な確認が必要な部分については、専門家である税理士や社会保険労務士に相談しながら進めることをおすすめします。
ホステスが法人化する最適なタイミングを見極めよう!

今回は、個人事業主として働く方が法人化(法人成り)を検討する際のタイミングについて解説しました。
法人化を考える場合、会社の形態や資本金、設立手続きなど、考慮すべき要素は多岐にわたります。 開業当初から法人としてスタートする選択肢もあれば、一定期間は個人事業として運営し、収益が安定した段階で法人化するという流れもあります。
手続きや税制の仕組みを踏まえると、一般的には収益や事業規模が安定した段階で法人化を検討するのが現実的です。ただし、最適なタイミングは事業内容や個々の状況によって異なるため、税理士など専門家に相談しながら判断することをおすすめします。
本記事を参考にして、法人化に向けた準備やタイミングを見極めていきましょう。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。





