メニュー
会社設立
ブラックでも融資を受けられる?信用情報に不安がある場合の資金調達方法と成功させるポイント
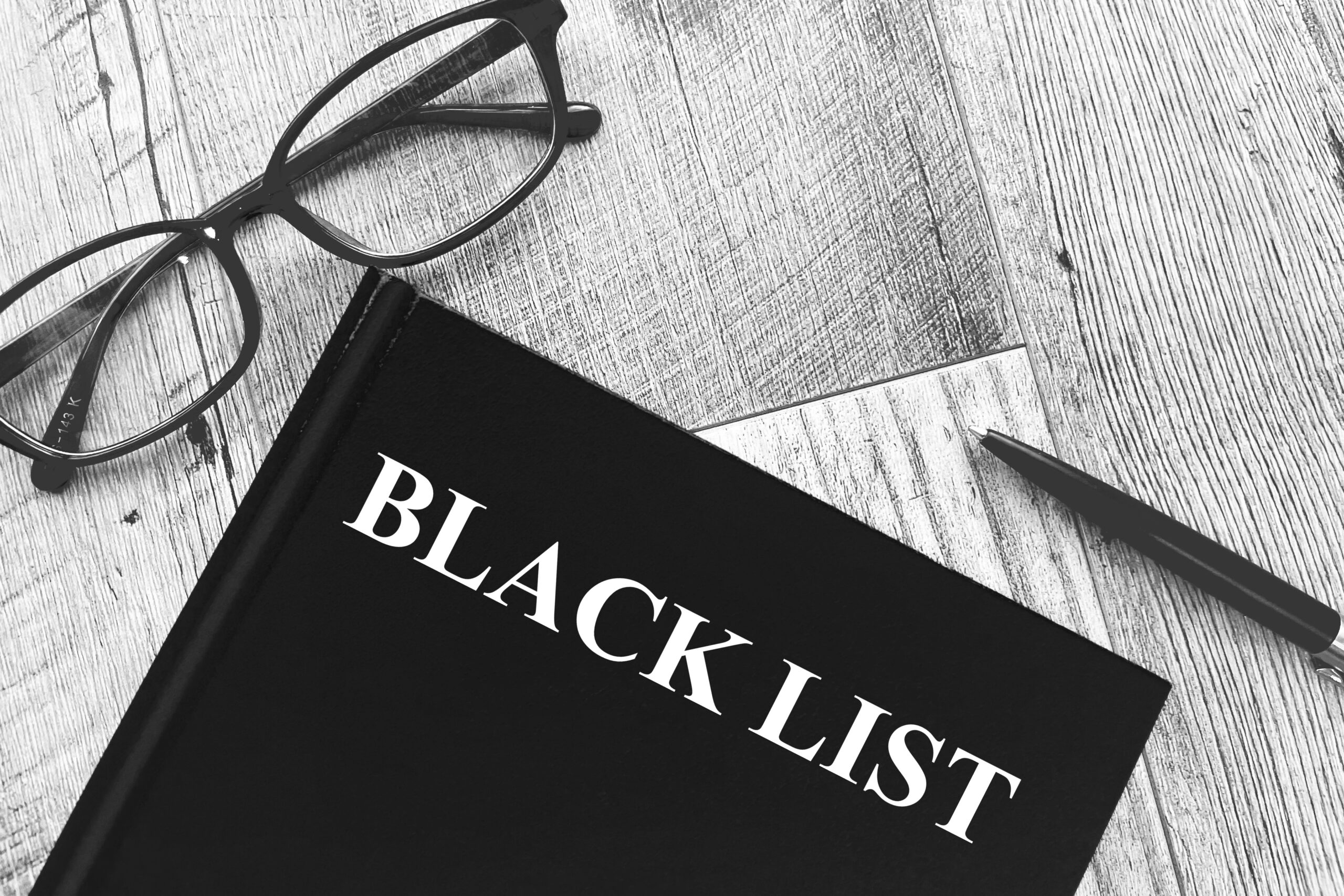
読了目安時間:約 7分
信用情報に不安な点がある、いわゆる「ブラック状態」では、銀行や信用金庫からの資金調達は難しくなる傾向があります。
しかし、信用情報に不安があっても、説得力のある売上計画や返済計画が立てられていれば、融資を受けられる場合があるほか、公的融資や制度融資、融資以外の資金調達手段を活用すれば、事業継続のための資金を確保できる可能性があります。
本記事では、ブラック状態でも融資を受けるためのポイントや、審査に落ちる原因、その他の資金調達方法をわかりやすく解説します。
目次
融資審査に落ちる主な原因

融資に通るかどうかは金融機関の審査基準によって異なりますが、「返済できるか」「事業が継続できるか」「信頼できるか」という3点が中心となります。
そのため、これらに不安があると判断された場合、審査で否決となる場合があるので注意が必要です。
ここでは、審査に落ちる代表的な原因と、改善に向けて考えるべき視点を解説していきます。
信用情報に問題がある
クレジットカードやローンの延滞、債務整理、代位弁済などの履歴は信用情報機関に記録され、金融機関はこれを照会します。
いわゆる「ブラック状態」の場合、銀行や信用金庫での新規融資は難しくなります。
ただし、信用情報の履歴は永続的に残るわけではなく、数年で消えるケースが多いです。また、後述しますが、信用情報に問題があっても公的融資や保証協会付き融資を受けられるケースもあります。
納税・社会保険の未納や滞納がある
税金や社会保険料をきちんと納めているかは、「経営者としての責任感」を判断するうえで大切な要素です。
そのため、未納や滞納がある場合、資金繰りがすでに逼迫していると見られ、融資は通りにくくなる場合があります。なお、金融機関は税務署や年金機構に確認をすることもあります。
もし、未納がある場合は、分納手続きを行うなどして「支払い計画を立てて実行している」状態にすることが信用を回復する第一歩となります。誠実な対応を心がけるようにしましょう。
参考:日本年金機構
直近の決算で赤字が続いている
赤字決算は「事業が現在うまく回っていない」と判断されることがあるため、融資は慎重になります。
ただし、赤字であっても黒字化の根拠が説明できる場合には融資が通ることがあります。例えば、新規投資が一段落し利益が見込める状態である場合や、一時的な売上減の要因が明確で改善策が実行されている場合などが挙げられます。
金融機関は現状の数字だけではなく、事業の持続性や改善の可能性も見ていることを把握しておきましょう。
自己資金が極端に少ない・資本金が薄い
自己資金が少なく「借入でまかないたい」という状態は、金融機関からはリスクが高いと見られる可能性があります。
経営者自身が事業にどれだけ覚悟と責任を持って投資しているかを示す指標となるのが「自己資金」や「資本金」です。資金が極端に少ないと、事業が少しつまずいただけで資金繰りが悪化し、返済が滞る可能性があります。
そのため、事業計画を立てる際には、借入に依存しすぎず、自己資金と借入のバランスを重視した計画が求められます。
参考:国税庁|資本金等の額及び資本等取引
資金使途が曖昧・売上計画や返済計画に根拠がない
融資が必要な理由(資金使途)が曖昧だったり、売上計画が「希望的観測」に近い数字で作られている場合、金融機関から信用できないと判断される場合があります。
特に「事業計画に根拠があるか」どうかは審査で重視されやすいポイントです。
設備投資なら見積書、人件費なら配置計画、売上見込みなら顧客・販路・契約見込み、といったような裏付け資料を提出するのが望ましいです。「なぜ必要で、どう回収し、返済できるのか」を言葉と数字で説明できると良いでしょう。
既存借入が多く返済比率が高い
既存借入が多い場合、毎月の返済負担が重くなり、新たな返済能力が低いと見なされます。金融機関は返済比率(キャッシュフローに対して返済が占める割合)を基準に判断を行う傾向があります。
返済比率が高いほど、新規融資は難しくなる傾向があるので注意が必要です。
改善策としては、返済条件の変更、借入の一本化、利益率改善などが挙げられます。返済できる仕組みがあると判断されると、融資を受けられる場合があります。
事業の持続性・業界の安定性に不安がある
事業そのものが将来の収益を確保できるかどうかは融資判断ポイントとなり得ます。
例えば、市場縮小が続く業界や、依存先が一社しかないケースなどでは、事業継続リスクが高いと見られることがあります。しかし、それだけで融資が不可になるわけではありません。
改善策や他社との差別化、新規販路開拓、利益強化のための対策を説明できるかが重要です。金融機関は現在だけでなく未来の数字も見るため、持続性を示すには、現状分析と改善行動の提示が求められます。
ブラックでも融資は可能?融資審査で見られる信用情報の仕組み

融資審査では、企業の決算書や事業計画だけでなく、経営者個人の「信用情報」も重視されます。信用情報とは、ローンやクレジット支払いなど、金融取引の履歴を記録したデータのことです。
延滞や債務整理がある場合、いわゆる「ブラック状態」とされ、銀行融資は非常に通りにくくなります。ただし、信用情報は永続的に残るものではなく、また金融機関の種類によって審査の視点も異なります。
ここでは、信用情報の仕組みや履歴が残る期間、そしてブラックでも融資が受けられる可能性について解説します。
金融ブラックになる主な原因
ブラック状態になる主な原因は、クレジットカードやローンの延滞、強制解約、代位弁済、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)などです。
こうした金融事故情報は信用情報機関に記録され、金融機関は融資審査の際に照会する場合があります。
そのため、たとえ事業が順調でも、個人の信用情報に事故があると「返済管理能力に問題がある」と判断され、融資が難しくなることがあります。
信用情報機関(CIC・JICC・KSC)とは?何を管理している?
信用情報は、国内3つの信用情報機関によって管理されています。
- CIC:主にクレジットカードやショッピング取引
- JICC:消費者金融、カードローン、リースなど
- KSC(全銀協):銀行・信用金庫・信用組合などの金融事故情報
これらの機関は情報を相互に交流しており、銀行はほぼ全ての信用情報を確認できます。
記録される内容は、「契約日・利用額・返済状況・延滞履歴・債務整理の有無」などがあり、融資審査においては数字や事業計画だけではなく、これらの情報も評価対象となるのです。
延滞や債務整理はどのくらい履歴が残るのか
延滞の履歴は一般的に 5年、任意整理や代位弁済は 5年〜7年、個人再生や自己破産は5年〜10年記録が残るとされています。
記録が残っている期間は、金融機関での新規融資が難しくなりますが、期間が過ぎれば信用情報は復旧し、再び融資を受けられることもあるでしょう。
また、履歴が残っている期間であっても、返済意思・資金繰り管理能力・事業の再建性などが証明できれば、融資が通るケースもあります。
公的機関の融資なら受けられる可能性がある
ブラック状態で民間銀行の融資が通らなかった場合でも、公的融資を活用することで、融資の可能性が残されている場合があります。日本政策金融公庫は、民間銀行とは異なり「中小企業・小規模事業者の支援」を目的とした政府系金融機関です。
融資基準は民間より厳しい場合もありますが、信用情報だけで審査を否定するのではなく、審査では過去よりも事業の将来性・改善可能性・返済計画の実現性を重視する傾向があります。
そのため、過去に延滞や返済トラブルがあった場合でも、再発防止策が明確であれば融資が通る可能性があります。
参考:日本政策金融公庫|融資制度を探す
自治体の制度融資を活用する方法もある
自治体の制度融資は、各都道府県や市が信用保証協会と金融機関と連携して行う融資制度で、金利が低く、保証料補助がつく場合もあるため、資金繰り改善に有効です。
ブラック状態であっても、税金・社会保険の滞納がなく、改善計画が明確であれば審査の余地がある点が特徴です。
また、自治体の商工相談窓口や商工会議所で、事業計画書作成や申請手続きの支援を受けることができるため、個人で金融機関へ直接交渉するよりも成功率が高まります。
参考:制度融資の活用 | 起業マニュアル – J-Net21 – 中小機構
ブラックでも融資を受けるためのポイント

信用情報に問題がある状態でも、すぐに融資を諦める必要はありません。
金融機関は単に過去の履歴だけを見ているのではなく、現在の経営状況や再建の見込みなどを総合的に評価します。そのため、たとえブラックでも再起できる根拠を示すことができれば、融資につながる可能性はあります。
ここからは、ブラックでも融資検討が可能となる具体的な対策を解説します。
資金繰り表と返済計画を明確にする
金融機関が最も重視するのは「返済可能性」です。そのため、毎月の入金・支払・借入返済を時系列で整理した資金繰り表が重要になります。
資金繰り表がない状態で融資を申し込むと、「経営状況を把握できていない=返済能力に不安がある」と判断される場合があります。
また、返済計画は希望額から逆算するのではなく、現実的に返済できる範囲から算出することが大切です。数字に基づいた説明ができるほど、金融機関の信頼は高まります。
参考:日本政策金融公庫|資金繰り表
資金使途を具体的に説明できるようにする
「なぜこの資金が必要なのか」を明確に説明できることは、融資審査において非常に重要です。ただ「資金が足りない」「運転資金が必要」という抽象的な説明では信用されない可能性があります。
仕入費用なら見積書、設備投資なら型番と用途、売上向上に関わる支出なら販路や顧客の情報など、裏付け資料を揃えることで説得力が高まります。
金融機関は「お金の使い道が明確で、返済につながるか」という点も見ています。そのため、資金使途と収益改善の関係性を言語化して整理しておくことが大切です。
取引実績のある金融機関に相談する
融資の相談は、これまで取引関係のある金融機関を検討することも有効です。取引実績のある金融機関は、入出金の動きや事業規模を把握しているため、現状の説明がしやすく、理解を得やすい傾向があります。
また、新規の金融機関と違い「連続した取引と関係性」を評価する場合もあります。
担当者とのコミュニケーションが取れている場合は、事業改善計画や資金繰りの状況を共有することで、融資以外の支援やリスケジュールの提案を受けられる可能性があります。
税理士に事業計画書と交渉をサポートしてもらう
融資審査では、数字と計画に基づく説明が不可欠ですが、経営者が日々の業務の中で計画書を整えるのは簡単ではありません。
税理士のサポートを受けることで、事業計画書の内容に整合性が生まれ、金融機関から「管理体制が整っている事業者」と評価されやすくなります。
また、税理士は金融機関との交渉経験があることが多いため、適切な説明方法や提出資料の整え方までアドバイスを受けることが可能です。結果として、融資の可能性を高めることにつながります。
融資以外で検討しておきたい資金調達方法

ブラック状態で金融機関の融資が難しい場合でも、資金を確保する方法は複数あります。
ここでは、融資以外に検討できる資金調達の方法について詳しく説明しますので、参考にしてください。
ファクタリング
ファクタリングは、売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらい、入金前に資金を確保する方法です。
融資と異なり「借入」ではないため、信用情報に事故があっても利用しやすい点が特徴です。
ただし、手数料は金融機関の金利よりも高い傾向があり、継続利用すると資金繰りを圧迫する可能性もあります。利用する際は、本来の売掛入金までの期間を埋める短期資金対策として捉え、必要な局面に限定して活用することがポイントです。
参考:金融庁|ファクタリングの利用に関する注意喚起
クラウドファンディングの活用
クラウドファンディングは、事業の理念や新商品・新サービスの価値を提示し、不特定多数から資金を集める方法です。
「共感」が資金調達の軸になるため、信用情報に不安があっても可能性があります。特に、地域密着型の店舗開業、商品開発、社会貢献型のプロジェクトと相性がよい手法です。
また、支援者との関係性を深めることで、顧客基盤の拡大・販路形成につながる点もメリットとなります。資金調達だけでなく支援者を巻き込む広報効果が得られる場合があります。
補助金・助成金の活用
国や自治体が用意する補助金・助成金は、一般的に返済義務がない点が大きな魅力です。
ただし、採択率がある・申請書類が複雑という課題があります。そのため、商工会議所、自治体支援窓口、税理士・中小企業診断士などのサポートを受けながら申請するのが有効です。
補助金は主に設備投資・IT導入・販路開拓といった新しい取り組みに対して支援する制度であるため、単なる資金不足ではなく、事業成長につながる計画であることを明確に示す必要があります。
参考:補助金ポータル|補助金・助成金・支援金をさがす
資産を増やす・支出を減らす
資金調達は「外部から入れる」だけではなく、「内部から生み出す・守る」ことを検討するのも有効です。特にキャッシュが不足している時は、利益よりも資金繰り(キャッシュフロー) が優先される傾向があります。
例えば、収益を圧迫している事業の整理や不要資産の売却、固定費の見直し、コストの変動費化などによって、毎月の資金流出を減らすことで、手元資金の持続性を高められます。また、設備や機械を購入せず、リース・レンタルで運用することで、初期費用を抑えつつ必要な資源を確保できる場合があります。
このように、経営を安定させるためには外部資金調達と同時に、内部改善を進めることも大切なポイントです。
課題を整理し利用できる資金調達方法を検討しよう

ブラック状態であっても、資金調達の道は完全に閉ざされているわけではありません。重要なのは、信用情報の問題を正しく理解し、資金使途や返済計画を明確に示すことです。
また、公的融資や制度融資の活用、ファクタリングやクラウドファンディング、補助金・助成金の利用、そして内部改善による資金確保など、複数の方法を検討することで、事業の安定化につなげられます。
まずは現状を整理し、信頼できる専門家のサポートを受けながら計画的に取り組むことが成功のポイントです。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。





