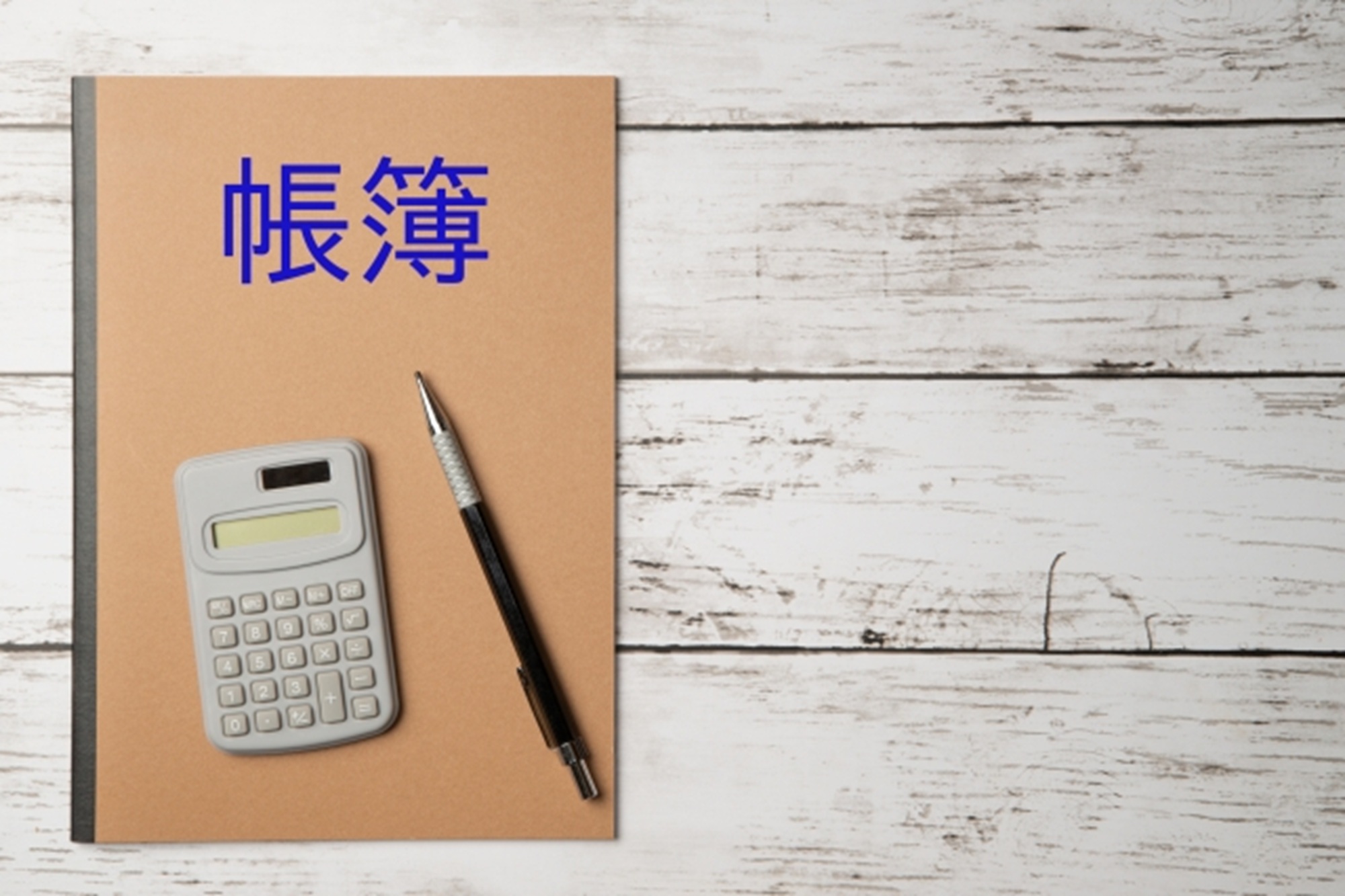メニュー
- 税務調査
申告漏れと脱税は何が違う?類似した言葉との違いやリスクを解説

読了目安時間:約 6分
ニュースを見ていると、所得隠しが発覚し、脱税した容疑で告発されたといった事例を見かけます。また、最近では、スポーツ選手が申告漏れによって追徴課税がなされ、修正申告を行ったというニュースもありました。申告漏れや脱税、所得隠しなどは、全て、税金を正しく納付しない行為につながるものです。しかし、税金の不正に関わる話題では、申告漏れや脱税など、似たような言葉が多いため、それぞれにどのような違いがあるのか分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、申告漏れと脱税など、類似した言葉の違いについて解説します。
目次
申告漏れと脱税の違いとは?
では早速、申告漏れと脱税の違いから確認していきましょう。
申告漏れとは
申告漏れとは、確定申告を行った際に、税金の額を本来納めるべき額よりも少なく申告することを指す言葉です。例えば、収入として報告しなければならない売上の一部を計上していなかった場合などは、申告漏れに該当します。また、フリマアプリやネットオークション、動画配信などで得た収入を申告していない場合、暗号資産の取引で得た収入の申告をしないといった行為も申告漏れにあたるものです。
このほか、収入を少なく申告することだけでなく、経費にできない支出を誤って経費計上してしまった場合も、申告漏れに該当します。また、適用されないはずの控除制度を誤って適用してしまった場合など、税法に関する理解が不足していたために生じた行為も申告漏れに含まれます。つまり、申告をしなかったという行為だけでなく、過少申告につながる行為全般を申告漏れと呼んでいるのです。
脱税とは
脱税とは、意図的に不正な行為をし、納税を免れようとしたり、納税する税金の額を低く抑えようとする行為です。特に、悪質な仮装・隠蔽行為などが見られ、多額の税金逃れをしていた場合を脱税と呼ぶことが多くなっています。
申告漏れと脱税の違い
申告漏れと脱税の違いは、意図的に税金を逃れようとしたかどうかという点です。申告漏れは、意図的ではなく、過失や税法についての理解不足などから、結果として納税額が不足してしまった事例を指します。一方、脱税は、意図的に現金で受け取った分の売上を低く申告していたり、架空の領収書を捏造して、経費を過大に計上したりといった行為が見られた場合に使われる言葉です。
脱税と所得隠しは何が違う?
意図的に、売上を低く申告するということは、所得の一部を隠す行為でもあります。そのため、脱税と所得隠しは何が違うのか疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。所得隠しとは、売上を隠蔽したり、書類の改ざんなどをして所得を隠すような行為のことです。
脱税も意図的に所得を低く申告する行為であり、両者に違いがあるわけではありません。所得隠しのうち、特に悪質な行為が認められ、刑事罰の対象となり得る可能性がある事例などを脱税と呼ぶケースが多くなっています。
申告漏れと脱税のペナルティの違い
申告漏れと脱税は、意図的に税金を逃れるための行為をしていたかどうかといった点に違いがあります。申告漏れに該当するのは、悪意があったわけではなく、ミスや知識不足などから納税額が不足してしまうケースです。一方、脱税は、支払う税金の額を少なくしようと意図的に不正を行うことを指します。したがって誤りの結果として納付すべき税額が少なくなったケースと意図的に税金の納付を逃れようとしたケースでは、課せられるペナルティも変わってくるのです。
申告漏れの場合は過少申告加算税が課される
税務調査によって申告漏れが発覚した場合、納税者には自主的に誤っている箇所を修正し、申告を行うとともに不足分の納税と加算税の納税が求められます。加算税にはいくつかの種類がありますが、申告漏れによって納付する税額が少なかった場合には「過少申告加算税」が適用されます。
過少申告加算税の税率は、10%です。ただし、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分についての税率は、15%となります。
脱税の場合は重加算税が課される
意図的に売上を隠蔽したり、経費を水増しするなどして、多額の納税を免れようとした脱税行為が発覚した場合には、重加算税が課されます。重加算税は、ミスによって申告額が少なくなってしまった場合に課せられる過少申告加算税に比べ、課される税率は重くなります。
過少申告加算税に代えて重加算税が課せられる場合の税率は35%です。また、そもそも確定申告をせず、多額の所得を意図的に隠していたような場合は、無申告加算税に代えて40%の重加算税が課されます。
さらに、過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがある納税者や前年度や前々年度に無申告加算税や無申告重加算税を課された納税者は、重加算税の税率がさらに10%加算されます。過少申告税の10%または15%に比べると、重加算税の税率は35~50%と非常に重たくなるのです。
脱税では刑事罰が科せられる可能性もある
意図的に不正を行い、消費税や法人税、所得税の納税を逃れようとするケースは脱税に該当し、脱税の場合、重加算税が課されるだけでなく、刑事罰も科される可能性があります。刑事罰とは、罪を犯し、刑事裁判で有罪が確定した場合に執行される処分のことです。つまり、脱税は犯罪行為として扱われるのです。
脱税行為が疑われる場合、裁判所の令状を持った国税局査察部の査察官が訪れ、予告なく、強制調査を始めます。納税者はこの調査を拒否することはできません。強制調査は、検察に告発することを目的に実行される調査です。帳簿や関係書類などは押収され、査察官と検察が協議をしながら所得状況について詳しい調査を進めます。
検察の捜査により逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがあると判断された場合などは、逮捕に至る可能性もあるのです。逮捕されると身柄を拘束され、10日間にわたって勾留されることとなります。勾留期間中も捜査は続けられ、必要に応じて勾留が延長される場合もあります。捜査の結果、起訴が確定すれば、地方裁判所において刑事裁判が行われます。
脱税の刑事罰は、10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科となります。申告漏れに比べて、脱税の場合には課せられるペナルティにも大きな違いがあることがお分かりになるでしょう。
脱税とみなされる行為とは
脱税とみなされる行為には、次のようなものがあります。
売上の過少申告
税金を逃れようとするためには、所得額を低く抑えなければなりません。所得は、収入から経費を差し引いて算出します。また、所得税も法人税も、所得額に該当する税率をかけて算出するものです。そのため、売上を本来よりも低い金額で申告すると、所得額を低く見せかけることができ、課せられる税金も低く抑えられます。したがって、脱税行為を行うケースでは、売上を過少に申告するパターンがよく見られます。
しかしながら、銀行の取引については記録が残ります。そのため、売上の一部を記録が残らないように現金で受け取り、売上として計上しない事例などがあります。また、会社名義の銀行口座ではなく、役員個人の銀行口座に振り込ませることで所得を隠す事例もあります。
経費の水増し
所得額を減らし、課税額を抑えるためには、売上を低く申告する方法のほか、経費を過大に計上する方法があります。経費の水増しも、脱税の際に行われることが多い行為です。具体的には、事業とは関係のない、プライベートな支出まで経費として計上するケースが多くなっています。例えば、取引先と関連しない飲食費を交際費として計上したり、プライベートで使用する自動車を会社名義で購入し、経費として計上するようなケースが考えられます。
また、実際には支払っていない支出を経費として計上するケースもあります。領収書を捏造し、取引があったかのように装って、経費を支払ったように見せかけるのです。そのほか、他人の領収書をもらい、自分の支出のように装うケースもあります。
二重帳簿の作成
二重帳簿とは、取引を正しく記録した帳簿のほかに、所得額を低く装うために実態とは異なる取引状況を記録した確定申告用の帳簿を作成することです。
二重帳簿を作成し、税務調査の際には、実態とは異なる帳簿を提出して調査の目をごまかし、不正に税金を逃れようとするケースがあります。二重帳簿は財務諸表作成時の根拠となる資料を、複数用意するという行為です。企業の会計においては、財務諸表の信頼性を担保するため、会計帳簿は1つのみとするという単一性の原則が採用されています。例えば、確定申告の際に提出した書類と、金融機関に融資を申し込む際に準備する書類が異なっていた場合、相手を欺く行為となるでしょう。つまり、単一性の原則は二重帳簿を禁止するルールであるといえます。二重帳簿を作成し、所得額を低く見せかけるという行為も脱税で用いられることの多い手法です。
税務調査の前に申告漏れに気付いた場合の対処法
税務調査の前に申告漏れがあることに気が付く場合もあるでしょう。その場合は、自主的に修正申告をし、正しい額の納税を行うようにしましょう。
確定申告の期限内に申告漏れに気付いた場合
確定申告の期限内に、申告漏れに気が付いた場合には、提出した申告書を修正し、再提出することで正しく作り直した、新しい日付の申告書が受理されます。特にその他の書類などの準備をする必要もありません。e-Taxで申請した場合も手書きで申告書を作成した場合も、どちらでも期限内であれば、修正した申告書を提出するだけで、正しく申告を行うことが可能です。
期限後に修正申告をする場合
確定申告の期限を過ぎて申告漏れに気が付いた場合には、修正申告が必要です。法人の場合は、国税庁のウェブサイトなどから修正申告書を入手します。先に提出した申告書の控えと修正が必要な勘定科目の明細、修正後の決算書を準備し、修正後の所得金額と税額、修正の理由を記載し、税務署に提出をします。追加納税が発生した場合には、税務署から納付書が送付されるため、納付書受領後は速やかに納付をしなければなりません。
個人の場合も国税庁のウェブサイトや税務署から修正申告書を入手し、必要な箇所を記入して税務署に提出をし、追徴課税分を納付します。
申告漏れに気付いたときに自主的に修正申告をするメリット
申告漏れに気が付いたときは、できるだけ早く修正申告をすることをおすすめします。それは、納税者が税務調査で指摘を受ける前に自主的に修正申告をし、申告漏れを正すと、課せられるペナルティを軽減できるからです。
税務調査によって所得漏れが発覚した場合は、過少申告加算税の納税が求められます。その際の過少申告加算税の税率は、10%または15%です。しかし、税務調査の事前通知を受ける前に、自主的に修正申告を行った場合、過少申告加算税は課されません。また、事前通知を受け取った後でも税務調査が実施される前に、自ら修正申告をした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分については10%の税率に軽減されるのです。
税務調査で申告漏れを指摘された場合、本来よりも多い額の納税が必要になります。申告漏れに気が付いたときには、そのタイミングで修正申告を行えば、不足分の税金を納めるだけで済むのです。
申告漏れの修正申告で生じるデメリットもある?
実は、申告漏れに気付いて自主的に修正申告をする行為によってデメリットが発生する場合もあります。それは、税務調査の事前通知を受けてから税務調査の実施前までに修正申告を行う場合です。修正申告が行われたことで、調査官がほかにも誤った処理をしている箇所があるのではという疑いを抱かせてしまう可能性があります。そのため、税務調査を担当する調査官によっては、修正申告書が提出されるとより厳格な調査を行い、細かな不備まで指摘される場合があるのです。
したがって、申告漏れの自覚があり、税務調査の事前通知を受けた場合には早めに税理士に相談し、修正申告をするべきかアドバイスを求めることをおすすめします。
まとめ
申告漏れと脱税の違いは、意図的に税金を逃れようとしたのか、ミスや理解不足などによって結果、過少申告となってしまったのかという点です。仮装・隠蔽などを行い、多額の納税を逃れようとする行為は脱税に該当します。
また、申告漏れと脱税ではペナルティにも違いがあります。申告漏れの場合は、過少申告加算税が課されますが、脱税の場合にはより税率の重い重加算税が課されます。さらに、行政罰だけでなく、刑事罰も科される恐れもあるなど、脱税行為の方がより重いペナルティが科されるという違いがあるのです。
脱税に該当する行為や申告漏れに該当する行為がある場合は、税務調査が入る前に自主的に修正申告をすることでペナルティを軽減できる可能性があります。早めに税理士に相談をしましょう。
-免責事項-
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時点の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計5,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
- 現在、税務調査が入っているので困っている
- 過去分からサポートしてくれる税理士に依頼したい
- 税務調査に強い税理士に変更したい
- 自分では対応できないので、税理士に依頼したい
税務調査の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 税務署目線、税理士目線、お客様目線の三方良しの考え方でアドバイス
- 過去の無申告分から現在まですべて対応可能
- 査察案件から税務署案件までの経験と実績が豊富にあります
- 顧問税理士がさじを投げた案件も途中から対応できます
30秒で完了かんたん税務調査リスク診断